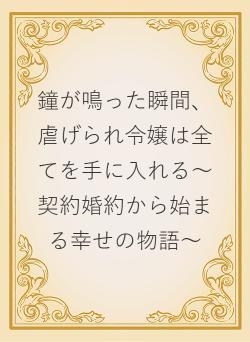「うん。ごめん。僕は……ユベールって言うんだ」
「やっぱり……そうだったんですね。私はリゼット・バルテ……です。先ほどはお答えできずに申し訳ありません」
さすがに伯爵令嬢、とまでは名乗れず、私はそう言って立ち上がり、挨拶をしようとした。が、足がうまく上がらない。まるで棒のように硬く、固まっているかのようだった。
もたつく私の姿を見たユベール……くん? さん? は「ちょっとごめん」と言い、私を抱き上げた。
「あっ」
ヴィクトル様と似た容姿をしているせいか、不謹慎にも胸が高鳴った。すでに婚約破棄を言い渡された身なのに、未練がましい……と思う。彼はヴィクトル様ではないのに。
「多分、今の自分の姿を見れば、立ち上がれなかった理由が分かると思うんだ。覚悟はいい?」
「……はい」
いまいちユベールの言っていることが理解できなかったが、今は前に進むべきだと思った。
ここで足踏みしていても何も分からない。分からないのなら、怖くても進んだ方がいい、と私の何かが言う。
多分、彼の優しさが、私の背中を押してくれているのだろう。
「やっぱり……そうだったんですね。私はリゼット・バルテ……です。先ほどはお答えできずに申し訳ありません」
さすがに伯爵令嬢、とまでは名乗れず、私はそう言って立ち上がり、挨拶をしようとした。が、足がうまく上がらない。まるで棒のように硬く、固まっているかのようだった。
もたつく私の姿を見たユベール……くん? さん? は「ちょっとごめん」と言い、私を抱き上げた。
「あっ」
ヴィクトル様と似た容姿をしているせいか、不謹慎にも胸が高鳴った。すでに婚約破棄を言い渡された身なのに、未練がましい……と思う。彼はヴィクトル様ではないのに。
「多分、今の自分の姿を見れば、立ち上がれなかった理由が分かると思うんだ。覚悟はいい?」
「……はい」
いまいちユベールの言っていることが理解できなかったが、今は前に進むべきだと思った。
ここで足踏みしていても何も分からない。分からないのなら、怖くても進んだ方がいい、と私の何かが言う。
多分、彼の優しさが、私の背中を押してくれているのだろう。