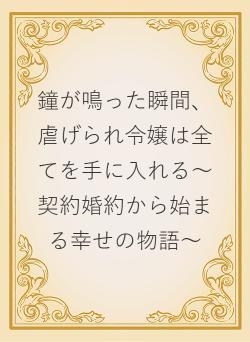「今日からここがお前の家になる」
今はもう、顔すら憶えていない両親に連れられ、マニフィカ公爵家の門を潜った。
五歳の私でも分かる、綺麗で豪華なマニフィカ公爵邸。大きさもバルテ伯爵邸とは比べ物にならないほど大きくて、圧倒されたのを憶えている。
そのお屋敷から出迎えてくれた、当時のマニフィカ公爵夫妻とヴィクトル様。
私がこの方たちの家族に、というよりも、雲の上の方とのご対面に、ただただ緊張し通しだった。
それは両親も同じ思いだったらしく、応接室で軽く挨拶を交わすと、早々に帰って行ってしまう。
取り残された私を温かく迎えてくれたのは……そうだ。ヴィクトル様だけだったような気がする。
いきなり現れた私をどう扱って良いのか。公爵夫妻は優しく接してくれたけれど、どこか戸惑っているのが、ありありと見えたのだ。
恐らく、ヴィクトル様の婚約者にしたい、と望まれていた方が、すでにいたのかもしれない。
マニフィカ公爵家の一人息子だ。もっと有益な家門から、または仲の良い方の娘などもいらっしゃったのだろう。
当時、十歳だったヴィクトル様なら、そのようなお話があってもおかしくはなかった。
今はもう、顔すら憶えていない両親に連れられ、マニフィカ公爵家の門を潜った。
五歳の私でも分かる、綺麗で豪華なマニフィカ公爵邸。大きさもバルテ伯爵邸とは比べ物にならないほど大きくて、圧倒されたのを憶えている。
そのお屋敷から出迎えてくれた、当時のマニフィカ公爵夫妻とヴィクトル様。
私がこの方たちの家族に、というよりも、雲の上の方とのご対面に、ただただ緊張し通しだった。
それは両親も同じ思いだったらしく、応接室で軽く挨拶を交わすと、早々に帰って行ってしまう。
取り残された私を温かく迎えてくれたのは……そうだ。ヴィクトル様だけだったような気がする。
いきなり現れた私をどう扱って良いのか。公爵夫妻は優しく接してくれたけれど、どこか戸惑っているのが、ありありと見えたのだ。
恐らく、ヴィクトル様の婚約者にしたい、と望まれていた方が、すでにいたのかもしれない。
マニフィカ公爵家の一人息子だ。もっと有益な家門から、または仲の良い方の娘などもいらっしゃったのだろう。
当時、十歳だったヴィクトル様なら、そのようなお話があってもおかしくはなかった。