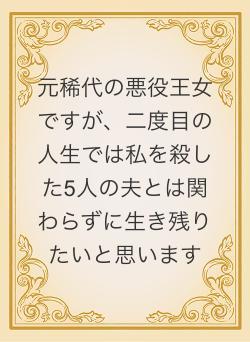クローゼットの中にはたくさんのドレスが用意されていて、その中から薄桃色のワンピースを選ぶと、カンタロウが着替えを手伝って髪の手入れとセットまでも丁寧に行ってくれた。
お姉様が聖女だと認定を受けてから私のことは二の次になり、新しいドレスも買ってもらうことはなくなった。
昔は少数いた使用人も、姉と母を優先させるようになってから自分で髪や肌の手入れもしていたし、そんな少数の使用人もいつの間にかいなくなり、私が使用人ポジションになっていたのだけれど。
こんな風に着替えの手伝いをしてもらうのも、肌や髪を誰かに整えてもらうのも久しぶりすぎて、なんだかむず痒い気持ちになった。
「ほら、とっても綺麗になった。あんたは肌も白いし、髪の毛も綺麗な白銀なんだから、ちゃんと手入れしてセットすれば映えるのよ。いつか舞踏会に出ることがあったら、私にセットさせてね。こんな簡単に三つ編みしただけじゃなくて、もっと綺麗にセットしてあげるんだから」
「こんなに綺麗にしてもらって……お手数かけてごめんなさ──」
「謝るの禁止」
じとっとした目で見られると何も言えない。
そうだ、さっきオズ様にも言われたばかりなのに。
長年の間についた謝り癖は昨日今日で抜けるものではないようだ。
「あの、えっと、ありがとう、カンタロウ」
私が感謝を述べると、カンタロウは「うん、それでいいのよ」と満足げにうなずいて笑った。
見た目は私よりもずっと年下に見えるのに、なんだかお姉さんみたいで不思議な気持ちだ。
「カンタロウ、厨房に案内してくれる? 朝食を作らないと」
ここに無償で置いてもらっているのは料理を作るためなのだから、しっかりと与えられた役目を果たさなければ。
「いいわよ。ついてらっしゃい」
えへんと鼻息荒く進む少女の後ろについて歩く。
まるで小さな親分と大きな子分だ。
綺麗な生花や花の絵が所々に飾ってある廊下を歩き続け、一階に降りて奥へと進んでいくと、大きな扉が見えてきた。
「ここよ」
広い厨房の奥の棚にはたくさんの食材が並べられている。
食材のストックが少なかったフェブリール男爵家とは大違いね。
ストックできるほどのお金を使わせてはもらえなかったもの。
それにしても、こんなにも広い公爵家の厨房でありながら、コックの姿一つない。
「あの、カンタロウ、このお屋敷のコックは……」
「そんなのいないわよ。オズが毎食作ってる。……殺人級の不味さだけどね……」
そういえば昨日、「オズのご飯は不味い」ってまる子がこぼしてたっけ。
毎食を名門公爵家の公爵様自らが作っているだなんて……。
そういえばここまで歩いてきた間にも、使用人の姿も見当たらなかった。
「もしかして使用人も……?」
「いないわよ。ここに住んでいるのはオズと、私と、まる子だけよ。もうずっと前から、ね」
そう語ったカンタロウの顔は、どこか悲しげで、私はそれ以上何も聞くことはできなかった。
「さて、何にしようかな」
とりあえず保管されていた食材を机の上に並べてみる。
白いパンに肉、魚、卵。
大量の板チョコ。
野菜は根菜から葉物野菜、それに何かよくわからない赤やら紫やらの謎の色まである草類(おおそらく薬草)。
「……とりあえず時間もないし、今回はあまり時間を取らないものにさせていただきましょう」
謎の草には触れてはならない。
だってなんか動いてるものもあるもの……。
私は壁にかけてあるフリフリのエプロンを取ると、急いで調理に取り掛かった。
***
「──お待たせしました」
広間の広いテーブルの上に並べた朝食。
葉物野菜と卵のスープ。
白パンにカリカリベーコン。
簡単なものばかりで申し訳ないけれど、とりあえずはできた。
「お~……!!」
「これは……!!」
目を輝かせて目の前の料理を見つめるイケメンと少女。
もとい、まる子とカンタロウ。
「とってもおいしそうじゃないか!!」
「えぇ!! オズの料理とは天と地の差!!」
「あれはゲテモノ料理というものだからね……料理とは言いたくない……」
「おい」
いったいいつもどんなご飯を食べているんだろう。
「ゴホンッ、では……。実りと作り手に感謝を──」
「いただきます」
オズ様が食膳の祈りをささげると同時に、私はつい前世の食前の言葉を発していた。
しまった。今までは大丈夫だったけど、前世の記憶を思い出しちゃったからつい……。
「それは何の言葉だ?」
「す、すみません!! えっと、前世の食前に言う言葉です。あなた、つまり食材の命を頂きます、という感謝と、作り手への感謝を込めて言う言葉で……。前世を思い出したからか、つい出てしまって……」
前世の名前は覚えていないというのに……。
癖って恐ろしい……。
「ふむ……うん、良い言葉だ。うちでも取り入れよう」
「へ?」
予想外に帰ってきた言葉に目をぱちぱちとさせると、オズさまは気にする様子もなく「いただきます」と両手を合わせ、食事を始めてしまった。
それに倣ってまる子とカンタロウも「いただきます」と続け食べ始める。
「!! おいしい……すごくおいしいよ!!」
「ほんと!! セシリア様様だわ!!」
「君たちがいつも言っていただけのことはある。君は料理が上手だな、セシリア」
こんなに喜ばれたのは初めてだ。
私は目の前の人達の嬉しそうな顔に自分の頬が緩むのを感じながら、久しぶりに楽しい食卓を囲んだのだった。
お姉様が聖女だと認定を受けてから私のことは二の次になり、新しいドレスも買ってもらうことはなくなった。
昔は少数いた使用人も、姉と母を優先させるようになってから自分で髪や肌の手入れもしていたし、そんな少数の使用人もいつの間にかいなくなり、私が使用人ポジションになっていたのだけれど。
こんな風に着替えの手伝いをしてもらうのも、肌や髪を誰かに整えてもらうのも久しぶりすぎて、なんだかむず痒い気持ちになった。
「ほら、とっても綺麗になった。あんたは肌も白いし、髪の毛も綺麗な白銀なんだから、ちゃんと手入れしてセットすれば映えるのよ。いつか舞踏会に出ることがあったら、私にセットさせてね。こんな簡単に三つ編みしただけじゃなくて、もっと綺麗にセットしてあげるんだから」
「こんなに綺麗にしてもらって……お手数かけてごめんなさ──」
「謝るの禁止」
じとっとした目で見られると何も言えない。
そうだ、さっきオズ様にも言われたばかりなのに。
長年の間についた謝り癖は昨日今日で抜けるものではないようだ。
「あの、えっと、ありがとう、カンタロウ」
私が感謝を述べると、カンタロウは「うん、それでいいのよ」と満足げにうなずいて笑った。
見た目は私よりもずっと年下に見えるのに、なんだかお姉さんみたいで不思議な気持ちだ。
「カンタロウ、厨房に案内してくれる? 朝食を作らないと」
ここに無償で置いてもらっているのは料理を作るためなのだから、しっかりと与えられた役目を果たさなければ。
「いいわよ。ついてらっしゃい」
えへんと鼻息荒く進む少女の後ろについて歩く。
まるで小さな親分と大きな子分だ。
綺麗な生花や花の絵が所々に飾ってある廊下を歩き続け、一階に降りて奥へと進んでいくと、大きな扉が見えてきた。
「ここよ」
広い厨房の奥の棚にはたくさんの食材が並べられている。
食材のストックが少なかったフェブリール男爵家とは大違いね。
ストックできるほどのお金を使わせてはもらえなかったもの。
それにしても、こんなにも広い公爵家の厨房でありながら、コックの姿一つない。
「あの、カンタロウ、このお屋敷のコックは……」
「そんなのいないわよ。オズが毎食作ってる。……殺人級の不味さだけどね……」
そういえば昨日、「オズのご飯は不味い」ってまる子がこぼしてたっけ。
毎食を名門公爵家の公爵様自らが作っているだなんて……。
そういえばここまで歩いてきた間にも、使用人の姿も見当たらなかった。
「もしかして使用人も……?」
「いないわよ。ここに住んでいるのはオズと、私と、まる子だけよ。もうずっと前から、ね」
そう語ったカンタロウの顔は、どこか悲しげで、私はそれ以上何も聞くことはできなかった。
「さて、何にしようかな」
とりあえず保管されていた食材を机の上に並べてみる。
白いパンに肉、魚、卵。
大量の板チョコ。
野菜は根菜から葉物野菜、それに何かよくわからない赤やら紫やらの謎の色まである草類(おおそらく薬草)。
「……とりあえず時間もないし、今回はあまり時間を取らないものにさせていただきましょう」
謎の草には触れてはならない。
だってなんか動いてるものもあるもの……。
私は壁にかけてあるフリフリのエプロンを取ると、急いで調理に取り掛かった。
***
「──お待たせしました」
広間の広いテーブルの上に並べた朝食。
葉物野菜と卵のスープ。
白パンにカリカリベーコン。
簡単なものばかりで申し訳ないけれど、とりあえずはできた。
「お~……!!」
「これは……!!」
目を輝かせて目の前の料理を見つめるイケメンと少女。
もとい、まる子とカンタロウ。
「とってもおいしそうじゃないか!!」
「えぇ!! オズの料理とは天と地の差!!」
「あれはゲテモノ料理というものだからね……料理とは言いたくない……」
「おい」
いったいいつもどんなご飯を食べているんだろう。
「ゴホンッ、では……。実りと作り手に感謝を──」
「いただきます」
オズ様が食膳の祈りをささげると同時に、私はつい前世の食前の言葉を発していた。
しまった。今までは大丈夫だったけど、前世の記憶を思い出しちゃったからつい……。
「それは何の言葉だ?」
「す、すみません!! えっと、前世の食前に言う言葉です。あなた、つまり食材の命を頂きます、という感謝と、作り手への感謝を込めて言う言葉で……。前世を思い出したからか、つい出てしまって……」
前世の名前は覚えていないというのに……。
癖って恐ろしい……。
「ふむ……うん、良い言葉だ。うちでも取り入れよう」
「へ?」
予想外に帰ってきた言葉に目をぱちぱちとさせると、オズさまは気にする様子もなく「いただきます」と両手を合わせ、食事を始めてしまった。
それに倣ってまる子とカンタロウも「いただきます」と続け食べ始める。
「!! おいしい……すごくおいしいよ!!」
「ほんと!! セシリア様様だわ!!」
「君たちがいつも言っていただけのことはある。君は料理が上手だな、セシリア」
こんなに喜ばれたのは初めてだ。
私は目の前の人達の嬉しそうな顔に自分の頬が緩むのを感じながら、久しぶりに楽しい食卓を囲んだのだった。