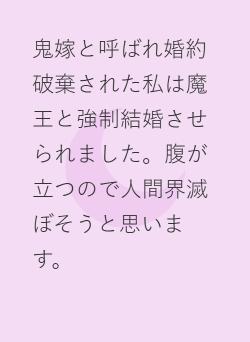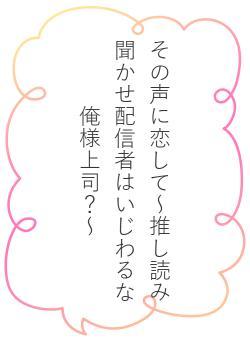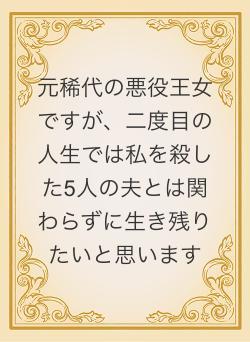「……よかったのかね?」
「え?」
「いや……。ジュローデル公爵に何も言わずに出てきて」
王都へ向かう馬車に乗って、向かいに座る宰相様がためらいがちに尋ねた。
何も思わないわけではない。
なんて不義理なことをしてしまっているんだろうとい、若干の罪悪感は否めない。
今度こそ嫌われてしまったかもしれないという恐怖も。
でも──。
「私は一番大切なもののためなら、何を思われても大丈夫です。たとえオズ様が私を嫌いになってしまっても。私は……大丈夫、です」
嫌われることをいまさら恐れはしない。
なのにどうしてか、オズ様に嫌われることを想像すると、全身から温度が失われていくような、そんな気がしてしまう。
それでも私は、自分に「大丈夫」だと、そう言い聞かせる。
だってそれが私の、最善だから。
「……そうか……。すまない。あなたにばかりつらい思いをさせて。……気づいていたのだ。私も、陛下も、殿下も。聖女として認定された姉のもとで小さくなっていくあなたに。だが気づいていて、誰も何も言わなかった。手を差し伸べたのは、なんとなく気づいていた我々ではなく、噂も聞かぬ辺境に住む、オズ・ジュローデル公爵だった。私たちはいつもそうだ。ジュローデル公爵領、トレンシスの不当な扱いに気づいていながら、過去の決断にとらわれて何もしてこなかった。変わるべきは、われわれの意識だというのに」
誰もが気づいていながら、見て見ぬふりをする。
その結果が今のトレンシスだ。
……そうか……。
トレンシスは──私なんだ……。
オズ様が手を差し伸べてくれる前の。
滅びゆくのをただ待っていた脆い私と同じ。
なら今度は私が、トレンシスにとってのオズ様になる。
「そんな中ドルトは一人、自分で考え、われわれの思う常識を壊し、ジュローデル公爵領へと移り住み、医師になった。私は、君やドルトを尊敬するよ」
「ドルト先生はオズ様と幼馴染なのですよね?」
確かタウンハウスがトレンシスに会って、よく一緒に遊んでたって言ってたっけ。
「あぁ。もともと私や妻と公爵夫妻は仲が良くてね。あの町にタウンハウスを構えて、よく行っていたんだ。空気の良いあの町で、ドルトの出産もしてね。それから年に何度もドルトを連れてタウンハウスに行き、そのたびに二人でよく遊んでいた」
小さなころのオズ様とドルト先生。
二人が遊ぶ様子は今からじゃ想像がつかないけれど、きっと二人とも、今とあまり変わらないんだろうなぁ。
「ジュローデル公爵のお父上とお母上のことがあって、ドルトはとても心配していた。そして自分にできることを自分なりに考えてきたのだろう。王立学園を卒業してすぐに医学の学校へ行きたいと言い出してね。その理由がトレンシスの医師として、トレンシスを支えたいからだって。それから二年。医学校へ通い、医師免許を取ったドルトは、宣言通り家を出てトレンシスの医師になった」
貴族として生きてきた彼が家を出て辺境の医師になるというのは、いったいどれだけの覚悟を持ってのことなのだろうか。
私には想像もつかないけれど、それだけの決意をするほどに、きっとドルト先生はオズ様のことが大切だったんだ。
今の私のように。
「ドルト先生は、皆に慕われる大切なトレンシスのお医者様です。きっとこれからもあの町を守ってくださる」
「……あぁ。それはあなたもだ」
「私も?」
「あの町に、いや、ジュローデル公爵にとって、かけがえのない大切なものだ」
私が……かけがえのない……?
「なるべく情報はフェブリール男爵家に行かぬよう、規制をしよう。殿下のことが終われば、すぐにでも帰ってもったらいい。あとはこちらで何とでもする」
「え、でも……」
混乱しない?
お姉様か、私か、どちらが本当の聖女なのか、と。
「大丈夫。もしも何かあっても、彼らならきっと……」
「?」
「あぁ、城が見えた。さぁ、これからすぐに殿下の部屋に来てもらうことになるが……良いかな?」
殿下のお部屋に。
私はごくりと喉を鳴らすと、意を決して宰相様に視線を向け、頷いた。
「はい。……いつでも……!!」
「え?」
「いや……。ジュローデル公爵に何も言わずに出てきて」
王都へ向かう馬車に乗って、向かいに座る宰相様がためらいがちに尋ねた。
何も思わないわけではない。
なんて不義理なことをしてしまっているんだろうとい、若干の罪悪感は否めない。
今度こそ嫌われてしまったかもしれないという恐怖も。
でも──。
「私は一番大切なもののためなら、何を思われても大丈夫です。たとえオズ様が私を嫌いになってしまっても。私は……大丈夫、です」
嫌われることをいまさら恐れはしない。
なのにどうしてか、オズ様に嫌われることを想像すると、全身から温度が失われていくような、そんな気がしてしまう。
それでも私は、自分に「大丈夫」だと、そう言い聞かせる。
だってそれが私の、最善だから。
「……そうか……。すまない。あなたにばかりつらい思いをさせて。……気づいていたのだ。私も、陛下も、殿下も。聖女として認定された姉のもとで小さくなっていくあなたに。だが気づいていて、誰も何も言わなかった。手を差し伸べたのは、なんとなく気づいていた我々ではなく、噂も聞かぬ辺境に住む、オズ・ジュローデル公爵だった。私たちはいつもそうだ。ジュローデル公爵領、トレンシスの不当な扱いに気づいていながら、過去の決断にとらわれて何もしてこなかった。変わるべきは、われわれの意識だというのに」
誰もが気づいていながら、見て見ぬふりをする。
その結果が今のトレンシスだ。
……そうか……。
トレンシスは──私なんだ……。
オズ様が手を差し伸べてくれる前の。
滅びゆくのをただ待っていた脆い私と同じ。
なら今度は私が、トレンシスにとってのオズ様になる。
「そんな中ドルトは一人、自分で考え、われわれの思う常識を壊し、ジュローデル公爵領へと移り住み、医師になった。私は、君やドルトを尊敬するよ」
「ドルト先生はオズ様と幼馴染なのですよね?」
確かタウンハウスがトレンシスに会って、よく一緒に遊んでたって言ってたっけ。
「あぁ。もともと私や妻と公爵夫妻は仲が良くてね。あの町にタウンハウスを構えて、よく行っていたんだ。空気の良いあの町で、ドルトの出産もしてね。それから年に何度もドルトを連れてタウンハウスに行き、そのたびに二人でよく遊んでいた」
小さなころのオズ様とドルト先生。
二人が遊ぶ様子は今からじゃ想像がつかないけれど、きっと二人とも、今とあまり変わらないんだろうなぁ。
「ジュローデル公爵のお父上とお母上のことがあって、ドルトはとても心配していた。そして自分にできることを自分なりに考えてきたのだろう。王立学園を卒業してすぐに医学の学校へ行きたいと言い出してね。その理由がトレンシスの医師として、トレンシスを支えたいからだって。それから二年。医学校へ通い、医師免許を取ったドルトは、宣言通り家を出てトレンシスの医師になった」
貴族として生きてきた彼が家を出て辺境の医師になるというのは、いったいどれだけの覚悟を持ってのことなのだろうか。
私には想像もつかないけれど、それだけの決意をするほどに、きっとドルト先生はオズ様のことが大切だったんだ。
今の私のように。
「ドルト先生は、皆に慕われる大切なトレンシスのお医者様です。きっとこれからもあの町を守ってくださる」
「……あぁ。それはあなたもだ」
「私も?」
「あの町に、いや、ジュローデル公爵にとって、かけがえのない大切なものだ」
私が……かけがえのない……?
「なるべく情報はフェブリール男爵家に行かぬよう、規制をしよう。殿下のことが終われば、すぐにでも帰ってもったらいい。あとはこちらで何とでもする」
「え、でも……」
混乱しない?
お姉様か、私か、どちらが本当の聖女なのか、と。
「大丈夫。もしも何かあっても、彼らならきっと……」
「?」
「あぁ、城が見えた。さぁ、これからすぐに殿下の部屋に来てもらうことになるが……良いかな?」
殿下のお部屋に。
私はごくりと喉を鳴らすと、意を決して宰相様に視線を向け、頷いた。
「はい。……いつでも……!!」