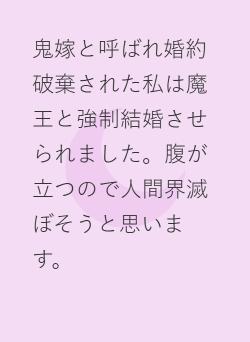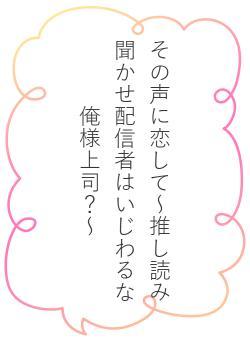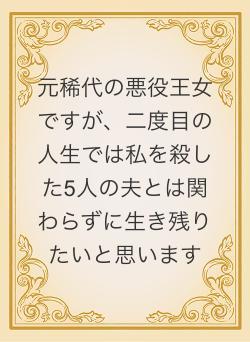「大丈夫でしょうか……宰相様。私が依頼を断ったせいで陛下に罰を下されたりは……」
「そこらへんは大丈夫だろう。陛下はその親とは違って分別の付くまともな方だからな。それに、宰相がもし罰を受けるとしても、奴らのために君を差し出すことはできない。君の姉がクズなのを見抜くことができなかったのも、君のことを知りながら放置して何もしてやらなかったのも、自分たちの落ち度だ。王太子が婚約者の妹のことを知らないはずなどないのだからな」
確かにそうだ。
何度かローゼリアお姉様を訪ねてうちに来られた時、ご挨拶はしているもの。
ぼろぼろのドレスで掃除をしているのだって見られたことがある。
それでも殿下は、それを見ないふりをした。
まるでそれが当り前の光景かのように。
《《そういうもの》》なのだと、私を認識していたんだと思う。
「セシリア」
「はい」
「君が気に病むことはない。因果応報。そういうものだ」
確かにそう言ってしまえばそれまでだ。だけど……。
もし、もしも王太子殿下がお亡くなりになったとして──。
「もし、王女殿下が王位を継がれることになったら……」
オズ様は、国王命令でもなんでも出されて結婚してしまうんじゃ……。
それはなんだか、嫌だ。
私の言葉にオズ様が苦々しく顔をゆがめる。
「……そうなれば俺は逃亡でも何でもする。あの女と結婚するとか……地獄でしかない」
そこまで!?
でも結局はオズ様は逃げることはされないんだろうな。
だって彼には、大切にしているこのトレンシスがあるのだから。
「それに、王太子を治せば当然莫大な褒賞をもらうことができるだろう。何が何でも治そうとする人間は出てくる。きっと」
褒賞……。
お金、地位、それとも──。
ぁ……そうか……。
気づいてしまった一つの可能性に、私ははやる気持ちをこらえる。
「セシリア、俺はこれから少し調合室にこもる。君はゆっくりしていなさい」
「は、はい」
オズ様は私の返事に頷くと、私の頭をひと撫でしてから部屋を後にした。
「……」
一人応接室に残った私は、たどり着いた一つの思考を巡らせていた。
ドクン、ドクンと大きく胸が鳴る。
私が、唯一オズ様にできること。
この町にできること。
私が恩を返せるのは、きっとこれしかない。
「……たしか宰相様、ドルト先生の様子を見て帰られるって言ってたわよね」
つぶやいた私は急いで部屋を出ると、ドルト先生の診療所へと向かうのだった。