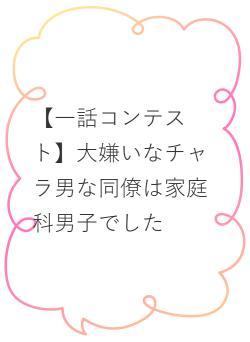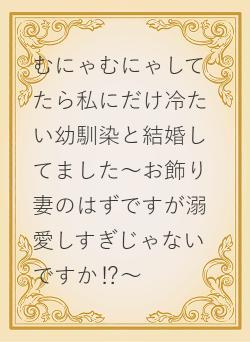「……」
「……」
まただわ。
眉間にしわを寄せて机の上の書類とにらめっこ。
オズ様はここのところ夜中によく執務室で難しい顔をして書類を見ている。
そして時々こんなふうに難しい顔の中に悔しさのようなものが滲んでいるのだ。
あまり考えすぎて お身体を壊さなければいいのだけれど……。
「……そうだわ……!!」
たまには執務中のおやつも良いわよね?
気分転換にもなるし。
私はそう思い立つと、オズ様の執務室の前からそっと離れて厨房へと降りていった。
──トントントン。控えめに扉を叩く。
「オズ様、セシリアです」
「セシリア? どうぞ」
入室の許可が出て、私は厨房から持ってきたトレーを左手に移し、右手で扉をゆっくりと引き開けた。
「失礼します」
「どうした? こんな時間に。眠れないのか?」
こんな時間だという認識はあるにもかかわらず、オズ様はまだ仕事をしてるんですね。──なんてお小言、言えない……!!
でも少しはわかってほしい。
心配している人間がいるということを。
「あの……これ」
私は持っていたトレーを執務机の前のローテーブルへそっと置いた。
「ん? これは?」
オズ様の視線は机に置かれたトレーの上のものへと移る。
いつもの就寝前の薬茶と、もう一つ。
白く丸いものが浮いたあずき色のスープ。
「これはおしることいいます。豆を煮てお団子を入れたもので、私の前世の世界の甘味なんですよ」
この世界にも小豆……ではないけれど、味がそっくりな豆がある。
あずきというには大きくて、縦の直径が五センチもあるビッグサイズの豆だけれど。
この豆、もともと甘みの強い豆だからおかずには向かないけれど、スイーツとしてよく使われるのよね。
砂糖なしで作れる身体にやさしい食材だ。
甘味好きのオズ様にはきっと気に入ってもらえるはず。
「これでも食べて、少し休憩なさってください」
「……そうだな。わかった。いただこう」
オズ様は持っていたペンを机に置くと、ソファの方へ腰を下ろしてから、無言で立っている私を見上げた。
「? あ、あの……?」
戸惑う私に、とんとん、と自分の隣の座席をたたいた。
「そこに立って居られても気になる。座りなさい」
「は、はい、失礼します……!!」
やや緊張しながらオズ様の隣へと腰を下ろす私を見て、どこか満足げにうなずくオズ様。
「では、いただきます」
丁寧に手を合わせ、私の前世の食前の言葉を述べると、オズ様はスプーンでそのあずき色のスープをひとすくいし、口に運んだ。
「……っ!! おいしい……!!」
美味しい、いただきましたぁーっ!!
「なんだこれは……。甘みがしつこくなく、だが確かに味も甘みもはっきりと感じられる……。上品な甘さ、というのだろうか? 嫌味がない味だ。この団子に絡ませて食べると、上品さが際立つな。それに暖かくて、身体の芯から温まるようだ」
いつもより饒舌な食レポ……!!
よっぽど気に入ってくれたのね、オズ様。
「ふふ。気に入っていただけたならよかったです。最近、夜遅くまで悩んでいらっしゃるようでしたので」
「……そうか……心配かけてしまったな。すまない」
少し視線を伏せてから、オズ様は続けた。
「実は、酒の取引について少し考えていてな」
「お酒の?」
「あぁ。この町の名産が酒だということは、以前話しただろう? その産地はすべて王都産にかえられていることも」
「っ……はい……」
産地偽装。
自分たちの先祖が難癖付けて追放した公爵家の領地。まさかそこでおいしいお酒が造られることになるだなんて、誤算だったことだろう。
広く流通させたいがそれでは自分たちのしたことと矛盾させてしまう。
だから、産地を王都産に変えて売り出すという取引をし始めた。
このジュローデル公爵領トレンシスの町は森に囲まれていて外部との接触があまりない。
外貨を得るためには、不利な内容であってもそれに飛びつくしかなかったのだろう。
町の皆もきっとそれがわかっているから、悔しくても受け入れているのよね。
「俺が開発したトレンシスの酒入りの菓子も、全てが王都産として出回っていてな。それらを何とかトレンシス産として売ることができたならば、王都に幾分も取られることなく名産収入が入るのに、と思ってな」
そうか。
産地は王都産として売り出されているから、普通領地に入る分が王都と分け合った上での収入になってしまうのか。
トレンシスは地図にすら載ることが許されなかった町。
当然観光客だっていないし、領地としての収入は少ない。
町の設備のほとんどもおそらく公爵家のお金で賄っている状態だ。
このままじゃ──。
「このままではいずれ遠くない未来、トレンシスは立ち行かなくなる」
「っ……」
トレンシスがなくなるかもしれない……?
そんなの……嫌だ……!!
「公爵家は残るだろうが、トレンシスがなくなれば公爵家に意味はない。あそこは、祖父母についてきてくれた人々の町。何もない場所に移ってきてくれた人たちが一から作り上げた、大切な町なのだからな」
追放されて領地を移された時についてきてくれた人たちと作り上げたトレンシス。
今までの領地から新しい領地、しかも地図にも乗ることのない断絶された場所への移動は、さぞ不安だったろう。
それでもついてきてくれた人々がいたから、あの町はできたのよね。
だからここはこんなにも領民と領主の仲が良いんだと思う。
まるでそう、家族、みたいな。
「オズ様、トレンシスは──」
「大丈夫だ。俺が、何とかできるように考える」
ここのところ難しい顔で考えてらっしゃったのは、このことだったのね。
残念だけれど、権力も何もない私にはなにもできない。
ただ、見守る事しか。
「……ちゃんと、寝てくださいね?」
「あぁ。最近は前よりも眠れているから、大丈夫だ。ありがとう、セシリア。君も早く寝なさい」
オズ様の大きな手が私の頭をそっと撫でる。
この流れもなんだかとても自然に感じられるようになってしまった。
「はい、おやすみなさい、オズ様」
私は立ち上がると、静かに扉の方へと歩いていく。
「セシリア」
ふと呼び止められて振り返ると、いつもクールなオズ様がふんわりと優しい笑みを浮かべて私を見つめていた。
「とてもおいしかった。ありがとう」
「っ……!! はいっ!!」
この優しい領主様に、この優しい町に、今、私ができることは何だろう。
そんな答えの見えないことを考えながら、私は眠りにつくのだった。
「……」
まただわ。
眉間にしわを寄せて机の上の書類とにらめっこ。
オズ様はここのところ夜中によく執務室で難しい顔をして書類を見ている。
そして時々こんなふうに難しい顔の中に悔しさのようなものが滲んでいるのだ。
あまり考えすぎて お身体を壊さなければいいのだけれど……。
「……そうだわ……!!」
たまには執務中のおやつも良いわよね?
気分転換にもなるし。
私はそう思い立つと、オズ様の執務室の前からそっと離れて厨房へと降りていった。
──トントントン。控えめに扉を叩く。
「オズ様、セシリアです」
「セシリア? どうぞ」
入室の許可が出て、私は厨房から持ってきたトレーを左手に移し、右手で扉をゆっくりと引き開けた。
「失礼します」
「どうした? こんな時間に。眠れないのか?」
こんな時間だという認識はあるにもかかわらず、オズ様はまだ仕事をしてるんですね。──なんてお小言、言えない……!!
でも少しはわかってほしい。
心配している人間がいるということを。
「あの……これ」
私は持っていたトレーを執務机の前のローテーブルへそっと置いた。
「ん? これは?」
オズ様の視線は机に置かれたトレーの上のものへと移る。
いつもの就寝前の薬茶と、もう一つ。
白く丸いものが浮いたあずき色のスープ。
「これはおしることいいます。豆を煮てお団子を入れたもので、私の前世の世界の甘味なんですよ」
この世界にも小豆……ではないけれど、味がそっくりな豆がある。
あずきというには大きくて、縦の直径が五センチもあるビッグサイズの豆だけれど。
この豆、もともと甘みの強い豆だからおかずには向かないけれど、スイーツとしてよく使われるのよね。
砂糖なしで作れる身体にやさしい食材だ。
甘味好きのオズ様にはきっと気に入ってもらえるはず。
「これでも食べて、少し休憩なさってください」
「……そうだな。わかった。いただこう」
オズ様は持っていたペンを机に置くと、ソファの方へ腰を下ろしてから、無言で立っている私を見上げた。
「? あ、あの……?」
戸惑う私に、とんとん、と自分の隣の座席をたたいた。
「そこに立って居られても気になる。座りなさい」
「は、はい、失礼します……!!」
やや緊張しながらオズ様の隣へと腰を下ろす私を見て、どこか満足げにうなずくオズ様。
「では、いただきます」
丁寧に手を合わせ、私の前世の食前の言葉を述べると、オズ様はスプーンでそのあずき色のスープをひとすくいし、口に運んだ。
「……っ!! おいしい……!!」
美味しい、いただきましたぁーっ!!
「なんだこれは……。甘みがしつこくなく、だが確かに味も甘みもはっきりと感じられる……。上品な甘さ、というのだろうか? 嫌味がない味だ。この団子に絡ませて食べると、上品さが際立つな。それに暖かくて、身体の芯から温まるようだ」
いつもより饒舌な食レポ……!!
よっぽど気に入ってくれたのね、オズ様。
「ふふ。気に入っていただけたならよかったです。最近、夜遅くまで悩んでいらっしゃるようでしたので」
「……そうか……心配かけてしまったな。すまない」
少し視線を伏せてから、オズ様は続けた。
「実は、酒の取引について少し考えていてな」
「お酒の?」
「あぁ。この町の名産が酒だということは、以前話しただろう? その産地はすべて王都産にかえられていることも」
「っ……はい……」
産地偽装。
自分たちの先祖が難癖付けて追放した公爵家の領地。まさかそこでおいしいお酒が造られることになるだなんて、誤算だったことだろう。
広く流通させたいがそれでは自分たちのしたことと矛盾させてしまう。
だから、産地を王都産に変えて売り出すという取引をし始めた。
このジュローデル公爵領トレンシスの町は森に囲まれていて外部との接触があまりない。
外貨を得るためには、不利な内容であってもそれに飛びつくしかなかったのだろう。
町の皆もきっとそれがわかっているから、悔しくても受け入れているのよね。
「俺が開発したトレンシスの酒入りの菓子も、全てが王都産として出回っていてな。それらを何とかトレンシス産として売ることができたならば、王都に幾分も取られることなく名産収入が入るのに、と思ってな」
そうか。
産地は王都産として売り出されているから、普通領地に入る分が王都と分け合った上での収入になってしまうのか。
トレンシスは地図にすら載ることが許されなかった町。
当然観光客だっていないし、領地としての収入は少ない。
町の設備のほとんどもおそらく公爵家のお金で賄っている状態だ。
このままじゃ──。
「このままではいずれ遠くない未来、トレンシスは立ち行かなくなる」
「っ……」
トレンシスがなくなるかもしれない……?
そんなの……嫌だ……!!
「公爵家は残るだろうが、トレンシスがなくなれば公爵家に意味はない。あそこは、祖父母についてきてくれた人々の町。何もない場所に移ってきてくれた人たちが一から作り上げた、大切な町なのだからな」
追放されて領地を移された時についてきてくれた人たちと作り上げたトレンシス。
今までの領地から新しい領地、しかも地図にも乗ることのない断絶された場所への移動は、さぞ不安だったろう。
それでもついてきてくれた人々がいたから、あの町はできたのよね。
だからここはこんなにも領民と領主の仲が良いんだと思う。
まるでそう、家族、みたいな。
「オズ様、トレンシスは──」
「大丈夫だ。俺が、何とかできるように考える」
ここのところ難しい顔で考えてらっしゃったのは、このことだったのね。
残念だけれど、権力も何もない私にはなにもできない。
ただ、見守る事しか。
「……ちゃんと、寝てくださいね?」
「あぁ。最近は前よりも眠れているから、大丈夫だ。ありがとう、セシリア。君も早く寝なさい」
オズ様の大きな手が私の頭をそっと撫でる。
この流れもなんだかとても自然に感じられるようになってしまった。
「はい、おやすみなさい、オズ様」
私は立ち上がると、静かに扉の方へと歩いていく。
「セシリア」
ふと呼び止められて振り返ると、いつもクールなオズ様がふんわりと優しい笑みを浮かべて私を見つめていた。
「とてもおいしかった。ありがとう」
「っ……!! はいっ!!」
この優しい領主様に、この優しい町に、今、私ができることは何だろう。
そんな答えの見えないことを考えながら、私は眠りにつくのだった。