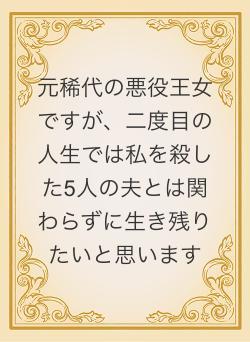王都に行くにはジュローデル公爵家のある森を抜け、フェブリール男爵家を通らねばならない。
私は顔を見られないように外套のフードを目深にかぶり、馬車の中、オズ様の向かいの席に座る。
御者はまる子とカンタロウが務め、私たちは森を抜けた。
驚いたことに、森への出入り口にはちゃんと門があり、区切られていたのだ。
「こっち側にちゃんと道があったんですね」
「君が森に入ったのは正規ルートではないからな。町の者は皆ここから出入りする。地図に乗っていない町とはいえ、公爵領。きちんと整備されている。まぁ、噂のおかげで安易に森に入る馬鹿はめったにいないがな」
はいすみません。
滅多にいない馬鹿がここにいます。
でも本当に驚いた。
入り組んだ場所にあるとはいえ、男爵領の東側にちゃんと門があるだなんて知らなかったもの。
男爵家の裏の森だって、森の先は行き止まりなのだと思っていたくらいだし。
ということは、お父様たちは知っていたのよね。
裏の森が、公爵領に続いていることを……。
「セシリア、大丈夫か?」
「へ?」
私がぼんやりと考えていると、オズ様が心配そうに私を覗き込んだ。
「男爵領に来るのは久しぶりだろう? 大丈夫か?」
「あ……」
私がフェブリール男爵家を出て二か月と少しが経った。
以前は考えるだけで胸が苦しくなったものだけれど、今はもうそんなこともない。
それはきっと、オズ様達が私の居場所をくれたから。
「大丈夫です。私にはオズ様が……。優しい皆さんがいる、トレンシスの町がありますから」
私はあの町の人達が大好きだ。
だからオズ様が良いと言ってくれる限りは、ジュローデル公爵領にいたい。
でも──きっとそう遠くない未来、私は行かねばならない。
オズ様は公爵様だもの。
いずれは綺麗な奥様を迎えて、公爵領を盛り立てていかねばならないもの。
いつまでもお世話になるわけにはいかない。
私がオズ様の幸せの邪魔をしてはいけない。
オズ様がご結婚される。
その時には、まる子たちが何と言おうとすぐにオズ様に送ってもらおう。
私を、次の世へ──。
痛み無く。苦しみなく。楽に。綺麗に。
最後に見るのは、私は、オズ様のお顔が良い。
「セシリア? どうした? 何か考え事か?」
「へ? あ、えっと……はい。オズ様のことを考えていました」
「は!?」
いや何その驚き様は。
茹でられたみたいに顔が真っ赤なんですけど!?
「お、俺のことというのは……」
「あー……その、オズ様が結婚する日の……事?」
「………………は?」
今度はものすごいこわばった顔で固まってしまわれた!?
微妙に不機嫌そうなのはなぜ!?
「あ、あの、オズ様?」
「そんな心配を君がする必要はない。俺は婚約者はいないし、興味すらないんだからな」
婚約者がいない、は……まぁそうなのだろう。
いたらこんな得体のしれない女を屋敷に置いておくはずがない。
この二か月ちょっと、オズ様が女性と懇意にしているところもみたことはないし。
「公爵家の方で婚約者がいないというのはすごく珍しいですよね」
大体貴族というものは子供の頃に親によって婚約者を決められるというのに。
「うちは親が自由恋愛を推奨してたからな。相手がいなければ跡継ぎは養子でも良いと、許可も出されてる」
「そ、そうなんですか……」
公爵家としては異例だけれど、本人の意思が尊重されるというのは素敵なことだと思う。
親同士に決められた結婚で不幸になったという話はよく聞くものだし。
「そういう君は?」
「へ?」
「君は男爵家と言えど貴族だろう。その……婚約者はいなかったのか?」
眉間にしわを刻んですごむように尋ねるオズ様。
こ、怖い……!!
何でこんなに不機嫌に!?
「わ、私は四歳頃からいてもいないような存在だったので、婚約者はおろか友人すらいませんでしたからね!? それに、そもそも、オズ様と同じでそういうものに興味なんてありませんっっ!!」
なぜだろう。
オズ様には誤解されたくない。
思わず迫るように顔を近づけ否定すると、オズ様が「わ、わかった!! わかったから!! 近い!!」と私の両肩を押し返す。
「こほんっ。まぁ、あれだ。お互いそんな存在はいないのだから、結婚云々の心配はいらない。君がいたい思うまで、君が大切だと思う人間ができるまで、ジュローデルの屋敷にいると良い。オレも、まる子も、カンタロウも、そう思ってる」
赤い瞳がまっすぐに私を見つめる。
無表情なのに、その言葉一つ一つから優しさが伝わってくる。
あぁ……やっぱり私、オズ様好きだなぁ……。
……………………好き!?!?
いやいやいや!! 違う!! 違うよ!?
そういう好きとかじゃないわよ!?
わ、私……え……これ……。
「セシリア」
「ひゃい!?」
思わず声がひっくり返ってしまった。
「ついたぞ。……どうした? 顔が赤いが……」
気づけば馬車は停車し、窓の外は王都の検問所のようだった。
この中はもう王都だ。
「い、いえ!! なんでもないですっ!!」
「? そうか? ここを抜けたらすぐに病院まで向かう。いいな?」
「はい。心の準備はできています!!」
私が言うと、オズ様は口角をわずかに上げて頷いた。
やってやる。
はやく終わらせて、皆一緒にトレンシスの町に帰るんだ──!!
私は顔を見られないように外套のフードを目深にかぶり、馬車の中、オズ様の向かいの席に座る。
御者はまる子とカンタロウが務め、私たちは森を抜けた。
驚いたことに、森への出入り口にはちゃんと門があり、区切られていたのだ。
「こっち側にちゃんと道があったんですね」
「君が森に入ったのは正規ルートではないからな。町の者は皆ここから出入りする。地図に乗っていない町とはいえ、公爵領。きちんと整備されている。まぁ、噂のおかげで安易に森に入る馬鹿はめったにいないがな」
はいすみません。
滅多にいない馬鹿がここにいます。
でも本当に驚いた。
入り組んだ場所にあるとはいえ、男爵領の東側にちゃんと門があるだなんて知らなかったもの。
男爵家の裏の森だって、森の先は行き止まりなのだと思っていたくらいだし。
ということは、お父様たちは知っていたのよね。
裏の森が、公爵領に続いていることを……。
「セシリア、大丈夫か?」
「へ?」
私がぼんやりと考えていると、オズ様が心配そうに私を覗き込んだ。
「男爵領に来るのは久しぶりだろう? 大丈夫か?」
「あ……」
私がフェブリール男爵家を出て二か月と少しが経った。
以前は考えるだけで胸が苦しくなったものだけれど、今はもうそんなこともない。
それはきっと、オズ様達が私の居場所をくれたから。
「大丈夫です。私にはオズ様が……。優しい皆さんがいる、トレンシスの町がありますから」
私はあの町の人達が大好きだ。
だからオズ様が良いと言ってくれる限りは、ジュローデル公爵領にいたい。
でも──きっとそう遠くない未来、私は行かねばならない。
オズ様は公爵様だもの。
いずれは綺麗な奥様を迎えて、公爵領を盛り立てていかねばならないもの。
いつまでもお世話になるわけにはいかない。
私がオズ様の幸せの邪魔をしてはいけない。
オズ様がご結婚される。
その時には、まる子たちが何と言おうとすぐにオズ様に送ってもらおう。
私を、次の世へ──。
痛み無く。苦しみなく。楽に。綺麗に。
最後に見るのは、私は、オズ様のお顔が良い。
「セシリア? どうした? 何か考え事か?」
「へ? あ、えっと……はい。オズ様のことを考えていました」
「は!?」
いや何その驚き様は。
茹でられたみたいに顔が真っ赤なんですけど!?
「お、俺のことというのは……」
「あー……その、オズ様が結婚する日の……事?」
「………………は?」
今度はものすごいこわばった顔で固まってしまわれた!?
微妙に不機嫌そうなのはなぜ!?
「あ、あの、オズ様?」
「そんな心配を君がする必要はない。俺は婚約者はいないし、興味すらないんだからな」
婚約者がいない、は……まぁそうなのだろう。
いたらこんな得体のしれない女を屋敷に置いておくはずがない。
この二か月ちょっと、オズ様が女性と懇意にしているところもみたことはないし。
「公爵家の方で婚約者がいないというのはすごく珍しいですよね」
大体貴族というものは子供の頃に親によって婚約者を決められるというのに。
「うちは親が自由恋愛を推奨してたからな。相手がいなければ跡継ぎは養子でも良いと、許可も出されてる」
「そ、そうなんですか……」
公爵家としては異例だけれど、本人の意思が尊重されるというのは素敵なことだと思う。
親同士に決められた結婚で不幸になったという話はよく聞くものだし。
「そういう君は?」
「へ?」
「君は男爵家と言えど貴族だろう。その……婚約者はいなかったのか?」
眉間にしわを刻んですごむように尋ねるオズ様。
こ、怖い……!!
何でこんなに不機嫌に!?
「わ、私は四歳頃からいてもいないような存在だったので、婚約者はおろか友人すらいませんでしたからね!? それに、そもそも、オズ様と同じでそういうものに興味なんてありませんっっ!!」
なぜだろう。
オズ様には誤解されたくない。
思わず迫るように顔を近づけ否定すると、オズ様が「わ、わかった!! わかったから!! 近い!!」と私の両肩を押し返す。
「こほんっ。まぁ、あれだ。お互いそんな存在はいないのだから、結婚云々の心配はいらない。君がいたい思うまで、君が大切だと思う人間ができるまで、ジュローデルの屋敷にいると良い。オレも、まる子も、カンタロウも、そう思ってる」
赤い瞳がまっすぐに私を見つめる。
無表情なのに、その言葉一つ一つから優しさが伝わってくる。
あぁ……やっぱり私、オズ様好きだなぁ……。
……………………好き!?!?
いやいやいや!! 違う!! 違うよ!?
そういう好きとかじゃないわよ!?
わ、私……え……これ……。
「セシリア」
「ひゃい!?」
思わず声がひっくり返ってしまった。
「ついたぞ。……どうした? 顔が赤いが……」
気づけば馬車は停車し、窓の外は王都の検問所のようだった。
この中はもう王都だ。
「い、いえ!! なんでもないですっ!!」
「? そうか? ここを抜けたらすぐに病院まで向かう。いいな?」
「はい。心の準備はできています!!」
私が言うと、オズ様は口角をわずかに上げて頷いた。
やってやる。
はやく終わらせて、皆一緒にトレンシスの町に帰るんだ──!!