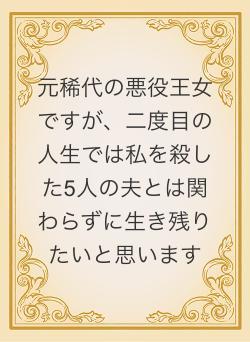「あんたも懲りないわねぇ。まーた怒られてそっぽ向かれるのがオチよ?」
「いいのっ。それでも私は、このままにしてほしくはないから」
私は、ルーシア様みたいに思われていないからもう無理だけど、愛されているというのにそれがわからないまま、この場所に馴染めず悲しみのまま人生を終えてほしくはない。
「はぁ……。あんたって、自分のことにはものすごい後ろ向き発言してるのに、変なところで前向きっていうか……意外と頑固よね」
「まぁまぁ、それがセシリアの良いところだよ、カンタロウ。あぁ、着いたね」
話をしているうちに孤児院に到着した。
空はもうオレンジ色に染まり、きっとオズ様ももう少しで帰ってきてしまう。
まぁ、書き置きをしておいたから大丈夫だとは思うけれど。
「こんばんはー」
「はい」
木の扉を叩いて声をかけると、すぐに出てきたのは私が会いに来た目的人物であるルーシア様だった。
私を見るなりに眉を顰めて、あからさまな拒否反応を示すルーシア様。
でもどんな顔をしても無駄だ。
常日頃から虫けらを見るような目で見られてきて、むしろそれが通常運転な私には効きはしないわ!!
「何の用ですの?」
「ルーシア様、あなたにお話があって参りました」
「私にはありませんわ。お帰りになって」
「嫌です」
「!!」
「ルーシア様がお話を聞いてくれるまで、私、帰りません」
初めてかもしれない。
人に対してこんな風にわがままを言うのは。
だけどどうしても、今は譲れない。
思いのこもったカップケーキを、彼女に食べてもらいたいから。
「……はぁ……。わかりましたわ。今は小さな子たちがまだお勉強中ですので、外でもよろしくて?」
「はい!! ありがとうございます!!」
***
ルーシア様に連れられてやってきたのは、孤児院の裏庭。
小さな畑が耕してあり、そこにはジュローデル公爵家のような薬草などではなく、おいしそうな野菜が育てられている。
そんな畑の前のベンチに、二人並んで座る。
「で、何ですの? 私に話とは」
「あ……、え、えっと……。ルーシア様、その……」
いざとなるとどう切り出せば良いのかわからずに、持っていたバスケットをぎゅっと握りしめる。
「はぁ……本当、腹の立つ方」
「え?」
「男爵家で身分は低くても、魔力がなくても、追い出されることなくデビュタントまでして、そのうえジュローデル公爵家にまで取り入って……。私は……家に置いてもらうことも、デビュタントをさせてもらうこともなかったのに……」
「っ……」
そうか……。
7歳の魔力測定式の後孤児院に入れられたルーシア様は、デビュタントを過ごしていないんだ。
私ですら、たとえお下がりでおばあ様がデビュタントで着ていた時代遅れのドレスを着たとしても、踊る事すら許されなかったとしても、ちゃんと陛下へのあいさつはさせてもらえたのに……。
デビュタントはすべての未成年貴族のあこがれの一つ。
デビュタントを経て成人と認められる部分が大きく、大切な儀式だ。
それをすることもなく、ご両親の思いもわからないままここに送られたルーシア様は、いったいどんな気持ちで今までいたのだろう。
「何で私ばっかり……。貴族に生まれたにもかかわらず、掃除をしたり、洗濯をしたり、料理までしなくてはならないの?」
あぁ、でも、それは──。
「……ルーシア様だけではないです」
「っ、何ですって?」
碧眼の瞳が鋭く私を睨みつける。
だけど怯むわけにはいかない。
「ここの子たちは皆、分担して料理や掃除、お洗濯をしているではないですか。……私は……たった一人で、その全てを10年以上行ってまいりました」
「!? すべてを……一人で、ですって? そんな……だってあなた、男爵家といえど貴族でしょう!?それも姉の聖女認定で多額の援助金まである家が……。使用人は──」
「皆辞めました。あの頃はわからなかったけれど、耐えられなかったのでしょうね。お給金も支払われない月があったり、些細なことで鞭で打たれたり、料理が気に入らないからとせっかく作ったものもひっくり返してダメになる日々が……」
私はもっといろんな目にあってきたけれど、ずっとそれは自分が駄目だから叱られているのだと、それが当然で、不当なものであるはずがないと思い込んでいた。
もっと頑張って役に立てばきっと……。そう思っていたからこそ耐えてきたのだと思う。
「使用人がいなくなって、私はすべての仕事をするようになりました。私こそが、あの家の使用人だったのです」
それを言葉にするのはまだ胸が痛むけれど、彼女には話すべきだと思った。
「っ、じゃぁ、ローゼリア嬢が聖女になってから、あなたが王都に来ることがなかったのは……。何年もあなたの顔を見なかったのは……」
「……家で、仕事をしていたからです」
本当は行きたかった。
だって昔、ルーシア様にお会いしたあの日、別れ際に約束したのだから。
“今度は王都のタウンハウスにも遊びに来てくださいましね”
“はい!! ぜひ!!”
ルーシア様のブロディジィ公爵領はここから遠い。
だから隣の王都にあるタウンハウスで会おうと、約束したのだ。
忘れてなんかいない。
「一年目は、今だけだ、お姉様の聖女修行や王妃教育が忙しいから仕方がない。来年こそは会いに行ける。二年目は、まだまだ私が駄目だから、王都に連れていってはもらえないんだ。もっと要領よくできるようにならないと。三年目は、また会いに行けなかった。私が駄目で、出涸らしだから……。そうして四年、五年、十年以上を過ごしてきました。そして──諦めた」
「あなた……」
「私がオズ様のところにいるのは、婚約とか結婚とか、そういうのじゃない。私は……私は男爵家を出て、オズ様に拾っていただいたのです」
まさか来世に送ってもらうために、と言うわけにはいかないのでひどくぼんやりとした言い方になってしまったけれど、きっと大まかには伝わっただろう。
「ルーシア様、これを」
そう持っていたバスケットを呆然としたままの彼女に差し出す。
「これは?」
「開けてみてください」
「?」
訝しげに首をかしげながら、ルーシア様はバスケットを受け取りゆっくりと開けていく。
「これは……カップケーキ?」
「はい。食べてみてください。焼きたてです」
「……」
難しそうな顔をしながらも、一口、ルーシア様がカップケーキをかじった瞬間、その碧眼の瞳が大きく見開かれた。
「!! これ……この味……お母様、の……? 何で……何であなたが……」
「公爵夫妻が先ほど訪ねて来られたんです。多額の寄付をもって」
「寄付、ですって?」
「はい。孤児院へ。夫妻は年に一度、孤児院に寄付をしに来られているのだそうです。なぜだかわかりますか?」
私の問いかけに、ルーシア様は首を横に振った。
「ルーシア様のため、です」
「私の……?」
「はい。地方によっては孤児院の経営が立ち行かなくなり、子どもたちが質素な生活を強いられ不当な扱いをされる場所もあるのは、ルーシア様もご存じですよね?」
「え、えぇ……」
悲しいけれど、行政がすべての孤児院を監視して手を回すことができないのが現実だ。
うちの男爵領の孤児院のように、貧しい場所はたくさんある。
「ルーシア様に,、そんな思いをさせたくないからです。ここまで来て、多額の寄付をしてくださいるのも。突然カップケーキを作ってほしいとわけのわからないお願いをしたのにそれに応え、ジュローデル公爵家の厨房で手ずからつくて下さったのも。その理由が、まだわかりませんか? その思いが、まだ伝わりませんか?」
そうルーシア様を見ると、唇をキュッと噛み締めて、目には涙が浮かんでいた。
理解したはずだ。
まだ幼かった七歳の頃の彼女のままじゃない。
十年をすごして立派な大人となった彼女だから。
「っ……私を……嫌いになったわけじゃ、なかったのですね……? 私は……っ、大切に、してもらっていたのですね……っ?」
ぽろり、ぽろりと両の目から零れ落ちる雫。
そしてそれを皮切りに、次から次へと涙は止めどなく溢れる。
「っ、ふっ……お父様……っ、お母様ぁ……っ!!」
私は何を言うでもなく、ただルーシア様の隣で彼女が泣き止むまでの間、その背を撫で続けるのだった。
「いいのっ。それでも私は、このままにしてほしくはないから」
私は、ルーシア様みたいに思われていないからもう無理だけど、愛されているというのにそれがわからないまま、この場所に馴染めず悲しみのまま人生を終えてほしくはない。
「はぁ……。あんたって、自分のことにはものすごい後ろ向き発言してるのに、変なところで前向きっていうか……意外と頑固よね」
「まぁまぁ、それがセシリアの良いところだよ、カンタロウ。あぁ、着いたね」
話をしているうちに孤児院に到着した。
空はもうオレンジ色に染まり、きっとオズ様ももう少しで帰ってきてしまう。
まぁ、書き置きをしておいたから大丈夫だとは思うけれど。
「こんばんはー」
「はい」
木の扉を叩いて声をかけると、すぐに出てきたのは私が会いに来た目的人物であるルーシア様だった。
私を見るなりに眉を顰めて、あからさまな拒否反応を示すルーシア様。
でもどんな顔をしても無駄だ。
常日頃から虫けらを見るような目で見られてきて、むしろそれが通常運転な私には効きはしないわ!!
「何の用ですの?」
「ルーシア様、あなたにお話があって参りました」
「私にはありませんわ。お帰りになって」
「嫌です」
「!!」
「ルーシア様がお話を聞いてくれるまで、私、帰りません」
初めてかもしれない。
人に対してこんな風にわがままを言うのは。
だけどどうしても、今は譲れない。
思いのこもったカップケーキを、彼女に食べてもらいたいから。
「……はぁ……。わかりましたわ。今は小さな子たちがまだお勉強中ですので、外でもよろしくて?」
「はい!! ありがとうございます!!」
***
ルーシア様に連れられてやってきたのは、孤児院の裏庭。
小さな畑が耕してあり、そこにはジュローデル公爵家のような薬草などではなく、おいしそうな野菜が育てられている。
そんな畑の前のベンチに、二人並んで座る。
「で、何ですの? 私に話とは」
「あ……、え、えっと……。ルーシア様、その……」
いざとなるとどう切り出せば良いのかわからずに、持っていたバスケットをぎゅっと握りしめる。
「はぁ……本当、腹の立つ方」
「え?」
「男爵家で身分は低くても、魔力がなくても、追い出されることなくデビュタントまでして、そのうえジュローデル公爵家にまで取り入って……。私は……家に置いてもらうことも、デビュタントをさせてもらうこともなかったのに……」
「っ……」
そうか……。
7歳の魔力測定式の後孤児院に入れられたルーシア様は、デビュタントを過ごしていないんだ。
私ですら、たとえお下がりでおばあ様がデビュタントで着ていた時代遅れのドレスを着たとしても、踊る事すら許されなかったとしても、ちゃんと陛下へのあいさつはさせてもらえたのに……。
デビュタントはすべての未成年貴族のあこがれの一つ。
デビュタントを経て成人と認められる部分が大きく、大切な儀式だ。
それをすることもなく、ご両親の思いもわからないままここに送られたルーシア様は、いったいどんな気持ちで今までいたのだろう。
「何で私ばっかり……。貴族に生まれたにもかかわらず、掃除をしたり、洗濯をしたり、料理までしなくてはならないの?」
あぁ、でも、それは──。
「……ルーシア様だけではないです」
「っ、何ですって?」
碧眼の瞳が鋭く私を睨みつける。
だけど怯むわけにはいかない。
「ここの子たちは皆、分担して料理や掃除、お洗濯をしているではないですか。……私は……たった一人で、その全てを10年以上行ってまいりました」
「!? すべてを……一人で、ですって? そんな……だってあなた、男爵家といえど貴族でしょう!?それも姉の聖女認定で多額の援助金まである家が……。使用人は──」
「皆辞めました。あの頃はわからなかったけれど、耐えられなかったのでしょうね。お給金も支払われない月があったり、些細なことで鞭で打たれたり、料理が気に入らないからとせっかく作ったものもひっくり返してダメになる日々が……」
私はもっといろんな目にあってきたけれど、ずっとそれは自分が駄目だから叱られているのだと、それが当然で、不当なものであるはずがないと思い込んでいた。
もっと頑張って役に立てばきっと……。そう思っていたからこそ耐えてきたのだと思う。
「使用人がいなくなって、私はすべての仕事をするようになりました。私こそが、あの家の使用人だったのです」
それを言葉にするのはまだ胸が痛むけれど、彼女には話すべきだと思った。
「っ、じゃぁ、ローゼリア嬢が聖女になってから、あなたが王都に来ることがなかったのは……。何年もあなたの顔を見なかったのは……」
「……家で、仕事をしていたからです」
本当は行きたかった。
だって昔、ルーシア様にお会いしたあの日、別れ際に約束したのだから。
“今度は王都のタウンハウスにも遊びに来てくださいましね”
“はい!! ぜひ!!”
ルーシア様のブロディジィ公爵領はここから遠い。
だから隣の王都にあるタウンハウスで会おうと、約束したのだ。
忘れてなんかいない。
「一年目は、今だけだ、お姉様の聖女修行や王妃教育が忙しいから仕方がない。来年こそは会いに行ける。二年目は、まだまだ私が駄目だから、王都に連れていってはもらえないんだ。もっと要領よくできるようにならないと。三年目は、また会いに行けなかった。私が駄目で、出涸らしだから……。そうして四年、五年、十年以上を過ごしてきました。そして──諦めた」
「あなた……」
「私がオズ様のところにいるのは、婚約とか結婚とか、そういうのじゃない。私は……私は男爵家を出て、オズ様に拾っていただいたのです」
まさか来世に送ってもらうために、と言うわけにはいかないのでひどくぼんやりとした言い方になってしまったけれど、きっと大まかには伝わっただろう。
「ルーシア様、これを」
そう持っていたバスケットを呆然としたままの彼女に差し出す。
「これは?」
「開けてみてください」
「?」
訝しげに首をかしげながら、ルーシア様はバスケットを受け取りゆっくりと開けていく。
「これは……カップケーキ?」
「はい。食べてみてください。焼きたてです」
「……」
難しそうな顔をしながらも、一口、ルーシア様がカップケーキをかじった瞬間、その碧眼の瞳が大きく見開かれた。
「!! これ……この味……お母様、の……? 何で……何であなたが……」
「公爵夫妻が先ほど訪ねて来られたんです。多額の寄付をもって」
「寄付、ですって?」
「はい。孤児院へ。夫妻は年に一度、孤児院に寄付をしに来られているのだそうです。なぜだかわかりますか?」
私の問いかけに、ルーシア様は首を横に振った。
「ルーシア様のため、です」
「私の……?」
「はい。地方によっては孤児院の経営が立ち行かなくなり、子どもたちが質素な生活を強いられ不当な扱いをされる場所もあるのは、ルーシア様もご存じですよね?」
「え、えぇ……」
悲しいけれど、行政がすべての孤児院を監視して手を回すことができないのが現実だ。
うちの男爵領の孤児院のように、貧しい場所はたくさんある。
「ルーシア様に,、そんな思いをさせたくないからです。ここまで来て、多額の寄付をしてくださいるのも。突然カップケーキを作ってほしいとわけのわからないお願いをしたのにそれに応え、ジュローデル公爵家の厨房で手ずからつくて下さったのも。その理由が、まだわかりませんか? その思いが、まだ伝わりませんか?」
そうルーシア様を見ると、唇をキュッと噛み締めて、目には涙が浮かんでいた。
理解したはずだ。
まだ幼かった七歳の頃の彼女のままじゃない。
十年をすごして立派な大人となった彼女だから。
「っ……私を……嫌いになったわけじゃ、なかったのですね……? 私は……っ、大切に、してもらっていたのですね……っ?」
ぽろり、ぽろりと両の目から零れ落ちる雫。
そしてそれを皮切りに、次から次へと涙は止めどなく溢れる。
「っ、ふっ……お父様……っ、お母様ぁ……っ!!」
私は何を言うでもなく、ただルーシア様の隣で彼女が泣き止むまでの間、その背を撫で続けるのだった。