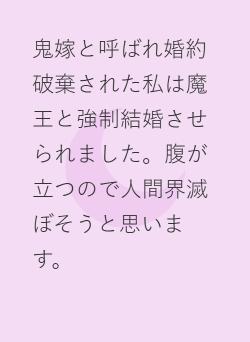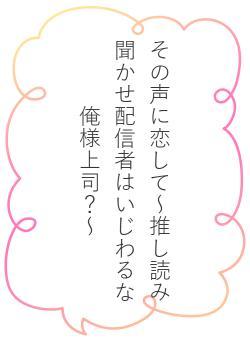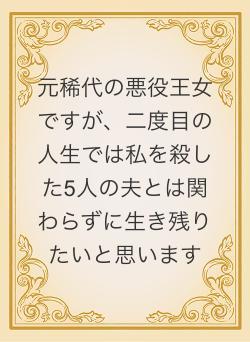Sideオズ
「寝たか……」
俺の腕の中で泣きつかれてすやすやと眠り始めたあどけない寝顔を見て、ふぅ、と息をつく。
こういうのは慣れてないんだ。
約二週間前、森で寝る前の散歩をしていると、一人の女性を見つけた。
白銀の長い髪。
雪のように白い肌。
そして赤い瞳。
ゼイオンとクレンシスがいつも話していた女性だと、すぐにわかった。
いつもいつも俺のところに来ては、その女性の話をしていたからな。
料理が絶品だということも。
いつも理不尽に怒鳴られていることも。
よくぶたれていることも。
彼らは人とは違う。
姿かたちも違えば考え方もまた違うし、何より人の醜さを長い間見てきた彼らは、俺以上にあまり人を好まない。
そんな彼らが、彼女のことだけはいつも気にかけていた。
だからこそ、俺も気になってしまったんだ。
赤い瞳は魔力が高い証。
俺や《《師匠》》以外にそんな人間がいるということが、嬉しかったのもあるんだと思う。
実際に会った彼女は、俺を見るなりにこう言った。
“あなたが……悪い魔法使いさん、ですか?”
思わず思考が停止した。
それは俺が、俺に近寄らせないように流した噂だからだ。
近寄らせないように流したというのに、逆に噂を知っていながら俺を探す人間がいるとか思わないだろう!?
よっぽどの変人か、あるいは妙な正義感で悪い魔法使いを倒しに来た阿保か、それとも好奇心に駆られてきてしまった残念な奴か。
だが彼女はどれも違った。
俺に用事があるから探していたと言われて話を聞こうと屋敷に連れて帰ったが、抱き上げた彼女の身体は細く軽く、到底健康そうには見えなかった。
誰かを抱きかかえたことなんてないから、どれが正解かなんてわからないが。
抱き上げられて涙目で顔を赤くして見上げる彼女に、少しばかり動揺したのは俺の心の内に留めておこうと思う。
至近距離で見た彼女の顔。
目の下にうっすらとクマができていることに気づいた俺は、屋敷に戻ってすぐ、就寝前に飲む用に作っていた魔法薬茶を彼女に出した。
寝る前に森を散歩してから体力を使ってこの茶を飲んで眠ると、悪夢に起きたとしても身体をすっきりとした状態で、短い時間でもしっかり眠ることができる。
そうして聞いた彼女の話は、俺が想像していたよりもずっと濃く、重かった。
ゼイオン達から話は聞いていたが、彼女の扱いは娘や妹への扱いではない。
メイド、いや、奴隷のような扱いだ。
聖女だという彼女の姉のことは知っている。
王太子がよく自慢していたからな。
未だ聖女の力を使えたことはないが、とても美しく可憐な女性なのだと。
身体を弱くして生まれたが、いつか自分は聖女と結婚した史上最も幸福な王として君臨するだろうとか馬鹿なことを言っていたが、あれは見かけに騙されて肝心なものが見えていないんだろうな。
悪気のない悪意ほど質の悪いものはない。
彼女は自分を出涸らしだと言った。
名前を呼ばれなくなって、いったいどのくらいの年月が経っていたのか……。
とっさに俺が『セシリア』とつけていた。
『セシリア』。
薬草の中で最も美しく、聖なる薬草と呼ばれる幻の薬草。
なぜか、彼女にぴったりだと思ったんだ。
弱弱しくて、今にも消えそうなほど自信なさげですぐに謝る。
だけど芯の強さと心の美しさは、隠せるようなものではなかった。
それから約二週間、彼女の前世の知識というものに助けられて、町の季節病も少しずつ落ち着き始めた。
今回は少し疲れていたのもあり、病が移って俺も倒れてしまったが……。
それもこれもあのバカ王女のせいだな。
やっぱり王都なんかに行くもんじゃない。
俺のこの赤い瞳に畏怖しながらも、その地位と容姿に群がってくる女性の筆頭──ルビィ・フォン・アーレンシュタイン。
濃い化粧に、もつれないか心配になる程のぐるぐる巻いた髪。
甲高い声に傲慢な態度。
兄である王太子は気弱で温厚だが、そんな彼らが甘やかしたからこそ出来上がったモンスター王女。
まぁ、聖女と言われているセシリアの姉があぁなるのも時間の問題だろうな。
優しいふりをした悪意の塊である分、こちらの方が質が悪いが……。
今はまだちらほらと患者がいるぐらいだが、王都の病のピークはこれからになるだろう。
今年の病は少しばかり治りが遅く広がりやすい。
その時王家がどう出るか……はぁ、頭が痛い。
「……とりあえず、これをどうすべきか」
俺は腕の中ですやすやと眠る女性を見る。
俺のために危険な水中エリアにまで入って薬草を採り、薬茶を作ってくれたセシリア。
彼女の魔力が、まさか聖女の力だったなんてな……。
図らずも、その名がぴったりと合う人間だったということか。
俺の両親のこと、俺の罪を話すことができたというのは、俺が彼女を信用しているということなのか……自分でも驚いた。
そして『悪い魔法使い』の噂の意図と意味に気づいても尚、彼女は俺を『良い魔法使い』だと言う。
彼女に現実を突きつけたというのに、泣きながらも、こんなにも無防備に俺に縋り付く。
まったく、予測不可能だな、この女性は。
これはあれか。刷り込みか?
名を与えたから俺を母のように思うとかそういう……?
……考えるのはやめよう。
「まったく……本当に、無防備なものだな」
出会った時に抱き上げた時よりもいくらか柔らかくなった感触に安心を覚えながらも、妙に顔に熱が集まる。
まさか……下、着てないのか!?
っ、そうか、水中エリアで!?
大方ドレスだけ脱いで入って、薬草を取って出てきた後にでも下着を脱いでまたドレスだけ着たんだろうがそれはダメだ!!
女性は身体を冷やすべきではないと母上が言っていたし、何よりそんな姿で男の部屋に来るとか何考えてるんだ!?
と、とりあえず離さねば……!!
「!?」
離れない!?
何だこれは……!!
すごい力で俺の服にしがみついてて離れない!!
「くそっ、なんて力だ……!! まる子!! カンタロウ!!」
たまらずにまる子とカンタロウを呼べば、「はいよー」と軽い返事をしながら現れた二匹。
俺もこの二匹のこの呼び名にすっかり慣れてしまった。
「これをなんとかしてくれ……!!」
なんて力してるんだ。
これが長年の家事で鍛えた力だというのか……!!
「あらぁ……。もうラブラブって感じ?」
「オズ、がっついたら嫌われるよ」
「何もしてない!! そんな関係じゃない!! 早く何とかしろ!!」
ニマニマとした笑みを浮かべてこっちを見るな。
俺は何もしていない。
「もー、意気地なしね」
「そんなだから彼女できないんだよ」
「お前ら……」
余計なお世話だ。
そもそもそんなものいらないし、この家を継ぐ者がいないなら養子でもとって継がせればいいとも思っている。
それに、俺の見た目にしか興味のない女性に来られても逆に迷惑だ。
「仕方ないなぁ」
言いながら二匹は人型に変身すると、二人がかりでセシリアを離しにかかる。が──。
「……しっかり張り付いてるわね」
「離れたくないっていう確固たる意志を感じるよ。これはダメだね」
諦めた!?
「とりあえず布団に入れたげて。風邪ひくから。じゃ、私たちはこれで」
「ごゆっくりー」
「は!? ちょ、お、おい!!」
信じられん……。
この状態を投げて出ていってしまった。
とりあえず彼女まで身体を壊してもいけない。
俺は彼女をそのまま布団に引き入れると、抱き込んだ状態でベッドに一緒に転げた。
「……」
これは仕方ないんだ。
別にやましい気持ちはない。
彼女の手が緩んだら、すぐに離れて俺はソファに移動しよう。
そう必死に意識を保っていた俺だが、セシリアが作った薬茶のおかげか何なのか、押し寄せてきた眠気には勝てず、そのまま眠りに落ちてしまうのだった。
「寝たか……」
俺の腕の中で泣きつかれてすやすやと眠り始めたあどけない寝顔を見て、ふぅ、と息をつく。
こういうのは慣れてないんだ。
約二週間前、森で寝る前の散歩をしていると、一人の女性を見つけた。
白銀の長い髪。
雪のように白い肌。
そして赤い瞳。
ゼイオンとクレンシスがいつも話していた女性だと、すぐにわかった。
いつもいつも俺のところに来ては、その女性の話をしていたからな。
料理が絶品だということも。
いつも理不尽に怒鳴られていることも。
よくぶたれていることも。
彼らは人とは違う。
姿かたちも違えば考え方もまた違うし、何より人の醜さを長い間見てきた彼らは、俺以上にあまり人を好まない。
そんな彼らが、彼女のことだけはいつも気にかけていた。
だからこそ、俺も気になってしまったんだ。
赤い瞳は魔力が高い証。
俺や《《師匠》》以外にそんな人間がいるということが、嬉しかったのもあるんだと思う。
実際に会った彼女は、俺を見るなりにこう言った。
“あなたが……悪い魔法使いさん、ですか?”
思わず思考が停止した。
それは俺が、俺に近寄らせないように流した噂だからだ。
近寄らせないように流したというのに、逆に噂を知っていながら俺を探す人間がいるとか思わないだろう!?
よっぽどの変人か、あるいは妙な正義感で悪い魔法使いを倒しに来た阿保か、それとも好奇心に駆られてきてしまった残念な奴か。
だが彼女はどれも違った。
俺に用事があるから探していたと言われて話を聞こうと屋敷に連れて帰ったが、抱き上げた彼女の身体は細く軽く、到底健康そうには見えなかった。
誰かを抱きかかえたことなんてないから、どれが正解かなんてわからないが。
抱き上げられて涙目で顔を赤くして見上げる彼女に、少しばかり動揺したのは俺の心の内に留めておこうと思う。
至近距離で見た彼女の顔。
目の下にうっすらとクマができていることに気づいた俺は、屋敷に戻ってすぐ、就寝前に飲む用に作っていた魔法薬茶を彼女に出した。
寝る前に森を散歩してから体力を使ってこの茶を飲んで眠ると、悪夢に起きたとしても身体をすっきりとした状態で、短い時間でもしっかり眠ることができる。
そうして聞いた彼女の話は、俺が想像していたよりもずっと濃く、重かった。
ゼイオン達から話は聞いていたが、彼女の扱いは娘や妹への扱いではない。
メイド、いや、奴隷のような扱いだ。
聖女だという彼女の姉のことは知っている。
王太子がよく自慢していたからな。
未だ聖女の力を使えたことはないが、とても美しく可憐な女性なのだと。
身体を弱くして生まれたが、いつか自分は聖女と結婚した史上最も幸福な王として君臨するだろうとか馬鹿なことを言っていたが、あれは見かけに騙されて肝心なものが見えていないんだろうな。
悪気のない悪意ほど質の悪いものはない。
彼女は自分を出涸らしだと言った。
名前を呼ばれなくなって、いったいどのくらいの年月が経っていたのか……。
とっさに俺が『セシリア』とつけていた。
『セシリア』。
薬草の中で最も美しく、聖なる薬草と呼ばれる幻の薬草。
なぜか、彼女にぴったりだと思ったんだ。
弱弱しくて、今にも消えそうなほど自信なさげですぐに謝る。
だけど芯の強さと心の美しさは、隠せるようなものではなかった。
それから約二週間、彼女の前世の知識というものに助けられて、町の季節病も少しずつ落ち着き始めた。
今回は少し疲れていたのもあり、病が移って俺も倒れてしまったが……。
それもこれもあのバカ王女のせいだな。
やっぱり王都なんかに行くもんじゃない。
俺のこの赤い瞳に畏怖しながらも、その地位と容姿に群がってくる女性の筆頭──ルビィ・フォン・アーレンシュタイン。
濃い化粧に、もつれないか心配になる程のぐるぐる巻いた髪。
甲高い声に傲慢な態度。
兄である王太子は気弱で温厚だが、そんな彼らが甘やかしたからこそ出来上がったモンスター王女。
まぁ、聖女と言われているセシリアの姉があぁなるのも時間の問題だろうな。
優しいふりをした悪意の塊である分、こちらの方が質が悪いが……。
今はまだちらほらと患者がいるぐらいだが、王都の病のピークはこれからになるだろう。
今年の病は少しばかり治りが遅く広がりやすい。
その時王家がどう出るか……はぁ、頭が痛い。
「……とりあえず、これをどうすべきか」
俺は腕の中ですやすやと眠る女性を見る。
俺のために危険な水中エリアにまで入って薬草を採り、薬茶を作ってくれたセシリア。
彼女の魔力が、まさか聖女の力だったなんてな……。
図らずも、その名がぴったりと合う人間だったということか。
俺の両親のこと、俺の罪を話すことができたというのは、俺が彼女を信用しているということなのか……自分でも驚いた。
そして『悪い魔法使い』の噂の意図と意味に気づいても尚、彼女は俺を『良い魔法使い』だと言う。
彼女に現実を突きつけたというのに、泣きながらも、こんなにも無防備に俺に縋り付く。
まったく、予測不可能だな、この女性は。
これはあれか。刷り込みか?
名を与えたから俺を母のように思うとかそういう……?
……考えるのはやめよう。
「まったく……本当に、無防備なものだな」
出会った時に抱き上げた時よりもいくらか柔らかくなった感触に安心を覚えながらも、妙に顔に熱が集まる。
まさか……下、着てないのか!?
っ、そうか、水中エリアで!?
大方ドレスだけ脱いで入って、薬草を取って出てきた後にでも下着を脱いでまたドレスだけ着たんだろうがそれはダメだ!!
女性は身体を冷やすべきではないと母上が言っていたし、何よりそんな姿で男の部屋に来るとか何考えてるんだ!?
と、とりあえず離さねば……!!
「!?」
離れない!?
何だこれは……!!
すごい力で俺の服にしがみついてて離れない!!
「くそっ、なんて力だ……!! まる子!! カンタロウ!!」
たまらずにまる子とカンタロウを呼べば、「はいよー」と軽い返事をしながら現れた二匹。
俺もこの二匹のこの呼び名にすっかり慣れてしまった。
「これをなんとかしてくれ……!!」
なんて力してるんだ。
これが長年の家事で鍛えた力だというのか……!!
「あらぁ……。もうラブラブって感じ?」
「オズ、がっついたら嫌われるよ」
「何もしてない!! そんな関係じゃない!! 早く何とかしろ!!」
ニマニマとした笑みを浮かべてこっちを見るな。
俺は何もしていない。
「もー、意気地なしね」
「そんなだから彼女できないんだよ」
「お前ら……」
余計なお世話だ。
そもそもそんなものいらないし、この家を継ぐ者がいないなら養子でもとって継がせればいいとも思っている。
それに、俺の見た目にしか興味のない女性に来られても逆に迷惑だ。
「仕方ないなぁ」
言いながら二匹は人型に変身すると、二人がかりでセシリアを離しにかかる。が──。
「……しっかり張り付いてるわね」
「離れたくないっていう確固たる意志を感じるよ。これはダメだね」
諦めた!?
「とりあえず布団に入れたげて。風邪ひくから。じゃ、私たちはこれで」
「ごゆっくりー」
「は!? ちょ、お、おい!!」
信じられん……。
この状態を投げて出ていってしまった。
とりあえず彼女まで身体を壊してもいけない。
俺は彼女をそのまま布団に引き入れると、抱き込んだ状態でベッドに一緒に転げた。
「……」
これは仕方ないんだ。
別にやましい気持ちはない。
彼女の手が緩んだら、すぐに離れて俺はソファに移動しよう。
そう必死に意識を保っていた俺だが、セシリアが作った薬茶のおかげか何なのか、押し寄せてきた眠気には勝てず、そのまま眠りに落ちてしまうのだった。