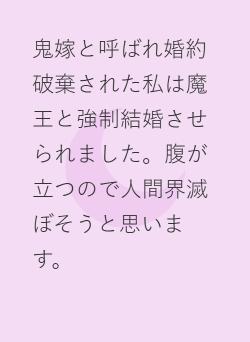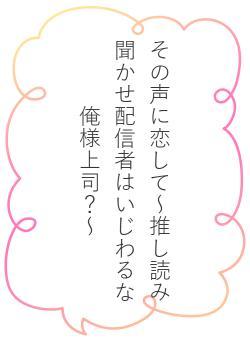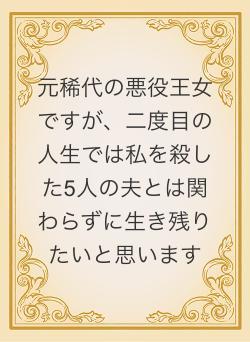「光……魔法……?」
って──聖女しか使えない治癒魔法とかのことよね!?
「わ、私は聖女じゃないし、何かの間違いでは……?」
「いや、間違いない。もともと君が大きな魔力を持っているということはわかっていた。まさかこんな特殊な力だとは思っていなかったが……」
私が魔力を持っているとわかっていた?
私はそんなもの生まれてこの方使ったためしがないのに?
訳が分からず首をかしげる私に、オズ様が補足する。
「君のその赤い目。それは魔力が大量に蓄えられている証だ。俺も、君と同じ色をしているだろう?」
そういえばそうだ。
私の目の色と、オズ様の目の色。
同じ、濃い赤色──。
お父様ともお母様とも姉とも違う色で、不気味だと言われてきた色だけれど、オズ様と一緒の色だと思うと、なんだか少しうれしい。
「君は魔力測定式に行っていないと言っていたな? では姉の時には見学に行ったのではないか?」
「は、はい。お父様やお母様、お姉様と魔力測定の部屋に入った瞬間、魔力測定の石が白く輝いたのを、はっきりと見ました!!」
あの衝撃は忘れられない。
眩い白銀の光。
伝承として知られる聖女の光が、自分の大好きな姉の測定で見ることができるなんて、なんて素晴らしいのだろうと感動した。
「それはおそらく、君の力だ。君の大きすぎる聖なる魔力の方に反応したのだろう、その魔力測定器は」
「えぇ!? じゃ、じゃぁ……」
「聖女は君の方だ。セシリア」
うっそぉ……。
私が……聖女……?
出涸らしじゃ、なかったってこと?
「このジュローデル公爵家は、魔力の高いものも生まれやすく、この目をしていても『あぁ、また魔力の高い子が生まれたか』と普通に思われるが、王都やほかの町では違う。『おかしな目をしている』、『恐ろしい。魔物の子だ』。そんな風に畏怖の目で見られることが多い。この目の色が魔力の高い者の証だということもあまり知られていないし。だが、聖女となれば赤い目への畏怖も覆すだろう。君の待遇も変化するはずだ。……セシリア。君は、どうする? このままここにいるか? それとも親元に帰るか?」
「っ……!!」
親元……お父様とお母様、お姉様のところに……。
オズ様は何でそんなことを言うんだろう?
私が邪魔になったのかしら?
不安になってオズ様を見上げると、私の不安をわかっているかのように息をついて続けた。
「もちろん、俺はいつまでいてくれても構わない。君の実家は今、とても大変みたいだがな」
「大変?」
何かあったのかしら?
借金取り? ──は、もしあったとしても聖女だと思われているお姉様の出生家だから王家が何とかするか。
今だって聖女の養育費として毎月相当量のお金が王家から支払われているし。
それでもお母様やお姉様のドレスや宝飾品をたくさん買ってしまって厳しい月もあるけれど。
「食事を作る者もおらず、掃除をする者も、自分たちの肌や髪の手入れをする者もいないことで仕方なくメイドを雇ったようだが、皆すぐに逃げるようにやめていったようだ。今や家は荒れ放題、身体の手入れも自分ではできないから、髪も肌も荒れてピリピリしているようだな。特に君の母親は」
そうか。
今まで私が全部やってきたから……。
私がいなくなってしまったせいで、お父様とお母様が……お姉様が困ってる……!!
「見てみるか?」
そう言ってチェストテーブルから出して差し出したのは、綺麗な細工が施された銀の手鏡。
「これは?」
「これは望見《のぞみ》の鏡と言って、望む人や場所の今を見ることができるものだ。君の家族の今、見てみるか?」
私の家族の、今……。
見たい。
お父様とお母様、それにお姉様が、私を必要としてくれているところを。
だって私はずっと、それを願っていたのだから。
もしも私を必要としてくれているならば……それならば私は──。
差し出された手鏡を受け取り、家族を思い浮かべると、鏡に映し出された一週間ぶりの家族の姿。
“またメイドはやめたの? 私、これから殿下とデートなのに……”
“あぁかわいそうなローゼリア。お腹もすいたでしょうに……”
“仕方ない。今日もレストランで食べるか。陛下からいただいている今月の金ももうすぐ底をついてしまうが……仕方がない”
元々の美しさはあるものの、髪はパサつき乱れた食生活のせいか肌は荒れて吹き出物まで出ているお姉様とお母様。
あぁ、私がいなくなったから……。
早く帰って綺麗にしてあげないと。
そう思い鏡を返そうとした、刹那──。
“あぁまったく!! あの出涸らしがいなくなったせいで散々だわ!! いったいどこで何をしているのかしら!!”
お母様……。
“本当だ!! 育ててやった恩も忘れて突然にいなくなりおって!!”
お父様……。
“もしかして、攫われて殺されたりしたのかしら……。それとも売られて……?”
やっぱりお姉様だけは心配して── “でも……”
“でも、それならちゃんと従順な代わりのメイドを用意しておいてほしかったわ。出涸らしちゃんみたいな”
────え──……?
「お姉……様……?」
代わりのメイドって……それってまるで……。
“あの子はぐずで駄目だったけど、家事だけはできたからねぇ”
“えぇ。重宝していたのに……私の可愛い──出涸らしちゃん”
まるで、私は家族ではなくて……メイドのようじゃないか──。
“まったく、あいつは一体どこにいるのか”
“生きて帰ってきたら罰を与えないといけないわね”
あぁ……わかっていたじゃないか。
前世の記憶を取り戻したその時から。
うすうす感じていたはずだ。
だから私は、今世がつらいと感じたんでしょう?
だから私は、来世に期待したんでしょう?
だから私は──自らの意思で、あそこを出たんでしょう?
私は愛されてなんていなかった。
その事実が痛くて、苦しくて、目の奥が熱くなって、雫となって零れ落ちる。
「セシ──」
「わかってた……はずなのに……。愛されてないって、わかってたのに……っ」
一度零れ落ちた雫は、とめどなく赤の瞳からあふれ出し、自分でも止めることができない。
こういう時どうすればいいのかわからない。
ただ涙をこぼれさせるしかない私の手に、骨ばった大きなそれがそっと被さった。
「オズ、さま……?」
「どうするか、というのは、俺が決めることはできない。でも、どんな決断をしても、それが君の出したものなら、俺も、まる子も、カンタロウも、それを認めるだろう。君の思いが、一番大切なものなのだから」
「っ……」
一言一言が、ゆっくりと胸にしみて、心が色を変えていくように思えた。
そうだ。
私は一人じゃない。
私を大切に尊重してくれる人たちがいる。
だったらもう──。
あの家は──。
いらない──!!
「うっ……うぅっ……オズざばぁぁぁぁああああ!!」
しがみつくようにオズ様の胸に飛び込めば、一瞬動きを止めた後、そっと優しく包み込んでくれたオズ様。
何を言うわけでもなく、ただ黙って抱きしめ、頭をなでてくれる感触を感じながら、私はそっと目を閉じた。
って──聖女しか使えない治癒魔法とかのことよね!?
「わ、私は聖女じゃないし、何かの間違いでは……?」
「いや、間違いない。もともと君が大きな魔力を持っているということはわかっていた。まさかこんな特殊な力だとは思っていなかったが……」
私が魔力を持っているとわかっていた?
私はそんなもの生まれてこの方使ったためしがないのに?
訳が分からず首をかしげる私に、オズ様が補足する。
「君のその赤い目。それは魔力が大量に蓄えられている証だ。俺も、君と同じ色をしているだろう?」
そういえばそうだ。
私の目の色と、オズ様の目の色。
同じ、濃い赤色──。
お父様ともお母様とも姉とも違う色で、不気味だと言われてきた色だけれど、オズ様と一緒の色だと思うと、なんだか少しうれしい。
「君は魔力測定式に行っていないと言っていたな? では姉の時には見学に行ったのではないか?」
「は、はい。お父様やお母様、お姉様と魔力測定の部屋に入った瞬間、魔力測定の石が白く輝いたのを、はっきりと見ました!!」
あの衝撃は忘れられない。
眩い白銀の光。
伝承として知られる聖女の光が、自分の大好きな姉の測定で見ることができるなんて、なんて素晴らしいのだろうと感動した。
「それはおそらく、君の力だ。君の大きすぎる聖なる魔力の方に反応したのだろう、その魔力測定器は」
「えぇ!? じゃ、じゃぁ……」
「聖女は君の方だ。セシリア」
うっそぉ……。
私が……聖女……?
出涸らしじゃ、なかったってこと?
「このジュローデル公爵家は、魔力の高いものも生まれやすく、この目をしていても『あぁ、また魔力の高い子が生まれたか』と普通に思われるが、王都やほかの町では違う。『おかしな目をしている』、『恐ろしい。魔物の子だ』。そんな風に畏怖の目で見られることが多い。この目の色が魔力の高い者の証だということもあまり知られていないし。だが、聖女となれば赤い目への畏怖も覆すだろう。君の待遇も変化するはずだ。……セシリア。君は、どうする? このままここにいるか? それとも親元に帰るか?」
「っ……!!」
親元……お父様とお母様、お姉様のところに……。
オズ様は何でそんなことを言うんだろう?
私が邪魔になったのかしら?
不安になってオズ様を見上げると、私の不安をわかっているかのように息をついて続けた。
「もちろん、俺はいつまでいてくれても構わない。君の実家は今、とても大変みたいだがな」
「大変?」
何かあったのかしら?
借金取り? ──は、もしあったとしても聖女だと思われているお姉様の出生家だから王家が何とかするか。
今だって聖女の養育費として毎月相当量のお金が王家から支払われているし。
それでもお母様やお姉様のドレスや宝飾品をたくさん買ってしまって厳しい月もあるけれど。
「食事を作る者もおらず、掃除をする者も、自分たちの肌や髪の手入れをする者もいないことで仕方なくメイドを雇ったようだが、皆すぐに逃げるようにやめていったようだ。今や家は荒れ放題、身体の手入れも自分ではできないから、髪も肌も荒れてピリピリしているようだな。特に君の母親は」
そうか。
今まで私が全部やってきたから……。
私がいなくなってしまったせいで、お父様とお母様が……お姉様が困ってる……!!
「見てみるか?」
そう言ってチェストテーブルから出して差し出したのは、綺麗な細工が施された銀の手鏡。
「これは?」
「これは望見《のぞみ》の鏡と言って、望む人や場所の今を見ることができるものだ。君の家族の今、見てみるか?」
私の家族の、今……。
見たい。
お父様とお母様、それにお姉様が、私を必要としてくれているところを。
だって私はずっと、それを願っていたのだから。
もしも私を必要としてくれているならば……それならば私は──。
差し出された手鏡を受け取り、家族を思い浮かべると、鏡に映し出された一週間ぶりの家族の姿。
“またメイドはやめたの? 私、これから殿下とデートなのに……”
“あぁかわいそうなローゼリア。お腹もすいたでしょうに……”
“仕方ない。今日もレストランで食べるか。陛下からいただいている今月の金ももうすぐ底をついてしまうが……仕方がない”
元々の美しさはあるものの、髪はパサつき乱れた食生活のせいか肌は荒れて吹き出物まで出ているお姉様とお母様。
あぁ、私がいなくなったから……。
早く帰って綺麗にしてあげないと。
そう思い鏡を返そうとした、刹那──。
“あぁまったく!! あの出涸らしがいなくなったせいで散々だわ!! いったいどこで何をしているのかしら!!”
お母様……。
“本当だ!! 育ててやった恩も忘れて突然にいなくなりおって!!”
お父様……。
“もしかして、攫われて殺されたりしたのかしら……。それとも売られて……?”
やっぱりお姉様だけは心配して── “でも……”
“でも、それならちゃんと従順な代わりのメイドを用意しておいてほしかったわ。出涸らしちゃんみたいな”
────え──……?
「お姉……様……?」
代わりのメイドって……それってまるで……。
“あの子はぐずで駄目だったけど、家事だけはできたからねぇ”
“えぇ。重宝していたのに……私の可愛い──出涸らしちゃん”
まるで、私は家族ではなくて……メイドのようじゃないか──。
“まったく、あいつは一体どこにいるのか”
“生きて帰ってきたら罰を与えないといけないわね”
あぁ……わかっていたじゃないか。
前世の記憶を取り戻したその時から。
うすうす感じていたはずだ。
だから私は、今世がつらいと感じたんでしょう?
だから私は、来世に期待したんでしょう?
だから私は──自らの意思で、あそこを出たんでしょう?
私は愛されてなんていなかった。
その事実が痛くて、苦しくて、目の奥が熱くなって、雫となって零れ落ちる。
「セシ──」
「わかってた……はずなのに……。愛されてないって、わかってたのに……っ」
一度零れ落ちた雫は、とめどなく赤の瞳からあふれ出し、自分でも止めることができない。
こういう時どうすればいいのかわからない。
ただ涙をこぼれさせるしかない私の手に、骨ばった大きなそれがそっと被さった。
「オズ、さま……?」
「どうするか、というのは、俺が決めることはできない。でも、どんな決断をしても、それが君の出したものなら、俺も、まる子も、カンタロウも、それを認めるだろう。君の思いが、一番大切なものなのだから」
「っ……」
一言一言が、ゆっくりと胸にしみて、心が色を変えていくように思えた。
そうだ。
私は一人じゃない。
私を大切に尊重してくれる人たちがいる。
だったらもう──。
あの家は──。
いらない──!!
「うっ……うぅっ……オズざばぁぁぁぁああああ!!」
しがみつくようにオズ様の胸に飛び込めば、一瞬動きを止めた後、そっと優しく包み込んでくれたオズ様。
何を言うわけでもなく、ただ黙って抱きしめ、頭をなでてくれる感触を感じながら、私はそっと目を閉じた。