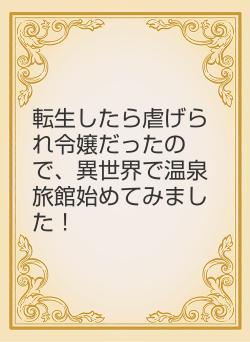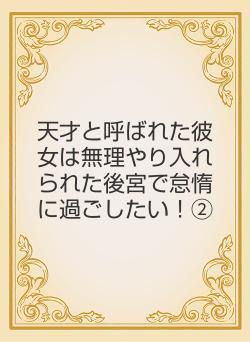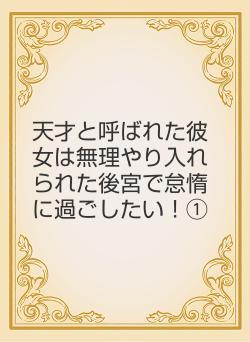この作家の他の作品
表紙を見る
異世界で温泉旅館始めました。ざまぁに事件や恋愛、日常、世界の謎解きあり!
表紙を見る
両親に無理やり後宮にいれられたリアンだったけれど、怠惰なふりして、その智謀で数々の問題を解決していく!
表紙を見る
両親に無理矢理入れられた後宮。怠惰に過ごしてさっさと後宮からお払い箱にされたいけれど……!?
その天才的な頭脳で後宮から出ていけるか!?
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
天才と呼ばれた彼女は無理矢理入れられた後宮で、怠惰な生活を極めようとする③
を読み込んでいます