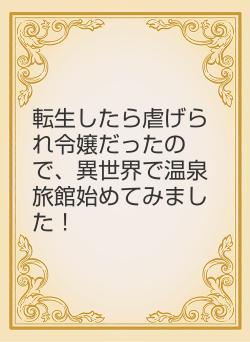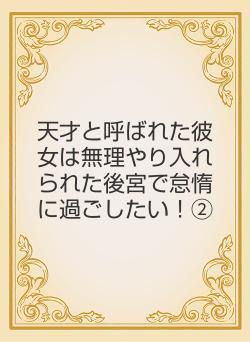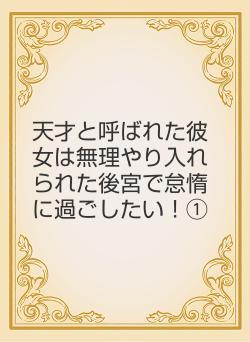ある日は庭園でポカポカとした陽射しのなかうたた寝。またある日はお茶を飲みつつ恋愛小説の本を読んでいた。またある日はボーッと雨が降っている窓の外を眺めていた。
「ウィルバート、怠惰すぎませんか?あの王妃は……自分が一国の王妃だという自覚はあるんですか!?」
リアンの行動を見張っていたらしく、報告してくるコンラッド。オレの執務室までやってきて、わざわざ言いに来るなんて、よっぽどイラついてるのか?
「リアンなら大丈夫だ。気にするな」
「いや、気になるでしょう!?王妃主催のお茶会もめったに開かない、外へもあまり行かない。夜会も好きじゃない……っていう話じゃないですか。なぜか騎士たちには人気がありましたが……」
城の皆に聞いたのか?
「ウィルバートにふさわしくないと思うんです」
コンラッドのイライラした様子にオレはハハッと笑う。
「一国の王妃がですよ!?王族や貴族の義務とはなにかを教えなければならないでしょう!?笑い事ではありません……しかし、少しウィルバートの雰囲気変わりましたね。あの王妃の影響ですか?なんだか柔らかくなったような……」
「そうか?変わったかな?」
「前のウィルバートの方が好きです」
そう言い捨てるように言って出ていく。オレは変わってない。皆の前でウィルの自分を出せなかっただけだ。
しかしコンラッドの苛立ちが気になり、オレは執務室から出て、追いかける。やはりリアンを捕まえていた!予想通りだ。後宮近くの広い廊下のホールで声をかけていた。
「王妃様、勝負をしませんか?」
「え?何かしら?」
コンラッドは自分の使用人にチェスの盤と駒を持たせていた。これは……。
「暇そうな王妃様なので、少し暇つぶしに付き合ってあげようかと思いまして」
リアンの目の奥が光を帯びたが、コンラッドは気づかない。
「ルールなどはわかりますか?」
普段のリアンなら、馬鹿にしてんの!?と怒りそうだけど、相手は大国の王子と思って我慢してるのか、穏やかな王妃の仮面を張り付けたまま、ニッコリ笑う。
「ええ……まぁ………暇つぶしなんて、嫌ですわ。ホホホッ。コンラッド王子の相手になりますでしょうか?」
でも怒ってるよな?怒ってると思う。リアンは負けず嫌いなんだよなぁ。勝負を受けるらしい。用意された椅子に座る。
「コンラッド、やめておいたほうが良いぞ!」
オレの制止の声が聞こえているはずなのに、無視をして、コンラッドがメイド達に言う。
「王妃様のためにお茶とお茶菓子を用意してあげてください。のんびりと楽しみましょう」
「あら、気が利きますわね」
「ハハハッ!手をつける余裕などないかもしれませんけどね」
リアンとコンラッドの視線がぶつかり合った。リアンの表情は穏やかだが、内には激しさを秘めている。それがオレにはわかる。コンラッドはコンラッドで本気だ。
「キングはクイーンが守りますわ」
リアンはそう言って盤上にクイーンを一番先にタンッと音を立てて並べたのだった。
「ウィルバート、怠惰すぎませんか?あの王妃は……自分が一国の王妃だという自覚はあるんですか!?」
リアンの行動を見張っていたらしく、報告してくるコンラッド。オレの執務室までやってきて、わざわざ言いに来るなんて、よっぽどイラついてるのか?
「リアンなら大丈夫だ。気にするな」
「いや、気になるでしょう!?王妃主催のお茶会もめったに開かない、外へもあまり行かない。夜会も好きじゃない……っていう話じゃないですか。なぜか騎士たちには人気がありましたが……」
城の皆に聞いたのか?
「ウィルバートにふさわしくないと思うんです」
コンラッドのイライラした様子にオレはハハッと笑う。
「一国の王妃がですよ!?王族や貴族の義務とはなにかを教えなければならないでしょう!?笑い事ではありません……しかし、少しウィルバートの雰囲気変わりましたね。あの王妃の影響ですか?なんだか柔らかくなったような……」
「そうか?変わったかな?」
「前のウィルバートの方が好きです」
そう言い捨てるように言って出ていく。オレは変わってない。皆の前でウィルの自分を出せなかっただけだ。
しかしコンラッドの苛立ちが気になり、オレは執務室から出て、追いかける。やはりリアンを捕まえていた!予想通りだ。後宮近くの広い廊下のホールで声をかけていた。
「王妃様、勝負をしませんか?」
「え?何かしら?」
コンラッドは自分の使用人にチェスの盤と駒を持たせていた。これは……。
「暇そうな王妃様なので、少し暇つぶしに付き合ってあげようかと思いまして」
リアンの目の奥が光を帯びたが、コンラッドは気づかない。
「ルールなどはわかりますか?」
普段のリアンなら、馬鹿にしてんの!?と怒りそうだけど、相手は大国の王子と思って我慢してるのか、穏やかな王妃の仮面を張り付けたまま、ニッコリ笑う。
「ええ……まぁ………暇つぶしなんて、嫌ですわ。ホホホッ。コンラッド王子の相手になりますでしょうか?」
でも怒ってるよな?怒ってると思う。リアンは負けず嫌いなんだよなぁ。勝負を受けるらしい。用意された椅子に座る。
「コンラッド、やめておいたほうが良いぞ!」
オレの制止の声が聞こえているはずなのに、無視をして、コンラッドがメイド達に言う。
「王妃様のためにお茶とお茶菓子を用意してあげてください。のんびりと楽しみましょう」
「あら、気が利きますわね」
「ハハハッ!手をつける余裕などないかもしれませんけどね」
リアンとコンラッドの視線がぶつかり合った。リアンの表情は穏やかだが、内には激しさを秘めている。それがオレにはわかる。コンラッドはコンラッドで本気だ。
「キングはクイーンが守りますわ」
リアンはそう言って盤上にクイーンを一番先にタンッと音を立てて並べたのだった。