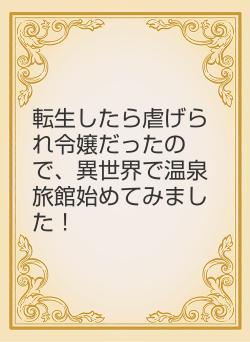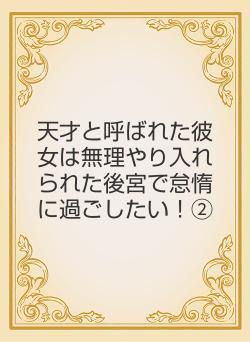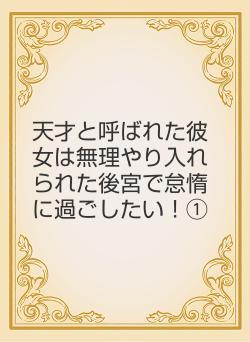コンラッド王子は眉目秀麗。その妹も紛うことなく美人だった。同じような白銀の髪を持ち、小柄ながらも女性らしく、少し儚げな笑みを浮かべている。
「可愛らしいお方ではないですか!」
宰相がそう言う。
「あの生意気な王妃も良いが、タイプが違って、またいいんじゃねーの?こっちのほうが女らしくて良いだろう」
ガルシア将軍がそう言う。
「あの大国の後ろ盾ができるなんて、我が国にとっても願ったり叶ったりです」
「利用できるものはしようぜ」
「ウィルバート様とお似合いですよっ!」
オレの腹心の三騎士までそう言う。
「僭越ながら……」
もう皆、なにも言うな!とよくリアンの護衛を頼んでいるセオドアを睨む。
「リアン様も陛下も御心のままにされたら良いのでは?」
「は!?」
なにか?とセオドアがあまり動かない表情で尋ね返してくる。
「い、いや、なんか……意外な言葉が返ってきたから……」
「リアン様の才能はなかなか得難いものです。あのような策士……いえ、王妃様がこの国のために働いていること、誰もが知らないから言えることなのです」
「どうした!?セオドア!?」
お傍で見ておりますからと言う……まさかリアンに惚れてないよな!?ちょっと今、不安になったぞ!?オレ以外にもリアンの良さをわかる人が出てくるとは……これ、独占欲なのか?モヤモヤする!
「なんで、リアン様を褒めてるのにたたっ斬るような視線を送って来るんです?殺気感じるんですが?」
「あ、ごめん。嫉妬だった」
何言ってるんですかとセオドアは呆れている。
とりあえずリアンの元へ行き、説明が必要だろう。オレはコンラッド王子の妹やらに挨拶する前に後宮へ急いだ。
………遅かった。後宮へ行く途中で、コンラッド王子、そしてその妹が廊下でリアンと出会ってしまっていた。
会話が聞こえる。飛び出そうとして足を止めた。
「……王妃様がお許しくださるなんて、理解のある方なのですね」
コンラッド王子?なにをリアンは許した?リアンの表情は扇子で隠されていて見えない。
「お兄様、優しい王妃様ですわね」
本当だねと笑う兄妹。微笑ましい風景に見える。
「それでは失礼いたしますわ。滞在をお楽しみください」
クルッと踵を返してリアンは去っていく。コンラッドとその妹がオレに気づく。
「あ、ウィルバート、ちょうどよかった。なかなか理解のある方じゃないか?」
「ウィルバート様、お会いできて嬉しいですわ」
オレは眉をひそめる。
「リアンがなんと……?」
「陛下に妹を紹介したいのですが、よろしいですか?と聞いたら、かまわないとおっしゃっていたよ」
その言葉に何も考えられなくなって、非礼とわかっていながらも、挨拶もせずに走ってリアンを追いかけていた。
どういうつもりで!?……どんな気持ちでリアンは言ったんだ!?
後宮の扉を開ける。オレだけが入れる場所。リアンは!?警備兵がオレの様子に驚いて、リアン様は部屋にいますと言った。
「リアン!?」
バンッと扉を開けると、彼女はゆったりとソファーに座り、アナベルにお茶を頼んで、淹れてもらっていた。
「ウィルバート、どうしたの?そんなに慌てて……」
なにもなかったように装う彼女。リアンは策を作り上げるとき、賭け事をするとき、その表情も感情も消す。こんな顔をする時はたいていオレは負ける。勝ったことがない……いや、今、負けてどうする!
「コンラッドになぜあんなことを言う!?」
アナベル、席を外してとリアンが言うと、かしこまりましたとメイドが出ていく。室内には二人だけ。
「この国の利益になると思ったからよ。ウィルバート、隣国たちが不穏な動きをしているわ。戦争で血が流すより、コンラッド王子の国の後ろ盾があれば避けれるわ」
普通の王妃はそこまで自分で考えないだろ!?そう思ったが、相手はリアン。
「正論かもしれないが、オレが受け入れるわけがないだろ!?」
オレにはできない。王であるウィルバートなら国益を優先するべきだと語りかける。だけど……だけど……優しいウィルは嫌だと言っている。僕にはたった一人。リアンだけで良いと。
リアンの傍へいき、手を取り、引き寄せようとしたが、サッとリアンは避ける。
「私、一人になりたいのよ」
わかった……と言うしかなかった。リアンが謝る必要はないのにごめんなさいと言った。
新しい妃を迎える。そんなことになるとはオレもリアンも考えていなかった。話が進む時はあっという間だった。
「可愛らしいお方ではないですか!」
宰相がそう言う。
「あの生意気な王妃も良いが、タイプが違って、またいいんじゃねーの?こっちのほうが女らしくて良いだろう」
ガルシア将軍がそう言う。
「あの大国の後ろ盾ができるなんて、我が国にとっても願ったり叶ったりです」
「利用できるものはしようぜ」
「ウィルバート様とお似合いですよっ!」
オレの腹心の三騎士までそう言う。
「僭越ながら……」
もう皆、なにも言うな!とよくリアンの護衛を頼んでいるセオドアを睨む。
「リアン様も陛下も御心のままにされたら良いのでは?」
「は!?」
なにか?とセオドアがあまり動かない表情で尋ね返してくる。
「い、いや、なんか……意外な言葉が返ってきたから……」
「リアン様の才能はなかなか得難いものです。あのような策士……いえ、王妃様がこの国のために働いていること、誰もが知らないから言えることなのです」
「どうした!?セオドア!?」
お傍で見ておりますからと言う……まさかリアンに惚れてないよな!?ちょっと今、不安になったぞ!?オレ以外にもリアンの良さをわかる人が出てくるとは……これ、独占欲なのか?モヤモヤする!
「なんで、リアン様を褒めてるのにたたっ斬るような視線を送って来るんです?殺気感じるんですが?」
「あ、ごめん。嫉妬だった」
何言ってるんですかとセオドアは呆れている。
とりあえずリアンの元へ行き、説明が必要だろう。オレはコンラッド王子の妹やらに挨拶する前に後宮へ急いだ。
………遅かった。後宮へ行く途中で、コンラッド王子、そしてその妹が廊下でリアンと出会ってしまっていた。
会話が聞こえる。飛び出そうとして足を止めた。
「……王妃様がお許しくださるなんて、理解のある方なのですね」
コンラッド王子?なにをリアンは許した?リアンの表情は扇子で隠されていて見えない。
「お兄様、優しい王妃様ですわね」
本当だねと笑う兄妹。微笑ましい風景に見える。
「それでは失礼いたしますわ。滞在をお楽しみください」
クルッと踵を返してリアンは去っていく。コンラッドとその妹がオレに気づく。
「あ、ウィルバート、ちょうどよかった。なかなか理解のある方じゃないか?」
「ウィルバート様、お会いできて嬉しいですわ」
オレは眉をひそめる。
「リアンがなんと……?」
「陛下に妹を紹介したいのですが、よろしいですか?と聞いたら、かまわないとおっしゃっていたよ」
その言葉に何も考えられなくなって、非礼とわかっていながらも、挨拶もせずに走ってリアンを追いかけていた。
どういうつもりで!?……どんな気持ちでリアンは言ったんだ!?
後宮の扉を開ける。オレだけが入れる場所。リアンは!?警備兵がオレの様子に驚いて、リアン様は部屋にいますと言った。
「リアン!?」
バンッと扉を開けると、彼女はゆったりとソファーに座り、アナベルにお茶を頼んで、淹れてもらっていた。
「ウィルバート、どうしたの?そんなに慌てて……」
なにもなかったように装う彼女。リアンは策を作り上げるとき、賭け事をするとき、その表情も感情も消す。こんな顔をする時はたいていオレは負ける。勝ったことがない……いや、今、負けてどうする!
「コンラッドになぜあんなことを言う!?」
アナベル、席を外してとリアンが言うと、かしこまりましたとメイドが出ていく。室内には二人だけ。
「この国の利益になると思ったからよ。ウィルバート、隣国たちが不穏な動きをしているわ。戦争で血が流すより、コンラッド王子の国の後ろ盾があれば避けれるわ」
普通の王妃はそこまで自分で考えないだろ!?そう思ったが、相手はリアン。
「正論かもしれないが、オレが受け入れるわけがないだろ!?」
オレにはできない。王であるウィルバートなら国益を優先するべきだと語りかける。だけど……だけど……優しいウィルは嫌だと言っている。僕にはたった一人。リアンだけで良いと。
リアンの傍へいき、手を取り、引き寄せようとしたが、サッとリアンは避ける。
「私、一人になりたいのよ」
わかった……と言うしかなかった。リアンが謝る必要はないのにごめんなさいと言った。
新しい妃を迎える。そんなことになるとはオレもリアンも考えていなかった。話が進む時はあっという間だった。