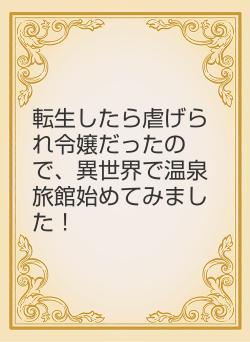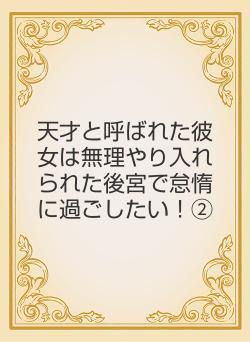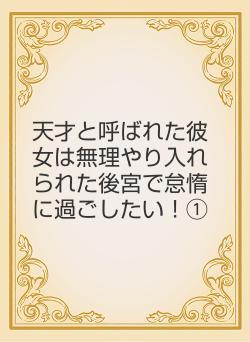コンラッド王子とは幼い頃からの付き合いだ。3歳年下で友人のようでもあり弟のようでもある。コンラッドもオレを兄のように慕ってくれているのがわかる。だから、多少気心がしれていて、互いの愚痴なんて言い合うこともある。
夕食後に二人で酒を飲みつつ、話をする。
「久しぶりに来れて嬉しいです。最近、忙しくて……結婚式にも行きたかったのに、父王が行くと言ってこれなかったので……」
「コンラッドが国にいてくれたら、安心だからな」
「僕なんてまだまだです。獅子王と呼ばれるウィルバートに比べたら……それよりあの王妃様のどこが良かったのか、聞きたかったんです」
その物言いに少しひっかかる。グラスの中の酒が空になっているので、赤い液体を注いでやると、コンラッドはありがとうございますと丁寧に礼を言う。
コンラッドの話し方は丁寧なんだが、言いたいことは言う性格なんだよな。
「なんか変だったか?」
今日のリアンは完璧すぎるほど完璧な王妃を演じきっていた。どこが落第点だった?
「怒らないでくださいよ?退屈でつまらない女性だと思いました。教科書どおりのどこにでもいる人だと。そんな人を選ぶなんて………え?なんでウィルバートが笑ってるんですか?」
オレはハハッと笑いが出てしまった。いや、待て、ここでリアンの努力を無駄にするな!
「いや、なんでもない。そうか。普通の王妃だったか。だけどオレの最愛の妃で、リアン意外を娶るつもりはない」
「どこが良いんですか!?」
「全部」
即答!?とコンラッドが驚く。
「ウィルバートと親戚になりたいから、僕の妹なんてどうかな?って思うんだけど、だめですか?悪い話ではないでしょう?」
「国のためには悪い話ではないな。だけどオレはリアンだけでいいんだ」
「随分、頑なですね。頭の良い、ウィルバートならこの話の意味を理解してくれると思ったのに……なんでですか?」
まあ、大国であるコンラッドの国から妃をもらうとなると、臣下が小躍りするくらい喜ぶだろうし、これはかなり破格の申し出だった。昔からオレに懐いていて、弟のようなコンラッドは……まさか自分の妹まで勧めてくるとは予想できなかった。
「コンラッド、そんなにリアンはだめだったか?」
「いいえ。普通の王なら完璧な王妃で良いんじゃないですか?ウィルバートがそんな王妃を選ぶことに驚いてます。そのような王妃一人を愛するとは思えません」
鋭いなぁとほくそ笑む。
「だから僕の妹を滞在期間中、推しまくりますよ!なんなら国から呼んで会ってみてもらってもいい。妹は才色兼備です!」
「は!?コンラッド!?」
怒りすら見え隠れする。なんでだ!?リアンの演技は完璧でコンラッドも完璧な王妃だと認めていた。なぜダメなのだろう。及第点だと思うけどな?
「まあ……酒を飲むか?落ち着けコンラッド」
「しばらくここに滞在してもいいですか?」
「いつも来たら長くいるだろ?わざわざ聞かなくてもいいが……どうした?」
「なんでもありません」
なんだか嫌な予感がしたが、いつもくると長いので、普段通りといえば普段通りだった。
しかしこの嫌な予感は当たった。
夕食後に二人で酒を飲みつつ、話をする。
「久しぶりに来れて嬉しいです。最近、忙しくて……結婚式にも行きたかったのに、父王が行くと言ってこれなかったので……」
「コンラッドが国にいてくれたら、安心だからな」
「僕なんてまだまだです。獅子王と呼ばれるウィルバートに比べたら……それよりあの王妃様のどこが良かったのか、聞きたかったんです」
その物言いに少しひっかかる。グラスの中の酒が空になっているので、赤い液体を注いでやると、コンラッドはありがとうございますと丁寧に礼を言う。
コンラッドの話し方は丁寧なんだが、言いたいことは言う性格なんだよな。
「なんか変だったか?」
今日のリアンは完璧すぎるほど完璧な王妃を演じきっていた。どこが落第点だった?
「怒らないでくださいよ?退屈でつまらない女性だと思いました。教科書どおりのどこにでもいる人だと。そんな人を選ぶなんて………え?なんでウィルバートが笑ってるんですか?」
オレはハハッと笑いが出てしまった。いや、待て、ここでリアンの努力を無駄にするな!
「いや、なんでもない。そうか。普通の王妃だったか。だけどオレの最愛の妃で、リアン意外を娶るつもりはない」
「どこが良いんですか!?」
「全部」
即答!?とコンラッドが驚く。
「ウィルバートと親戚になりたいから、僕の妹なんてどうかな?って思うんだけど、だめですか?悪い話ではないでしょう?」
「国のためには悪い話ではないな。だけどオレはリアンだけでいいんだ」
「随分、頑なですね。頭の良い、ウィルバートならこの話の意味を理解してくれると思ったのに……なんでですか?」
まあ、大国であるコンラッドの国から妃をもらうとなると、臣下が小躍りするくらい喜ぶだろうし、これはかなり破格の申し出だった。昔からオレに懐いていて、弟のようなコンラッドは……まさか自分の妹まで勧めてくるとは予想できなかった。
「コンラッド、そんなにリアンはだめだったか?」
「いいえ。普通の王なら完璧な王妃で良いんじゃないですか?ウィルバートがそんな王妃を選ぶことに驚いてます。そのような王妃一人を愛するとは思えません」
鋭いなぁとほくそ笑む。
「だから僕の妹を滞在期間中、推しまくりますよ!なんなら国から呼んで会ってみてもらってもいい。妹は才色兼備です!」
「は!?コンラッド!?」
怒りすら見え隠れする。なんでだ!?リアンの演技は完璧でコンラッドも完璧な王妃だと認めていた。なぜダメなのだろう。及第点だと思うけどな?
「まあ……酒を飲むか?落ち着けコンラッド」
「しばらくここに滞在してもいいですか?」
「いつも来たら長くいるだろ?わざわざ聞かなくてもいいが……どうした?」
「なんでもありません」
なんだか嫌な予感がしたが、いつもくると長いので、普段通りといえば普段通りだった。
しかしこの嫌な予感は当たった。