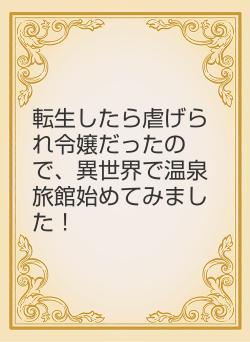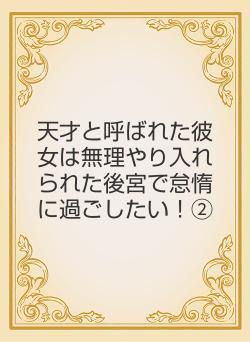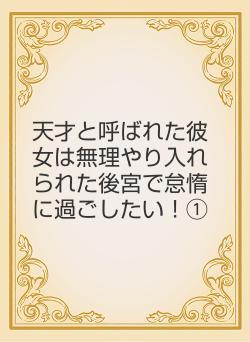「だから言ったでしょおおおお!?」
宰相が朝から興奮気味でうるさい。他の臣下も動揺を隠せない。ザワザワと騒めく会議室。
「大人しく陛下がシンシア様を娶っていれば、こうならないんですよっ!読みました!?このの゙脅しの書状を!?」
顔面に近づけてくる書面を奪い取る。
「あー、読んだ読んだ」
オレは面倒くさくなって適当に相槌を打ち、机にポイッと書面を放り投げた。
「皆さん、人に責任おしつけていい気なものですね」
オレの後ろに影のように控えているセオドアがボソッと言う。……最近、言いたいことをボソッというようになってきている。リアンの影響か!?前はくらーいやつで、静かで本当にオレの影のようになっていたんだが?
「セオドア〜。あの王妃様に肩入れしすぎると、また陛下から護衛を外されっぞ〜」
一番近くにいた三騎士の1人で、最年少のエリックがからかう。長髪の髪を後に束ねていて、まだ幼さが残る顔立ちだが、剣の腕は三騎士の中では一番だ。無言でセオドアはジロリと睨みつける。
「で、どーするの?王様?………イテッ」
他の三騎士に口を慎めと頭をゴンッとゲンゴツされているエリック。
「あっちはやる気だろうな。兵力を国境近くに集結させている」
会議室の空気が重くなる。オレに視線が集まる。
「……言いたいことはわかる。だけどあちらの国の申し出どおりにするということは傀儡国家になることだ。つまり属国。平等な同盟などではない。資源と人を差し出し、あの国の戦力の一つとなれということだ」
「しかし!このままでは民たちを戦に巻き込むことに!!」
宰相……おまえ、チェンジするぞ?せめて、なんか解決方法を出せよ!これだから……あの彼女が動くんだ!オレも頼りないのかもしれないけど!
なんとなく自分も不甲斐なく感じる。
……ま、まあ、自己嫌悪に陥るのはずっと後でいいだろ。切り替えよう。
――さあ。始めるぞ。
息を吸い込む。獅子王の仮面をかぶれ。ウィルバートの王としての威厳と強さを見せろ。覚悟を決めろ。目を鋭くさせ皆を見渡す。
「オレはこの戦い、必ず勝利に導き、エイルシア王国を守る!皆も知ってのとおりだが、オレは戦で1度たりとて負けたことはない。この獅子王と呼ばれた名に賭けて必ず勝つ!勝利を手にするぞ!」
暗い雰囲気の会議室でオレは立ち上がり、堂々とした態度と強い声を張り上げた。臣下たちが陛下!陛下!と少し感動したように立ち上がり、元気が出てきた。
……会議室の雰囲気はともかく、オレは三日前のリアンのことが心配で、気が重くて仕方なかった。
宰相が朝から興奮気味でうるさい。他の臣下も動揺を隠せない。ザワザワと騒めく会議室。
「大人しく陛下がシンシア様を娶っていれば、こうならないんですよっ!読みました!?このの゙脅しの書状を!?」
顔面に近づけてくる書面を奪い取る。
「あー、読んだ読んだ」
オレは面倒くさくなって適当に相槌を打ち、机にポイッと書面を放り投げた。
「皆さん、人に責任おしつけていい気なものですね」
オレの後ろに影のように控えているセオドアがボソッと言う。……最近、言いたいことをボソッというようになってきている。リアンの影響か!?前はくらーいやつで、静かで本当にオレの影のようになっていたんだが?
「セオドア〜。あの王妃様に肩入れしすぎると、また陛下から護衛を外されっぞ〜」
一番近くにいた三騎士の1人で、最年少のエリックがからかう。長髪の髪を後に束ねていて、まだ幼さが残る顔立ちだが、剣の腕は三騎士の中では一番だ。無言でセオドアはジロリと睨みつける。
「で、どーするの?王様?………イテッ」
他の三騎士に口を慎めと頭をゴンッとゲンゴツされているエリック。
「あっちはやる気だろうな。兵力を国境近くに集結させている」
会議室の空気が重くなる。オレに視線が集まる。
「……言いたいことはわかる。だけどあちらの国の申し出どおりにするということは傀儡国家になることだ。つまり属国。平等な同盟などではない。資源と人を差し出し、あの国の戦力の一つとなれということだ」
「しかし!このままでは民たちを戦に巻き込むことに!!」
宰相……おまえ、チェンジするぞ?せめて、なんか解決方法を出せよ!これだから……あの彼女が動くんだ!オレも頼りないのかもしれないけど!
なんとなく自分も不甲斐なく感じる。
……ま、まあ、自己嫌悪に陥るのはずっと後でいいだろ。切り替えよう。
――さあ。始めるぞ。
息を吸い込む。獅子王の仮面をかぶれ。ウィルバートの王としての威厳と強さを見せろ。覚悟を決めろ。目を鋭くさせ皆を見渡す。
「オレはこの戦い、必ず勝利に導き、エイルシア王国を守る!皆も知ってのとおりだが、オレは戦で1度たりとて負けたことはない。この獅子王と呼ばれた名に賭けて必ず勝つ!勝利を手にするぞ!」
暗い雰囲気の会議室でオレは立ち上がり、堂々とした態度と強い声を張り上げた。臣下たちが陛下!陛下!と少し感動したように立ち上がり、元気が出てきた。
……会議室の雰囲気はともかく、オレは三日前のリアンのことが心配で、気が重くて仕方なかった。
三日前、リアンから外出の許可を極秘裏に欲しいと言われた。そろそろ約束の帰ってくる時間のはずだが?
「リアン!?帰ってきたか!?」
オレは部屋の扉を開けた。
「あら?ウィルバート、ただいま」
良かった。帰ってきていた。室内には二人いた。ドレスを身にまとう一人の女性ともう一人の人物は黒色のローブのフードを深く被っていて、パサッとフードをとって顔を出した。
それはリアンで……ドレスのほうはアナベルだった。
「お嬢様〜!遅いですよっ!」
「やっと帰ってきたか。セオドアは迎えに来たか?」
あの会議のあとにすぐ行かせたが……。
「ええ。来てくれたわよ」
「師匠は元気だったか?」
「相変わらず元気よ。いろいろ頼み事したけど……関わりたくないと言いつつも、ウィルバートと私に免じて、今回は手を貸すと言ってくれたわ」
師匠のもとへ行く必要がどうしてもあるとリアンが言い張った。どうやら師匠の助けを借りる説得はできたらしい。リアンはオレが微妙な顔をしていることに気づき、スッと手を伸ばして宥めるように頬に触れた。
「後宮から出てたから、心配かけた?ごめんなさいね……でも、私の戦略にはどうしても師匠が必要だったの」
「心配だった。本当は後宮の箱に閉じ込めておけるものなら、おきたいよ。でも無理やり閉じ込めても壊すだろ」
「まぁ……そうね。必要ならばね」
「だよな……それなら。きちんと行き先を知り、護衛をきちんとつけるほうがマシだ」
後宮におさまるようなリアンではないと本当は分かってて、後宮に入れたのはオレだ。そして今回はリアンが……。
「私の本気、見せてあげるわ」
そう言って、コンラッドの国を相手に戦略を立てた。
「戦うのはオレの役目だと言ったけどな?」
「……戦は目に見えるところで戦うものばかりではないわ。そして始まる前からもう始まってるのよ」
コホンと咳払い。あ……アナベルがいたな。
「仲良くお話をしているのはよろしいのですが、お嬢様の゙身代わりも大変なのですよっ!」
「怠惰にすごすだけじゃないの」
「緊張するんですよ!誤魔化すのも大変です!誰もがお嬢様のように心臓に毛が生えているわけではありませんっ!」
そして、クルッとオレの方を向く。
「陛下、こんな無茶なお嬢様ですが、お嫌いにならないでくださいね」
「ならないよ」
ニッコリオレは笑って即答すると、アナベルのほうが赤面している。
「ふたりっきりにしてくれるかな?」
もちろんですとアナベルはそう言って、出ていった。
「ほんとに閉じ込めて置きたいくらいだよ。姿が見えないと怖くて不安になる」
「ウィルバート……」
オレは近づいて行くとリアンが名を呼び、2歩ほど下がろうとしたが、腕を掴んで離れさせない。
「あのね……甘い雰囲気になりたいところだけどね?」
「え?うん?」
「姿が見えないと不安なのよね?」
「はぁ?……まあ、そうだけど?」
怠惰で天才の彼女は悪い笑いを浮かべた。
ずっと昔からリアンを見つめ続けていたウィルのオレが『この顔をする時は気をつけたほうがいい』そう教えてくれる。
口にした彼女の提案は到底のめるものではなかった。
「リアン!?帰ってきたか!?」
オレは部屋の扉を開けた。
「あら?ウィルバート、ただいま」
良かった。帰ってきていた。室内には二人いた。ドレスを身にまとう一人の女性ともう一人の人物は黒色のローブのフードを深く被っていて、パサッとフードをとって顔を出した。
それはリアンで……ドレスのほうはアナベルだった。
「お嬢様〜!遅いですよっ!」
「やっと帰ってきたか。セオドアは迎えに来たか?」
あの会議のあとにすぐ行かせたが……。
「ええ。来てくれたわよ」
「師匠は元気だったか?」
「相変わらず元気よ。いろいろ頼み事したけど……関わりたくないと言いつつも、ウィルバートと私に免じて、今回は手を貸すと言ってくれたわ」
師匠のもとへ行く必要がどうしてもあるとリアンが言い張った。どうやら師匠の助けを借りる説得はできたらしい。リアンはオレが微妙な顔をしていることに気づき、スッと手を伸ばして宥めるように頬に触れた。
「後宮から出てたから、心配かけた?ごめんなさいね……でも、私の戦略にはどうしても師匠が必要だったの」
「心配だった。本当は後宮の箱に閉じ込めておけるものなら、おきたいよ。でも無理やり閉じ込めても壊すだろ」
「まぁ……そうね。必要ならばね」
「だよな……それなら。きちんと行き先を知り、護衛をきちんとつけるほうがマシだ」
後宮におさまるようなリアンではないと本当は分かってて、後宮に入れたのはオレだ。そして今回はリアンが……。
「私の本気、見せてあげるわ」
そう言って、コンラッドの国を相手に戦略を立てた。
「戦うのはオレの役目だと言ったけどな?」
「……戦は目に見えるところで戦うものばかりではないわ。そして始まる前からもう始まってるのよ」
コホンと咳払い。あ……アナベルがいたな。
「仲良くお話をしているのはよろしいのですが、お嬢様の゙身代わりも大変なのですよっ!」
「怠惰にすごすだけじゃないの」
「緊張するんですよ!誤魔化すのも大変です!誰もがお嬢様のように心臓に毛が生えているわけではありませんっ!」
そして、クルッとオレの方を向く。
「陛下、こんな無茶なお嬢様ですが、お嫌いにならないでくださいね」
「ならないよ」
ニッコリオレは笑って即答すると、アナベルのほうが赤面している。
「ふたりっきりにしてくれるかな?」
もちろんですとアナベルはそう言って、出ていった。
「ほんとに閉じ込めて置きたいくらいだよ。姿が見えないと怖くて不安になる」
「ウィルバート……」
オレは近づいて行くとリアンが名を呼び、2歩ほど下がろうとしたが、腕を掴んで離れさせない。
「あのね……甘い雰囲気になりたいところだけどね?」
「え?うん?」
「姿が見えないと不安なのよね?」
「はぁ?……まあ、そうだけど?」
怠惰で天才の彼女は悪い笑いを浮かべた。
ずっと昔からリアンを見つめ続けていたウィルのオレが『この顔をする時は気をつけたほうがいい』そう教えてくれる。
口にした彼女の提案は到底のめるものではなかった。
戦の用意は着々と進んでいる。忙しない空気が後宮まで届いてくる。
「お嬢様……」
「何かしら?」
「お嬢様………陛下の許可は得たと言えども……」
「アナベル、ウィルバートは私の姿が見えたほうが安心だって言っていたでしょう?」
「いえいえいえいえ!あれは言葉のアヤってやつでしょう!?意味が違いますっ!」
私はズボンを履いて、頭は短い黒髪のカツラをかぶる。足元は戦闘用のブーツ。腰には細剣を帯剣。どこからどうみても、少年である。王妃様にはみえない。
「ふっ……変装も天才的な私ね!」
「考え直してくださーいっ!」
金の髪のかつらを被り、ドレスを着ているアナベルが涙声で言う。
「アナベル、私の影武者をするための、アドバイスしておくわ」
「は、はい?」
「できる限り、怠惰に過ごすのよっ!」
「お嬢様ーーーっ!」
アナベルの声が情けない感じで響いたのだった。
「国を……ウィルバートを守りに行ってくるわ。怠惰な王妃様を頼むわよ!」
そう。私はいつもどおり、部屋から出ないでゴロゴロ怠惰に過ごしていればいいのよ。
ウィルバートがセオドアと待っていた。一頭の馬をくれる。ウィルバードは複雑な顔をしている。周囲が、その少年は?と尋ねる。
「オレの小姓だ。気にするな」
「小姓!?珍しいですね。毎回、幼い者を連れて行くのは危ないから、護衛や雑用係などいらないと、遠征の時に言っていたのに?」
まぁ……優しい王さまじゃないの。私はうんうんと隣で頷く。セオドアはハァ……と重いため息をなぜか後ろで吐いている。
「三騎士がいれば、小姓なんていらないでしょう」
「足手まといにしか、なりませんよ!」
「そんな軟弱そうな子供……」
私はバチッと手の中で雷撃を弾かせる。
「や、やめろー!このリア……ムを煽るなっ!」
ウィルバードの制止の声は間に合わず、ドンッという爆音とともに近くの木が真っ二つになった。シーーーンと静まる。ウィルバートが額に手をやる。
「リアンは魔法も天才的なんだけどやることが派手でさ……」
「陛下、《《リアム》》と呼ばないと……」
ヒソヒソとウィルバートとセオドアが話している。
「魔道士なのか!?」
「なっ、なんだ今の一撃は!?」
驚く皆に私はにやりと笑う。
ああ……すごく久しぶり。魔法を使う、この感覚良いわ!
「《《リアム》》と言う。全力で陛下をお守りし、役に立ちたいと思っているので、よろしく頼む」
偉そうなガキだなーーっ!と三騎士の一番若そうな子が言う。自分もガキじゃないのと私は冷たい目で一瞥する。
ウィルバートが私を見て、確認する。頬には一筋の汗。連れて行きたくはないと顔に書いてある。
「あまり戦は見せたくないんだが、仕方ないのか?これ?」
「今回の戦略、話したでしょう?私、抜きでは成り立たない」
「そうなれば、全力で戦うさ……城にいて……」
くどいっ!と私にぴしゃりと言われる。ヒョイッと馬に乗る私。行くわよと声をかけると、諦めたようにウィルバートは1度、下を向いて、そして顔を上げた。そこには強い眼差しで前を見据える王がいた。
「ついて来るなら、足手まといになるなよ!………全軍!我らが国を!愛すべき民を人を守る!勝ってこの場に、再び全員で立つ!行くぞ!」
オーーッ!と王城の門で、威勢のよい掛け声が響いたのだった。
ウィルバートは私の策を起用する。しかし今回の策は大規模で簡単なことではない。その場へ行き、判断せねばならないことがある。
だから、今回は一緒に行くと私は言った。
……それに、戦は始まる前に終っているものだ。いくつものパターンを組み合わせ、敗北する原因をすべて潰しておくものだわ。
そう思いながらも、やはり戦場へ行くというのは怖い。本当は怖い。
机上では私は天才で駒を自由に操る。本当の戦場は人の命がかかっている。でも私が動かないことでウィルバートを失うことになったら、後悔してもしきれないじゃない。
……ウィルバートだけを生かすことは傀儡国家になっても、それは保障されていたであろう。でも彼の性格上、その道は選ばないであろうということもわかっていた。それは民にとって幸せではないからだ。
馬上で強い眼差しで前を向き、マントをはためかせているウィルバート。獅子王と呼ばれるに相応しい雰囲気。
私は彼の手足となり、駒となり動く。怠惰な王妃様は今頃、城の中でお茶を飲んでいる時間を過ごしている。私は少年のリアム。この世で最も優秀で天才的な参謀。そう心に言い聞かせる。
ぎゅっと手綱を握りしめる。
私はどんな手を使って勝つわよ!天才と言われる所以を今こそ教えてあげるわ!
「お嬢様……」
「何かしら?」
「お嬢様………陛下の許可は得たと言えども……」
「アナベル、ウィルバートは私の姿が見えたほうが安心だって言っていたでしょう?」
「いえいえいえいえ!あれは言葉のアヤってやつでしょう!?意味が違いますっ!」
私はズボンを履いて、頭は短い黒髪のカツラをかぶる。足元は戦闘用のブーツ。腰には細剣を帯剣。どこからどうみても、少年である。王妃様にはみえない。
「ふっ……変装も天才的な私ね!」
「考え直してくださーいっ!」
金の髪のかつらを被り、ドレスを着ているアナベルが涙声で言う。
「アナベル、私の影武者をするための、アドバイスしておくわ」
「は、はい?」
「できる限り、怠惰に過ごすのよっ!」
「お嬢様ーーーっ!」
アナベルの声が情けない感じで響いたのだった。
「国を……ウィルバートを守りに行ってくるわ。怠惰な王妃様を頼むわよ!」
そう。私はいつもどおり、部屋から出ないでゴロゴロ怠惰に過ごしていればいいのよ。
ウィルバートがセオドアと待っていた。一頭の馬をくれる。ウィルバードは複雑な顔をしている。周囲が、その少年は?と尋ねる。
「オレの小姓だ。気にするな」
「小姓!?珍しいですね。毎回、幼い者を連れて行くのは危ないから、護衛や雑用係などいらないと、遠征の時に言っていたのに?」
まぁ……優しい王さまじゃないの。私はうんうんと隣で頷く。セオドアはハァ……と重いため息をなぜか後ろで吐いている。
「三騎士がいれば、小姓なんていらないでしょう」
「足手まといにしか、なりませんよ!」
「そんな軟弱そうな子供……」
私はバチッと手の中で雷撃を弾かせる。
「や、やめろー!このリア……ムを煽るなっ!」
ウィルバードの制止の声は間に合わず、ドンッという爆音とともに近くの木が真っ二つになった。シーーーンと静まる。ウィルバートが額に手をやる。
「リアンは魔法も天才的なんだけどやることが派手でさ……」
「陛下、《《リアム》》と呼ばないと……」
ヒソヒソとウィルバートとセオドアが話している。
「魔道士なのか!?」
「なっ、なんだ今の一撃は!?」
驚く皆に私はにやりと笑う。
ああ……すごく久しぶり。魔法を使う、この感覚良いわ!
「《《リアム》》と言う。全力で陛下をお守りし、役に立ちたいと思っているので、よろしく頼む」
偉そうなガキだなーーっ!と三騎士の一番若そうな子が言う。自分もガキじゃないのと私は冷たい目で一瞥する。
ウィルバートが私を見て、確認する。頬には一筋の汗。連れて行きたくはないと顔に書いてある。
「あまり戦は見せたくないんだが、仕方ないのか?これ?」
「今回の戦略、話したでしょう?私、抜きでは成り立たない」
「そうなれば、全力で戦うさ……城にいて……」
くどいっ!と私にぴしゃりと言われる。ヒョイッと馬に乗る私。行くわよと声をかけると、諦めたようにウィルバートは1度、下を向いて、そして顔を上げた。そこには強い眼差しで前を見据える王がいた。
「ついて来るなら、足手まといになるなよ!………全軍!我らが国を!愛すべき民を人を守る!勝ってこの場に、再び全員で立つ!行くぞ!」
オーーッ!と王城の門で、威勢のよい掛け声が響いたのだった。
ウィルバートは私の策を起用する。しかし今回の策は大規模で簡単なことではない。その場へ行き、判断せねばならないことがある。
だから、今回は一緒に行くと私は言った。
……それに、戦は始まる前に終っているものだ。いくつものパターンを組み合わせ、敗北する原因をすべて潰しておくものだわ。
そう思いながらも、やはり戦場へ行くというのは怖い。本当は怖い。
机上では私は天才で駒を自由に操る。本当の戦場は人の命がかかっている。でも私が動かないことでウィルバートを失うことになったら、後悔してもしきれないじゃない。
……ウィルバートだけを生かすことは傀儡国家になっても、それは保障されていたであろう。でも彼の性格上、その道は選ばないであろうということもわかっていた。それは民にとって幸せではないからだ。
馬上で強い眼差しで前を向き、マントをはためかせているウィルバート。獅子王と呼ばれるに相応しい雰囲気。
私は彼の手足となり、駒となり動く。怠惰な王妃様は今頃、城の中でお茶を飲んでいる時間を過ごしている。私は少年のリアム。この世で最も優秀で天才的な参謀。そう心に言い聞かせる。
ぎゅっと手綱を握りしめる。
私はどんな手を使って勝つわよ!天才と言われる所以を今こそ教えてあげるわ!
話は少し前に戻る。
「リアン様を連れて行くというのは正気ですか!?」
いつも冷静なセオドアがオレに再度尋ねる。
「はっきり言って、オレも連れて行きたくない。だけど……たとえ警備を厚くし、後宮から出れないようにしたとしても、リアンはどんな手を使っても出ていく」
「は!?」
「それが彼女だ。王命だと言っても出ていく。王命に背いて処刑になろうとも行く。それなら傍に置いておくほうがマシなんだ」
「はあ!?」
「リアンにはオレたちが見えているもの以上のものが見えている。それゆえ連れて行くことにした。今回の戦は決して負けられないものだ。勝つこと意外に道はない」
セオドアがそれはわかりますが……と口ごもる。
「おまえにリアンの護衛を命じる」
ハッとセオドアが顔をオレに向ける。
「しかし!陛下の影武者としての役目があります!陛下を危険に晒すことになります!」
セオドアにしては珍しく感情を出す。幼い頃よりオレの影武者を演じてきた。
「構わない。リアンを守れ。その手も足も傷つけることを許さない」
ここで、出来ないと食ってかかると思った。以前のセオドアならば、オレ以外をどうして守らなければならない?と淡々と無表情でそう答えていただろう。
しかし、今は………。
「………それが王命でありますならば、命を賭けてもリアン様をお守りいたします」
「助かる。頼む」
膝を折り、静かに頷いた。了承した……セオドアもまたオレと同じ光を感じているんだろうと思う。もちろん役目的にはオレのことを最優先事項としている男だが。
リアンは人を惹きつける。暗い雨の中にずっと居たものであればあるほど、その雲間から出てくる太陽のような存在で照らす。
迷いのない強い光、導く光は道を明るく照らす。
だからオレも闇を抜けてこれた。
あの日……雨がずっと降り続いていた。誰かが流した涙のように。
幼い頃、冷たい雨が降る日にオレは王になった。
「思ったより早かったか……」
「最近、あまり体調が優れませんでしたから」
セオドアがそう言う。雨が降っているためか昼中だというのに暗い。話し声の中に雨音が混ざる。
「父王の葬儀はいつになる?」
「1週間後です」
まだ幼さの残るセオドア。また同じ歳のオレも幼い。
しかし年齢など関係なく、しなくてはならないことは避けれない。
「そうか。じゃあ、それまでに片付けよう。厄介な奴らをな」
「御心のままに……」
そう言って、オレとセオドアは父王の時にいた、好き勝手にしていたやつらを粛清していった。代わりに能力のあるものをその座へ据えていく。入れ替えは素早く、文句を言う暇を与えない。
「殿下、これ以上は……」
宰相が怯えている。
「わかっている。なぜ、ここまで腐敗するまで見過ごしていた?まあ……父はあまり政務がお好きではなかったから、おまえを責めるのも間違いかもしれないけどな」
「な、なぜ、ここまで……」
「なぜ、オレが臣下のしていることを知っていたか?ここまでするのか?と聞きたいか?」
はい……と頷く。
「この国を良くしたい……というのは、表向きの理由かもしれない。本音はたった一人に軽蔑されたくないためだな」
ウィルが大切にしている彼女は私塾で目を輝かせて新しいことを知り、学び、楽しげに今日も勉強していることだろう。きっとそのうち、その実力を持って、王宮に来る。そしてウィルかウィルバードだと知る。その時に良い王だと思われたい。
我ながら単純な理由だよな苦笑してしまう。王ならばもっと志し高く持たないとダメだろうに……だけどこんな小さな望みがオレを強くしてくれる。
ウィルでいられる時間は後、どのくらいあるんだろうか。彼女に恥じない王にせめてなって、ウィルバートとして会いたい。
「はあ……!?誰に!?」
「宰相、怯えているが、オレはおまえを罷免する気はない。父王が仕事をしない分、おまえが真面目にしてくれていたおかげで国は回った。国の金に手を出したり、己の私心のために人事をしたりしていないからな」
……真面目だけが取り柄の宰相。悪くはない。私腹を肥やすことに長けていない。それが良い。
逆恨みをしてきたやつらはセオドアや三人の騎士に阻まれる。ダラダラと己の地位に胡座をかいてたやつらに負けるわけがない。
父王の葬儀はずっと雨が降り続いていた。
王になりたくないが、この道しかない。王になることで、生き残れた。やっとここまできた。でも……もし違う道があれば、きっとオレは………。
雨を見上げて思う。父が亡くなっても涙は流すことはなかった。
「リアン様を連れて行くというのは正気ですか!?」
いつも冷静なセオドアがオレに再度尋ねる。
「はっきり言って、オレも連れて行きたくない。だけど……たとえ警備を厚くし、後宮から出れないようにしたとしても、リアンはどんな手を使っても出ていく」
「は!?」
「それが彼女だ。王命だと言っても出ていく。王命に背いて処刑になろうとも行く。それなら傍に置いておくほうがマシなんだ」
「はあ!?」
「リアンにはオレたちが見えているもの以上のものが見えている。それゆえ連れて行くことにした。今回の戦は決して負けられないものだ。勝つこと意外に道はない」
セオドアがそれはわかりますが……と口ごもる。
「おまえにリアンの護衛を命じる」
ハッとセオドアが顔をオレに向ける。
「しかし!陛下の影武者としての役目があります!陛下を危険に晒すことになります!」
セオドアにしては珍しく感情を出す。幼い頃よりオレの影武者を演じてきた。
「構わない。リアンを守れ。その手も足も傷つけることを許さない」
ここで、出来ないと食ってかかると思った。以前のセオドアならば、オレ以外をどうして守らなければならない?と淡々と無表情でそう答えていただろう。
しかし、今は………。
「………それが王命でありますならば、命を賭けてもリアン様をお守りいたします」
「助かる。頼む」
膝を折り、静かに頷いた。了承した……セオドアもまたオレと同じ光を感じているんだろうと思う。もちろん役目的にはオレのことを最優先事項としている男だが。
リアンは人を惹きつける。暗い雨の中にずっと居たものであればあるほど、その雲間から出てくる太陽のような存在で照らす。
迷いのない強い光、導く光は道を明るく照らす。
だからオレも闇を抜けてこれた。
あの日……雨がずっと降り続いていた。誰かが流した涙のように。
幼い頃、冷たい雨が降る日にオレは王になった。
「思ったより早かったか……」
「最近、あまり体調が優れませんでしたから」
セオドアがそう言う。雨が降っているためか昼中だというのに暗い。話し声の中に雨音が混ざる。
「父王の葬儀はいつになる?」
「1週間後です」
まだ幼さの残るセオドア。また同じ歳のオレも幼い。
しかし年齢など関係なく、しなくてはならないことは避けれない。
「そうか。じゃあ、それまでに片付けよう。厄介な奴らをな」
「御心のままに……」
そう言って、オレとセオドアは父王の時にいた、好き勝手にしていたやつらを粛清していった。代わりに能力のあるものをその座へ据えていく。入れ替えは素早く、文句を言う暇を与えない。
「殿下、これ以上は……」
宰相が怯えている。
「わかっている。なぜ、ここまで腐敗するまで見過ごしていた?まあ……父はあまり政務がお好きではなかったから、おまえを責めるのも間違いかもしれないけどな」
「な、なぜ、ここまで……」
「なぜ、オレが臣下のしていることを知っていたか?ここまでするのか?と聞きたいか?」
はい……と頷く。
「この国を良くしたい……というのは、表向きの理由かもしれない。本音はたった一人に軽蔑されたくないためだな」
ウィルが大切にしている彼女は私塾で目を輝かせて新しいことを知り、学び、楽しげに今日も勉強していることだろう。きっとそのうち、その実力を持って、王宮に来る。そしてウィルかウィルバードだと知る。その時に良い王だと思われたい。
我ながら単純な理由だよな苦笑してしまう。王ならばもっと志し高く持たないとダメだろうに……だけどこんな小さな望みがオレを強くしてくれる。
ウィルでいられる時間は後、どのくらいあるんだろうか。彼女に恥じない王にせめてなって、ウィルバートとして会いたい。
「はあ……!?誰に!?」
「宰相、怯えているが、オレはおまえを罷免する気はない。父王が仕事をしない分、おまえが真面目にしてくれていたおかげで国は回った。国の金に手を出したり、己の私心のために人事をしたりしていないからな」
……真面目だけが取り柄の宰相。悪くはない。私腹を肥やすことに長けていない。それが良い。
逆恨みをしてきたやつらはセオドアや三人の騎士に阻まれる。ダラダラと己の地位に胡座をかいてたやつらに負けるわけがない。
父王の葬儀はずっと雨が降り続いていた。
王になりたくないが、この道しかない。王になることで、生き残れた。やっとここまできた。でも……もし違う道があれば、きっとオレは………。
雨を見上げて思う。父が亡くなっても涙は流すことはなかった。
この作家の他の作品
表紙を見る
異世界で温泉旅館始めました。ざまぁに事件や恋愛、日常、世界の謎解きあり!
表紙を見る
両親に無理やり後宮にいれられたリアンだったけれど、怠惰なふりして、その智謀で数々の問題を解決していく!
表紙を見る
両親に無理矢理入れられた後宮。怠惰に過ごしてさっさと後宮からお払い箱にされたいけれど……!?
その天才的な頭脳で後宮から出ていけるか!?
この作品を見ている人にオススメ
エラーが発生しました。