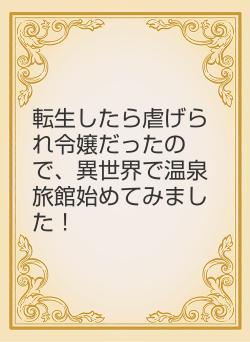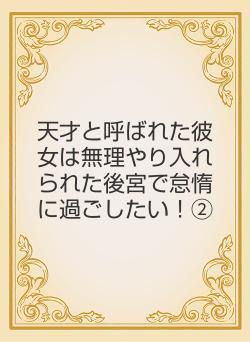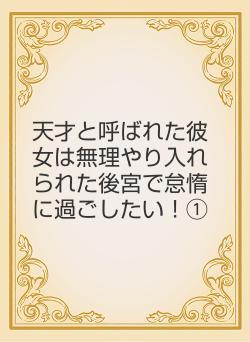三日前、リアンから外出の許可を極秘裏に欲しいと言われた。そろそろ約束の帰ってくる時間のはずだが?
「リアン!?帰ってきたか!?」
オレは部屋の扉を開けた。
「あら?ウィルバート、ただいま」
良かった。帰ってきていた。室内には二人いた。ドレスを身にまとう一人の女性ともう一人の人物は黒色のローブのフードを深く被っていて、パサッとフードをとって顔を出した。
それはリアンで……ドレスのほうはアナベルだった。
「お嬢様〜!遅いですよっ!」
「やっと帰ってきたか。セオドアは迎えに来たか?」
あの会議のあとにすぐ行かせたが……。
「ええ。来てくれたわよ」
「師匠は元気だったか?」
「相変わらず元気よ。いろいろ頼み事したけど……関わりたくないと言いつつも、ウィルバートと私に免じて、今回は手を貸すと言ってくれたわ」
師匠のもとへ行く必要がどうしてもあるとリアンが言い張った。どうやら師匠の助けを借りる説得はできたらしい。リアンはオレが微妙な顔をしていることに気づき、スッと手を伸ばして宥めるように頬に触れた。
「後宮から出てたから、心配かけた?ごめんなさいね……でも、私の戦略にはどうしても師匠が必要だったの」
「心配だった。本当は後宮の箱に閉じ込めておけるものなら、おきたいよ。でも無理やり閉じ込めても壊すだろ」
「まぁ……そうね。必要ならばね」
「だよな……それなら。きちんと行き先を知り、護衛をきちんとつけるほうがマシだ」
後宮におさまるようなリアンではないと本当は分かってて、後宮に入れたのはオレだ。そして今回はリアンが……。
「私の本気、見せてあげるわ」
そう言って、コンラッドの国を相手に戦略を立てた。
「戦うのはオレの役目だと言ったけどな?」
「……戦は目に見えるところで戦うものばかりではないわ。そして始まる前からもう始まってるのよ」
コホンと咳払い。あ……アナベルがいたな。
「仲良くお話をしているのはよろしいのですが、お嬢様の゙身代わりも大変なのですよっ!」
「怠惰にすごすだけじゃないの」
「緊張するんですよ!誤魔化すのも大変です!誰もがお嬢様のように心臓に毛が生えているわけではありませんっ!」
そして、クルッとオレの方を向く。
「陛下、こんな無茶なお嬢様ですが、お嫌いにならないでくださいね」
「ならないよ」
ニッコリオレは笑って即答すると、アナベルのほうが赤面している。
「ふたりっきりにしてくれるかな?」
もちろんですとアナベルはそう言って、出ていった。
「ほんとに閉じ込めて置きたいくらいだよ。姿が見えないと怖くて不安になる」
「ウィルバート……」
オレは近づいて行くとリアンが名を呼び、2歩ほど下がろうとしたが、腕を掴んで離れさせない。
「あのね……甘い雰囲気になりたいところだけどね?」
「え?うん?」
「姿が見えないと不安なのよね?」
「はぁ?……まあ、そうだけど?」
怠惰で天才の彼女は悪い笑いを浮かべた。
ずっと昔からリアンを見つめ続けていたウィルのオレが『この顔をする時は気をつけたほうがいい』そう教えてくれる。
口にした彼女の提案は到底のめるものではなかった。
「リアン!?帰ってきたか!?」
オレは部屋の扉を開けた。
「あら?ウィルバート、ただいま」
良かった。帰ってきていた。室内には二人いた。ドレスを身にまとう一人の女性ともう一人の人物は黒色のローブのフードを深く被っていて、パサッとフードをとって顔を出した。
それはリアンで……ドレスのほうはアナベルだった。
「お嬢様〜!遅いですよっ!」
「やっと帰ってきたか。セオドアは迎えに来たか?」
あの会議のあとにすぐ行かせたが……。
「ええ。来てくれたわよ」
「師匠は元気だったか?」
「相変わらず元気よ。いろいろ頼み事したけど……関わりたくないと言いつつも、ウィルバートと私に免じて、今回は手を貸すと言ってくれたわ」
師匠のもとへ行く必要がどうしてもあるとリアンが言い張った。どうやら師匠の助けを借りる説得はできたらしい。リアンはオレが微妙な顔をしていることに気づき、スッと手を伸ばして宥めるように頬に触れた。
「後宮から出てたから、心配かけた?ごめんなさいね……でも、私の戦略にはどうしても師匠が必要だったの」
「心配だった。本当は後宮の箱に閉じ込めておけるものなら、おきたいよ。でも無理やり閉じ込めても壊すだろ」
「まぁ……そうね。必要ならばね」
「だよな……それなら。きちんと行き先を知り、護衛をきちんとつけるほうがマシだ」
後宮におさまるようなリアンではないと本当は分かってて、後宮に入れたのはオレだ。そして今回はリアンが……。
「私の本気、見せてあげるわ」
そう言って、コンラッドの国を相手に戦略を立てた。
「戦うのはオレの役目だと言ったけどな?」
「……戦は目に見えるところで戦うものばかりではないわ。そして始まる前からもう始まってるのよ」
コホンと咳払い。あ……アナベルがいたな。
「仲良くお話をしているのはよろしいのですが、お嬢様の゙身代わりも大変なのですよっ!」
「怠惰にすごすだけじゃないの」
「緊張するんですよ!誤魔化すのも大変です!誰もがお嬢様のように心臓に毛が生えているわけではありませんっ!」
そして、クルッとオレの方を向く。
「陛下、こんな無茶なお嬢様ですが、お嫌いにならないでくださいね」
「ならないよ」
ニッコリオレは笑って即答すると、アナベルのほうが赤面している。
「ふたりっきりにしてくれるかな?」
もちろんですとアナベルはそう言って、出ていった。
「ほんとに閉じ込めて置きたいくらいだよ。姿が見えないと怖くて不安になる」
「ウィルバート……」
オレは近づいて行くとリアンが名を呼び、2歩ほど下がろうとしたが、腕を掴んで離れさせない。
「あのね……甘い雰囲気になりたいところだけどね?」
「え?うん?」
「姿が見えないと不安なのよね?」
「はぁ?……まあ、そうだけど?」
怠惰で天才の彼女は悪い笑いを浮かべた。
ずっと昔からリアンを見つめ続けていたウィルのオレが『この顔をする時は気をつけたほうがいい』そう教えてくれる。
口にした彼女の提案は到底のめるものではなかった。