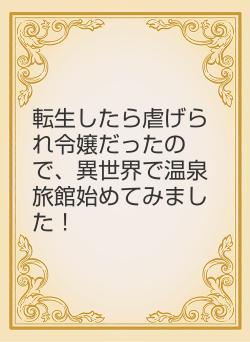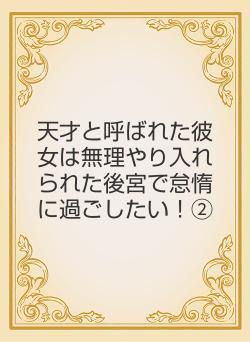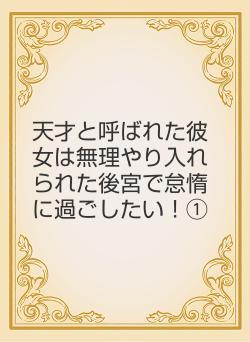アナベルがムッとしている。
「お嬢様、シンシア様はなぜドレスの色をかぶせて来るのでしょうか?毎回ですよ」
シンシアや他の貴族の娘たちとお茶会を開催して、何度か過ごしたが、確かに毎回かぶせてくる。
「気にしないわ」
「気にしてますよね?」
ボソッとセオドアが間髪入れずに言う。
「う、うるさいわねっ!私はネチネチとした地味な攻撃が実は嫌いなのよっ!」
「ストレートな嫌がらせならお嬢様は仕返しがお得意ですよねー」
「それも余計な一言よっ!」
昔から私を見てきたアナベルは笑ってそう言う。
シンシアは地味にチクチクやってくるのだ。服の色だけではなく、私とウィルバートの貴重な゙お茶の時間に合わせて、コンラッドとやってきたり、私がお気に入りの庭園でお昼寝しようとすると、騒がしく他の人を連れてやってきて話しかけてきたり、私が廊下を歩いていると『ごめんなさい!』と何故か謝って慌てるように避けて、私はなんっにも言ってないのに怖がらせてるようにみせたり、楽器を奏でて披露する場ではわざと私の時に大きい声で話すようにしたり………。
「地味な攻撃のほうがストレス溜まるわ」
性格的にそうでしょうねぇとアナベルとセオドアがウンウンとうなずいている。
しかも今は詳しくは言えないけど、いろいろすることが山積みで、反撃するような暇がないのよね。
それもそろそろ終わりを迎えようとしている。我ながらよく我慢したと褒めたい!
「そういえば、セオドア、最近護衛に来てなかったわよね?どうしたの?休暇でもとっていたの?」
すっかり私の護衛騎士になったと思っていたんだけど、違うのかしら?
「陛下の謎の嫉妬によって、一時、王妃様の護衛の任務を解かれてました」
「えっ?何に嫉妬したの?」
セオドアがまったくわかりませんと首を傾げていた。ウィルバートはいったいなにに嫉妬したわけ……?この私でもわからないことはあるわねと思った。
その日の夕食会のことだった。
「リアン王妃の大好物と聞いて、アマーズンの実を取り寄せましたよ。どうぞ」
コンラッド王子とシンシアがジッと私の反応を待つ。
「まあ!それは嬉しいですわ。大好物ですの」
やせ我慢の言葉だと思われたのか、たくさん食べてくださいね!とシンシアが面白そうにクスッと笑って言う。
「あれ?コンラッド、いつリアンの好みを聞いたんだ?リアン、良かったな。アマーズンの実、これだけあったら、食べ放題だな」
何も知らない、ウィルバートが呑気にそういうと、二人の兄妹は……えっ!?と固まる。
「高級で貴重な実ゆえ、なかなか手に入らないのに、こんなにたくさんありがとうございます」
私はお礼を述べて、口に甘くてみずみずしい果実を入れてにーっこり幸せそうに何粒も食べる。
美味しい!と頬をおさえて食べる仕草に微妙な顔をするコンラッド王子。
私の後ろに控えてるアナベルが額に手を置いてボソッという。
「お嬢様は本当に人が悪いです……」
目の前には呆気にとられたコンラッドとシンシアがいた。
「お嬢様、シンシア様はなぜドレスの色をかぶせて来るのでしょうか?毎回ですよ」
シンシアや他の貴族の娘たちとお茶会を開催して、何度か過ごしたが、確かに毎回かぶせてくる。
「気にしないわ」
「気にしてますよね?」
ボソッとセオドアが間髪入れずに言う。
「う、うるさいわねっ!私はネチネチとした地味な攻撃が実は嫌いなのよっ!」
「ストレートな嫌がらせならお嬢様は仕返しがお得意ですよねー」
「それも余計な一言よっ!」
昔から私を見てきたアナベルは笑ってそう言う。
シンシアは地味にチクチクやってくるのだ。服の色だけではなく、私とウィルバートの貴重な゙お茶の時間に合わせて、コンラッドとやってきたり、私がお気に入りの庭園でお昼寝しようとすると、騒がしく他の人を連れてやってきて話しかけてきたり、私が廊下を歩いていると『ごめんなさい!』と何故か謝って慌てるように避けて、私はなんっにも言ってないのに怖がらせてるようにみせたり、楽器を奏でて披露する場ではわざと私の時に大きい声で話すようにしたり………。
「地味な攻撃のほうがストレス溜まるわ」
性格的にそうでしょうねぇとアナベルとセオドアがウンウンとうなずいている。
しかも今は詳しくは言えないけど、いろいろすることが山積みで、反撃するような暇がないのよね。
それもそろそろ終わりを迎えようとしている。我ながらよく我慢したと褒めたい!
「そういえば、セオドア、最近護衛に来てなかったわよね?どうしたの?休暇でもとっていたの?」
すっかり私の護衛騎士になったと思っていたんだけど、違うのかしら?
「陛下の謎の嫉妬によって、一時、王妃様の護衛の任務を解かれてました」
「えっ?何に嫉妬したの?」
セオドアがまったくわかりませんと首を傾げていた。ウィルバートはいったいなにに嫉妬したわけ……?この私でもわからないことはあるわねと思った。
その日の夕食会のことだった。
「リアン王妃の大好物と聞いて、アマーズンの実を取り寄せましたよ。どうぞ」
コンラッド王子とシンシアがジッと私の反応を待つ。
「まあ!それは嬉しいですわ。大好物ですの」
やせ我慢の言葉だと思われたのか、たくさん食べてくださいね!とシンシアが面白そうにクスッと笑って言う。
「あれ?コンラッド、いつリアンの好みを聞いたんだ?リアン、良かったな。アマーズンの実、これだけあったら、食べ放題だな」
何も知らない、ウィルバートが呑気にそういうと、二人の兄妹は……えっ!?と固まる。
「高級で貴重な実ゆえ、なかなか手に入らないのに、こんなにたくさんありがとうございます」
私はお礼を述べて、口に甘くてみずみずしい果実を入れてにーっこり幸せそうに何粒も食べる。
美味しい!と頬をおさえて食べる仕草に微妙な顔をするコンラッド王子。
私の後ろに控えてるアナベルが額に手を置いてボソッという。
「お嬢様は本当に人が悪いです……」
目の前には呆気にとられたコンラッドとシンシアがいた。