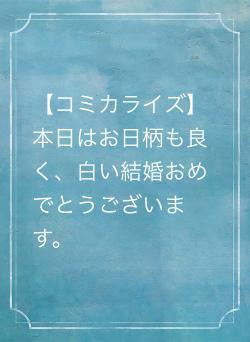彼の赤くなった横顔を見上げて言った。
「もっと、好きになった」
赤くなった顔のまま鷹羽くんは言って、つられて私も顔が熱くなった。
鷹羽くんはどう考えても私と付き合うような人ではないけれど、好きでいてくれることは間違いないみたい。
「あのね……」
「うん」
「私不思議に思って居ることがあるんだけど、聞いて良い?」
「良いよ」
「……どうして、私の事好きなの? 今まで私たち、ほとんど話したこともないよね?」
本当に不思議だ。何かきっかけめいた出来事があったなら、私だって『あの時なのかも』と思ったはずだ。
けれど、そんな出来事なんて思いつかない。
ただただ、いつ彼が好きになってくれたのかわからないだけ。
鷹羽くんはそれを聞いて、いきなり立ち止まった。
私もそれにつられて足を止める。彼は一度ふーっと大きく息をついて、私の目を見て言った。
「う、ん。……もし」
「もし?」
「もしだけど、有馬が僕のこと、好きになってくれたら、そうしたら好きになった理由を言う。それまでは言いたくない」
どくん、と胸が高鳴った。
「……今は僕のことをなんとも思っていないと思うけど、そうなってもらえるように頑張りたい」
自分の言い聞かせるように呟くと、鷹羽くんははっとしたように前を向いた。
「嘘みたい」
私は思っていることをそのままするりと口に出した。はっと口を覆うけど遅い。
鷹羽くんは驚いたようにして、再度私を見た。
「もっと、好きになった」
赤くなった顔のまま鷹羽くんは言って、つられて私も顔が熱くなった。
鷹羽くんはどう考えても私と付き合うような人ではないけれど、好きでいてくれることは間違いないみたい。
「あのね……」
「うん」
「私不思議に思って居ることがあるんだけど、聞いて良い?」
「良いよ」
「……どうして、私の事好きなの? 今まで私たち、ほとんど話したこともないよね?」
本当に不思議だ。何かきっかけめいた出来事があったなら、私だって『あの時なのかも』と思ったはずだ。
けれど、そんな出来事なんて思いつかない。
ただただ、いつ彼が好きになってくれたのかわからないだけ。
鷹羽くんはそれを聞いて、いきなり立ち止まった。
私もそれにつられて足を止める。彼は一度ふーっと大きく息をついて、私の目を見て言った。
「う、ん。……もし」
「もし?」
「もしだけど、有馬が僕のこと、好きになってくれたら、そうしたら好きになった理由を言う。それまでは言いたくない」
どくん、と胸が高鳴った。
「……今は僕のことをなんとも思っていないと思うけど、そうなってもらえるように頑張りたい」
自分の言い聞かせるように呟くと、鷹羽くんははっとしたように前を向いた。
「嘘みたい」
私は思っていることをそのままするりと口に出した。はっと口を覆うけど遅い。
鷹羽くんは驚いたようにして、再度私を見た。