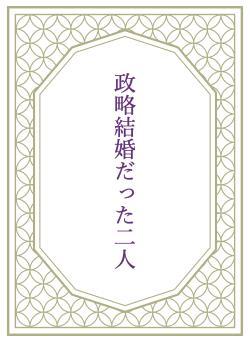「ウルと結婚なんかしてみなさいな。きっと、三日で離婚よ」
「はは、三日保つかどうかも怪しいな?」
私もウルも譲らない性格なので、下手に夫婦になどなったら意見がぶつかり合って喧嘩ばかりの日々だろう。何より、彼と家庭を築くなんてこと、全然想像できない。
彼の方も同じ意見のようで、アシェラとベッドになんか入ったら寝首をかかれそう、なんて随分と失礼なことを呟いた。
「で? さっきから俺の足を踏みつけているお前は、何か言うことはないのか? ──ロッツ」
その失礼な男の左足を思い切り踏みつけてやると、どうやらすでに右足を踏んでいた者があったらしい。
両足の甲に大きさ違いの靴跡を刻まれて情けない顔をするウル越しに、私は同志に目を向けた。
すると、綺麗な菫色の瞳がこちらを見つめ返してきたかと思ったら、ゆっくりとその口が開き──
「僕はね、アシェラが決めたことに口出しをしないよ」
私は、がっかりした。
「でも、幸せになってほしいと思う。大切なひとだから」
「そう……ありがとう」
この時、私達は三年生になっていた。
お人形さんのように愛らしかったロッツに、身長を抜かされたと気づいたのはつい先日のことだ。
年齢にして十三歳。入学した時よりも大人びた私は、もう自覚していた。
彼に──ロッツに、恋をしていることに。
「はは、三日保つかどうかも怪しいな?」
私もウルも譲らない性格なので、下手に夫婦になどなったら意見がぶつかり合って喧嘩ばかりの日々だろう。何より、彼と家庭を築くなんてこと、全然想像できない。
彼の方も同じ意見のようで、アシェラとベッドになんか入ったら寝首をかかれそう、なんて随分と失礼なことを呟いた。
「で? さっきから俺の足を踏みつけているお前は、何か言うことはないのか? ──ロッツ」
その失礼な男の左足を思い切り踏みつけてやると、どうやらすでに右足を踏んでいた者があったらしい。
両足の甲に大きさ違いの靴跡を刻まれて情けない顔をするウル越しに、私は同志に目を向けた。
すると、綺麗な菫色の瞳がこちらを見つめ返してきたかと思ったら、ゆっくりとその口が開き──
「僕はね、アシェラが決めたことに口出しをしないよ」
私は、がっかりした。
「でも、幸せになってほしいと思う。大切なひとだから」
「そう……ありがとう」
この時、私達は三年生になっていた。
お人形さんのように愛らしかったロッツに、身長を抜かされたと気づいたのはつい先日のことだ。
年齢にして十三歳。入学した時よりも大人びた私は、もう自覚していた。
彼に──ロッツに、恋をしていることに。
フェルデン公爵家は、代々ヴィンセント王国の宰相を務めてきた。
そのため、現フェルデン公爵のたった一人の子供であるロッツにも、期待と責任が重くのしかかっている。いずれヴィンセント国王となるウルを支えるのも彼だろう。
ウルは強くて魅力的な男だが、情に脆くて奔放だ。彼の代わりに冷酷な決断を下し舵を取ることを、きっとロッツは求められる。
私もそうだ。
ラインが次のヒンメル国王となるならば、明らかに力不足の彼を支えるのは私の役目。
しかし、私も、ロッツも、天才ではない。
ともに血の滲むような努力をした上で、毎回首位争いをしているのだ。
ロッツの痛みが、私にはわかる。
私の痛みも、きっと彼が知っているだろう。
切磋琢磨し合える彼の存在が尊かった。
負ければ悔しいが、しかし素直に賞賛の気持ちが湧くこの関係が愛おしい。
ロッツもまた、私の努力を認め、一人の人間として尊重してくれているのがひしひしと伝わってくる。
だから──
「──ちょっと成績がいいからって、調子に乗るなよ!」
人生をともに歩むことを定められてしまった相手から、こんな風に努力も志も踏み躙られてしまうと、私は何もかもが虚しくなってしまう。
成績表が張り出された日の放課後、ラインは決まって私を王宮の自室に呼びつけた。
そうして、成績の振るわない自分をばかにしている、と根も葉もないことを言って詰るのだ。
部屋には私達二人だけ。彼の理不尽な発言を諌める者はいない。
「ちょっとはさぁ、僕に花を持たそうとか考えつかないわけ!?」
ラインは思慮に欠ける言動が多いが、よほどのことでもない限りダールグレン公爵家から婚約解消を申し出るのは難しいということだけは理解していた。
だから、少しくらい暴言を吐きつけたって、私が自分から離れられないと思っているのだろう。それがまた、彼を苛立たせているのかもしれない。
ともかく、私も反論するだけ無駄だと知っているから、毎回黙って彼の話を聞き流してきたが……
そのため、現フェルデン公爵のたった一人の子供であるロッツにも、期待と責任が重くのしかかっている。いずれヴィンセント国王となるウルを支えるのも彼だろう。
ウルは強くて魅力的な男だが、情に脆くて奔放だ。彼の代わりに冷酷な決断を下し舵を取ることを、きっとロッツは求められる。
私もそうだ。
ラインが次のヒンメル国王となるならば、明らかに力不足の彼を支えるのは私の役目。
しかし、私も、ロッツも、天才ではない。
ともに血の滲むような努力をした上で、毎回首位争いをしているのだ。
ロッツの痛みが、私にはわかる。
私の痛みも、きっと彼が知っているだろう。
切磋琢磨し合える彼の存在が尊かった。
負ければ悔しいが、しかし素直に賞賛の気持ちが湧くこの関係が愛おしい。
ロッツもまた、私の努力を認め、一人の人間として尊重してくれているのがひしひしと伝わってくる。
だから──
「──ちょっと成績がいいからって、調子に乗るなよ!」
人生をともに歩むことを定められてしまった相手から、こんな風に努力も志も踏み躙られてしまうと、私は何もかもが虚しくなってしまう。
成績表が張り出された日の放課後、ラインは決まって私を王宮の自室に呼びつけた。
そうして、成績の振るわない自分をばかにしている、と根も葉もないことを言って詰るのだ。
部屋には私達二人だけ。彼の理不尽な発言を諌める者はいない。
「ちょっとはさぁ、僕に花を持たそうとか考えつかないわけ!?」
ラインは思慮に欠ける言動が多いが、よほどのことでもない限りダールグレン公爵家から婚約解消を申し出るのは難しいということだけは理解していた。
だから、少しくらい暴言を吐きつけたって、私が自分から離れられないと思っているのだろう。それがまた、彼を苛立たせているのかもしれない。
ともかく、私も反論するだけ無駄だと知っているから、毎回黙って彼の話を聞き流してきたが……
「本当に、アシェラは可愛くないなっ! 僕に捨てられたら、君なんて誰にも見向きされないくせにっ!」
この時は、我慢ができなかった。
ここに来る少し前に、偶然見てしまったからだ。
校舎の陰で、キスをする二人の姿を。
才色兼備と評判の五年生の公爵令嬢と──ロッツだった。
それは、私の初恋が静かに幕を閉じた瞬間だった。
脳裏に焼き付いたその光景を振り払うように、私は一度ぎゅっときつく瞼を閉じる。
そうして、再び開いた両目でラインを見据えた。
「な、何だよ……」
とたんに、ビクリと慄いた情けない許嫁に対し、にっこりと微笑む。
小さく首を傾げて、私は言い放った。
「私が可愛くしていれば──あなたの成績が、少しは伸びるのですか?」
「なっ、なな、何だと……っ!?」
カッと顔を赤くしたラインが衝動的に右手を振り上げる。
浅はかな相手に、私はいっそほくそ笑んだ。
パンッと乾いた音が響き、扉の向こうで聞き耳でも立てていたのか、侍従が血相を変えて飛び込んでくる。
私が誰かにぶたれたのは、あれが最初で最後だった。
この時は、我慢ができなかった。
ここに来る少し前に、偶然見てしまったからだ。
校舎の陰で、キスをする二人の姿を。
才色兼備と評判の五年生の公爵令嬢と──ロッツだった。
それは、私の初恋が静かに幕を閉じた瞬間だった。
脳裏に焼き付いたその光景を振り払うように、私は一度ぎゅっときつく瞼を閉じる。
そうして、再び開いた両目でラインを見据えた。
「な、何だよ……」
とたんに、ビクリと慄いた情けない許嫁に対し、にっこりと微笑む。
小さく首を傾げて、私は言い放った。
「私が可愛くしていれば──あなたの成績が、少しは伸びるのですか?」
「なっ、なな、何だと……っ!?」
カッと顔を赤くしたラインが衝動的に右手を振り上げる。
浅はかな相手に、私はいっそほくそ笑んだ。
パンッと乾いた音が響き、扉の向こうで聞き耳でも立てていたのか、侍従が血相を変えて飛び込んでくる。
私が誰かにぶたれたのは、あれが最初で最後だった。
「いきなり暴力を振るうなんて……たとえ王家が相手でも、十分婚約解消を願い出ていい理由になると思うんですけどね。姉上も、それを計算していたのでしょう?」
「まったく計算がなかったと言えば、嘘になるわね。まあ、そううまくはいかなかったけれど」
「殿下を謹慎させた上、わざわざ陛下自らうちに謝りにいらしたんでしたっけ?」
「ええ。二度とあんなことはさせない、と床に額を擦り付ける勢いで謝られてしまっては、父様も陛下の面子を潰すわけにはいかなかったのでしょう」
祭壇の向こうにいた野ネズミが、ちょこちょこと階段を降りてきた。
しかし、私とジャック以外は壇上の茶番劇に気を取られていて、その小さな存在に気づくそぶりもない。
野ネズミは私の足下で立ち止まると、ふいにこちらを見上げてくる。
その深淵のごとき闇色の瞳を見返し、私の思考は再び過去へ飛ぶのだった。
「まったく計算がなかったと言えば、嘘になるわね。まあ、そううまくはいかなかったけれど」
「殿下を謹慎させた上、わざわざ陛下自らうちに謝りにいらしたんでしたっけ?」
「ええ。二度とあんなことはさせない、と床に額を擦り付ける勢いで謝られてしまっては、父様も陛下の面子を潰すわけにはいかなかったのでしょう」
祭壇の向こうにいた野ネズミが、ちょこちょこと階段を降りてきた。
しかし、私とジャック以外は壇上の茶番劇に気を取られていて、その小さな存在に気づくそぶりもない。
野ネズミは私の足下で立ち止まると、ふいにこちらを見上げてくる。
その深淵のごとき闇色の瞳を見返し、私の思考は再び過去へ飛ぶのだった。
三年生前期の成績が張り出された翌日。
私が左の頬を腫らして登校してきたものだから、王立学校は騒然となった。
もちろん、私は前日のことを他言などしなかったが、ラインが謹慎させられていると知れ渡れば、何があったのかは自ずとわかるだろう。
「俺が、ラインから奪ってやろうか?」
前日と同じセリフを、今度は真剣な顔をして言ってきたウルに、私は殊更明るい笑みを浮かべて否と答えた。
彼の横にいたロッツに──昨日失恋したばかりの相手に、かわいそうなどと絶対に思われたくなかったからだ。
「アシェラ、何があったの!? どうして、ラインは……」
「彼が短絡的なのは、今に始まったことではないわ。気にしないで」
険しい顔をして詰め寄ってきたロッツに、私は何でもないようにそう返す。
昨日の放課後に彼とキスをしていた五年生の公爵令嬢が、教室の入り口からすごい形相でこちらを睨んでいた。
これ以降、私はロッツに対する気持ちに蓋をし、友人として卒業までの時間を過ごす。
彼の方はその後、ウルと同じように恋人を取っ替え引っ替えし、私の胸は何度も痛みに苛まれたが、平静を取り繕うのなんて簡単だった。
だって、私はダールグレン公爵家の娘。
望まぬ結婚も、恋を捨てるのも──それが祖国のためになるのならば、特権階級に生まれ落ちた人間にとっての責務である。
私も、そしてラインも、どれだけ相手に不満があろうとも逃れられない。
そう、思っていた──諦めていた。
「何もかもを捨てて、自分に正直に生きられるような勇気がないの──私は、臆病者よ」
「臆病者だったとしても、私はアシェラが好きだよ? 野ネズミの神様もそう思うって」
鋭いところがあるスピカは私の想いに気づいていたようで、いつもそっと寄り添ってくれた。
なお、スピカは何かと野ネズミの神様とやらを引き合いに出してきたが、彼女が仲良くしていたらしいそいつを、私は一度も見たことがなかった。
私が左の頬を腫らして登校してきたものだから、王立学校は騒然となった。
もちろん、私は前日のことを他言などしなかったが、ラインが謹慎させられていると知れ渡れば、何があったのかは自ずとわかるだろう。
「俺が、ラインから奪ってやろうか?」
前日と同じセリフを、今度は真剣な顔をして言ってきたウルに、私は殊更明るい笑みを浮かべて否と答えた。
彼の横にいたロッツに──昨日失恋したばかりの相手に、かわいそうなどと絶対に思われたくなかったからだ。
「アシェラ、何があったの!? どうして、ラインは……」
「彼が短絡的なのは、今に始まったことではないわ。気にしないで」
険しい顔をして詰め寄ってきたロッツに、私は何でもないようにそう返す。
昨日の放課後に彼とキスをしていた五年生の公爵令嬢が、教室の入り口からすごい形相でこちらを睨んでいた。
これ以降、私はロッツに対する気持ちに蓋をし、友人として卒業までの時間を過ごす。
彼の方はその後、ウルと同じように恋人を取っ替え引っ替えし、私の胸は何度も痛みに苛まれたが、平静を取り繕うのなんて簡単だった。
だって、私はダールグレン公爵家の娘。
望まぬ結婚も、恋を捨てるのも──それが祖国のためになるのならば、特権階級に生まれ落ちた人間にとっての責務である。
私も、そしてラインも、どれだけ相手に不満があろうとも逃れられない。
そう、思っていた──諦めていた。
「何もかもを捨てて、自分に正直に生きられるような勇気がないの──私は、臆病者よ」
「臆病者だったとしても、私はアシェラが好きだよ? 野ネズミの神様もそう思うって」
鋭いところがあるスピカは私の想いに気づいていたようで、いつもそっと寄り添ってくれた。
なお、スピカは何かと野ネズミの神様とやらを引き合いに出してきたが、彼女が仲良くしていたらしいそいつを、私は一度も見たことがなかった。
結局、六年間の王立学校在学期間中、全十二回の成績発表のうち三回ばかり、私は悔しくも二位に終わっている。
単独首位を取れたのは四回。残り五回は同点首位で、争った相手は十二回ともロッツだった。
彼やウル、マチアスやスピカと、十歳から十六歳まで多感な時期をともに過ごした経験は、私にとってかけがえのない財産になっている。
無心に勉学に打ち込むことも、積極的に人脈を広げる努力もせず、無為に過ごしていたラインは、そんなことは知る由もないだろう。
けれども彼には、私にはない勇気があった。
それが証明されたのが、王立学校を卒業して四年あまりが経った今日、この瞬間だ。
過去から現在に意識を──野ネズミの黒々とした瞳から壇上に視線を戻した私は改めて口を開く。
「祖父達が勝手に決めた私との婚約を放棄し、自分で選んだ相手を妻とする──自分に正直に生きようとする勇気が、ラインにはあった」
「いやー……ただ単に、立場をわかっていないだけのような気もしますけど?」
ジャックが呆れるのはもっともで、ラインの立場では誉められたことではないし、実際誰も誉めてはくれないだろう。
私とて、ふざけるなと思わないでもないけれど……
「私には、できなかった。だから少しだけ、ラインが羨ましい」
「姉上……」
降り注ぐ日の光に照らされたラインとナミは、幸せそうだった。
たとえ、その光が神の祝福ではないとしても。
彼らがこれから歩む道筋には、光が差すことはないとわかっていても、あの光景を美しいと感じたのだ。
自嘲の笑みを浮かべる私を、ジャックと、そしてなぜか野ネズミも見つめていた。
そんな中、祭壇の真下にいた大司祭が、血の気の引いた顔でこちらを振り返る。
縋るようなその眼差しを、私は微笑みでもって拒絶した。
そして今度は、彼が聖女だと言いふらしたナミが、ヒンメル王国にやってきた時の記憶を手繰り寄せる。
単独首位を取れたのは四回。残り五回は同点首位で、争った相手は十二回ともロッツだった。
彼やウル、マチアスやスピカと、十歳から十六歳まで多感な時期をともに過ごした経験は、私にとってかけがえのない財産になっている。
無心に勉学に打ち込むことも、積極的に人脈を広げる努力もせず、無為に過ごしていたラインは、そんなことは知る由もないだろう。
けれども彼には、私にはない勇気があった。
それが証明されたのが、王立学校を卒業して四年あまりが経った今日、この瞬間だ。
過去から現在に意識を──野ネズミの黒々とした瞳から壇上に視線を戻した私は改めて口を開く。
「祖父達が勝手に決めた私との婚約を放棄し、自分で選んだ相手を妻とする──自分に正直に生きようとする勇気が、ラインにはあった」
「いやー……ただ単に、立場をわかっていないだけのような気もしますけど?」
ジャックが呆れるのはもっともで、ラインの立場では誉められたことではないし、実際誰も誉めてはくれないだろう。
私とて、ふざけるなと思わないでもないけれど……
「私には、できなかった。だから少しだけ、ラインが羨ましい」
「姉上……」
降り注ぐ日の光に照らされたラインとナミは、幸せそうだった。
たとえ、その光が神の祝福ではないとしても。
彼らがこれから歩む道筋には、光が差すことはないとわかっていても、あの光景を美しいと感じたのだ。
自嘲の笑みを浮かべる私を、ジャックと、そしてなぜか野ネズミも見つめていた。
そんな中、祭壇の真下にいた大司祭が、血の気の引いた顔でこちらを振り返る。
縋るようなその眼差しを、私は微笑みでもって拒絶した。
そして今度は、彼が聖女だと言いふらしたナミが、ヒンメル王国にやってきた時の記憶を手繰り寄せる。
あれは今から四年前、私やロッツが王立学校を卒業する間際のことだ。
大聖堂の祭壇の前──今まさにラインとともに立っている場所に現れた彼女は、その場に居合わせた司祭達に対し、自分はニホンなる小さな島国からやってきたと語ったという。
その噂をどこからか聞きつけてきたロッツに引っ張られて、私とウルも彼女に会いにいったのだ。
驚いたのは、異世界から来た、なんて奇想天外な主張をするわりに、ナミがあまりに凡庸だったこと。さらに……
「──出た、悪役令嬢!」
「まあ……それって、私のことかしら?」
初対面にもかかわらず、私を指差し悪役呼ばわりしてきたことだ。
これには、ロッツもウルも眉を顰めたが、一番眦をつり上げたのは私の手を握ってくっついてきていた小さな女の子──六歳になったヒンメル王女オリビアだった。
「無礼な女。アシェラが美しいから、しっとしたんでしょう。おまえは心までみにくくて救いようがないわね」
「ひ、ひどい……! ロッツ、この子何なの?」
切れ味鋭い六歳児の言葉にナミはすぐに涙ぐんで、なぜかロッツに縋ろうとしたが、彼もウルも相手にしなかった。
そもそも、ひどいのはどっちなのだか。
私はおそらく、これをきっかけに彼女に敵認定されたのだろう。
ナミを見る限り、異世界というのは随分と稚拙で野蛮なところなのかもしれない。
また、彼女が持ってきたスマホとかいう摩訶不思議な光る板は興味深かったが、その構造やら製法を尋ねたところで、本人は何一つ答えられなかった。
「しょ、しょうがないじゃない! 私が作ったんじゃないもん!」
「自分が使っているものがどういう理屈で成り立っているのか、知りたいとは思わなかったの?」
「普通思わないでしょ! そんなの知らなくたって、使えればいいんだし!」
「そうね……使えているうちは、いいのだけれど」
命あるものはいつか必ず死ぬ。
物も、やがて壊れる。
そんな当たり前のことも、異世界では教わらないのだろうか。
結局スマホとやらは三日と経たずに光を失い、本当にただの板となってしまった。
と同時に、ロッツもウルもナミに対する一切の興味を失い、必然的に私もそれ以上彼女と関わることはなかった。
オリビアに至っては、あれから四年経った現在でも蛇蝎のごとくナミを嫌っているらしい。
一方で、ダールグレン公爵家に対抗する術を渇望していた大聖堂と、何よりこの国の王子であるラインが、ナミという存在自体に過剰な可能性を見出した。
ナミは、ヒンメル王国のために神が選んで遣わせた聖女に違いないと騒ぎ始めたのだ。
大聖堂の祭壇の前──今まさにラインとともに立っている場所に現れた彼女は、その場に居合わせた司祭達に対し、自分はニホンなる小さな島国からやってきたと語ったという。
その噂をどこからか聞きつけてきたロッツに引っ張られて、私とウルも彼女に会いにいったのだ。
驚いたのは、異世界から来た、なんて奇想天外な主張をするわりに、ナミがあまりに凡庸だったこと。さらに……
「──出た、悪役令嬢!」
「まあ……それって、私のことかしら?」
初対面にもかかわらず、私を指差し悪役呼ばわりしてきたことだ。
これには、ロッツもウルも眉を顰めたが、一番眦をつり上げたのは私の手を握ってくっついてきていた小さな女の子──六歳になったヒンメル王女オリビアだった。
「無礼な女。アシェラが美しいから、しっとしたんでしょう。おまえは心までみにくくて救いようがないわね」
「ひ、ひどい……! ロッツ、この子何なの?」
切れ味鋭い六歳児の言葉にナミはすぐに涙ぐんで、なぜかロッツに縋ろうとしたが、彼もウルも相手にしなかった。
そもそも、ひどいのはどっちなのだか。
私はおそらく、これをきっかけに彼女に敵認定されたのだろう。
ナミを見る限り、異世界というのは随分と稚拙で野蛮なところなのかもしれない。
また、彼女が持ってきたスマホとかいう摩訶不思議な光る板は興味深かったが、その構造やら製法を尋ねたところで、本人は何一つ答えられなかった。
「しょ、しょうがないじゃない! 私が作ったんじゃないもん!」
「自分が使っているものがどういう理屈で成り立っているのか、知りたいとは思わなかったの?」
「普通思わないでしょ! そんなの知らなくたって、使えればいいんだし!」
「そうね……使えているうちは、いいのだけれど」
命あるものはいつか必ず死ぬ。
物も、やがて壊れる。
そんな当たり前のことも、異世界では教わらないのだろうか。
結局スマホとやらは三日と経たずに光を失い、本当にただの板となってしまった。
と同時に、ロッツもウルもナミに対する一切の興味を失い、必然的に私もそれ以上彼女と関わることはなかった。
オリビアに至っては、あれから四年経った現在でも蛇蝎のごとくナミを嫌っているらしい。
一方で、ダールグレン公爵家に対抗する術を渇望していた大聖堂と、何よりこの国の王子であるラインが、ナミという存在自体に過剰な可能性を見出した。
ナミは、ヒンメル王国のために神が選んで遣わせた聖女に違いないと騒ぎ始めたのだ。
「──で、結局あのバカ王子は、自分こそがその聖女様に選ばれた存在だと言いたいわけですね?」
そんなジャックの呟きが聞こえて、私の意識が再び過去から戻ってくる。
姉の私と違って天才肌の弟は、呆れ顔で続けた。
「姉上の名声が高まれば高まるほど、卑屈になってましたものねぇ、ライン殿下。自分よりバカのふりをしろって要求してきたこともあったんですって?」
「それで本当にバカのふりをするようなら、結局はその者もバカなのでしょう。私は、自分の名声のためでもラインのためでもなく、ヒンメル王国のために努力をしたんですもの」
そして今、私はヒンメル王妃にはならない──ラインに人生を捧げないで済むことが決定した。
私の笑顔を見るなりますます顔色を悪くした大司祭が、祭壇に続く階段に縋り付くようにして、嗄れた声で言う。
「で、殿下……恐れながら、これはあまりにも唐突なお話でございます。陛下は……父君はご承知なさっていらっしゃるので……」
「父上には、これからナミと一緒にご報告に伺うつもりだ! 将来国王となる僕が聖女と結ばれることを、さぞお喜びになることだろう!」
それを聞いた大司祭が、喉の奥でひいっと悲鳴を上げた。
この後ラインから、大聖堂の祭壇の前で私に婚約破棄を言い渡してきたと報告を受けた国王陛下も、同じくひいっと悲鳴を上げるだろう。
王子の自覚がないラインの扱いに悩み、将来私が彼を支えることに人一倍期待を寄せていたのは、国王陛下なのだから。
「陛下、泣いちゃうかも……いや、禿げちゃうかもしれませんねー」
「まあまあ、お気の毒ねぇ」
「あーあ、ヒンメル王国は前途多難だなぁー」
「大丈夫よ。陛下の子供は、ラインだけではないわ」
かつて、私を引っ叩いたことで危うく婚約解消の話が出かけたのを、国王陛下が臣下に頭を下げてまで回避したというのに、本当に気の毒なことである。
親の心子知らずとはよく言ったものだ。
しかし、今回ばかりは国王陛下といえど婚約解消を阻止することはできないだろう。
観客が大勢いたのが理由ではない。
場所が、問題だった。
そんなジャックの呟きが聞こえて、私の意識が再び過去から戻ってくる。
姉の私と違って天才肌の弟は、呆れ顔で続けた。
「姉上の名声が高まれば高まるほど、卑屈になってましたものねぇ、ライン殿下。自分よりバカのふりをしろって要求してきたこともあったんですって?」
「それで本当にバカのふりをするようなら、結局はその者もバカなのでしょう。私は、自分の名声のためでもラインのためでもなく、ヒンメル王国のために努力をしたんですもの」
そして今、私はヒンメル王妃にはならない──ラインに人生を捧げないで済むことが決定した。
私の笑顔を見るなりますます顔色を悪くした大司祭が、祭壇に続く階段に縋り付くようにして、嗄れた声で言う。
「で、殿下……恐れながら、これはあまりにも唐突なお話でございます。陛下は……父君はご承知なさっていらっしゃるので……」
「父上には、これからナミと一緒にご報告に伺うつもりだ! 将来国王となる僕が聖女と結ばれることを、さぞお喜びになることだろう!」
それを聞いた大司祭が、喉の奥でひいっと悲鳴を上げた。
この後ラインから、大聖堂の祭壇の前で私に婚約破棄を言い渡してきたと報告を受けた国王陛下も、同じくひいっと悲鳴を上げるだろう。
王子の自覚がないラインの扱いに悩み、将来私が彼を支えることに人一倍期待を寄せていたのは、国王陛下なのだから。
「陛下、泣いちゃうかも……いや、禿げちゃうかもしれませんねー」
「まあまあ、お気の毒ねぇ」
「あーあ、ヒンメル王国は前途多難だなぁー」
「大丈夫よ。陛下の子供は、ラインだけではないわ」
かつて、私を引っ叩いたことで危うく婚約解消の話が出かけたのを、国王陛下が臣下に頭を下げてまで回避したというのに、本当に気の毒なことである。
親の心子知らずとはよく言ったものだ。
しかし、今回ばかりは国王陛下といえど婚約解消を阻止することはできないだろう。
観客が大勢いたのが理由ではない。
場所が、問題だった。
「殿下! 無礼を承知で申し上げます! どうか……どうか、お考え直しくださいっ!!」
「大司祭ともあろうものが何を言う? 知らないわけではあるまい! 大聖堂の祭壇の前──ヒンメルの神の御前で宣言したことは、何があっても撤回できないんだ!」
「し、しかし……!」
「黙れ! お前、ナミの後見人のくせに、僕との仲にケチをつける気かっ!」
大司祭は浅はかだが、ラインほど愚かではない。
この王子がヒンメル王国を一人で背負うことも、ナミがそれを支えることも、まったくもって現実的ではない、とこの四年で思い知ったのだろう。
「王立学校を卒業して、四年。姉上がヒンメル王国をはじめ、大陸中の国々の歴史を研究し、王立学校と各国の関わり方、ひいてはヒンメル王国の今後のあり方を模索している間、あの王子はいったい何考えて生きてたんでしょうね?」
「ナミと楽しくやっていたんじゃないかしら。私としては、ラインに放っておかれたおかげで誰にも邪魔されずに研究に打ち込めて、たいそう快適でしたけれど」
ヒンメル王国が廃れればヒンメル聖教も廃れる。これは自然の摂理だ。
ナミを聖女として持ち上げたことも、彼女をラインにあてがったことも、失策であったと大聖堂も認めざるをえない。
それを証拠に、大聖堂はここ最近ダールグレン公爵家に擦り寄り始めていた。
今日、私とジャックがこうして大聖堂を訪れたのだって、年に一回ここで開かれるバザーに十数年ぶりに呼ばれた父の名代だ。
バザーの開催を明日に控え、多くの物品と寄付を届けた私達を、大司祭は揉み手をしながら歓迎した。
あの聖職者とは思えぬ俗臭ぷんぷんの笑顔に完璧な挨拶を返せた弟を、私はたくさん誉めてあげたい。
そんなことをつらつらと考えていると、アシェラ、とふいに壇上から声がかかった。
ラインに名前を呼ばれたのは随分と久方ぶりのことだが、あいにく何の感慨も浮かばない。
それでも、はい、と私が従順そうに返事をすると、彼はなぜか勝ち誇った顔をして……
「僕を慕ってくれているアシェラには申しわけ──」
「──おかまいなく」
わざわざ聞く価値もない話を始めたため、最後まで言わせなかった。
ラインはあからさまにムッとした表情をし、彼に肩を抱かれているナミも不快そうに顔を歪めたが、私は逆にここぞとばかりに満面の笑みを浮かべる。
そうして、大聖堂中の視線が自分に集まるのを確認してから、口を開いた。
「殿下と妃殿下に、神の御加護があらんことをお祈り申し上げます。どうぞ、末長くお幸せに」
これには、ラインもナミも、ぽかんとした顔になった。
ラインは私の鼻をへし折ってやろうと、こんな公衆の面前で婚約破棄劇を敢行したに違いない。
ナミも、大聖堂からダールグレン公爵家への悪意を植え付けられていただろうし、相変わらず私自身のことを敵視していたようだから。
ラインもナミも、婚約破棄されて打ち拉がれる私の惨めな姿を見たかったのだろう。
見当違いな二人の間抜け面に、ジャックは隣で懸命に笑いを噛み殺している。
かと思ったら彼が、ああ! と大仰に声を上げた。
「大司祭ともあろうものが何を言う? 知らないわけではあるまい! 大聖堂の祭壇の前──ヒンメルの神の御前で宣言したことは、何があっても撤回できないんだ!」
「し、しかし……!」
「黙れ! お前、ナミの後見人のくせに、僕との仲にケチをつける気かっ!」
大司祭は浅はかだが、ラインほど愚かではない。
この王子がヒンメル王国を一人で背負うことも、ナミがそれを支えることも、まったくもって現実的ではない、とこの四年で思い知ったのだろう。
「王立学校を卒業して、四年。姉上がヒンメル王国をはじめ、大陸中の国々の歴史を研究し、王立学校と各国の関わり方、ひいてはヒンメル王国の今後のあり方を模索している間、あの王子はいったい何考えて生きてたんでしょうね?」
「ナミと楽しくやっていたんじゃないかしら。私としては、ラインに放っておかれたおかげで誰にも邪魔されずに研究に打ち込めて、たいそう快適でしたけれど」
ヒンメル王国が廃れればヒンメル聖教も廃れる。これは自然の摂理だ。
ナミを聖女として持ち上げたことも、彼女をラインにあてがったことも、失策であったと大聖堂も認めざるをえない。
それを証拠に、大聖堂はここ最近ダールグレン公爵家に擦り寄り始めていた。
今日、私とジャックがこうして大聖堂を訪れたのだって、年に一回ここで開かれるバザーに十数年ぶりに呼ばれた父の名代だ。
バザーの開催を明日に控え、多くの物品と寄付を届けた私達を、大司祭は揉み手をしながら歓迎した。
あの聖職者とは思えぬ俗臭ぷんぷんの笑顔に完璧な挨拶を返せた弟を、私はたくさん誉めてあげたい。
そんなことをつらつらと考えていると、アシェラ、とふいに壇上から声がかかった。
ラインに名前を呼ばれたのは随分と久方ぶりのことだが、あいにく何の感慨も浮かばない。
それでも、はい、と私が従順そうに返事をすると、彼はなぜか勝ち誇った顔をして……
「僕を慕ってくれているアシェラには申しわけ──」
「──おかまいなく」
わざわざ聞く価値もない話を始めたため、最後まで言わせなかった。
ラインはあからさまにムッとした表情をし、彼に肩を抱かれているナミも不快そうに顔を歪めたが、私は逆にここぞとばかりに満面の笑みを浮かべる。
そうして、大聖堂中の視線が自分に集まるのを確認してから、口を開いた。
「殿下と妃殿下に、神の御加護があらんことをお祈り申し上げます。どうぞ、末長くお幸せに」
これには、ラインもナミも、ぽかんとした顔になった。
ラインは私の鼻をへし折ってやろうと、こんな公衆の面前で婚約破棄劇を敢行したに違いない。
ナミも、大聖堂からダールグレン公爵家への悪意を植え付けられていただろうし、相変わらず私自身のことを敵視していたようだから。
ラインもナミも、婚約破棄されて打ち拉がれる私の惨めな姿を見たかったのだろう。
見当違いな二人の間抜け面に、ジャックは隣で懸命に笑いを噛み殺している。
かと思ったら彼が、ああ! と大仰に声を上げた。
この作家の他の作品
表紙を見る
王城でのパーティーの最中に毒を盛られて絶命した
侯爵令嬢アヴィス。
王子の許嫁として清く正しく慎ましく生きてきた彼女の魂は、
本来なら天界に行くはずが、気がつくとなぜか魔界にいて、
酔っ払った魔王と愉快な仲間達の血肉により新たな肉体を得ていた。
アヴィスを我が子と呼んで溺愛する美貌の最強魔王ギュスターヴをはじめ、
堕天使、夢魔、女吸血鬼やツンデレメイドなどイカれた面々をも振り回しつつ、
アヴィスは元気いっぱいかつ自由気ままに新しい人生を歩み出す。
しかし、自分に毒を盛ったと冤罪をかけられた王子を心配して軽率に地界に戻ってみたり、
うっかり騙されたり攫われたり召喚されたりと慌ただしい日々の中、
アヴィスは世界が生前思っていたものとは違うこと、
さらに自分を殺した真犯人とそれに天界の思惑が関わっていることを知る。
また、魔界に来て早々アヴィスに懐いた屍剣士のことを、
許嫁の王子はなぜか知っているようで……
「魔王たる私の寝首を掻く者がいるとしたら……それはお前だろうな、アヴィス」
門限五時、厳守!
最強の保護者こと魔王のスネを全力でかじりながら第二の人生を謳歌するアヴィスと、
その扱いに悩んで育児板を覗きつつも毎回力業で解決してしまう魔王による、
おもしろおかしく
血腥く
そして、愛に溢れる日々の物語。
表紙を見る
代々コーヒー狂を輩出してきた
フォルコ家の娘イヴは
王宮一階大階段脇にある
コーヒー専門店『カフェ・フォルコ』
の店長代理を務めている。
さまざまな獣人の末裔が暮らす世界でコーヒーを提供する傍ら
彼女は優れた記憶力を活かして客から客への伝言も請け負う。
兄の幼馴染みで、強く頼もしく、そして
〝世界一かわいい〟
第一王子ウィリアムに
見守られ助けられながら
常連客同士の仲を取り持ったり
時には修羅場に巻き込まれたりと
日々大忙し!
表紙を見る
高齢の魔王に代わり、人間の箱入り末王女アメリと結婚したのは、魔王の副官を務める青年魔族ローエン。
「出自に問題がある自分は、一国の姫を娶るには分不相応だ」
そう思い込んでいるローエンは、唯一誇れる肩書きである〝魔王の副官〟の沽券を保とうと努めるのだが、アメリ姫の笑顔の前では調子を崩されっぱなしで……
政略結婚で始まった二人の、新婚生活一月目。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…