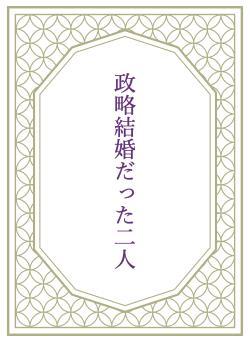前のページを表示する
最初にロッツの行動に疑問を抱いたのは、四年前──ナミが現れた時だった。
私とウルは彼に誘われ、異世界から来たというナミに会いに行ったわけだが、彼女はその時ロッツの名前を知っていた。
つまり、彼らはすでに面識があったのだ。
「ナミは〝摩訶不思議な光る板を持って現れただけの異世界人を自称する只人〟だった。ウルと引き合わせるに値する人材ではなかったわ。あなたは彼女と先に会って、それを確認したはずよ」
それなのに、どうしてロッツはウルを会わせたのか?
「あなたがナミと本当に会わせたかったのは、ウルじゃない。ウルの行くところにならどこへでもついて行きたがったオリビア王女と──そして、私を会わせたかったのね」
オリビアがナミを嫌うであろうことも、ナミが私を敵視するようになることも、ロッツは確信していたのだろう。
──性悪王女と悪役令嬢に寄ってたかってイジワルをされる可哀想なワタシ!
そう、ナミが自分の状況を脚色することも、彼は分かっていた。
明確な敵を持ったナミは、自分をちやほやする大聖堂とラインにどんどんと依存していく。
聖女に選ばれた自分に酔うラインの心もますます私から離れていった。
「そもそもおかしいのよね。聖女なんてもの、ヒンメル聖教の経典にはどこにも載っていないの。それなのに、どうして大聖堂がナミにそう称することを思いついたのか……」
ところで、ラインとの婚約破棄から三日が経ったが、その間、傷心のあまり自室に閉じこもったことになっている私を見舞った者が何人もいた。
大司祭もその一人だ。
一気に老け込んだ様子の彼を手厚くもてなしつつ、私は問うた。
いったい誰が、最初に〝聖女〟なんて言葉を持ち出したのか、と。
私とウルは彼に誘われ、異世界から来たというナミに会いに行ったわけだが、彼女はその時ロッツの名前を知っていた。
つまり、彼らはすでに面識があったのだ。
「ナミは〝摩訶不思議な光る板を持って現れただけの異世界人を自称する只人〟だった。ウルと引き合わせるに値する人材ではなかったわ。あなたは彼女と先に会って、それを確認したはずよ」
それなのに、どうしてロッツはウルを会わせたのか?
「あなたがナミと本当に会わせたかったのは、ウルじゃない。ウルの行くところにならどこへでもついて行きたがったオリビア王女と──そして、私を会わせたかったのね」
オリビアがナミを嫌うであろうことも、ナミが私を敵視するようになることも、ロッツは確信していたのだろう。
──性悪王女と悪役令嬢に寄ってたかってイジワルをされる可哀想なワタシ!
そう、ナミが自分の状況を脚色することも、彼は分かっていた。
明確な敵を持ったナミは、自分をちやほやする大聖堂とラインにどんどんと依存していく。
聖女に選ばれた自分に酔うラインの心もますます私から離れていった。
「そもそもおかしいのよね。聖女なんてもの、ヒンメル聖教の経典にはどこにも載っていないの。それなのに、どうして大聖堂がナミにそう称することを思いついたのか……」
ところで、ラインとの婚約破棄から三日が経ったが、その間、傷心のあまり自室に閉じこもったことになっている私を見舞った者が何人もいた。
大司祭もその一人だ。
一気に老け込んだ様子の彼を手厚くもてなしつつ、私は問うた。
いったい誰が、最初に〝聖女〟なんて言葉を持ち出したのか、と。
「大司祭様は、ロッツだと言ったわ。ナミが現れたその日のうちに会いにきたロッツが、〝異世界から聖女が遣わされたのかな〟って呟いたんですって。あなた、覚えはある?」
「どうかなぁ。そんなどうでもいいこと、覚えてないかも」
とぼけるロッツを一睨みして、私は続ける。
「あなたの行動が怪しいと思うようになったとたん、他にもひっかかることがいくつか出てきたのよね」
私はここでロッツの胸ぐらを離したが、すかさずその手を握られてしまった。
彼はそれに唇を寄せながら、美しく微笑んで首を傾げる。
「へえ、例えば?」
「そう、例えば──私が、ラインに引っ叩かれた時」
とたん、わずかに強ばった目の前の顔に、私も微笑み返して続けた。
「侍従がすぐに飛び込んできたのよ。いつもはそんなことしないのに、あの時に限ってどうして扉の外で聞き耳を立てていたのか……思い返すと不思議なのよね」
国王陛下も、この三日の間に私を訪ねてきていた。
私とラインの関係がもはや修復不可能と悟った陛下は、これまでの彼の心ない行いを詫び、父の請求通りに慰謝料を支払うと約束してくれた。
そんな彼に、ちょうど件の侍従が随行していたため、私はこっそり当時のことを尋ねたのだ。
「彼もね、ロッツに言われたのですって」
そう告げても、目の前の相手が焦る様子はなかったが……
「どうかなぁ。そんなどうでもいいこと、覚えてないかも」
とぼけるロッツを一睨みして、私は続ける。
「あなたの行動が怪しいと思うようになったとたん、他にもひっかかることがいくつか出てきたのよね」
私はここでロッツの胸ぐらを離したが、すかさずその手を握られてしまった。
彼はそれに唇を寄せながら、美しく微笑んで首を傾げる。
「へえ、例えば?」
「そう、例えば──私が、ラインに引っ叩かれた時」
とたん、わずかに強ばった目の前の顔に、私も微笑み返して続けた。
「侍従がすぐに飛び込んできたのよ。いつもはそんなことしないのに、あの時に限ってどうして扉の外で聞き耳を立てていたのか……思い返すと不思議なのよね」
国王陛下も、この三日の間に私を訪ねてきていた。
私とラインの関係がもはや修復不可能と悟った陛下は、これまでの彼の心ない行いを詫び、父の請求通りに慰謝料を支払うと約束してくれた。
そんな彼に、ちょうど件の侍従が随行していたため、私はこっそり当時のことを尋ねたのだ。
「彼もね、ロッツに言われたのですって」
そう告げても、目の前の相手が焦る様子はなかったが……
「今日はラインの虫の居所がよくないから、取り返しのつかないことにならないよう注意しておいた方がいいよって。実際に虫の居所がよくないのは私の方だったけれど……あの日、私がラインにぶたれることも、あなたの想定内だったのね?」
「──ちがう!」
ここで、ロッツは初めて声を荒げた。
一瞬口を噤んだ私に少しだけばつが悪そうな顔をして、ちがうよ、と繰り返す。
「あんなことになる前に止めさせるために、わざわざ忠告したんだ。ラインに嫌がられても同席しろって言ったのに、あの侍従ときたら……。僕は誓って、君に痛い思いをさせる気なんて、なかった」
「そう、じゃあ──」
私はロッツの手を乱暴に振り払い、静かに問うた。
「私に、上級生とキスしているところを見せたのも、わざと?」
ロッツは一瞬きょとんとした顔をした。
かと思ったら、にっこりと微笑んで答える。
「そのつもりであそこにいたわけじゃないけど、君に見られたことには気づいていたよ。アシェラが嫉妬してくれて、うれしかったなぁ」
「最低……私があの時、あなたを好きだったことにも気づいていたのね?」
「うん、もちろん。アシェラが僕を好きになるのは真理だよ。だって、僕がそうなるように仕向けたんだもん」
「人の心をなんだと思っているのよ……」
腹を立てたら負けだと分かっていても、どうにもムカムカとしてしまう。
私は余裕のない表情を見られまいと顔を背けようとしたが、ふいに伸びてきた手にそれを阻まれてしまった。
ロッツは両の手で私の頬を包み込むと、お互いの鼻先がぶつかり合うくらいにまで顔を近づけて言う。
「言っておくけど──僕が先に、アシェラを好きになったんだからね?」
「……え?」
思いも寄らない言葉に、私は視線を上げる。
とたん、菫色の瞳に全てを絡め取られてしまった。
「──ちがう!」
ここで、ロッツは初めて声を荒げた。
一瞬口を噤んだ私に少しだけばつが悪そうな顔をして、ちがうよ、と繰り返す。
「あんなことになる前に止めさせるために、わざわざ忠告したんだ。ラインに嫌がられても同席しろって言ったのに、あの侍従ときたら……。僕は誓って、君に痛い思いをさせる気なんて、なかった」
「そう、じゃあ──」
私はロッツの手を乱暴に振り払い、静かに問うた。
「私に、上級生とキスしているところを見せたのも、わざと?」
ロッツは一瞬きょとんとした顔をした。
かと思ったら、にっこりと微笑んで答える。
「そのつもりであそこにいたわけじゃないけど、君に見られたことには気づいていたよ。アシェラが嫉妬してくれて、うれしかったなぁ」
「最低……私があの時、あなたを好きだったことにも気づいていたのね?」
「うん、もちろん。アシェラが僕を好きになるのは真理だよ。だって、僕がそうなるように仕向けたんだもん」
「人の心をなんだと思っているのよ……」
腹を立てたら負けだと分かっていても、どうにもムカムカとしてしまう。
私は余裕のない表情を見られまいと顔を背けようとしたが、ふいに伸びてきた手にそれを阻まれてしまった。
ロッツは両の手で私の頬を包み込むと、お互いの鼻先がぶつかり合うくらいにまで顔を近づけて言う。
「言っておくけど──僕が先に、アシェラを好きになったんだからね?」
「……え?」
思いも寄らない言葉に、私は視線を上げる。
とたん、菫色の瞳に全てを絡め取られてしまった。
「忘れもしない、あれは王立学校に入学して最初の成績発表の日──生まれて初めて敗北を味わった君の、愕然とした顔を見た時だよ」
「……最低なんですけれど」
「その綺麗な青い目を見開いてね、顔色は真っ白だった。泣いちゃうかなってドキドキしながら見ていたんだけど……君は、泣かなかったね。代わりに唇を噛み締めて、顔をぎゅっと顰めたんだ。なんて可愛い子なんだろうって、僕はその時、雷に打たれたような心地がしたんだよ」
「あなた、意地が悪いわ」
不貞腐れた私にふふと笑うと、ロッツは今度は私を膝に抱き上げてしまった。
いきなりのことに抗うことも忘れて固まった私を、幼い子をあやすみたいにゆらゆら揺らしながら続ける。
「どうやってお近づきになろうか策を練ろうとしていたら、翌日、君の方から話しかけてくれたんだもん。それはもう、天にも昇る気持ちだった。絶対この子と結婚しようって、その時決めたんだ」
「私の意思などお構いなく?」
「そんなことはないよ。単に、君も僕と結婚したいと思ってくれるように、誘導する気だっただけ。まあ、洗脳でもいいけど」
「こわ……」
私は、ロッツのことを大きく誤解していた。
私もロッツも天才ではなく、ともに血の滲むような努力をした上で、毎回首位争いをしていると思っていた。
お互いの痛みがわかる、切磋琢磨し合える尊い存在──そう思っていたのだ。
けれども違った。
ロッツは、私とは違う。
彼は、天才だ。
そして、それを隠していた。
では、なぜそうとわかるのかというと──彼の他にもう一人、身近にいるからだ。
私が逆立ちしたとしても、絶対に敵わないような、天才が。
「……最低なんですけれど」
「その綺麗な青い目を見開いてね、顔色は真っ白だった。泣いちゃうかなってドキドキしながら見ていたんだけど……君は、泣かなかったね。代わりに唇を噛み締めて、顔をぎゅっと顰めたんだ。なんて可愛い子なんだろうって、僕はその時、雷に打たれたような心地がしたんだよ」
「あなた、意地が悪いわ」
不貞腐れた私にふふと笑うと、ロッツは今度は私を膝に抱き上げてしまった。
いきなりのことに抗うことも忘れて固まった私を、幼い子をあやすみたいにゆらゆら揺らしながら続ける。
「どうやってお近づきになろうか策を練ろうとしていたら、翌日、君の方から話しかけてくれたんだもん。それはもう、天にも昇る気持ちだった。絶対この子と結婚しようって、その時決めたんだ」
「私の意思などお構いなく?」
「そんなことはないよ。単に、君も僕と結婚したいと思ってくれるように、誘導する気だっただけ。まあ、洗脳でもいいけど」
「こわ……」
私は、ロッツのことを大きく誤解していた。
私もロッツも天才ではなく、ともに血の滲むような努力をした上で、毎回首位争いをしていると思っていた。
お互いの痛みがわかる、切磋琢磨し合える尊い存在──そう思っていたのだ。
けれども違った。
ロッツは、私とは違う。
彼は、天才だ。
そして、それを隠していた。
では、なぜそうとわかるのかというと──彼の他にもう一人、身近にいるからだ。
私が逆立ちしたとしても、絶対に敵わないような、天才が。
「ジャックには、概ね悟られているとは思っていたよ。ただ、彼もアシェラとラインの婚約が気に入らないみたいだったから、僕のやり方を黙認してくれると高を括っていたんだけどね」
「ジャックは、自分からは何も言及してこなかったわよ。私の答え合わせに付き合ってくれたり、気まぐれにヒントをくれたりはしたけれど」
三つ下の弟ジャック。
彼は、ロッツと同じ天才だった。
王立学校時代は十二回の試験全てで満点首位を独占し、卒業した現在は国王陛下の補佐をする片手間で、王女オリビアの家庭教師まで務めている。
飄々としているように見せかけて、人の心を容易く意のままに操って支配する。
ジャックは間違いなく、ヒンメル王国の未来を背負う人間だった。
「ロッツだって、本当は全期満点首位を独占することは容易かったでしょうに。それなのに、どうして四回も私に勝たせたの?」
「だって、戦友だって思ってもらわないと、アシェラは僕を受け入れてくれなかったでしょ? 君の悔しがる顔も可愛いけど、喜ぶ顔はもっとずっと可愛いって知っていたからね」
「勝たせてもらったとも知らずに喜んでいた私を、ばかにしていたんでしょう?」
「アシェラをばかにしたことなんて、一度もないよ。いつだって一生懸命な君を尊敬していたし、君とともにあれた日々は今も僕の宝物だ」
そんなのうそだ、と吐き捨ててやりたくなった。
けれども思い止まったのは、ロッツと私の関係を、私とラインの関係に置き換えて想像したからだ。
ラインもかつて、私がよい成績を収める度に、凡庸な自分をばかにしているのかと詰った。
あの時、少しもそんなつもりはなかった私には、彼の気持ちが理解できなかったが……
「ラインも、きっとこんな気持ちだったのね」
私は、祖国のために努力をして結果を残しているだけであって、自分と彼を比べて優劣をつけたことなんて一度もなかった。
しかし、ラインはそう思わなかった。
私に嘲笑われているだろうと勝手に腹を立て……そして、ひどく傷ついていた。
私は彼と同じ立場になって、やっとそれに気づけたのだ。
「ラインに私の気持ちなんてわからないって思っていたけれど、私だって彼の気持ちをわかろうとはしなかった」
「ラインの話ばかりするの、やめてよ」
不貞腐れた顔をしたロッツが、手のひらで私の口を塞ごうとしてくる。
彼のこの嫉妬が本物なのか演技なのかは、私には判断がつかない。
けれども、もとよりロッツの気持ちなど慮るつもりもないため、その手を振り払って続けた。
「ロッツも同じよ。あなたがどれだけ天才だったとしても、私の気持ちはわからない」
「アシェラ……」
「私にも、あなたの気持ちはわからない」
「アシェラ」
ロッツから、ついに表情が消えた。
綺麗なばかりの人形のようなその顔を、私はまじまじと見つめて告げる。
「結局、人間は自分の気持ちしかわからないということね」
「ジャックは、自分からは何も言及してこなかったわよ。私の答え合わせに付き合ってくれたり、気まぐれにヒントをくれたりはしたけれど」
三つ下の弟ジャック。
彼は、ロッツと同じ天才だった。
王立学校時代は十二回の試験全てで満点首位を独占し、卒業した現在は国王陛下の補佐をする片手間で、王女オリビアの家庭教師まで務めている。
飄々としているように見せかけて、人の心を容易く意のままに操って支配する。
ジャックは間違いなく、ヒンメル王国の未来を背負う人間だった。
「ロッツだって、本当は全期満点首位を独占することは容易かったでしょうに。それなのに、どうして四回も私に勝たせたの?」
「だって、戦友だって思ってもらわないと、アシェラは僕を受け入れてくれなかったでしょ? 君の悔しがる顔も可愛いけど、喜ぶ顔はもっとずっと可愛いって知っていたからね」
「勝たせてもらったとも知らずに喜んでいた私を、ばかにしていたんでしょう?」
「アシェラをばかにしたことなんて、一度もないよ。いつだって一生懸命な君を尊敬していたし、君とともにあれた日々は今も僕の宝物だ」
そんなのうそだ、と吐き捨ててやりたくなった。
けれども思い止まったのは、ロッツと私の関係を、私とラインの関係に置き換えて想像したからだ。
ラインもかつて、私がよい成績を収める度に、凡庸な自分をばかにしているのかと詰った。
あの時、少しもそんなつもりはなかった私には、彼の気持ちが理解できなかったが……
「ラインも、きっとこんな気持ちだったのね」
私は、祖国のために努力をして結果を残しているだけであって、自分と彼を比べて優劣をつけたことなんて一度もなかった。
しかし、ラインはそう思わなかった。
私に嘲笑われているだろうと勝手に腹を立て……そして、ひどく傷ついていた。
私は彼と同じ立場になって、やっとそれに気づけたのだ。
「ラインに私の気持ちなんてわからないって思っていたけれど、私だって彼の気持ちをわかろうとはしなかった」
「ラインの話ばかりするの、やめてよ」
不貞腐れた顔をしたロッツが、手のひらで私の口を塞ごうとしてくる。
彼のこの嫉妬が本物なのか演技なのかは、私には判断がつかない。
けれども、もとよりロッツの気持ちなど慮るつもりもないため、その手を振り払って続けた。
「ロッツも同じよ。あなたがどれだけ天才だったとしても、私の気持ちはわからない」
「アシェラ……」
「私にも、あなたの気持ちはわからない」
「アシェラ」
ロッツから、ついに表情が消えた。
綺麗なばかりの人形のようなその顔を、私はまじまじと見つめて告げる。
「結局、人間は自分の気持ちしかわからないということね」
馬車は峠に差し掛かったらしく、勾配と揺れが激しくなった。
進行方向に向いた座席に座り直したロッツに、私はその腕の中から問う。
「ねえ、ロッツ。どうして、私とラインの婚約を解消させようとしたの?」
「そんなの、僕がアシェラと結婚したいからに決まって……」
「それも一因かもしれないけれど、一番の理由はそれじゃない」
「……」
きっぱりと言い切った私に、ロッツが口を噤む。
ガタガタと馬車が揺れた。
私を抱く腕に力が籠る。
菫色の瞳は逡巡しているように見えた。
私はそれをじっと見つめているうちに、不思議な心地を覚える。
十三歳のあの日──ロッツが五年生の公爵令嬢とキスしているのを目撃した日、私は彼に対する恋を諦めてよき友人であろうと決意した。
それなのに、ロッツの方はずっと私を手に入れる算段を立て続けていて、出会ってから十年が経った今、ついにこうしてヴィンセント王国へ連れ帰ろうとしているのだ。
すべては彼の思うがまま。
私は、彼の手のひらの上。
それなのに──
「ロッツ、はっきり言って」
私がそう急かすと、彼はひどく苦しそうな顔をした。
それでも、やがて観念したかのように口を開く。
「ヒンメル王国は、この大陸にとってなくてはならないものだ。王立学校は、各国の未来を背負う者達の出会いと交流の場となっている。国も文化も宗教も、全ての垣根を越えて学び切磋琢磨し合えるあんな場所は他にはありえない。万が一にもこれを廃れさせれば、やがて大陸中の不和に繋がるかもしれない。そんな国の王に──ラインは相応しくない」
きっぱりとそう言い切ったロッツは、それなのに、と続けた。
「アシェラが王妃となることに、ヒンメルの人々は希望を見出してしまっていた。君さえいれば、ラインが国王でもいけるんじゃないかってね」
相槌も打たない私に構わず、ロッツは畳み掛ける。
「僕に言わせれば、そんなものは幻想だよ。いくらアシェラが優秀でも、いつまでラインの泥舟で浮いていられると思う? そのうち、一緒に水底に沈むに決まってるんだ」
菫色の目がぐっと睨んだのは、ここにはいない元同級生の姿だろうか。
「幸い、ヒンメル国王にはもう一人子供が……王女がいる。オリビアはまだ幼く独善的なところはあるけれど、素直で勤勉だ。国民の受けもいい。何より──彼女の側にはジャックがいる」
弟の名が出たとたん、私の身体は無意識に震えた。
ロッツはそんな私を一度きつく抱き締めてから──私の望み通り、はっきりと引導を渡した。
進行方向に向いた座席に座り直したロッツに、私はその腕の中から問う。
「ねえ、ロッツ。どうして、私とラインの婚約を解消させようとしたの?」
「そんなの、僕がアシェラと結婚したいからに決まって……」
「それも一因かもしれないけれど、一番の理由はそれじゃない」
「……」
きっぱりと言い切った私に、ロッツが口を噤む。
ガタガタと馬車が揺れた。
私を抱く腕に力が籠る。
菫色の瞳は逡巡しているように見えた。
私はそれをじっと見つめているうちに、不思議な心地を覚える。
十三歳のあの日──ロッツが五年生の公爵令嬢とキスしているのを目撃した日、私は彼に対する恋を諦めてよき友人であろうと決意した。
それなのに、ロッツの方はずっと私を手に入れる算段を立て続けていて、出会ってから十年が経った今、ついにこうしてヴィンセント王国へ連れ帰ろうとしているのだ。
すべては彼の思うがまま。
私は、彼の手のひらの上。
それなのに──
「ロッツ、はっきり言って」
私がそう急かすと、彼はひどく苦しそうな顔をした。
それでも、やがて観念したかのように口を開く。
「ヒンメル王国は、この大陸にとってなくてはならないものだ。王立学校は、各国の未来を背負う者達の出会いと交流の場となっている。国も文化も宗教も、全ての垣根を越えて学び切磋琢磨し合えるあんな場所は他にはありえない。万が一にもこれを廃れさせれば、やがて大陸中の不和に繋がるかもしれない。そんな国の王に──ラインは相応しくない」
きっぱりとそう言い切ったロッツは、それなのに、と続けた。
「アシェラが王妃となることに、ヒンメルの人々は希望を見出してしまっていた。君さえいれば、ラインが国王でもいけるんじゃないかってね」
相槌も打たない私に構わず、ロッツは畳み掛ける。
「僕に言わせれば、そんなものは幻想だよ。いくらアシェラが優秀でも、いつまでラインの泥舟で浮いていられると思う? そのうち、一緒に水底に沈むに決まってるんだ」
菫色の目がぐっと睨んだのは、ここにはいない元同級生の姿だろうか。
「幸い、ヒンメル国王にはもう一人子供が……王女がいる。オリビアはまだ幼く独善的なところはあるけれど、素直で勤勉だ。国民の受けもいい。何より──彼女の側にはジャックがいる」
弟の名が出たとたん、私の身体は無意識に震えた。
ロッツはそんな私を一度きつく抱き締めてから──私の望み通り、はっきりと引導を渡した。
「ヒンメルの未来を担うのは、ラインとアシェラではない。オリビアとジャックだ。アシェラはもう──ヒンメルに必須の存在じゃないんだよ」
私は、たまらず両目を瞑った。
本当は、うすうす気づいていたのだ。
ただそれを認めることが辛くて、悔しくて、ずっと気づかないふりをしていた。
ジャックは生まれながらの天才で、私は努力に努力を重ねてようやく秀才と呼ばれるまでに這い上がった凡人。
その違いには、天と地ほど差がある。
ジャックがいれば、私はいらない。
私の努力を、祖国はもう必要としていない。
これを認めた瞬間、私は本当の意味で自由になったが、同時に心にぽっかりと大きな穴が空いた気分になった。
生きていくためには、きっとこの穴を何かで埋めなければならないだろう。
そんなことを考えながら目を開けて──ぎょっとした。
「……どうして、ロッツが泣くの?」
「僕にこんなことを言わせるなんて……アシェラはひどい」
目の前のロッツの頬が濡れている。
綺麗な菫色の瞳からは、次から次へと雫が溢れてきた。
大の男がこんなにボロボロと泣いていることに、私は呆気に取られる。
「言いたくなかった──気づかせたくなかったんだ。アシェラを、悲しませたくなかった。君の誇りを、傷つけたくなかった!」
ロッツは膝の上の私をぎゅうぎゅうと抱き締め、グスグスと鼻を啜りつつ震える声で言った。
その背中を宥めるように撫でながらも、この涙も計算なのかしら、とどこか冷めたことを考えている自分いる。
祖国に必要とされなくなった私は、これからこんな風に、ロッツに同情されつつヴィンセントで生きるのだろうか。
(虚しい……)
一つ、大きくため息をついた時だった。
「──わっ!?」
つんのめるようにして、馬車が急停止する。
さっと険しい表情になったロッツが、車窓のカーテンの隙間から外を覗いた。
夜の闇に沈んで、私の目には何も見えなかったが……
「──盗賊団だ」
潜めた声で、ロッツがそう呟いた。
「ちょっと片付けてくるね。絶対に、扉を開けてはいけないよ」
ロッツはそう言って、馬車を降りていった。
確か、近頃国境付近で盗賊団が暗躍しているとかなんとか父が言っていたような気がするが、運悪くそれに遭遇してしまったのだろう。
キンとかカンとか剣を打ち合う音や、オリャーだのドリャーだの男達の怒号が聞こえてくる。
ロッツもウルも腕に覚えがあるようだし、あのケットとかいう凄まじい面構えの御者も只者ではなさそうだった。
しかしながら相手の数が多いのか、なかなか決着がつくそぶりがない。
私は一人馬車の中、乳母が掛けてくれたケープを握り締めて息を潜めていたが……
「私はこれから、こんな風にロッツに守られるだけの人生を送るのかしら」
ふいに、ぽつりと自分の口から溢れ出したそんな言葉に、ぞっとした。
私は、ロッツのような天才ではないし、ウルみたいに周囲を惹きつけ従わせる天賦の才能を持っていない。
ケットのような屈強な身体でもない。
今出ていったって、きっと足手まといになるだけだろう。
けれど……
「私はずっと、対等でありたかった。ロッツとも、ラインとも……」
ヒヒンと馬のいななきが聞こえる。
それに交じって、カリカリと何かを引っ掻くような音が耳に届いた。
はっとして顔を上げた私は、思わず座席から腰を浮かせる。
カーテンの隙間から、黒々としたつぶらな瞳が覗いていたからだ。
「まあ……あなた、ついてきたの?」
よっ。
などと言って、窓の向こうでちっちゃな片手を上げたのは、紛れもない。
あの、黄金色の毛並みをした野ネズミだ。
野ネズミがよっなんて言うわけも、片手を上げて挨拶するわけもないので、やっぱり私は凄まじく疲れているのだろう。
そんな中、何やら野太い悲鳴がいくつも上がり、居ても立っても居られなくなる。
私は自分の荷物から取り出したあるものを握り締め、ついに馬車の扉を開いた。
ロッツはそう言って、馬車を降りていった。
確か、近頃国境付近で盗賊団が暗躍しているとかなんとか父が言っていたような気がするが、運悪くそれに遭遇してしまったのだろう。
キンとかカンとか剣を打ち合う音や、オリャーだのドリャーだの男達の怒号が聞こえてくる。
ロッツもウルも腕に覚えがあるようだし、あのケットとかいう凄まじい面構えの御者も只者ではなさそうだった。
しかしながら相手の数が多いのか、なかなか決着がつくそぶりがない。
私は一人馬車の中、乳母が掛けてくれたケープを握り締めて息を潜めていたが……
「私はこれから、こんな風にロッツに守られるだけの人生を送るのかしら」
ふいに、ぽつりと自分の口から溢れ出したそんな言葉に、ぞっとした。
私は、ロッツのような天才ではないし、ウルみたいに周囲を惹きつけ従わせる天賦の才能を持っていない。
ケットのような屈強な身体でもない。
今出ていったって、きっと足手まといになるだけだろう。
けれど……
「私はずっと、対等でありたかった。ロッツとも、ラインとも……」
ヒヒンと馬のいななきが聞こえる。
それに交じって、カリカリと何かを引っ掻くような音が耳に届いた。
はっとして顔を上げた私は、思わず座席から腰を浮かせる。
カーテンの隙間から、黒々としたつぶらな瞳が覗いていたからだ。
「まあ……あなた、ついてきたの?」
よっ。
などと言って、窓の向こうでちっちゃな片手を上げたのは、紛れもない。
あの、黄金色の毛並みをした野ネズミだ。
野ネズミがよっなんて言うわけも、片手を上げて挨拶するわけもないので、やっぱり私は凄まじく疲れているのだろう。
そんな中、何やら野太い悲鳴がいくつも上がり、居ても立っても居られなくなる。
私は自分の荷物から取り出したあるものを握り締め、ついに馬車の扉を開いた。
「これは……」
暗闇の中、盗賊達が持ち寄ったであろう松明でもって、驚くべき光景が浮かび上がっていた。
ロッツとウルとケット以外──つまり、盗賊達だけが何かの大群に襲われているのだ。
それは、茶色い毛並みの野ネズミだった。
「すごい……あの子達、もしかしてあなたのお友達?」
げぼくじゃ。
とかなんとか聞こえたような気がしたが、ともあれ味方ならばネズミでも何でも構わない。
私はとたんに、わくわくとした心地になった。
そのわくわくに背中を押され、馬車から御者台へと飛び移る。
ところが……
「お、女!? おい、すげぇ上玉、乗せてやがるじゃねぇかっ!!」
たまたま近くにいた盗賊に見つかってしまった。
しかも、彼が頭領なのだろうか。
図体の大きさも品の無さも悪意も、救いようのない方向にずば抜けている。
「荷も男もどうでもいい! この女だけもらってずらかるぞ!!」
男は爛々と目を輝かせ、身体中に張り付いていたネズミ達を振り払った。
そうして、その薄汚れた巨大な手を伸ばしてくる。
「アシェラ!!」
ロッツが鋭く私の名を呼んでこちらに駆け出したのと、
「──触らないでくださいな」
私の右の拳が唸るのは同時だった。
暗闇の中、盗賊達が持ち寄ったであろう松明でもって、驚くべき光景が浮かび上がっていた。
ロッツとウルとケット以外──つまり、盗賊達だけが何かの大群に襲われているのだ。
それは、茶色い毛並みの野ネズミだった。
「すごい……あの子達、もしかしてあなたのお友達?」
げぼくじゃ。
とかなんとか聞こえたような気がしたが、ともあれ味方ならばネズミでも何でも構わない。
私はとたんに、わくわくとした心地になった。
そのわくわくに背中を押され、馬車から御者台へと飛び移る。
ところが……
「お、女!? おい、すげぇ上玉、乗せてやがるじゃねぇかっ!!」
たまたま近くにいた盗賊に見つかってしまった。
しかも、彼が頭領なのだろうか。
図体の大きさも品の無さも悪意も、救いようのない方向にずば抜けている。
「荷も男もどうでもいい! この女だけもらってずらかるぞ!!」
男は爛々と目を輝かせ、身体中に張り付いていたネズミ達を振り払った。
そうして、その薄汚れた巨大な手を伸ばしてくる。
「アシェラ!!」
ロッツが鋭く私の名を呼んでこちらに駆け出したのと、
「──触らないでくださいな」
私の右の拳が唸るのは同時だった。
この作家の他の作品
表紙を見る
王城でのパーティーの最中に毒を盛られて絶命した
侯爵令嬢アヴィス。
王子の許嫁として清く正しく慎ましく生きてきた彼女の魂は、
本来なら天界に行くはずが、気がつくとなぜか魔界にいて、
酔っ払った魔王と愉快な仲間達の血肉により新たな肉体を得ていた。
アヴィスを我が子と呼んで溺愛する美貌の最強魔王ギュスターヴをはじめ、
堕天使、夢魔、女吸血鬼やツンデレメイドなどイカれた面々をも振り回しつつ、
アヴィスは元気いっぱいかつ自由気ままに新しい人生を歩み出す。
しかし、自分に毒を盛ったと冤罪をかけられた王子を心配して軽率に地界に戻ってみたり、
うっかり騙されたり攫われたり召喚されたりと慌ただしい日々の中、
アヴィスは世界が生前思っていたものとは違うこと、
さらに自分を殺した真犯人とそれに天界の思惑が関わっていることを知る。
また、魔界に来て早々アヴィスに懐いた屍剣士のことを、
許嫁の王子はなぜか知っているようで……
「魔王たる私の寝首を掻く者がいるとしたら……それはお前だろうな、アヴィス」
門限五時、厳守!
最強の保護者こと魔王のスネを全力でかじりながら第二の人生を謳歌するアヴィスと、
その扱いに悩んで育児板を覗きつつも毎回力業で解決してしまう魔王による、
おもしろおかしく
血腥く
そして、愛に溢れる日々の物語。
表紙を見る
代々コーヒー狂を輩出してきた
フォルコ家の娘イヴは
王宮一階大階段脇にある
コーヒー専門店『カフェ・フォルコ』
の店長代理を務めている。
さまざまな獣人の末裔が暮らす世界でコーヒーを提供する傍ら
彼女は優れた記憶力を活かして客から客への伝言も請け負う。
兄の幼馴染みで、強く頼もしく、そして
〝世界一かわいい〟
第一王子ウィリアムに
見守られ助けられながら
常連客同士の仲を取り持ったり
時には修羅場に巻き込まれたりと
日々大忙し!
表紙を見る
高齢の魔王に代わり、人間の箱入り末王女アメリと結婚したのは、魔王の副官を務める青年魔族ローエン。
「出自に問題がある自分は、一国の姫を娶るには分不相応だ」
そう思い込んでいるローエンは、唯一誇れる肩書きである〝魔王の副官〟の沽券を保とうと努めるのだが、アメリ姫の笑顔の前では調子を崩されっぱなしで……
政略結婚で始まった二人の、新婚生活一月目。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…