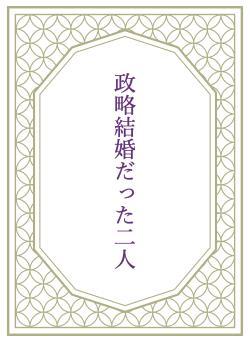「──アシェラ、すまなかった。ここまでお前の人生を縛ってきたこと……そうまでして守ってきた矜持を踏み躙られてしまったこと……すべては、私の責任だ」
「いいえ、父様。ラインとの婚約をお決めになったのは、父様ではなくお祖父様でしょう? それに、お祖父様もまさかこんなことになるとは想像もしていらっしゃらなかったでしょうから」
王立学校の学長室で逸早く騒動の報告を受けた父は、すぐさま国王陛下に謁見を願い出たのだという。
寝耳に水だった国王陛下は慌てふためき、いつぞやラインが私を引っ叩いた時と同様に謝り倒して婚約破棄を撤回しようとした。
ところが、そこにラインがナミをつれてやってきたものだから、さあ大変。
父こそが婚約破棄を阻止しにきたのだと勘違いしたラインは、彼の前で私のことを散々こき下ろし、いかに自分の妻にふさわしくないか、それはもう饒舌に語ったという。
もはや取りなすことも不可能と悟った国王陛下はその場に崩れ落ち、言いたいことを言い切ったラインは得意げに胸を張った。
異世界の王妃になれると信じて疑わないナミは悦に入り、這々の体で彼らを追ってきたらしい大司祭は紙のような顔色に。
そんな彼らに、父は静かに引導を渡したのだろう。
「アシェラには何の落ち度もない、一方的な婚約破棄だ。王家とライン殿下ご自身、それからナミの後見人である大司祭より、相応の慰謝料をいただくことになった」
彼らはこれを拒むことはできない。
なぜなら、世論がダールグレン公爵家に味方するからだ。
さらに、噂は十日と経たず大陸中に広がり、各国の要人となっている父の教え子達の耳にも届くだろう。
ヒンメル国王のもとには、公式非公式を問わず多く抗議や意見が寄せられるに違いない。
王家も、そして大聖堂も、もう父に頭が上がらなくなる。
(どこからどこまで、父様が計算していたのかは、わからないけれど……)
ところで、私は今年で二十歳になるのだが、貴族の娘ならすでに結婚して子供の一人や二人産んでいてもおかしくない年だ。
だからきっと、私にはすぐに新たな縁談相手があてがわれると思っていたが……
「慰謝料は、全てアシェラが受け取るといい。これからどう生きるかは、お前の好きに……」
「これからのことでしたら、もう決めております」
どうやらまだ結婚しなくていいようなので、父の気が変わらないうちに畳み掛ける。
「──私、旅に出ます。一人で」
しかし、そのせいで、大司祭と国王陛下に続いて父までも、ひいっと喉の奥で悲鳴を上げることになるとは思わなかった。
「いいえ、父様。ラインとの婚約をお決めになったのは、父様ではなくお祖父様でしょう? それに、お祖父様もまさかこんなことになるとは想像もしていらっしゃらなかったでしょうから」
王立学校の学長室で逸早く騒動の報告を受けた父は、すぐさま国王陛下に謁見を願い出たのだという。
寝耳に水だった国王陛下は慌てふためき、いつぞやラインが私を引っ叩いた時と同様に謝り倒して婚約破棄を撤回しようとした。
ところが、そこにラインがナミをつれてやってきたものだから、さあ大変。
父こそが婚約破棄を阻止しにきたのだと勘違いしたラインは、彼の前で私のことを散々こき下ろし、いかに自分の妻にふさわしくないか、それはもう饒舌に語ったという。
もはや取りなすことも不可能と悟った国王陛下はその場に崩れ落ち、言いたいことを言い切ったラインは得意げに胸を張った。
異世界の王妃になれると信じて疑わないナミは悦に入り、這々の体で彼らを追ってきたらしい大司祭は紙のような顔色に。
そんな彼らに、父は静かに引導を渡したのだろう。
「アシェラには何の落ち度もない、一方的な婚約破棄だ。王家とライン殿下ご自身、それからナミの後見人である大司祭より、相応の慰謝料をいただくことになった」
彼らはこれを拒むことはできない。
なぜなら、世論がダールグレン公爵家に味方するからだ。
さらに、噂は十日と経たず大陸中に広がり、各国の要人となっている父の教え子達の耳にも届くだろう。
ヒンメル国王のもとには、公式非公式を問わず多く抗議や意見が寄せられるに違いない。
王家も、そして大聖堂も、もう父に頭が上がらなくなる。
(どこからどこまで、父様が計算していたのかは、わからないけれど……)
ところで、私は今年で二十歳になるのだが、貴族の娘ならすでに結婚して子供の一人や二人産んでいてもおかしくない年だ。
だからきっと、私にはすぐに新たな縁談相手があてがわれると思っていたが……
「慰謝料は、全てアシェラが受け取るといい。これからどう生きるかは、お前の好きに……」
「これからのことでしたら、もう決めております」
どうやらまだ結婚しなくていいようなので、父の気が変わらないうちに畳み掛ける。
「──私、旅に出ます。一人で」
しかし、そのせいで、大司祭と国王陛下に続いて父までも、ひいっと喉の奥で悲鳴を上げることになるとは思わなかった。
「好きにしていいって言ったのに……父様は嘘つきだわ」
ビリビリという耳障りな音が響く中、私はもう何回目になるかもしれない愚痴をこぼした。
ラインから婚約破棄を言い渡されてから、今日で丸三日。
不本意ながら私は、ダールグレン公爵家の三階にある自室に軟禁されている。
あの夜、一人旅に出たいという私の申し出に、父もジャックも女だから危険だと猛反対した。
近頃国境沿いで盗賊団が暗躍しているとかなんとかうるさいので、だったら男のふりをして行くと言って早速髪を切り落とそうとすると、慌てふためいた二人は私をこの自室に閉じ込めてしまったのだ。
「私だって、一人で旅くらいできるわよ」
王立学校を卒業後、ロッツとウルはヴィンセント王国に戻るのではなく、二人で大陸中を旅して回っている。
そんな彼らから時々届く手紙を、私はこの四年間、何よりも楽しみにしてきた。
ずっと、彼らが羨ましかった。
私がラインと婚約していなかったら──いや、もしも男だったら一緒に連れていってもらえただろうか。
私は、自分がまだ井の中の蛙であることを知っている。
大きな父に守られたこの狭い井戸を出るのは、本当を言うと少し恐ろしいが、けれども婚約という足枷が外れたばかりの今しか、私は駆け出せないような気がするのだ。
そのためには、父を説得して許しを得るか──
「いいえ、もしかしたら父様は私を試しているのかもしれないわ。本気で旅に出たいなら自力でここから抜け出してみろ、ということなのね。きっとそう、そうに違いないわ」
そういうわけでこの日、ベランダからこっそり脱出する決意を固めた私は、部屋中のカーテンを引っ張り外してロープを作っているところだ。
現在、時刻は午後十時。
ジャック、乳母、母、父の順に先ほど就寝の挨拶をしにきたので、朝まではもうここを訪れる者はいないだろう。
奇しくも今宵は新月である。私はこの闇に紛れて家出を決行することにした。
最初に髪を切ると言ったせいか、ハサミやナイフなどの刃物を没収されてしまったが……
「あなたがいてくれてよかったわ」
思わぬ助っ人が、代わりにカーテンに切れ目を入れてくれたのだ。
私はその切れ目を利用して、さっきからカーテンを裂いている。
つまり、ビリビリという耳障りな音を立てているのは、私自身であった。
ビリビリという耳障りな音が響く中、私はもう何回目になるかもしれない愚痴をこぼした。
ラインから婚約破棄を言い渡されてから、今日で丸三日。
不本意ながら私は、ダールグレン公爵家の三階にある自室に軟禁されている。
あの夜、一人旅に出たいという私の申し出に、父もジャックも女だから危険だと猛反対した。
近頃国境沿いで盗賊団が暗躍しているとかなんとかうるさいので、だったら男のふりをして行くと言って早速髪を切り落とそうとすると、慌てふためいた二人は私をこの自室に閉じ込めてしまったのだ。
「私だって、一人で旅くらいできるわよ」
王立学校を卒業後、ロッツとウルはヴィンセント王国に戻るのではなく、二人で大陸中を旅して回っている。
そんな彼らから時々届く手紙を、私はこの四年間、何よりも楽しみにしてきた。
ずっと、彼らが羨ましかった。
私がラインと婚約していなかったら──いや、もしも男だったら一緒に連れていってもらえただろうか。
私は、自分がまだ井の中の蛙であることを知っている。
大きな父に守られたこの狭い井戸を出るのは、本当を言うと少し恐ろしいが、けれども婚約という足枷が外れたばかりの今しか、私は駆け出せないような気がするのだ。
そのためには、父を説得して許しを得るか──
「いいえ、もしかしたら父様は私を試しているのかもしれないわ。本気で旅に出たいなら自力でここから抜け出してみろ、ということなのね。きっとそう、そうに違いないわ」
そういうわけでこの日、ベランダからこっそり脱出する決意を固めた私は、部屋中のカーテンを引っ張り外してロープを作っているところだ。
現在、時刻は午後十時。
ジャック、乳母、母、父の順に先ほど就寝の挨拶をしにきたので、朝まではもうここを訪れる者はいないだろう。
奇しくも今宵は新月である。私はこの闇に紛れて家出を決行することにした。
最初に髪を切ると言ったせいか、ハサミやナイフなどの刃物を没収されてしまったが……
「あなたがいてくれてよかったわ」
思わぬ助っ人が、代わりにカーテンに切れ目を入れてくれたのだ。
私はその切れ目を利用して、さっきからカーテンを裂いている。
つまり、ビリビリという耳障りな音を立てているのは、私自身であった。
「それ、素敵な歯ね。そんなに丈夫なら、なんでも食べられるでしょう」
そう話しかけた私を、黒々としたつぶらな瞳が見上げてくる。
三日前、大聖堂にいたあの野ネズミである。
いつの間に馬車に乗り込んでいたのか、屋敷までついてきてしまったらしい。
私がこの自室に閉じ込められたばかりで最高にプンプンしているところに、そいつはひょっこりと現れた。
相変わらず薄汚れていたものだから、有無を言わさず洗面所でジャブジャブと丸洗い。
やめろぉー、とか言っていたような気もするが、野ネズミがしゃべるわけがないのできっと気のせいだろう。
しっかり汚れを落とせば、まるでよく実った小麦畑のような美しい黄金色の、ふかふかの毛並みになった。
とはいえ、きっと母や乳母などがこれを見たら卒倒するだろう。
父やジャックだって眉を顰め、追い出そうとするに違いない。
姿だけ見れば愛らしいが、何しろネズミは病気を媒介する生き物だ。
実際、ヒンメル王国は過去に何度も、ネズミによる疫病の蔓延で甚大な被害を出していた。
王家の始祖との知恵比べに負けたという、野ネズミの悪魔の意趣返しかもしれない。
私も彼らの恐ろしさを重々理解しているが、しかしどういうわけか、この目の前の野ネズミは邪険にしてはいけないような気がするのだ。
分けてやった食事を頬張る姿は愛らしく、それを眺めているうちに何やら心も穏やかになった。
「そうだ、まずはアーレンに行こう。スピカに会って、それからしばらく彼女のもとで働いてみるのもいいわね」
何かと野ネズミの神様とやらを引き合いに出していた隣国アーレン皇国の皇女スピカは、つい先日、七人の兄達を差し置いて皇位継承権第一位になった。
彼女とは卒業後も頻繁に手紙のやり取りをしているが、ラインに婚約破棄されたことはまだ伝えていない。
「どうせなら直接会って伝えましょう。あの子もずっと、私のことを心配してくれていたもの」
スピカの明るい笑顔を思い出し、一刻も早く彼女に会いたくなった私は、ついに結び終わったカーテンのロープをベランダの柵に括り付けた。
あらかじめ用意していた簡素な衣服に着替え、少しの衣類と食べ物、手持ちのお金などを詰め込んだ袋を背負う。
隣のジャックの部屋からは明かりが漏れていたが、カーテンが閉まっており、私の計画に気づいている様子はない。
そのさらに二つ向こうの両親の部屋もまだ明るかったが、幸いベランダに人影はなかった。
広い庭の向こうにある正門はすでに閉じられ、明かりも消えてしまっている。
あれを超えるのは至難の業であろうから、裏に回ろう。確か昔、ジャックがふざけて壊したせいで、柵が一本外れやすくなっている場所があったはずだ。
私はそんなことを考えながらベランダの柵を乗り越える。
運動神経が特別優れているわけではないが、なにしろ負けず嫌いなものだから、そんじょそこらの令嬢よりは度胸があると自負している。
そんなこんなで、カーテンのロープを支えにして早速二階付近まで壁を伝い降りたところ、ふと視線を感じて顔を上げた。
ベランダの柵の隙間から件の野ネズミが顔を出し、こちらを見下ろしていたのだ。
「……ネズミ。あなたも一緒にくる?」
ううむ、どうしようかのぅ。
なんて声が聞こえたような気がしたが、野ネズミがしゃべるわけがないのでやはり気のせいだろう。
しかし、逡巡するようにその場でくるくる回り始めたそいつに、焦れた私が片手を伸ばそうとした、その時だった。
「──アシェラぁああああ!?」
聞き覚えのある、しかしここにいるはずのない者の声が響いた。
そう話しかけた私を、黒々としたつぶらな瞳が見上げてくる。
三日前、大聖堂にいたあの野ネズミである。
いつの間に馬車に乗り込んでいたのか、屋敷までついてきてしまったらしい。
私がこの自室に閉じ込められたばかりで最高にプンプンしているところに、そいつはひょっこりと現れた。
相変わらず薄汚れていたものだから、有無を言わさず洗面所でジャブジャブと丸洗い。
やめろぉー、とか言っていたような気もするが、野ネズミがしゃべるわけがないのできっと気のせいだろう。
しっかり汚れを落とせば、まるでよく実った小麦畑のような美しい黄金色の、ふかふかの毛並みになった。
とはいえ、きっと母や乳母などがこれを見たら卒倒するだろう。
父やジャックだって眉を顰め、追い出そうとするに違いない。
姿だけ見れば愛らしいが、何しろネズミは病気を媒介する生き物だ。
実際、ヒンメル王国は過去に何度も、ネズミによる疫病の蔓延で甚大な被害を出していた。
王家の始祖との知恵比べに負けたという、野ネズミの悪魔の意趣返しかもしれない。
私も彼らの恐ろしさを重々理解しているが、しかしどういうわけか、この目の前の野ネズミは邪険にしてはいけないような気がするのだ。
分けてやった食事を頬張る姿は愛らしく、それを眺めているうちに何やら心も穏やかになった。
「そうだ、まずはアーレンに行こう。スピカに会って、それからしばらく彼女のもとで働いてみるのもいいわね」
何かと野ネズミの神様とやらを引き合いに出していた隣国アーレン皇国の皇女スピカは、つい先日、七人の兄達を差し置いて皇位継承権第一位になった。
彼女とは卒業後も頻繁に手紙のやり取りをしているが、ラインに婚約破棄されたことはまだ伝えていない。
「どうせなら直接会って伝えましょう。あの子もずっと、私のことを心配してくれていたもの」
スピカの明るい笑顔を思い出し、一刻も早く彼女に会いたくなった私は、ついに結び終わったカーテンのロープをベランダの柵に括り付けた。
あらかじめ用意していた簡素な衣服に着替え、少しの衣類と食べ物、手持ちのお金などを詰め込んだ袋を背負う。
隣のジャックの部屋からは明かりが漏れていたが、カーテンが閉まっており、私の計画に気づいている様子はない。
そのさらに二つ向こうの両親の部屋もまだ明るかったが、幸いベランダに人影はなかった。
広い庭の向こうにある正門はすでに閉じられ、明かりも消えてしまっている。
あれを超えるのは至難の業であろうから、裏に回ろう。確か昔、ジャックがふざけて壊したせいで、柵が一本外れやすくなっている場所があったはずだ。
私はそんなことを考えながらベランダの柵を乗り越える。
運動神経が特別優れているわけではないが、なにしろ負けず嫌いなものだから、そんじょそこらの令嬢よりは度胸があると自負している。
そんなこんなで、カーテンのロープを支えにして早速二階付近まで壁を伝い降りたところ、ふと視線を感じて顔を上げた。
ベランダの柵の隙間から件の野ネズミが顔を出し、こちらを見下ろしていたのだ。
「……ネズミ。あなたも一緒にくる?」
ううむ、どうしようかのぅ。
なんて声が聞こえたような気がしたが、野ネズミがしゃべるわけがないのでやはり気のせいだろう。
しかし、逡巡するようにその場でくるくる回り始めたそいつに、焦れた私が片手を伸ばそうとした、その時だった。
「──アシェラぁああああ!?」
聞き覚えのある、しかしここにいるはずのない者の声が響いた。
「──アシェラぁああああ!?」
突然、足下から名を叫ばれ、私は驚きのあまりロープから手を離してしまいそうになった。
「わっ……」
「ぎゃー! あぶないいいっ!! なにやってんのぉおお!?」
悲鳴のようなそのひどくやかましい声は、聞き覚えのある、しかしここにいるはずのない者の声だ。
私がなんとかロープを握り直したところ、バンッ、バンッ、と掃き出し窓を開ける音が続けて二つ響いた。
三階のベランダに、父とジャックが飛び出してくる。
父はベランダの柵から上半身を乗り出すようにして下を覗いているが、まだ私の存在には気づいていないようだ。
一方、真っ先に私に気づいたジャックが、あんぐりと口を開いたのが逆光の中でもわかった。
しかし、私は弟の間抜け面にかまっている余裕はない。
だって……
「──ロッツ?」
「と、ウルだな。二人とも立派な青年に成長したものだ──って、アシェラ!? お前、そこで何をっ!?」
「父様のご期待に応えようと、家出を決行している最中です」
「父さんは、そんな期待をした覚えはないんだがっ!? あああ、危ないっ……」
ダールグレン公爵家の庭に現れたのは、大陸を旅して回っているはずのロッツとウルだった。
二人とも、私では無理だと判断した正門を乗り越えてきたのだろうか。
父は思わぬ二人の登場に驚きつつ、さらにベランダからぶら下がっている私を見つけて飛び上がった。
「アシェラ、おい! やめなさい! ──ジャック、早く隣の部屋に行って、姉さんを引っ張り上げ……」
「ジャック、余計なことをしたらあなたの黒歴史を本にして出版するわ」
「ひー、やめてぇー、どれのことぉー?」
などと、家族で言い合っているうちに、ロッツが私の足下まで駆け寄ってくる。
そうして、その胸が膨らむほど大きく息を吸い込み……
「アシェラを──心の底から、愛しておりますっ!」
そう叫んだ。
「……は?」
今度は私が間抜け面をさらす番だった。
対して、ジャックはひゅうと口笛を吹く。
父の表情はベランダからぶら下がる私の角度では見えなかったが、おそらく呆気にとられているだろう。
しかし、ロッツはそんな私達の反応にも構わず続ける。
「この大陸のどこを探しても、アシェラほど美しく、賢く、何より愛おしく思う人はただ一人としておりませんでした!」
私は、カーテンのロープを両手でぎゅっと握り締めた。
ロッツはなおも続ける。
「僕の忠誠心はウルに捧げてしまいましたが、それ以外の心は何もかも生涯アシェラに捧げると、この場にいる全ての人に誓います!」
ロッツの後ろで両腕を組んで傍観しているウルの姿も、騒ぎを聞きつけてあちこちに灯された明かりによって浮かび上がる。
次期ヴィンセント国王は顔つきも体つきも随分と精悍になり、すでに王の風格を携えていた。
かつてはお人形さんのように愛らしかったロッツも中性的な印象が弱まり、洗練された大人の男性の雰囲気を纏っている。
二人とも、身分を隠して旅をしていたためか服装こそ簡素なものだが、只者ではないのは見るものが見れば歴然としているだろう。
この四年、彼らが物見遊山をしていたわけではないことが、ひしひしと伝わってきた。
「もしもこの言葉を違えたならば、あなた方は僕に石の礫をぶつけるがいい!」
なんだなんだと使用人達が庭に集まってくる。
彼らを見回し、ロッツが息もつかせぬ勢いで捲し立てた。
「ええ、万が一、億が一にもありえませんが、僕が血迷ったならばどうぞ殺してください! アシェラを裏切った生き恥を晒すくらいなら、めちゃめちゃのぐちゃぐちゃのやばやばになって死んだ方がましだ!」
とにかくめちゃくちゃな言葉が、ダールグレン公爵邸全体に響き渡るように宣言される。
人々は呆気に取られ、しんと静まり返った。
ごくり、と誰かの喉が鳴る音が、いやに大きく響いたような気がした。
その瞬間、ロッツはカッと両目を見開く。
「でも、今は生きたい! だって、アシェラが好きだもん! 大好きだもん!!」
「……っ」
もんって何だ、と突っ込む者は誰もいない。
誰も彼も、ダールグレン公爵邸ごと、突然の告白劇に圧倒されてしまっている。
ロッツは、満を持して叫んだ。
今度は私が間抜け面をさらす番だった。
対して、ジャックはひゅうと口笛を吹く。
父の表情はベランダからぶら下がる私の角度では見えなかったが、おそらく呆気にとられているだろう。
しかし、ロッツはそんな私達の反応にも構わず続ける。
「この大陸のどこを探しても、アシェラほど美しく、賢く、何より愛おしく思う人はただ一人としておりませんでした!」
私は、カーテンのロープを両手でぎゅっと握り締めた。
ロッツはなおも続ける。
「僕の忠誠心はウルに捧げてしまいましたが、それ以外の心は何もかも生涯アシェラに捧げると、この場にいる全ての人に誓います!」
ロッツの後ろで両腕を組んで傍観しているウルの姿も、騒ぎを聞きつけてあちこちに灯された明かりによって浮かび上がる。
次期ヴィンセント国王は顔つきも体つきも随分と精悍になり、すでに王の風格を携えていた。
かつてはお人形さんのように愛らしかったロッツも中性的な印象が弱まり、洗練された大人の男性の雰囲気を纏っている。
二人とも、身分を隠して旅をしていたためか服装こそ簡素なものだが、只者ではないのは見るものが見れば歴然としているだろう。
この四年、彼らが物見遊山をしていたわけではないことが、ひしひしと伝わってきた。
「もしもこの言葉を違えたならば、あなた方は僕に石の礫をぶつけるがいい!」
なんだなんだと使用人達が庭に集まってくる。
彼らを見回し、ロッツが息もつかせぬ勢いで捲し立てた。
「ええ、万が一、億が一にもありえませんが、僕が血迷ったならばどうぞ殺してください! アシェラを裏切った生き恥を晒すくらいなら、めちゃめちゃのぐちゃぐちゃのやばやばになって死んだ方がましだ!」
とにかくめちゃくちゃな言葉が、ダールグレン公爵邸全体に響き渡るように宣言される。
人々は呆気に取られ、しんと静まり返った。
ごくり、と誰かの喉が鳴る音が、いやに大きく響いたような気がした。
その瞬間、ロッツはカッと両目を見開く。
「でも、今は生きたい! だって、アシェラが好きだもん! 大好きだもん!!」
「……っ」
もんって何だ、と突っ込む者は誰もいない。
誰も彼も、ダールグレン公爵邸ごと、突然の告白劇に圧倒されてしまっている。
ロッツは、満を持して叫んだ。
「──アシェラ! 僕と! 結婚! して! くだ! さいっっっ!!」
あいにく、私とロッツはただの一度も恋仲になったことはない。
私は彼に想いを告げなかったし、彼からも何も匂わされたことはないのだ。
私達は、切磋琢磨し合える親友のはずだった。
ずっとそうだったじゃないか。
こちらの気も知らずに、他の女の子達と散々付き合っておいて、今更何だ。
などと、いろいろと言いたいことはある。
しかし、結局私の口から出たのは、こんな一言だった。
「重いわ」
その瞬間──ブツッという音とともに、私の体重を支えていたものがなくなった。
カーテンのロープがちぎれ……いや
「突然の、裏切り……」
ベランダの柵から顔を出していた野ネズミが、それを噛み切ってしまったようだ。
宙に放り出された私は、恨みがましく相手を睨み上げる。
背中を押してやったんじゃい!
などと言い返してきたような気がしたが、野ネズミがしゃべるわけがないのでやっぱり気のせい、あるいは私が相当疲れているのだろう。
「──アシェラ!!」
カーテンのロープと一緒に落ちてきた私を、ロッツが無事受け止めてくれた。
庭に集まった使用人達がわあああっと歓声を上げ、盛大な拍手が沸き起こる。
何しろ、つい三日前に一方的に婚約を破棄され、傷心のあまり自室に閉じこもっていた──ということになっている私に、突然訪ねてきた隣国の超名門公爵家の跡取り息子が熱烈な求婚をしたのだ。
私を案じ同情してくれていた彼らが、盛り上がらないわけがない。
おめでとうございます! お喜び申し上げます! とあちこちから祝福の声がかかった。中には涙ぐむ者までいる。
私自身も、そして父も、ロッツの申し出にまだ何も答えを返していないというのに、ダールグレン公爵邸はすでにお祭り騒ぎの様相を呈していた。
ロッツも、私を抱いたまま下ろそうとしない。
それどころか、私をぎゅうと抱き締めて言うのだ。
「アシェラ、僕とヴィンセントに行こう」
そんなロッツの肩越しにウルと目が合った。
ニヤリと笑ったその顔に、かつての少年っぽさが垣間見える。
裏表のない彼からロッツに視線を戻し、私はゆっくりと口を開いた。
「いや」
「……っ」
「って言ったら、どうする?」
「いやって言っても、このままさらっていく。僕はもう、君から離れたくないんだ」
幼子が駄々を捏ねるような物言いながら、こちらの表情には幼さの片鱗もない。
四年ぶりの相手の顔をまじまじと眺めてから、私は小さく肩を竦めた。
「残念ね。私、これから一人旅に出る予定なの」
「一人旅……?」
ロッツの秀麗な眉がピクリと震える。
「まず、アーレンへ行ってスピカに会うでしょ」
「だめ」
「そのあと、ちょっと遠いけれどヴォルフにまで足を伸ばして、マチアスにたかろうかと思うの」
「だめだよ」
さらに続けようとする私の言葉を、ロッツはきつく抱き締めて遮った。
「一人旅なんて、だめに決まっているでしょ? アシェラはこんなに可愛くて美しくて魅力的なんだよ? 君を放っておけるほど、世の野郎どもが枯れているわけないでしょ!?」
「でも、男のふりをするのよ。まずは髪を切って……」
「髪を切って男のふりをしたからなんだって言うの! 僕がモブ男だったら、君が男に見えようと、もしも実際に男であったとしても、絶対に声をかけている! 絶対! 絶対に、だっ!!」
「……そうかしら」
耳元でキャンキャンうるさく吠えるロッツから目を逸らし、私は屋敷を見上げた。
使用人達が持ち寄った明かりに照らされているせいで、庭を見下ろしている者達の表情もよく見える。
ベランダの手摺りに頬杖を突いたジャックはニヤニヤとして、私ではなくおそらくロッツを眺めている。
父は穏やかな笑みを浮かべているが、どうせ心のうちは私ごときには悟らせないだろう。
その後ろからそっと顔を出した母とだけは目が合った。
彼女が慈愛のこもった眼差しをして、小さく一つ頷く。
最後に、私は自室のベランダに目をやり──
「……アシェラ? 今、誰に手を振ったの?」
「小さなお友達、かしら」
ベランダの柵の隙間から、手を振っている野ネズミに応えた。
野ネズミが手を振ってくる幻覚が見えるだなんて、私はいよいよ疲れ切っているのだろう。
そんな自分も、この状況も、だんだんとおかしく思えてくる。
私はくすくすと笑いながら、何やら面白くなさそうな顔しているロッツの頬をペチペチ叩いて告げた。
「行くわ──ヴィンセントに」
「……っ」
「って言ったら、どうする?」
「いやって言っても、このままさらっていく。僕はもう、君から離れたくないんだ」
幼子が駄々を捏ねるような物言いながら、こちらの表情には幼さの片鱗もない。
四年ぶりの相手の顔をまじまじと眺めてから、私は小さく肩を竦めた。
「残念ね。私、これから一人旅に出る予定なの」
「一人旅……?」
ロッツの秀麗な眉がピクリと震える。
「まず、アーレンへ行ってスピカに会うでしょ」
「だめ」
「そのあと、ちょっと遠いけれどヴォルフにまで足を伸ばして、マチアスにたかろうかと思うの」
「だめだよ」
さらに続けようとする私の言葉を、ロッツはきつく抱き締めて遮った。
「一人旅なんて、だめに決まっているでしょ? アシェラはこんなに可愛くて美しくて魅力的なんだよ? 君を放っておけるほど、世の野郎どもが枯れているわけないでしょ!?」
「でも、男のふりをするのよ。まずは髪を切って……」
「髪を切って男のふりをしたからなんだって言うの! 僕がモブ男だったら、君が男に見えようと、もしも実際に男であったとしても、絶対に声をかけている! 絶対! 絶対に、だっ!!」
「……そうかしら」
耳元でキャンキャンうるさく吠えるロッツから目を逸らし、私は屋敷を見上げた。
使用人達が持ち寄った明かりに照らされているせいで、庭を見下ろしている者達の表情もよく見える。
ベランダの手摺りに頬杖を突いたジャックはニヤニヤとして、私ではなくおそらくロッツを眺めている。
父は穏やかな笑みを浮かべているが、どうせ心のうちは私ごときには悟らせないだろう。
その後ろからそっと顔を出した母とだけは目が合った。
彼女が慈愛のこもった眼差しをして、小さく一つ頷く。
最後に、私は自室のベランダに目をやり──
「……アシェラ? 今、誰に手を振ったの?」
「小さなお友達、かしら」
ベランダの柵の隙間から、手を振っている野ネズミに応えた。
野ネズミが手を振ってくる幻覚が見えるだなんて、私はいよいよ疲れ切っているのだろう。
そんな自分も、この状況も、だんだんとおかしく思えてくる。
私はくすくすと笑いながら、何やら面白くなさそうな顔しているロッツの頬をペチペチ叩いて告げた。
「行くわ──ヴィンセントに」
「──どうぞ、ごゆっくり」
ニヤニヤしながらそう言って、ウルが馬車の扉を外から閉めた。
前には、黒毛の馬が二頭。
ヴィンセント王子を祖国へと護送するための馬車なのに、肝心の彼は私とロッツを二人きりにするために御者台に座ると言う。
「ケット、酒」
「私は酒ではないですし、酒があったとしても殿下には一滴たりとも飲ませませんので」
「は? どういうつもりだ?」
「峠を越えたら、殿下に御者を代わってもらうつもりですけど? 飲酒運転、ダメ、ゼッタイ!」
御者はケットという名の、すこぶる厳つい顔つきをした若い男だった。
古くからヴィンセント王家に仕える軍人一家の出らしい。
その、主人を主人とも思わぬ物言いといい、気合が入っているのは面構えだけではなかった。
その後も、御者台の方からは彼とウルの軽妙な掛け合いが聞こえてくる。
私はそれにくすりと笑ってから、向かいに座ったロッツを見た。
「ちょうど、ヴィンセントに戻るところだったのね」
「そうなんだ、陛下に……ウルの父上に呼び戻されてね。アシェラの婚約破棄のことは、途中でスピカが教えてくれたんだよ」
スピカにはまだ婚約破棄の事実を連絡していなかったにもかかわらず、彼女は野ネズミの神様が知らせてきたと言ったらしい。
まさか、大聖堂からついてきたあの野ネズミが、仲間に伝言でも頼んでくれたのだろうか。摩訶不思議なこともあるものだと思っていると、向かいから伸びてきたロッツの右手が、膝の上に置いていた私の両手の上にそっと重なった。
「アシェラには悪いけど、僕にとっては一世一代の好機だった。君に告白するなら、今しかないって──」
随分と男らしい大きな手である。
自分のものとはあまりにも違うそれを、私はしばし無言のまま見下ろしていた。
そんな私を、ロッツもじっと見つめている気配がする。
今宵このままロッツとともにヴィンセントに行くと宣言した私を、父は止めなかった。
異国の公爵家同士の婚姻ともなれば、準備も体裁も十分に整える必要があるだろうに、ラインとのことを負い目に感じている父は私の意思を尊重してくれたのだ。
嫁ぎ先であるフェルデン公爵家当主が、父自身の旧知であることも大きいだろう。
そういうわけで、ロッツに抱かれたまま一人旅用の荷物だけ持って出発しようとしたところに、息を切らした乳母が駆け寄ってきて手製のケープを羽織らせてくれた。
彼女は一度ぎゅっと強く私の手を握り締めてから、お嬢様をどうかお願いします、と深々とロッツに頭を下げたのだった。
嘘偽りない愛情が編み込まれたケープが、今も私を包み込んで守ってくれている。
それに勇気づけられるようにして、私はようやく顔を上げた。
そうして、にっこりと微笑んで言う。
「ロッツは、大嘘つきね」
「……えっ?」
とたんに固まった彼の下から右手を引き抜いて、私はその胸ぐらをつかみ上げた。
綺麗な菫色の両目はぱちくりしているが、その奥は冷静にこちらの出方を観察している。
私は、自分がそれに怖気付く前に、一気に核心を衝いた。
「すべては、あなたの計画通り。私もラインも、この十年、あなたの手のひらの上で踊らされていたのね──ロッツ・フェルデンさん?」
最初にロッツの行動に疑問を抱いたのは、四年前──ナミが現れた時だった。
私とウルは彼に誘われ、異世界から来たというナミに会いに行ったわけだが、彼女はその時ロッツの名前を知っていた。
つまり、彼らはすでに面識があったのだ。
「ナミは〝摩訶不思議な光る板を持って現れただけの異世界人を自称する只人〟だった。ウルと引き合わせるに値する人材ではなかったわ。あなたは彼女と先に会って、それを確認したはずよ」
それなのに、どうしてロッツはウルを会わせたのか?
「あなたがナミと本当に会わせたかったのは、ウルじゃない。ウルの行くところにならどこへでもついて行きたがったオリビア王女と──そして、私を会わせたかったのね」
オリビアがナミを嫌うであろうことも、ナミが私を敵視するようになることも、ロッツは確信していたのだろう。
──性悪王女と悪役令嬢に寄ってたかってイジワルをされる可哀想なワタシ!
そう、ナミが自分の状況を脚色することも、彼は分かっていた。
明確な敵を持ったナミは、自分をちやほやする大聖堂とラインにどんどんと依存していく。
聖女に選ばれた自分に酔うラインの心もますます私から離れていった。
「そもそもおかしいのよね。聖女なんてもの、ヒンメル聖教の経典にはどこにも載っていないの。それなのに、どうして大聖堂がナミにそう称することを思いついたのか……」
ところで、ラインとの婚約破棄から三日が経ったが、その間、傷心のあまり自室に閉じこもったことになっている私を見舞った者が何人もいた。
大司祭もその一人だ。
一気に老け込んだ様子の彼を手厚くもてなしつつ、私は問うた。
いったい誰が、最初に〝聖女〟なんて言葉を持ち出したのか、と。
私とウルは彼に誘われ、異世界から来たというナミに会いに行ったわけだが、彼女はその時ロッツの名前を知っていた。
つまり、彼らはすでに面識があったのだ。
「ナミは〝摩訶不思議な光る板を持って現れただけの異世界人を自称する只人〟だった。ウルと引き合わせるに値する人材ではなかったわ。あなたは彼女と先に会って、それを確認したはずよ」
それなのに、どうしてロッツはウルを会わせたのか?
「あなたがナミと本当に会わせたかったのは、ウルじゃない。ウルの行くところにならどこへでもついて行きたがったオリビア王女と──そして、私を会わせたかったのね」
オリビアがナミを嫌うであろうことも、ナミが私を敵視するようになることも、ロッツは確信していたのだろう。
──性悪王女と悪役令嬢に寄ってたかってイジワルをされる可哀想なワタシ!
そう、ナミが自分の状況を脚色することも、彼は分かっていた。
明確な敵を持ったナミは、自分をちやほやする大聖堂とラインにどんどんと依存していく。
聖女に選ばれた自分に酔うラインの心もますます私から離れていった。
「そもそもおかしいのよね。聖女なんてもの、ヒンメル聖教の経典にはどこにも載っていないの。それなのに、どうして大聖堂がナミにそう称することを思いついたのか……」
ところで、ラインとの婚約破棄から三日が経ったが、その間、傷心のあまり自室に閉じこもったことになっている私を見舞った者が何人もいた。
大司祭もその一人だ。
一気に老け込んだ様子の彼を手厚くもてなしつつ、私は問うた。
いったい誰が、最初に〝聖女〟なんて言葉を持ち出したのか、と。
この作家の他の作品
表紙を見る
王城でのパーティーの最中に毒を盛られて絶命した
侯爵令嬢アヴィス。
王子の許嫁として清く正しく慎ましく生きてきた彼女の魂は、
本来なら天界に行くはずが、気がつくとなぜか魔界にいて、
酔っ払った魔王と愉快な仲間達の血肉により新たな肉体を得ていた。
アヴィスを我が子と呼んで溺愛する美貌の最強魔王ギュスターヴをはじめ、
堕天使、夢魔、女吸血鬼やツンデレメイドなどイカれた面々をも振り回しつつ、
アヴィスは元気いっぱいかつ自由気ままに新しい人生を歩み出す。
しかし、自分に毒を盛ったと冤罪をかけられた王子を心配して軽率に地界に戻ってみたり、
うっかり騙されたり攫われたり召喚されたりと慌ただしい日々の中、
アヴィスは世界が生前思っていたものとは違うこと、
さらに自分を殺した真犯人とそれに天界の思惑が関わっていることを知る。
また、魔界に来て早々アヴィスに懐いた屍剣士のことを、
許嫁の王子はなぜか知っているようで……
「魔王たる私の寝首を掻く者がいるとしたら……それはお前だろうな、アヴィス」
門限五時、厳守!
最強の保護者こと魔王のスネを全力でかじりながら第二の人生を謳歌するアヴィスと、
その扱いに悩んで育児板を覗きつつも毎回力業で解決してしまう魔王による、
おもしろおかしく
血腥く
そして、愛に溢れる日々の物語。
表紙を見る
代々コーヒー狂を輩出してきた
フォルコ家の娘イヴは
王宮一階大階段脇にある
コーヒー専門店『カフェ・フォルコ』
の店長代理を務めている。
さまざまな獣人の末裔が暮らす世界でコーヒーを提供する傍ら
彼女は優れた記憶力を活かして客から客への伝言も請け負う。
兄の幼馴染みで、強く頼もしく、そして
〝世界一かわいい〟
第一王子ウィリアムに
見守られ助けられながら
常連客同士の仲を取り持ったり
時には修羅場に巻き込まれたりと
日々大忙し!
表紙を見る
高齢の魔王に代わり、人間の箱入り末王女アメリと結婚したのは、魔王の副官を務める青年魔族ローエン。
「出自に問題がある自分は、一国の姫を娶るには分不相応だ」
そう思い込んでいるローエンは、唯一誇れる肩書きである〝魔王の副官〟の沽券を保とうと努めるのだが、アメリ姫の笑顔の前では調子を崩されっぱなしで……
政略結婚で始まった二人の、新婚生活一月目。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…