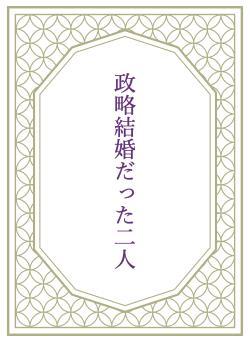この作家の他の作品
表紙を見る
王城でのパーティーの最中に毒を盛られて絶命した
侯爵令嬢アヴィス。
王子の許嫁として清く正しく慎ましく生きてきた彼女の魂は、
本来なら天界に行くはずが、気がつくとなぜか魔界にいて、
酔っ払った魔王と愉快な仲間達の血肉により新たな肉体を得ていた。
アヴィスを我が子と呼んで溺愛する美貌の最強魔王ギュスターヴをはじめ、
堕天使、夢魔、女吸血鬼やツンデレメイドなどイカれた面々をも振り回しつつ、
アヴィスは元気いっぱいかつ自由気ままに新しい人生を歩み出す。
しかし、自分に毒を盛ったと冤罪をかけられた王子を心配して軽率に地界に戻ってみたり、
うっかり騙されたり攫われたり召喚されたりと慌ただしい日々の中、
アヴィスは世界が生前思っていたものとは違うこと、
さらに自分を殺した真犯人とそれに天界の思惑が関わっていることを知る。
また、魔界に来て早々アヴィスに懐いた屍剣士のことを、
許嫁の王子はなぜか知っているようで……
「魔王たる私の寝首を掻く者がいるとしたら……それはお前だろうな、アヴィス」
門限五時、厳守!
最強の保護者こと魔王のスネを全力でかじりながら第二の人生を謳歌するアヴィスと、
その扱いに悩んで育児板を覗きつつも毎回力業で解決してしまう魔王による、
おもしろおかしく
血腥く
そして、愛に溢れる日々の物語。
表紙を見る
代々コーヒー狂を輩出してきた
フォルコ家の娘イヴは
王宮一階大階段脇にある
コーヒー専門店『カフェ・フォルコ』
の店長代理を務めている。
さまざまな獣人の末裔が暮らす世界でコーヒーを提供する傍ら
彼女は優れた記憶力を活かして客から客への伝言も請け負う。
兄の幼馴染みで、強く頼もしく、そして
〝世界一かわいい〟
第一王子ウィリアムに
見守られ助けられながら
常連客同士の仲を取り持ったり
時には修羅場に巻き込まれたりと
日々大忙し!
表紙を見る
高齢の魔王に代わり、人間の箱入り末王女アメリと結婚したのは、魔王の副官を務める青年魔族ローエン。
「出自に問題がある自分は、一国の姫を娶るには分不相応だ」
そう思い込んでいるローエンは、唯一誇れる肩書きである〝魔王の副官〟の沽券を保とうと努めるのだが、アメリ姫の笑顔の前では調子を崩されっぱなしで……
政略結婚で始まった二人の、新婚生活一月目。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
婚約破棄後に好きだった人から求婚されましたが、もう手のひらの上で踊らされるのはごめんです
を読み込んでいます