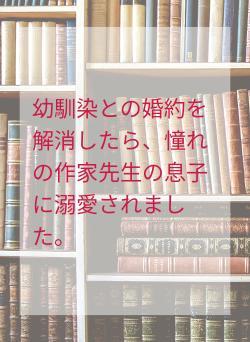驚いて慌ててパジャマのまま降りていくと、厨房の隅で圭ちゃんが頭を抱えてうずくまっていた。床に鍋がいくつか散乱している。
「いってぇ〜」
コックコートを着た圭ちゃんは、どうやら仕込みを開始しようとして上の棚から落ちてきた鍋で頭を打ったようだ。
「ちょっと、圭ちゃん大丈夫!?」
「だいじょばない」
涙目になって、掠れ声を出してゆっくりと立ち上がった。
「うわっ、祥子、なんてカッコで来てるんだよ!」
「……へ?」
圭ちゃんは、私の姿を見て驚いていた。
そういえば、パジャマのままで降りてきたんだった。
「『……へ?』じゃないよ。そんなカッコで男の前に立つなよ」
「ごめん。でも、圭ちゃんだし」
ちょっとはしたなかったかな、と思いつつも相手は幼馴染の圭ちゃんだ。
小さい頃は一緒に寝たこともあるし、特に気にしていなかった。
そっかぁ、圭ちゃんの前でもこういうの気にしなきゃいけないんだ。
ちょっと寂しいな、と思ったら圭ちゃんが残念そうな顔をして頭を抱えてた。
まだ頭が痛いのかな?
「け〜〜い〜〜き〜〜〜〜」
その時、背後からお父さんの低い声が聞こえた。
お父さんのこの言い方は、機嫌の悪い時だ。
「いってぇ〜」
コックコートを着た圭ちゃんは、どうやら仕込みを開始しようとして上の棚から落ちてきた鍋で頭を打ったようだ。
「ちょっと、圭ちゃん大丈夫!?」
「だいじょばない」
涙目になって、掠れ声を出してゆっくりと立ち上がった。
「うわっ、祥子、なんてカッコで来てるんだよ!」
「……へ?」
圭ちゃんは、私の姿を見て驚いていた。
そういえば、パジャマのままで降りてきたんだった。
「『……へ?』じゃないよ。そんなカッコで男の前に立つなよ」
「ごめん。でも、圭ちゃんだし」
ちょっとはしたなかったかな、と思いつつも相手は幼馴染の圭ちゃんだ。
小さい頃は一緒に寝たこともあるし、特に気にしていなかった。
そっかぁ、圭ちゃんの前でもこういうの気にしなきゃいけないんだ。
ちょっと寂しいな、と思ったら圭ちゃんが残念そうな顔をして頭を抱えてた。
まだ頭が痛いのかな?
「け〜〜い〜〜き〜〜〜〜」
その時、背後からお父さんの低い声が聞こえた。
お父さんのこの言い方は、機嫌の悪い時だ。