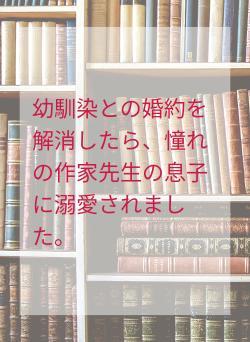「圭ちゃんも、昨日はありがとね」
「おう」
改めて昨夜のケーキのお礼を言うと、圭ちゃんもまた笑顔を返してくれた。
入口の鍵を閉めて、ショーケースのガラスを拭いておこうと、布巾を手に取る。
掃除の前に、私はずっと心に引っかかっていたことを、圭ちゃんに言うことにした。
「ねぇ、圭ちゃん。私、圭ちゃんの作るケーキ好きだけど」
「う、うん」
「さすがに、ずっとってわけにはいかないよね?」
「……え?」
そう言うと、圭ちゃんは驚いたような、困ったような顔をした。
「私、卒業したら家を出るし、圭ちゃんのケーキも卒業した方が……」
本当はずっと圭ちゃんのケーキも食べていたい。
でも、このままずるずると甘えたままでいいのかなって、思っていた。
だから、進路が分かれるこの機会にきっぱりとやめた方がいいって。
私の気持ちを伝えると、圭ちゃんは真剣な顔で叫んだ。
「しなくていい!」
そう言って、私の肩を掴んできた。