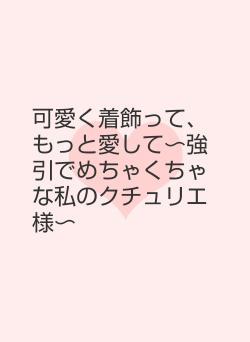「ん、美味い」
「本当ですか」
「おぅ、何だコレ?カリカリして美味いな」
「それはクルミです!アクセントに入れました!」
二口目も三口目も運ばれていくマフィンに顔が緩んで、ずっとドキドキが止まらなかった。
“手作りお菓子をあげるっていうのはマストじゃない?”
崎本先生は知っていますか?
そんなことが言われてるんですって。
崎本先生は気付いてますか?
そのマフィンにどんな気持ちが入ってるのか…
気付いてますか?
私、もう抑えきれないかもしれません。
腕を引いて引っ張って、そのまま胸の中に…
そんなことばかり夢に見て。
だって崎本先生は力には自信があるって言うから。
「美味かったサンキュ」
このまま抱きしめてくれたらいいのに。
「家庭科の実習でこんなビニール袋まで用意してんのか」
「ラッピングって言ってください」
「ラッピング」
ピンクのリボンに合うように、透明の袋に白色の文字やイラストが描かれてる。きっとこれがいいって選んで来たんだ。
「亜由ちゃんにもらったんです」
「へぇ、亜由ちゃんに…よかったな」
メガネの奥、瞳が微笑む。
私しか映っていなくて嬉しくなる。
「はい!」
目を閉じるのがもったいないくらいに。
「本当ですか」
「おぅ、何だコレ?カリカリして美味いな」
「それはクルミです!アクセントに入れました!」
二口目も三口目も運ばれていくマフィンに顔が緩んで、ずっとドキドキが止まらなかった。
“手作りお菓子をあげるっていうのはマストじゃない?”
崎本先生は知っていますか?
そんなことが言われてるんですって。
崎本先生は気付いてますか?
そのマフィンにどんな気持ちが入ってるのか…
気付いてますか?
私、もう抑えきれないかもしれません。
腕を引いて引っ張って、そのまま胸の中に…
そんなことばかり夢に見て。
だって崎本先生は力には自信があるって言うから。
「美味かったサンキュ」
このまま抱きしめてくれたらいいのに。
「家庭科の実習でこんなビニール袋まで用意してんのか」
「ラッピングって言ってください」
「ラッピング」
ピンクのリボンに合うように、透明の袋に白色の文字やイラストが描かれてる。きっとこれがいいって選んで来たんだ。
「亜由ちゃんにもらったんです」
「へぇ、亜由ちゃんに…よかったな」
メガネの奥、瞳が微笑む。
私しか映っていなくて嬉しくなる。
「はい!」
目を閉じるのがもったいないくらいに。