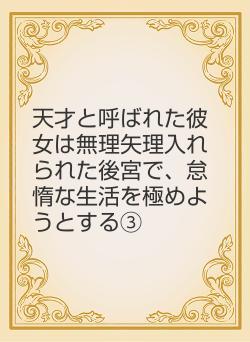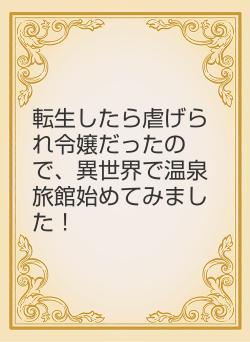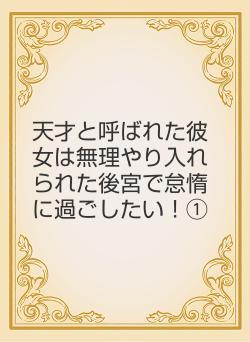アナベルがお嬢様っ!と呼ぶ。
「なに〜?」
「なにじゃありませんよ!王妃としての教育を適当にするのは、おやめください!」
「ちゃんとこなしてるでしょ?」
ソファーでゴロゴロしながら本を読む。時々、お茶を飲み、ダラダラ過ごすことを繰り返していると、アナベルが小言を言い出した。
「刺繍の課題を妹にさせて、楽器は無駄と断り、ダンスの授業にお作法も週一!どこぞの習い事ですかーっ!?もっと真面目に取り組んでください」
「刺繍はある程度できるし、楽器は楽団が弾いたプロの腕前のほうがいいし、ダンスもお作法も人前で恥ずかしくない程度であればいいわ。学科は特化しすぎてるほどだし、私を教えられるのは師匠くらいよ」
……と、言うわけで、レッツ☆怠惰生活続行である。お茶のおかわりーとアナベルに言うと、もう!ウィルバート様に愛想尽かされても知りませんよ!と怒られる。
そこへちょうど、ウィルバートがやってきた。
「廊下まで聞こえてるよー」
「申し訳ございません!」
アナベルが慌てて謝り、頭を下げる。
「いいんだよ。リアンについている先生方も覚えが良いと褒めているし、最近、セオドアまで、リアン様は怠惰を装い、皆を油断させているのでは?とか言っている」
いつの間にかセオドアの中で、私の評価が上がってるようで、怠惰に過ごす姿すら、なにか思惑があるとか思われているようだ。
「リアン、《《勉強しすぎ》》だよ」
ウィルバートの青い2つの目はすべてを見透かすようにジッと私を見ていた。ヒョイッと手に持っていた本を奪われた。そして『恋愛小説』と書かれたカバーをとる。
「ああっ!ウィルバート!よけいなことをしないでよっ!本を返しなさいよ!」
出てきた本来の本の題名は、この国の財政についてまとめたものだった。無言になる室内。
彼には最初から、バレていたらしい。ウィルバートが静寂を破る。
「リアン、なんで怠惰なフリしてるんだ?いや、そもそも怠惰なフリをしていたのは後宮から出るためだったんだろ?もしかして、オレのために勉強し、努力してくれてるのか?」
「もうっ!本を返しなさいよー!」
私はウィルバートから、本を奪い返す。カバーをかけ直した。
「お嬢様……?」
トトトトと、歩いて、私は窓辺に戻り、本を読むふりをし、顔を隠した。
「リアン?」
アナベルとウィルバートの視線が痛い。私は観念した。
「も、もう!私はあなたのために努力しているんじゃないわよ?私は私のためにしてるの。この天才リアンがウィルバートの足を引っ張るとか思われたくないのよっ!」
どうせ私のちっぽけなプライドのためよっ!と付け加えた。
「はー、なんだそれー。リアンが可愛い過ぎて困るー」
ウィルが顔を両手で覆う。
は!?今のどこが可愛いとか思えたの!?
空気を察して、アナベルは部屋から、そっと出ていった。なんで席を外すのよー!?なんの空気読んだのよ!?
二人っきりになると、おいでおいでとウィルバートが私を手招きする。私は渋々と傍に行く。
「オレにしたら、リアンが傍に居て、同じ道を歩いてくれているだけで、もう夢みたいなことなんだよ」
そう言ってニッコリ笑うと抱き寄せてギューッとする。いきなり抱きつかれて、私は動けなくなる。
「ちょ……ちょっと……離して!」
「オレに怠惰な時間をくれるんだろ?王でいるための充電させてもらってるんだよー。幸せだなー。……で、けっきょくなぜ怠惰なフリをしているのか教えてくれないのか?本当の理由はなんだ?」
「………秘密よ」
まぁいいかと笑われ、しばらく、こうしていてくれとウィルバートは、なかなか離してくれなかったのだった。
怠惰なフリをした私は怠惰な時間が欲しい王様に囚われてしまった。
本当は私だって、ウィルバートと過ごす、この穏やかで怠惰な時間が一番好きなの。だから怠惰なフリをしているの。そして私もあなたから幸せをもらってるのよと彼に伝えたい。なかなか上手く言えないけど……でも焦ることはないわ。
私が彼を愛してる気持ちを伝える時間はまだまだあるのだから。
「なに〜?」
「なにじゃありませんよ!王妃としての教育を適当にするのは、おやめください!」
「ちゃんとこなしてるでしょ?」
ソファーでゴロゴロしながら本を読む。時々、お茶を飲み、ダラダラ過ごすことを繰り返していると、アナベルが小言を言い出した。
「刺繍の課題を妹にさせて、楽器は無駄と断り、ダンスの授業にお作法も週一!どこぞの習い事ですかーっ!?もっと真面目に取り組んでください」
「刺繍はある程度できるし、楽器は楽団が弾いたプロの腕前のほうがいいし、ダンスもお作法も人前で恥ずかしくない程度であればいいわ。学科は特化しすぎてるほどだし、私を教えられるのは師匠くらいよ」
……と、言うわけで、レッツ☆怠惰生活続行である。お茶のおかわりーとアナベルに言うと、もう!ウィルバート様に愛想尽かされても知りませんよ!と怒られる。
そこへちょうど、ウィルバートがやってきた。
「廊下まで聞こえてるよー」
「申し訳ございません!」
アナベルが慌てて謝り、頭を下げる。
「いいんだよ。リアンについている先生方も覚えが良いと褒めているし、最近、セオドアまで、リアン様は怠惰を装い、皆を油断させているのでは?とか言っている」
いつの間にかセオドアの中で、私の評価が上がってるようで、怠惰に過ごす姿すら、なにか思惑があるとか思われているようだ。
「リアン、《《勉強しすぎ》》だよ」
ウィルバートの青い2つの目はすべてを見透かすようにジッと私を見ていた。ヒョイッと手に持っていた本を奪われた。そして『恋愛小説』と書かれたカバーをとる。
「ああっ!ウィルバート!よけいなことをしないでよっ!本を返しなさいよ!」
出てきた本来の本の題名は、この国の財政についてまとめたものだった。無言になる室内。
彼には最初から、バレていたらしい。ウィルバートが静寂を破る。
「リアン、なんで怠惰なフリしてるんだ?いや、そもそも怠惰なフリをしていたのは後宮から出るためだったんだろ?もしかして、オレのために勉強し、努力してくれてるのか?」
「もうっ!本を返しなさいよー!」
私はウィルバートから、本を奪い返す。カバーをかけ直した。
「お嬢様……?」
トトトトと、歩いて、私は窓辺に戻り、本を読むふりをし、顔を隠した。
「リアン?」
アナベルとウィルバートの視線が痛い。私は観念した。
「も、もう!私はあなたのために努力しているんじゃないわよ?私は私のためにしてるの。この天才リアンがウィルバートの足を引っ張るとか思われたくないのよっ!」
どうせ私のちっぽけなプライドのためよっ!と付け加えた。
「はー、なんだそれー。リアンが可愛い過ぎて困るー」
ウィルが顔を両手で覆う。
は!?今のどこが可愛いとか思えたの!?
空気を察して、アナベルは部屋から、そっと出ていった。なんで席を外すのよー!?なんの空気読んだのよ!?
二人っきりになると、おいでおいでとウィルバートが私を手招きする。私は渋々と傍に行く。
「オレにしたら、リアンが傍に居て、同じ道を歩いてくれているだけで、もう夢みたいなことなんだよ」
そう言ってニッコリ笑うと抱き寄せてギューッとする。いきなり抱きつかれて、私は動けなくなる。
「ちょ……ちょっと……離して!」
「オレに怠惰な時間をくれるんだろ?王でいるための充電させてもらってるんだよー。幸せだなー。……で、けっきょくなぜ怠惰なフリをしているのか教えてくれないのか?本当の理由はなんだ?」
「………秘密よ」
まぁいいかと笑われ、しばらく、こうしていてくれとウィルバートは、なかなか離してくれなかったのだった。
怠惰なフリをした私は怠惰な時間が欲しい王様に囚われてしまった。
本当は私だって、ウィルバートと過ごす、この穏やかで怠惰な時間が一番好きなの。だから怠惰なフリをしているの。そして私もあなたから幸せをもらってるのよと彼に伝えたい。なかなか上手く言えないけど……でも焦ることはないわ。
私が彼を愛してる気持ちを伝える時間はまだまだあるのだから。