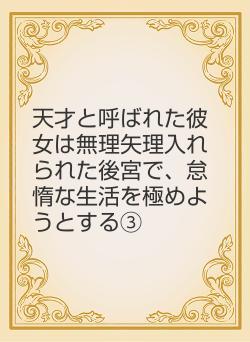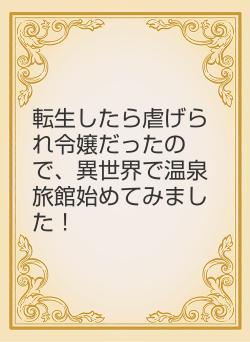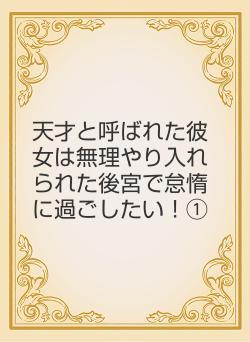朝から王宮内は賑やかだった。後宮内もバタバタと人が慌ただしく行き来している。
とうとうウィルバートとの結婚式の日が来たのだ。もう後戻りはできない。
「お嬢様、心の準備はどうですか?」
アナベルが優しく微笑んで尋ねる。
「大丈夫よ。ちょっと緊張感はあるけどね」
鏡の前には白いドレスと王家に伝わるティアラを頭につけている私がいた。長い手袋をメイドがつけてくれる。アナベルが私の唇にスッと紅を引く。
ネックレスを……と思ったところで、王宮付きのメイドがあら?と慌てだす。
「どうしたの?」
「な、ないんです!ネックレスが!!」
青ざめている。ティアラとネックレスは対になっている。王家の宝とも言える物が消えたとなれば大問題である。今にも泣き出しそうな彼女を私はちょっと落ちついて、大丈夫と宥める。
「しかしお嬢様、もうそろそろ陛下がいらっしゃいます!」
アナベルも動揺している。私は冷静にティアラとネックレスが対になっていたのに離れた瞬間はいつか?を考える。
「もうしわけございません!確かに朝、確認したんです!でもっ、その時は確かにありました!」
王宮付きのメイドは出来るメイドばかりだ。簡単なミスをするわけがない。朝、見たというなら、あったのは確実だ。私の部屋に入れるのはウィルバート、アナベル、王宮付きのメイドのみだ。たまにセオドアも護衛のために来るけど……基本的に入れる人は少ない。ウィルバートが嫌がるのだ。私の身を案じすぎていて、信頼できる者しか近寄らせたくないという理由だ。
すべて用意は済んだのに、ネックレスだけがない。私以外に、今、ネックレスが必要な人は誰だろう?と考える。
「もうメイドとして働けないばかりか流刑地にやられます!」
「たぶん、そろそろ解決するんじゃないかしら?」
私は焦っているメイドにそう言って安心させる。アナベルがどういうことです?と聞き返す。
「心配しないで、そろそろネックレスの方からやってくるわ」
『えっ!?』
そう言った瞬間にドアが開いた。白の詰め襟の服に金糸の刺繍。王冠を頭につけているウィルバートはキラキラとしているオーラを放ち、綺麗な顔立ちがさらに引き立っている。もうカッコいいが服を着て歩いてると言ってもいい!
一瞬、私は見惚れたが、一瞬だった。何故ならウィルバートがキリッとした表情を崩して、ヘニャーとした表情になり、私を褒めだしたからだ。
「うわぁ!リアン!とても綺麗だよ!ドレスも素敵だけど、君の美しさの前には、かすんでしまうね!これは誰にも見せたくないなー。オレだけにしたいな」
これから、大勢の民衆に披露しに行くんですけど?とツッコミたいのを我慢し、先に問題を片付けることにする。
「ウィルバート、ネックレス持っているわね?」
「あれっ?バレてた?」
アナベルとメイドが、なんで陛下が持っているんですかー!?と叫んだ。
「たぶん、ウィルバートは……」
私が言う前に、スタスタと私の後ろへやってきて、ニッコリと鏡の中で、私に笑いかけて視線を合わせた。
「オレがリアンにネックレスをつけたかったんだよ」
「まったく……持っていくなら言ってからにしなさいよ」
「リアンに反対されるだろ?」
……確かに。
ウィルバートは笑顔の中に少し陰のある表情をよぎらせ、私の首に触れて、ネックレスをつけた。
「これはオレの母がつけていたんだ。正妻はティアラだけだった。父は寵愛していた母にネックレスを贈り、母は亡くなるまで大切にしていたよ」
「亡くなったお母様が?」
私はウィルバートがお母様のことを話すとき、とても悲しい顔をすることに気づいている。幼い頃の彼は傷つき、甘えられずにここまできたのだろうか?それも……いつかきっと話してくれる日はくるだろうと思い、私は彼にも周りの誰にも聞かずにいる。
「うん。だからリアンにつけてもらえてよかった」
「ウィルバート……」
「良い雰囲気の中、申し訳ないのですが、時間ですよ」
セオドアが何してるんですか?時間ですが?と呆れたように言って、呼びにきた。チッと舌打ちして、邪魔するなよなとウィルバートが険しい顔をして、呟いた。さっきまでのしんみりとした雰囲気はどこいったのよ?
王宮のテラスに出るとワアアアアと大歓声が起きた。たくさんの人々が集まってくれていた。トランペットの音と共に白い鳥は飛び立ち、色とりどりのリボンのような旗がいくつも揺れる。花と紙ふぶきがまるで雪のように舞う。
私とウィルバートは手を振る。それはとても美しい光景だった。
横を見て目を合わせると、堂々としていて『獅子王』と呼ばれるにふさわしい王が自信に満ちた顔で、私に微笑みかけた。彼の強い眼差しに思わずドキッとした。
私とウィルバートは民に何度も手を振り、名残惜しみつつ、くるりと身を翻して、中へ入る。
ウィルバートが先に中に入り歩いていたが、人気の無くなったところで、急に立ち止まって、振り向かず私に聞く。
「これからもリアン、傍にいてくれるか?」
「ええ。あなたとこの国の民と一緒にずっといるわ」
私はそう微笑みながら、横に並び顔を見た………って!!
思わずマズイ!とウィルバートのマントを私は引っ張って、かぶせ、他の人に気づかれないように彼の顔を隠した。
「な、なんで、あなたが泣いてるのよっ!」
「ごめん。本当に嬉しくて……ありがとう。王妃になることを選んでくれて、僕の傍にいてくれてありがとう」
「花嫁が泣くものでしょうがーーーっ!」
泣くのそっちなの!?やっぱりウィルバートはウィルだわ!世話が焼けるわと思ったのだった。さっきまでの『獅子王』はどこいっちゃったのよ!?
でも私の前だけくらいはいいわ。強がってる彼が泣ける場所をいつでも作ってあげるわ。幼いウィルバートがずっと泣けなかった分もこれからは……。そう私は思って、彼の頬を両手で包み込んだ。
とうとうウィルバートとの結婚式の日が来たのだ。もう後戻りはできない。
「お嬢様、心の準備はどうですか?」
アナベルが優しく微笑んで尋ねる。
「大丈夫よ。ちょっと緊張感はあるけどね」
鏡の前には白いドレスと王家に伝わるティアラを頭につけている私がいた。長い手袋をメイドがつけてくれる。アナベルが私の唇にスッと紅を引く。
ネックレスを……と思ったところで、王宮付きのメイドがあら?と慌てだす。
「どうしたの?」
「な、ないんです!ネックレスが!!」
青ざめている。ティアラとネックレスは対になっている。王家の宝とも言える物が消えたとなれば大問題である。今にも泣き出しそうな彼女を私はちょっと落ちついて、大丈夫と宥める。
「しかしお嬢様、もうそろそろ陛下がいらっしゃいます!」
アナベルも動揺している。私は冷静にティアラとネックレスが対になっていたのに離れた瞬間はいつか?を考える。
「もうしわけございません!確かに朝、確認したんです!でもっ、その時は確かにありました!」
王宮付きのメイドは出来るメイドばかりだ。簡単なミスをするわけがない。朝、見たというなら、あったのは確実だ。私の部屋に入れるのはウィルバート、アナベル、王宮付きのメイドのみだ。たまにセオドアも護衛のために来るけど……基本的に入れる人は少ない。ウィルバートが嫌がるのだ。私の身を案じすぎていて、信頼できる者しか近寄らせたくないという理由だ。
すべて用意は済んだのに、ネックレスだけがない。私以外に、今、ネックレスが必要な人は誰だろう?と考える。
「もうメイドとして働けないばかりか流刑地にやられます!」
「たぶん、そろそろ解決するんじゃないかしら?」
私は焦っているメイドにそう言って安心させる。アナベルがどういうことです?と聞き返す。
「心配しないで、そろそろネックレスの方からやってくるわ」
『えっ!?』
そう言った瞬間にドアが開いた。白の詰め襟の服に金糸の刺繍。王冠を頭につけているウィルバートはキラキラとしているオーラを放ち、綺麗な顔立ちがさらに引き立っている。もうカッコいいが服を着て歩いてると言ってもいい!
一瞬、私は見惚れたが、一瞬だった。何故ならウィルバートがキリッとした表情を崩して、ヘニャーとした表情になり、私を褒めだしたからだ。
「うわぁ!リアン!とても綺麗だよ!ドレスも素敵だけど、君の美しさの前には、かすんでしまうね!これは誰にも見せたくないなー。オレだけにしたいな」
これから、大勢の民衆に披露しに行くんですけど?とツッコミたいのを我慢し、先に問題を片付けることにする。
「ウィルバート、ネックレス持っているわね?」
「あれっ?バレてた?」
アナベルとメイドが、なんで陛下が持っているんですかー!?と叫んだ。
「たぶん、ウィルバートは……」
私が言う前に、スタスタと私の後ろへやってきて、ニッコリと鏡の中で、私に笑いかけて視線を合わせた。
「オレがリアンにネックレスをつけたかったんだよ」
「まったく……持っていくなら言ってからにしなさいよ」
「リアンに反対されるだろ?」
……確かに。
ウィルバートは笑顔の中に少し陰のある表情をよぎらせ、私の首に触れて、ネックレスをつけた。
「これはオレの母がつけていたんだ。正妻はティアラだけだった。父は寵愛していた母にネックレスを贈り、母は亡くなるまで大切にしていたよ」
「亡くなったお母様が?」
私はウィルバートがお母様のことを話すとき、とても悲しい顔をすることに気づいている。幼い頃の彼は傷つき、甘えられずにここまできたのだろうか?それも……いつかきっと話してくれる日はくるだろうと思い、私は彼にも周りの誰にも聞かずにいる。
「うん。だからリアンにつけてもらえてよかった」
「ウィルバート……」
「良い雰囲気の中、申し訳ないのですが、時間ですよ」
セオドアが何してるんですか?時間ですが?と呆れたように言って、呼びにきた。チッと舌打ちして、邪魔するなよなとウィルバートが険しい顔をして、呟いた。さっきまでのしんみりとした雰囲気はどこいったのよ?
王宮のテラスに出るとワアアアアと大歓声が起きた。たくさんの人々が集まってくれていた。トランペットの音と共に白い鳥は飛び立ち、色とりどりのリボンのような旗がいくつも揺れる。花と紙ふぶきがまるで雪のように舞う。
私とウィルバートは手を振る。それはとても美しい光景だった。
横を見て目を合わせると、堂々としていて『獅子王』と呼ばれるにふさわしい王が自信に満ちた顔で、私に微笑みかけた。彼の強い眼差しに思わずドキッとした。
私とウィルバートは民に何度も手を振り、名残惜しみつつ、くるりと身を翻して、中へ入る。
ウィルバートが先に中に入り歩いていたが、人気の無くなったところで、急に立ち止まって、振り向かず私に聞く。
「これからもリアン、傍にいてくれるか?」
「ええ。あなたとこの国の民と一緒にずっといるわ」
私はそう微笑みながら、横に並び顔を見た………って!!
思わずマズイ!とウィルバートのマントを私は引っ張って、かぶせ、他の人に気づかれないように彼の顔を隠した。
「な、なんで、あなたが泣いてるのよっ!」
「ごめん。本当に嬉しくて……ありがとう。王妃になることを選んでくれて、僕の傍にいてくれてありがとう」
「花嫁が泣くものでしょうがーーーっ!」
泣くのそっちなの!?やっぱりウィルバートはウィルだわ!世話が焼けるわと思ったのだった。さっきまでの『獅子王』はどこいっちゃったのよ!?
でも私の前だけくらいはいいわ。強がってる彼が泣ける場所をいつでも作ってあげるわ。幼いウィルバートがずっと泣けなかった分もこれからは……。そう私は思って、彼の頬を両手で包み込んだ。