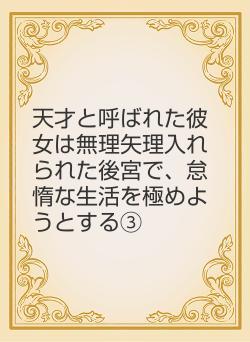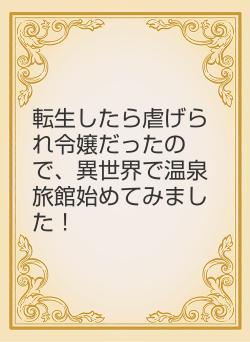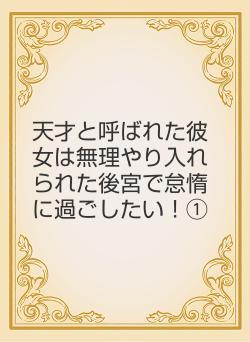「お嬢様、また白いバラの花が届いています」
また?と私は驚く。誰からなの?とアナベルに聞いても、後宮の入り口によく置かれているんですと困った顔をしている。
私は最初こそ、棘の部分に毒とか、花に何かを仕込ませてあるとか、疑っていたが、特に何も見つからない。それに花束の時もあれば、一輪だけ置いてあることもある。
気になるが、誰がなんの目的でしたのか、情報が少なすぎて、サッパリわからない……花に罪はないので、変だわと思いつつも花瓶に入れて飾っている。
「まさかリアンのことをこっそり想うやつがいるんじゃないだろうな!?」
ウィルバートはそう言って、険しい表情になる。……ちょっと怖いわ。
「まさか……それなら、カードの一つもつけるでしょう?名も明かすことがないなんて、どこの誰ともアピールできないじゃない?」
「いや!危ないから騎士団に言って、後宮の警備を増やしておこう」
「大丈夫よ。騎士団の仕事を増やしてしまうから、申し訳ないわ」
私が辞退しようとすると、心配だから駄目だ!とウィルバートは譲らなかった。
隣国の使者との外交を兼ねた夕食会が終わり、同席していたガルシア将軍が話しかけてきた。
「こないだ言っていた、騎士団の食事内容を、変えたら劇的に体力があがったぞ。宿舎の清掃と改築もする予定だ!」
「それは良かったわ。兵の健康管理は軍の強さに比例するわ」
確かに、そこは適当だった。礼を言う!と珍しく私に礼を言う。
「騎士団の……なんだ?」
「こないだガルシア将軍と勝負した時に、騎士団のお昼ご飯の様子をみて、メニューがあまりにも貧相だったから気になってて、進言しておいたの」
なるほどなぁとウィルバートが頷く。ガルシア将軍がやや呆れたように私に言う。
「王妃様と同じくらいの年齢の女性はもっと違うことに興味を示すぞ?」
「変かしら?」
「変人すぎるな!王妃様なら、もう少し女性らしく振る舞わんとな!陛下が王妃のどこが良いと思うのか謎だな」
アッハッハ!と大笑いされる。
私もそれは謎なのよと思うのだった。ウィルバートは私が良いとは言ってくれているものの……。
困ってしまいウィルバートを見ると、え?と不思議そうになる。
「なんで困った顔するんだ?今のままでいい。リアンの良さを皆は知らなくて良い。オレだけでいい。そしてリアンに手を出すやつにはオレは容赦しない!たとえガルシア将軍でもだ」
真顔で言うウィルバートが本気で言ってるとわかり、ガルシア将軍が、いや……この変な王妃には恋愛感情まったくないんだが?と言う。
変だと言いすぎよっ!と私はウィルバートの言葉が恥ずかしすぎて、ごまかすようにガルシア将軍に言い返し、その日は終わった。
いつもの日課となっている図書室から帰って来たときのことだった。
「お嬢様っ!あれ!あれを見てください」
アナベルが指差した方向には人影があり、白いバラをそっと一輪置く姿が見えた。私は駆け出す。すると足音に相手が驚いて、振り返る。腰を浮かして逃げようとする。
「待って!動かないで!ずっと花をくれていたのは、あなたなのっ!?」
私は逃さないわよ!とドーンと目の前に仁王立ちする。花を置いた人は凍りついたように動けなくなる。
「えええ!王妃さまっ!?」
「……あら?騎士の方?」
アナベルがそう言うと相手はゆっくりと立ち上がって、頷いた。冷や汗をぬぐっている。
「えーと……なぜ花を贈ってくれていたの?それも白いバラばかり?」
若い騎士はポリポリと気まずげに頬をかく。どうしようという緊張感が伝わる。
「実は……騎士団で王妃様は………」
口ごもっている。え?なにかしら……騎士団の方たちの嫌がらせだったとか、からかいの対象だったとか……!?
一瞬の間。
「王妃様は人気があるんです!!この花は後宮の警備に当たった者が、感謝の気持ちをこめて、置いてくるという習慣になってしまいまして……」
「ど、どどどどういうこと!?」
私の推測を越えてきた。何が起こってるの?アナベルだけはクスクス笑った。
「お嬢様は自分のことをご存知ないのです」
騎士の人がアナベルの言葉と笑い声に少しリラックスし、そうなんですか!?と言う。
「最近、騎士団の宿舎の清掃、改築……そして何より食事を良くして頂き、我々のことを気にかけてくれていることが、ほんとに嬉しいんです!それに先日のガルシア将軍との勝負で見せた、見事な戦略、狡くはありましたが、あの将軍に対して堂々としたお姿がほんとに素敵だと騎士団の中で尊敬する者が増えてまして……」
「ア、アナベル知ってたの!?」
私だけが騎士の言葉にオロオロしている。アナベルはもちろんですと答えた。
「メイドの間でも騎士団の方々がお嬢様のことを良く思ってると噂になっておりました。花まで贈られているなんて、ちょっとそこまでは、わかりませんでしたけど」
「いやぁ〜。誰かが花を贈ったと聞き、そこから流行ってしまいまして、堂々と贈るより、我々のささやかな感謝の気持ちを示そうという……」
そういうことだったのねと私は喜んでいいのか、困っていいのか微妙な気持ちになった。
「えーと、気持ちは嬉しいわ。ありがとうと皆さんにお伝えしてくれるかしら?お花はもうけっこうよ。ほんとに気持ちだけで嬉しいのよ。日々、この国のために鍛錬してくれる方々には逆に、私からお礼を言いたいわ」
私の言葉にジワッと涙が滲む騎士。
「な、なんてお優しい言葉!皆に必ずやお伝えしますっ!」
そう感涙し、去っていった。アナベルがポツリと言った。
「騎士団の方達の心を掌握しちゃいましたね……ほんとにお嬢様は男でしたら、立派な参謀か宰相か将軍かになってらっしゃったでしょうねぇ。もったいない気が少しします」
「そうかしら?買いかぶりすぎよ……それにしても、騎士団の方達がそんなふうに思ってくれていたなんてね。うーん、予想外だったわ。私もまだまだね」
人の心って予想し難いものだわと私は思ったのだった。
そして白いバラの花言葉は『尊敬』。思わぬ出来事に嬉しくて顔が綻びた。
また?と私は驚く。誰からなの?とアナベルに聞いても、後宮の入り口によく置かれているんですと困った顔をしている。
私は最初こそ、棘の部分に毒とか、花に何かを仕込ませてあるとか、疑っていたが、特に何も見つからない。それに花束の時もあれば、一輪だけ置いてあることもある。
気になるが、誰がなんの目的でしたのか、情報が少なすぎて、サッパリわからない……花に罪はないので、変だわと思いつつも花瓶に入れて飾っている。
「まさかリアンのことをこっそり想うやつがいるんじゃないだろうな!?」
ウィルバートはそう言って、険しい表情になる。……ちょっと怖いわ。
「まさか……それなら、カードの一つもつけるでしょう?名も明かすことがないなんて、どこの誰ともアピールできないじゃない?」
「いや!危ないから騎士団に言って、後宮の警備を増やしておこう」
「大丈夫よ。騎士団の仕事を増やしてしまうから、申し訳ないわ」
私が辞退しようとすると、心配だから駄目だ!とウィルバートは譲らなかった。
隣国の使者との外交を兼ねた夕食会が終わり、同席していたガルシア将軍が話しかけてきた。
「こないだ言っていた、騎士団の食事内容を、変えたら劇的に体力があがったぞ。宿舎の清掃と改築もする予定だ!」
「それは良かったわ。兵の健康管理は軍の強さに比例するわ」
確かに、そこは適当だった。礼を言う!と珍しく私に礼を言う。
「騎士団の……なんだ?」
「こないだガルシア将軍と勝負した時に、騎士団のお昼ご飯の様子をみて、メニューがあまりにも貧相だったから気になってて、進言しておいたの」
なるほどなぁとウィルバートが頷く。ガルシア将軍がやや呆れたように私に言う。
「王妃様と同じくらいの年齢の女性はもっと違うことに興味を示すぞ?」
「変かしら?」
「変人すぎるな!王妃様なら、もう少し女性らしく振る舞わんとな!陛下が王妃のどこが良いと思うのか謎だな」
アッハッハ!と大笑いされる。
私もそれは謎なのよと思うのだった。ウィルバートは私が良いとは言ってくれているものの……。
困ってしまいウィルバートを見ると、え?と不思議そうになる。
「なんで困った顔するんだ?今のままでいい。リアンの良さを皆は知らなくて良い。オレだけでいい。そしてリアンに手を出すやつにはオレは容赦しない!たとえガルシア将軍でもだ」
真顔で言うウィルバートが本気で言ってるとわかり、ガルシア将軍が、いや……この変な王妃には恋愛感情まったくないんだが?と言う。
変だと言いすぎよっ!と私はウィルバートの言葉が恥ずかしすぎて、ごまかすようにガルシア将軍に言い返し、その日は終わった。
いつもの日課となっている図書室から帰って来たときのことだった。
「お嬢様っ!あれ!あれを見てください」
アナベルが指差した方向には人影があり、白いバラをそっと一輪置く姿が見えた。私は駆け出す。すると足音に相手が驚いて、振り返る。腰を浮かして逃げようとする。
「待って!動かないで!ずっと花をくれていたのは、あなたなのっ!?」
私は逃さないわよ!とドーンと目の前に仁王立ちする。花を置いた人は凍りついたように動けなくなる。
「えええ!王妃さまっ!?」
「……あら?騎士の方?」
アナベルがそう言うと相手はゆっくりと立ち上がって、頷いた。冷や汗をぬぐっている。
「えーと……なぜ花を贈ってくれていたの?それも白いバラばかり?」
若い騎士はポリポリと気まずげに頬をかく。どうしようという緊張感が伝わる。
「実は……騎士団で王妃様は………」
口ごもっている。え?なにかしら……騎士団の方たちの嫌がらせだったとか、からかいの対象だったとか……!?
一瞬の間。
「王妃様は人気があるんです!!この花は後宮の警備に当たった者が、感謝の気持ちをこめて、置いてくるという習慣になってしまいまして……」
「ど、どどどどういうこと!?」
私の推測を越えてきた。何が起こってるの?アナベルだけはクスクス笑った。
「お嬢様は自分のことをご存知ないのです」
騎士の人がアナベルの言葉と笑い声に少しリラックスし、そうなんですか!?と言う。
「最近、騎士団の宿舎の清掃、改築……そして何より食事を良くして頂き、我々のことを気にかけてくれていることが、ほんとに嬉しいんです!それに先日のガルシア将軍との勝負で見せた、見事な戦略、狡くはありましたが、あの将軍に対して堂々としたお姿がほんとに素敵だと騎士団の中で尊敬する者が増えてまして……」
「ア、アナベル知ってたの!?」
私だけが騎士の言葉にオロオロしている。アナベルはもちろんですと答えた。
「メイドの間でも騎士団の方々がお嬢様のことを良く思ってると噂になっておりました。花まで贈られているなんて、ちょっとそこまでは、わかりませんでしたけど」
「いやぁ〜。誰かが花を贈ったと聞き、そこから流行ってしまいまして、堂々と贈るより、我々のささやかな感謝の気持ちを示そうという……」
そういうことだったのねと私は喜んでいいのか、困っていいのか微妙な気持ちになった。
「えーと、気持ちは嬉しいわ。ありがとうと皆さんにお伝えしてくれるかしら?お花はもうけっこうよ。ほんとに気持ちだけで嬉しいのよ。日々、この国のために鍛錬してくれる方々には逆に、私からお礼を言いたいわ」
私の言葉にジワッと涙が滲む騎士。
「な、なんてお優しい言葉!皆に必ずやお伝えしますっ!」
そう感涙し、去っていった。アナベルがポツリと言った。
「騎士団の方達の心を掌握しちゃいましたね……ほんとにお嬢様は男でしたら、立派な参謀か宰相か将軍かになってらっしゃったでしょうねぇ。もったいない気が少しします」
「そうかしら?買いかぶりすぎよ……それにしても、騎士団の方達がそんなふうに思ってくれていたなんてね。うーん、予想外だったわ。私もまだまだね」
人の心って予想し難いものだわと私は思ったのだった。
そして白いバラの花言葉は『尊敬』。思わぬ出来事に嬉しくて顔が綻びた。