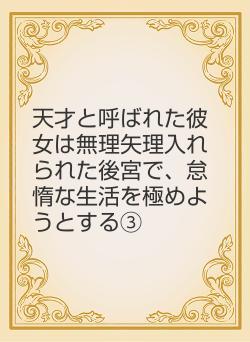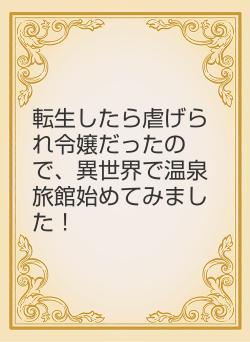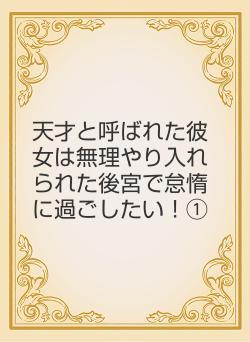幼い子が……こんなに幼い子が同じ机を並べて勉強しているなんて……。チラリと自分の横に座る可愛らしい女の子を見た。
その表情は楽しそうで、先生の話を真剣に聞いたり、なんの授業でも興味津々で質問していたりする。
……自分はここまで楽しそうに学べないなと見ていて思った。
「リアンは勉強好きなんだね」
「せっかくお父様にお願いをきいてもらえて、ここに入れたもの!できるだけいろんなことを知りたいのよ」
キラキラとした緑色の目は明るい色の光を帯びていて、人生を心から純粋に楽しんでいる。リアンのその目には世界は楽しいことだらけで、輝いて見えていることだろう。
それがオレにはとても眩しすぎるように感じたが、暗闇の心にスッと光が射し込んだような気がした。
そんな彼女を評価し、ガルシア将軍は言った。
「陛下はたいした王妃様を手に入れたもんだよ。っていうか、あの先生の私塾にいたなら、いたと言えよ!あの先生に学んだなら、そりゃ腹黒い……いや、なんでもない」
オレは笑う。ガルシア将軍に、こんなふうに笑いかけたのは初めてかもしれない。
「うん。そういう笑顔の顔を持つ王も良いのかもな。陛下は……あの先生の私塾へ行く前に戦術を俺と話していて、なんと言ったか覚えているか?」
「なにか言ったか?」
ガルシア将軍と話したこと?まったく覚えていない。
「『その戦術でいくと、相手を皆殺しにすることになるぞ!』と問うたら、『だからなんだ?皆殺しの何が悪い?』と平然としてたたろう?」
……覚えていない。
「その顔じゃあ、覚えてないな。それで、俺が先生に相談したら、私塾へ誘ってみると言われてな……今となってはなぜ私塾へ呼んだのか、わかる」
ガルシア将軍は苦笑した。
オレはそこで気づいた。師匠は最初からリアンとオレを出会わせようとしていたのだと。
毒殺で母を亡くし、周りには平民出のオレに冷たくする者や優しい仮面をつけて利用してやろうと近づく者が多く、オレは人を信じられずにいた。心を押し殺し、強いウィルバートの顔を作り上げたオレは孤独の中にいた。
「王は残酷な決断をくださねばならないこともある。だが、人を慈しむ心も忘れてはならないと師匠は言っていた。今ならわかる気がするよ」
オレの言葉にガルシア将軍は嬉しい顔をした。こんな穏やかに将軍と話せるとは思わなかった。リアンの力はすごい。彼女は気づいてはいないが、もしかしたら有能な宰相や参謀になっていたかもしれない。
もしかしたらのその未来を消して傍に置いているのはオレなのだ。だけど、ごめんと心の中で、謝る。どうしても慈悲の心を持つ王でいるためにリアンが必要なんだ。許してほしい……と。
その表情は楽しそうで、先生の話を真剣に聞いたり、なんの授業でも興味津々で質問していたりする。
……自分はここまで楽しそうに学べないなと見ていて思った。
「リアンは勉強好きなんだね」
「せっかくお父様にお願いをきいてもらえて、ここに入れたもの!できるだけいろんなことを知りたいのよ」
キラキラとした緑色の目は明るい色の光を帯びていて、人生を心から純粋に楽しんでいる。リアンのその目には世界は楽しいことだらけで、輝いて見えていることだろう。
それがオレにはとても眩しすぎるように感じたが、暗闇の心にスッと光が射し込んだような気がした。
そんな彼女を評価し、ガルシア将軍は言った。
「陛下はたいした王妃様を手に入れたもんだよ。っていうか、あの先生の私塾にいたなら、いたと言えよ!あの先生に学んだなら、そりゃ腹黒い……いや、なんでもない」
オレは笑う。ガルシア将軍に、こんなふうに笑いかけたのは初めてかもしれない。
「うん。そういう笑顔の顔を持つ王も良いのかもな。陛下は……あの先生の私塾へ行く前に戦術を俺と話していて、なんと言ったか覚えているか?」
「なにか言ったか?」
ガルシア将軍と話したこと?まったく覚えていない。
「『その戦術でいくと、相手を皆殺しにすることになるぞ!』と問うたら、『だからなんだ?皆殺しの何が悪い?』と平然としてたたろう?」
……覚えていない。
「その顔じゃあ、覚えてないな。それで、俺が先生に相談したら、私塾へ誘ってみると言われてな……今となってはなぜ私塾へ呼んだのか、わかる」
ガルシア将軍は苦笑した。
オレはそこで気づいた。師匠は最初からリアンとオレを出会わせようとしていたのだと。
毒殺で母を亡くし、周りには平民出のオレに冷たくする者や優しい仮面をつけて利用してやろうと近づく者が多く、オレは人を信じられずにいた。心を押し殺し、強いウィルバートの顔を作り上げたオレは孤独の中にいた。
「王は残酷な決断をくださねばならないこともある。だが、人を慈しむ心も忘れてはならないと師匠は言っていた。今ならわかる気がするよ」
オレの言葉にガルシア将軍は嬉しい顔をした。こんな穏やかに将軍と話せるとは思わなかった。リアンの力はすごい。彼女は気づいてはいないが、もしかしたら有能な宰相や参謀になっていたかもしれない。
もしかしたらのその未来を消して傍に置いているのはオレなのだ。だけど、ごめんと心の中で、謝る。どうしても慈悲の心を持つ王でいるためにリアンが必要なんだ。許してほしい……と。