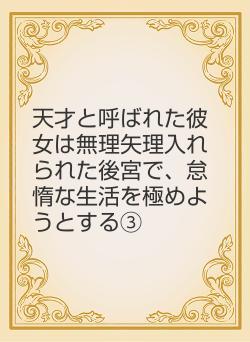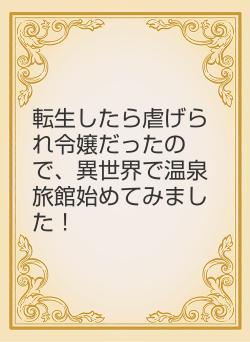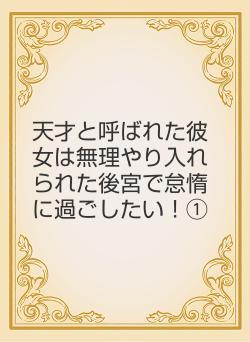「まったく……素直じゃないんだから」
私はクスクスと笑いながら、ガルシア将軍のことをアナベルに言うと、彼女は何故か半眼になった。
「じゃあ、お嬢様も素直に言ったらどうですか?ガルシア将軍がウィルバート様のことを痛めつけた話を聞いてしまって、売り言葉に買い言葉で、どんどん喧嘩を買うようなことをしていたと……」
ギクリと私はした。実はけっこう早くにガルシア将軍はウィルバートのことを考えてしていることだと気付いていた。それなのに精神的にガルシア将軍をオーバーキルしちゃった感はある。優しいアナベルはやりすぎですよと怒っている。
「えっ…と……」
「アナベルは見抜いておりましたよ!一番素直じゃないのはお嬢様ですよ。政治のこと、戦のことを真剣に学んでいるのだって、ウィルバート様が蛮族平定の戦に行かれると、長く帰ってこれず、寂しいからなのよと言えばいいんです!」
「ううっ………だって……」
ぐぅの音も出ないほど、アナベルに見抜かれている。さすが幼少期からの付き合いだ。
「なんですか?」
「言えないわよ!冷静に対処すべきなのに……やりすぎてしまったなって自分でもわかってるのよ!自分の気持ちをコントロールできないの!ウィルバートのことを好きすぎるのよ!」
「リアーン?お茶しに来た……えっ?」
「きゃああああ!」
いきなりウィルバートが扉を開けて、部屋に入ってきたため、悲鳴をあげた。なぜ、このタイミングなの!?狙ってるの!?
「な、なんだ!?ノックしたぞ!?」
「今の話を聞いてないわよね!?」
なんのことだ?とウィルバートは首を傾げた。アナベルが苦笑し、お茶の用意をする。ドキドキする心臓を抑える。
「今回のこと、ありがとう。オレはガルシア将軍のことをずっと誤解したままでいるところだった」
「えーと、良いのよ!気にしないで!」
さっきからの流れでウィルバートにまたその話をされて、思わず声がうわずってしまう。
「王を王とも思わない将軍の態度をずっと勘違いしていた。オレは平民出の王だし、未熟な王だし、認めてもらえていないんだなとか……けっこう悩んでいたんだけど、今度からはガルシア将軍が自然と膝を折るような王になるように努力していくよ」
私は目を丸くした。ウィルバートがとても前向きに話をしている。良き王になろうと決意する彼はとても眩しく見える。
「う、うん。良かったわ。悩みが解決したみたいで……」
ウィルバートはそして優しく微笑み、私に言った。
「リアンが傍にいてくれてよかった」
気を使って、アナベルがそっと部屋から出ていくのが見えた。いなくなると、ウィルバートがいたずらっぽく笑った。そして言う。
「……いつになったら、面と向かって好きとか愛してるとかリアンはオレに言ってくれるんだろう?」
「ウィルバートーーーっ!やっぱり聞こえていたんじゃないのーーーっ!」
私の声が後宮に響いたのだった。恥ずかしくて言えない。ウィルバートの顔を見ると、余計に言えなくなっちゃう!
素直じゃないのは私の方だ。
怠惰なフリして逃げているのも私だ。
ウィルバートは良い王になろうと、心が強くなっていっているのに、私はどうだろう?まったく成長してないんじゃないかしら?と、置いてきぼりになった気がして、少し寂しい気持ちになってしまった。
私はクスクスと笑いながら、ガルシア将軍のことをアナベルに言うと、彼女は何故か半眼になった。
「じゃあ、お嬢様も素直に言ったらどうですか?ガルシア将軍がウィルバート様のことを痛めつけた話を聞いてしまって、売り言葉に買い言葉で、どんどん喧嘩を買うようなことをしていたと……」
ギクリと私はした。実はけっこう早くにガルシア将軍はウィルバートのことを考えてしていることだと気付いていた。それなのに精神的にガルシア将軍をオーバーキルしちゃった感はある。優しいアナベルはやりすぎですよと怒っている。
「えっ…と……」
「アナベルは見抜いておりましたよ!一番素直じゃないのはお嬢様ですよ。政治のこと、戦のことを真剣に学んでいるのだって、ウィルバート様が蛮族平定の戦に行かれると、長く帰ってこれず、寂しいからなのよと言えばいいんです!」
「ううっ………だって……」
ぐぅの音も出ないほど、アナベルに見抜かれている。さすが幼少期からの付き合いだ。
「なんですか?」
「言えないわよ!冷静に対処すべきなのに……やりすぎてしまったなって自分でもわかってるのよ!自分の気持ちをコントロールできないの!ウィルバートのことを好きすぎるのよ!」
「リアーン?お茶しに来た……えっ?」
「きゃああああ!」
いきなりウィルバートが扉を開けて、部屋に入ってきたため、悲鳴をあげた。なぜ、このタイミングなの!?狙ってるの!?
「な、なんだ!?ノックしたぞ!?」
「今の話を聞いてないわよね!?」
なんのことだ?とウィルバートは首を傾げた。アナベルが苦笑し、お茶の用意をする。ドキドキする心臓を抑える。
「今回のこと、ありがとう。オレはガルシア将軍のことをずっと誤解したままでいるところだった」
「えーと、良いのよ!気にしないで!」
さっきからの流れでウィルバートにまたその話をされて、思わず声がうわずってしまう。
「王を王とも思わない将軍の態度をずっと勘違いしていた。オレは平民出の王だし、未熟な王だし、認めてもらえていないんだなとか……けっこう悩んでいたんだけど、今度からはガルシア将軍が自然と膝を折るような王になるように努力していくよ」
私は目を丸くした。ウィルバートがとても前向きに話をしている。良き王になろうと決意する彼はとても眩しく見える。
「う、うん。良かったわ。悩みが解決したみたいで……」
ウィルバートはそして優しく微笑み、私に言った。
「リアンが傍にいてくれてよかった」
気を使って、アナベルがそっと部屋から出ていくのが見えた。いなくなると、ウィルバートがいたずらっぽく笑った。そして言う。
「……いつになったら、面と向かって好きとか愛してるとかリアンはオレに言ってくれるんだろう?」
「ウィルバートーーーっ!やっぱり聞こえていたんじゃないのーーーっ!」
私の声が後宮に響いたのだった。恥ずかしくて言えない。ウィルバートの顔を見ると、余計に言えなくなっちゃう!
素直じゃないのは私の方だ。
怠惰なフリして逃げているのも私だ。
ウィルバートは良い王になろうと、心が強くなっていっているのに、私はどうだろう?まったく成長してないんじゃないかしら?と、置いてきぼりになった気がして、少し寂しい気持ちになってしまった。