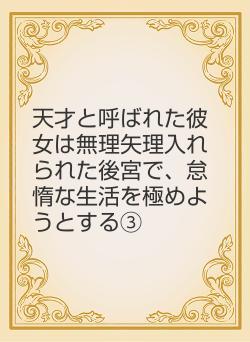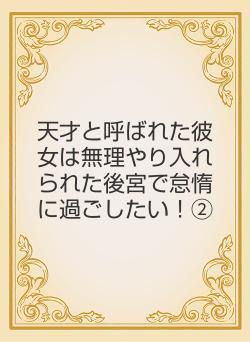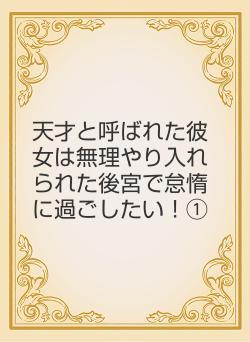夏が始まろうとする頃、私は社交界に乗り込むためにきた。
ちなみに王都ウィンダムの支店は順調に業績を伸ばしている。休日は行列ができるほどだ。その噂も王都に広がっていた今が貴婦人達の心をとらえるチャンスだ。
行き交う人々や民家の向こうに王城が見える。王城の周りには王族、貴族の家々の屋敷が立ち並んでいる。城に近ければ近いほど身分も高くなっていく。カムパネルラ公爵家は王城のすぐそばであった。
「ここだ」
私と私付きのメイドさん二名が一緒に降りる。屋敷の大きさに圧倒される。庭から馬車に乗り入れていき、家の門の前に来ると、ズラリと並ぶ使用人達。
『お帰りなさいませ。リヴィオ様』
本当のお坊ちゃんだったのねぇ。私の家の使用人達の人数とは比べ物にならない。
「ただいま。荷物を……」
リヴィオがそう言いかけるやいなや、使用人達がササッと動いて荷物を持っていく。
「ようこそ。バシュレ家のお嬢さん」
出てきたのは黒髪と碧眼のイケメンおじさま!中年男性なのだが、優しげな雰囲気と上品さが漂いなんとも言えない大人の男性の魅力溢れる人だ。
「えっ!?父さんがなぜここに!?」
ハハハと笑う。父ということはカムパネルラ公爵家の当主!?わざわざなんで出迎えに?
私はスッと服の裾を持ち、お辞儀をする。
「この度は滞在をお許し頂きありがとうございます。わたくし、セイラ=バシュレと申します」
「君が!そうか……バシュレ家のあの方の血をひいている孫娘だね。ハリー=カムパネルラだ」
祖父をご存知ですか?と聞くのは失礼なのだろうか?有名ではあるが……わからないのでニッコリと微笑んでおく。察したカムパネルラ公爵が補足してくれる。
「君のお祖父さんには昔、よく世話になってね。その黒髪と黒い眼の眼差し、よく似ているよ。そして家のヤンチャな三男坊を扱えてるところがスゴイ!」
パチパチと拍手までしてくれる。ヤンチャってリヴィオのこと??
「父さん!」
リヴィオがイライラとした声をあげ、鋭く睨みつける。学園では睨まれると恐れ慄く人が多かったが、ここでは誰も動じない。むしろ明るい声音が横から入る。
「あらあら。玄関先でなんですか。あなた、入って頂きましょうよ」
金色の髪に青い目をした美女。ドレスも普段着なのだろうが、決して派手ではないのにさりげ無い宝石のついた装飾品、レースの付け方などセンスの良さを感じさせる。振る舞いの動作一つも優雅だ。
「こちらは私の妻のオリビア=カムパネルラ」
「母さんまで!?なんで今日に限って、家にいるんだ!?いつも忙しくて二人ともいないだろうが!?」
リヴィオが動揺している。ホホホとオリビアが上品に扇子を口元に当てて笑う。
「あら?いけなかった?……殿下を殴って謹慎中なのに、逃亡したヤンチャ坊主を叱りたかったのよ」
「えええっ!?殴った?リヴィオ!?!?」
私がびっくりして顔を見るとプイッと明後日の方向を見てそらす。いや、現実逃避するなー!
「別にいいだろ!」
見つめていた私に視線を合わさないまま言い返す………不敬罪で問われる危険があるじゃない!なんてことしてきたの!?
「騎士団除名くらいで済んだのも父のおかげだぞー」
「謹慎していたはずなのに、いつの間にか屋敷から消えていて、こんなかわいいお嬢さんのところにいたなんてね」
二人の親に責められているというか、怒られているんだと察する。
まぁ、でもリヴィオにも話さないが、何かしらの理由があったんだろう。私は助け舟を出すことにした。
「えーと、滞在させて頂くお礼にお土産を持ってきました。けっこう便利な物なのですよ」
荷馬車から降ろしてもらう。冷凍庫、冷蔵庫、ドライヤー、洗濯機。
「これは!?なんですの?」
私は一つ一つ説明した。そのたびに感心するような声が周囲からあがる。
「なるほど……これはリヴィオが飽きないわけだ」
公爵が価値あるものと思ってくれたらしい。オリビアはメイド達が喜ぶわ!こんなに沢山いいのかしら!?とニコニコであるが…私の思惑はそこではない。扇子をパラリと開いて言う。
「使って頂いて、気に入りましたら、皆に教えて頂けたらと思います」
カムパネルラ公爵が目を丸くした。すぐに私の意図を察する。
「ほんとに……お祖父さんそっくりだよ!いや、残念すぎる。男だったら、王宮に連れて行って事務官に推薦したかった!私の右腕になりうる予感がする。今だから言うけどねぇ。君のお祖父さんは宰相の椅子を用意するとまで言われたんだよ。だけど断った。それでカムパネルラ公爵家にまわってきたってわけだ」
そういえばカムパネルラ公爵は宰相をしていると聞いたことがある。リヴィオはかなりのお坊ちゃんなわけだ。
「祖父にも私にも過ぎたお言葉ですわ」
「それでもね…君のお祖父さんは王国のために色々と尽くしてくれたんだよ。陰ながらね。だから、何か私からも恩返しがしたい。申し訳ないが、現バシュレ家当主は恩返しをするに値する者でないと判断してしまった。君なら良いかもしれない」
優しい眼差しで私を見る。なにかわからないが、お祖父様ありがとう。これで商売がうまくいく予感です。
ただで泊めてもらうだけでなく営業もするふてふてしい孫娘でゴメンナサイ。温泉旅館計画のためには元手となるお金と地道な営業だ。
そんな挨拶も済んで、私は部屋に案内してもらう。リヴィオに歩きながら、それとなく聞いたがすべてはぐらかされた。
「なぜ学園にきていたの?」
学園は特殊である。寄宿学校であり、幼い頃より入学して親元を離れなければならない。エリート教育を施されているところである。将来は約束されたようなものだか……公爵家の大事なお坊ちゃんが入る必要があったのだろうか?個別でも十分良い教師をつけれるだろう。
「自分から行きたいと言った。それだけだ。いらねー詮索すんな」
「ついでに聞くけど、なんで殿下殴ったの?さては……女性関係でしょ?」
リヴィオはモテる。学園のおねーさま、はては女教師にも気に入られていた。それが面白くない上級生に呼び出しをくらい………返り討ちにしてたな。懐かしい。私はまったく関係ないところで他人事で見てた。本の隙間から見えたとでも言おうか。
ジロリと睨まれたので、さっさと客間へ逃げ込んだ。当たりかもしれない。
さて、与えられたチャンスはモノにしていきたい。あまり時間もないことだし。とりあえず支店の様子でも見てこようかなと思いつつ、私が荷物をメイドと一緒に片付けていた時、ドアがノックされた。
「失礼するわね」
オリビアだ。メイドを数名連れていきなり来た。
「ごめんなさいね。急だけどハリーがわたくしの方が今回は適任ではないかと言ったので力にならせてもらうわ。わたくし主催の夜会に出て人脈作りをするといいわ」
「え!?そんな……甘えてばかりいられません。こうして滞在させてもらうだけでもありがたいです」
「良いのよ。どうせほぼ毎日なにかしらの集まりをしているのよ。逆に話題を提供してくれてこちらの方が嬉しいのよ。明日の夜会に出席しなさいな。たくさんの貴族が来るわよ。ご紹介するわ」
「ありがとうございます!あの、それでデザートなのですが……」
こうして明日の夜会にはアイスクリームをお披露目できることになったのだった。
支店のアイスクリーム屋『サニーサンデー』は王都の新聞にも取材された。サニーちゃんの着ぐるみをリヴィオが着て、すごく不機嫌なかわいいライオンが私の背後にいる写真が載った。
適役がいなかったので、頼んでみたら意外としてくれたリヴィオだが、残念なことに演技力はなかった。
威圧感たっぷりで子どもたちが逃げる雰囲気じゃないの。人選ミス。ニホンの某ディ○ニーランドとやらの遊園地のスタッフを見習ってほしいものだわ。
「もっと愛想よくしなさいよねっ」
「できるか!!」
「着ぐるみから殺意感じるのよ!」
「子供らが殴ってくるからだ!」
確かに一部の子供らは「えーい!へんなやつ!」とふざけてサニーちゃんに攻撃を仕掛けていた。やり返さなかっただけ……えらいのかな?脳裏にめちゃくちゃ戦闘に強い着ぐるみが浮かび、私の頬に一筋の汗が伝う。
サニーちゃん、今度はスタッフに頼もうと決心したのだった。
夕方になり、お互い夜会の準備に取りかかる。私は黒髪に合う青いドレスを選ぶ。髪を編み込み、纏め上げる器用なメイドさん。
「お嬢様はスラッとしておいでですから、このドレスのラインがきれいにみえますね!すっごくお似合いです!クールな感じです」
上手に褒めてくれるメイドさんのおかげで私、いつもの2割増しくらいに女らしくなれたかも。普段は男物に近い服を着て、馬を乗り回し、走り回っているから比較できるかどうかは謎だけど……。
「おい!もう良いか!?始まるぞ」
「はーい!」
ドアを開けると、そこには金糸の入った黒と紫を基調とした服を着ている、喋らなければ王子様のような彼がいた。
「おー………馬を乗り回しているときとは別人だな」
一瞬でリヴィオの王子タイム終了。悪かったわねっと言い返す。
「エスコートしてくれるの?」
「仕方がない。営業するんだろ」
そのとおり。営業スマイル用の笑顔を作る。扉の向こう側は華やかな音楽と着飾った人々。
まずオリビアに招待の礼を述べに行く。
私とリヴィオの姿を見て、心得たとばかりにお客様たちに語りかけた。
「皆様!今日は都で流行している『アイスクリーム』を特別に用意させてもらいましたの!良かったらご賞味くださいな」
私が営業するまでもなく、アイスクリームは噂になっていたようで、キャアキャア言いながら女性客は手を出し、試してみている。
その様子に私は良かったーと安堵する。オリビアがフフフッと笑いながら近づいてきた。
「なかなか貴方達お似合いよ」
「はあ??」
リヴィオが間の抜けた声をあげる。
「ビジネスパートナーです」
私もきっぱりと言っておく。あらーと残念そうなオリビア。リヴィオは余計なこと言うなよっ!と小声で母に釘をさしている。
クールなリヴィオが家では度々子ども扱いされている。面白いものをみれた。ジーニーが見たら指さして大笑いしてるだろうなぁ。
「あらっ?どこの誰かと思ったら……セイラじゃないの?」
ビクッと私は身震いした。背後から嫌な声。まさか!と振り返ると会いたくない人がいた。
「公爵夫人のパーティに来るなんて、図々しいこと!」
ソフィアである。相変わらず美人で、豊かな金色の髪を少し垂らして流行りの型のピンクのドレスを着ている。人形のように愛らしいが、口から出る言葉は毒を含んでいる。周りには聞こえないように耳許まで来てささやく。
「どうやって取り入ったの?」
私の中のセイラである部分がソフィアを怖がっていて口から言葉を失ってしまっている。無言の私を面白く思わなかったようで、スタスタと近づいてきたと思ったら手に持っていた溶けかけたアイスクリームをパッと私に投げつけた。ベットリとドレスに付く。クスクスと笑うソフィア。声は可愛く申し訳ない雰囲気を漂わせる。女優である。
「大変っ!ごめんなさい。許していただける?」
「あ……」
何するのよ!と怒鳴りたかったが、声が出ず、成り行きを見守っていたリヴィオが動いた。金色の目が燃えるように赤く染まっている。
「無礼だぞっ!オレが連れてきた客人と知っての行為か?」
その鋭い一声にソフィアが顔を強ばらせた。バッと私の腕を掴み、自分の後ろへ隠すように下がらせ、使用人に合図し、拭くものを持ってこさせる。そして耳元で怒りを込めた声で私に言った。
「セイラ!おまえ何しに来たんだ?しっかりしろ!」
ハッと目が覚める。本当にそうだ。私は弾かれたように声を出した。臆してる場合ではない。
「ソフィア嬢、構いませんわ。数あるドレスの一枚ですもの」
そこで騒ぎに集まってきた観衆にニッコリと微笑みかける。扇子を口元に当てて優雅にドレスの裾を持つ。
「このアイスクリームは私の領地で作られたものですの。皆様、如何かしら?お気に召したら、ぜひ夜会やお茶会にも、こうしてお届けいたしますわ。だけど一つ気をつけてくださいね!こうやって時々アイスクリームは空を飛ぶようですわ」
ドッと楽しげな笑い声が起こる。私はフワリと優雅にドレスを翻し、お辞儀して退出する。場の雰囲気を悪くしてしまっては公爵家にも申し訳ない。
「少し着替えの時間をいただきますわ。皆様、お楽しみくださいな。失礼いたします」
リヴィオに視線を送る。営業頼んだわよ!と私は意味を込めて見ると頷くリヴィオ。アイコンタクトで会話した。
部屋から出る前にチラリと見たソフィアは顔を赤くして怒りを隠せずにいた。
オリビアは場を盛り上げるために、音楽を!と楽師たちに声をかけた。会場は賑やかさを増した。
「ひどいです!」
「またソフィア様ですか!!」
怒るメイド達だが、すぐにドレスを用意する。
「失礼するわね」
オリビアの声だ。私は慌てて立ち上がる。
「申し訳ありません!騒ぎを起こしてしまって……」
「何を言うの!謝るのはこちらだわ……わたくしの客がこんなことをするなんて……もう二度と呼ばないことにするわ」
今をときめく公爵家の夜会から弾かれることは社交的にかなり痛い。それをわかっているのかいないのか……ソフィアは軽率すぎる。
「このドレス使ってくれる?」
手渡されたのは薄い生地でブルーグレイのドレス。ところどころに真珠が散りばめられた繊細なものだ。どう見ても……高い。
「わたくしの若い時のものなのよ。差し上げるわ。気に入っていて捨てれずにいたのよ」
「そんな!いけません!大事になさってるものでしょう!?」
オリビアはいいのよ。着てほしいのよと微笑む。逆に申し訳ない気持ちになりながらも受けとる。
「ありがとうございます」
私はオリビアの好意に甘えて、ブルーグレイのドレスを着用して戻った。オリビアが着れば似合うだろうが、私はどうだろうか?色気もない地味な自分の容貌に自信がない。
部屋に入った途端ら見た人々がざわめく。なんだろう?
「そ、それ……」
リヴィオすら動揺している。一瞬、何か考えるような間があったが手を差し出す。なに?それ?私は意味がわからず首を傾げた。
「一曲踊ろう」
えー。めんどくさいんだけどと思いつつ、なにやら注目を浴びているので、言われるままに踊る。
「なんで皆、驚いてるの?」
「それ、オレの父さんが母さんにあげたやつだ。婚約披露のとき、結婚式のパーティのとき、兄さんが生まれたときのお披露目……母さんが気に入っていて大切な時に着ていたものだ。まさかそれをセイラに渡すとか何考えてるんだか」
ボソボソと言う。ええええ!?そんな大事にしてたものを!?なぜ私に!?
「い、いいのかしら!?」
「くれるっていうからいいんだろ。似合うと思ったからおまえにやったんだろうしな」
リヴィオがなぜがそう言うと、長い睫毛の目を伏せる。一曲踊り終えると、周囲から集まってくる人達に囲まれた。
「公爵夫人が今、流行りのアイスクリームを取り入れるとは!美味しく頂きましたよ!」
「なんでも、お嬢様はあのバシュレ家の孫娘だそうですね」
「今度、お茶会にアイスクリームを頼んでもいいかしら?」
次から次へ相手をするのが忙しくて、私はソフィアの存在をすっかり忘れていたのだった。きっと覚えていたならば、恐ろしい形相でこちらを見ていたことに気づいていただろうに…。
ちなみに王都ウィンダムの支店は順調に業績を伸ばしている。休日は行列ができるほどだ。その噂も王都に広がっていた今が貴婦人達の心をとらえるチャンスだ。
行き交う人々や民家の向こうに王城が見える。王城の周りには王族、貴族の家々の屋敷が立ち並んでいる。城に近ければ近いほど身分も高くなっていく。カムパネルラ公爵家は王城のすぐそばであった。
「ここだ」
私と私付きのメイドさん二名が一緒に降りる。屋敷の大きさに圧倒される。庭から馬車に乗り入れていき、家の門の前に来ると、ズラリと並ぶ使用人達。
『お帰りなさいませ。リヴィオ様』
本当のお坊ちゃんだったのねぇ。私の家の使用人達の人数とは比べ物にならない。
「ただいま。荷物を……」
リヴィオがそう言いかけるやいなや、使用人達がササッと動いて荷物を持っていく。
「ようこそ。バシュレ家のお嬢さん」
出てきたのは黒髪と碧眼のイケメンおじさま!中年男性なのだが、優しげな雰囲気と上品さが漂いなんとも言えない大人の男性の魅力溢れる人だ。
「えっ!?父さんがなぜここに!?」
ハハハと笑う。父ということはカムパネルラ公爵家の当主!?わざわざなんで出迎えに?
私はスッと服の裾を持ち、お辞儀をする。
「この度は滞在をお許し頂きありがとうございます。わたくし、セイラ=バシュレと申します」
「君が!そうか……バシュレ家のあの方の血をひいている孫娘だね。ハリー=カムパネルラだ」
祖父をご存知ですか?と聞くのは失礼なのだろうか?有名ではあるが……わからないのでニッコリと微笑んでおく。察したカムパネルラ公爵が補足してくれる。
「君のお祖父さんには昔、よく世話になってね。その黒髪と黒い眼の眼差し、よく似ているよ。そして家のヤンチャな三男坊を扱えてるところがスゴイ!」
パチパチと拍手までしてくれる。ヤンチャってリヴィオのこと??
「父さん!」
リヴィオがイライラとした声をあげ、鋭く睨みつける。学園では睨まれると恐れ慄く人が多かったが、ここでは誰も動じない。むしろ明るい声音が横から入る。
「あらあら。玄関先でなんですか。あなた、入って頂きましょうよ」
金色の髪に青い目をした美女。ドレスも普段着なのだろうが、決して派手ではないのにさりげ無い宝石のついた装飾品、レースの付け方などセンスの良さを感じさせる。振る舞いの動作一つも優雅だ。
「こちらは私の妻のオリビア=カムパネルラ」
「母さんまで!?なんで今日に限って、家にいるんだ!?いつも忙しくて二人ともいないだろうが!?」
リヴィオが動揺している。ホホホとオリビアが上品に扇子を口元に当てて笑う。
「あら?いけなかった?……殿下を殴って謹慎中なのに、逃亡したヤンチャ坊主を叱りたかったのよ」
「えええっ!?殴った?リヴィオ!?!?」
私がびっくりして顔を見るとプイッと明後日の方向を見てそらす。いや、現実逃避するなー!
「別にいいだろ!」
見つめていた私に視線を合わさないまま言い返す………不敬罪で問われる危険があるじゃない!なんてことしてきたの!?
「騎士団除名くらいで済んだのも父のおかげだぞー」
「謹慎していたはずなのに、いつの間にか屋敷から消えていて、こんなかわいいお嬢さんのところにいたなんてね」
二人の親に責められているというか、怒られているんだと察する。
まぁ、でもリヴィオにも話さないが、何かしらの理由があったんだろう。私は助け舟を出すことにした。
「えーと、滞在させて頂くお礼にお土産を持ってきました。けっこう便利な物なのですよ」
荷馬車から降ろしてもらう。冷凍庫、冷蔵庫、ドライヤー、洗濯機。
「これは!?なんですの?」
私は一つ一つ説明した。そのたびに感心するような声が周囲からあがる。
「なるほど……これはリヴィオが飽きないわけだ」
公爵が価値あるものと思ってくれたらしい。オリビアはメイド達が喜ぶわ!こんなに沢山いいのかしら!?とニコニコであるが…私の思惑はそこではない。扇子をパラリと開いて言う。
「使って頂いて、気に入りましたら、皆に教えて頂けたらと思います」
カムパネルラ公爵が目を丸くした。すぐに私の意図を察する。
「ほんとに……お祖父さんそっくりだよ!いや、残念すぎる。男だったら、王宮に連れて行って事務官に推薦したかった!私の右腕になりうる予感がする。今だから言うけどねぇ。君のお祖父さんは宰相の椅子を用意するとまで言われたんだよ。だけど断った。それでカムパネルラ公爵家にまわってきたってわけだ」
そういえばカムパネルラ公爵は宰相をしていると聞いたことがある。リヴィオはかなりのお坊ちゃんなわけだ。
「祖父にも私にも過ぎたお言葉ですわ」
「それでもね…君のお祖父さんは王国のために色々と尽くしてくれたんだよ。陰ながらね。だから、何か私からも恩返しがしたい。申し訳ないが、現バシュレ家当主は恩返しをするに値する者でないと判断してしまった。君なら良いかもしれない」
優しい眼差しで私を見る。なにかわからないが、お祖父様ありがとう。これで商売がうまくいく予感です。
ただで泊めてもらうだけでなく営業もするふてふてしい孫娘でゴメンナサイ。温泉旅館計画のためには元手となるお金と地道な営業だ。
そんな挨拶も済んで、私は部屋に案内してもらう。リヴィオに歩きながら、それとなく聞いたがすべてはぐらかされた。
「なぜ学園にきていたの?」
学園は特殊である。寄宿学校であり、幼い頃より入学して親元を離れなければならない。エリート教育を施されているところである。将来は約束されたようなものだか……公爵家の大事なお坊ちゃんが入る必要があったのだろうか?個別でも十分良い教師をつけれるだろう。
「自分から行きたいと言った。それだけだ。いらねー詮索すんな」
「ついでに聞くけど、なんで殿下殴ったの?さては……女性関係でしょ?」
リヴィオはモテる。学園のおねーさま、はては女教師にも気に入られていた。それが面白くない上級生に呼び出しをくらい………返り討ちにしてたな。懐かしい。私はまったく関係ないところで他人事で見てた。本の隙間から見えたとでも言おうか。
ジロリと睨まれたので、さっさと客間へ逃げ込んだ。当たりかもしれない。
さて、与えられたチャンスはモノにしていきたい。あまり時間もないことだし。とりあえず支店の様子でも見てこようかなと思いつつ、私が荷物をメイドと一緒に片付けていた時、ドアがノックされた。
「失礼するわね」
オリビアだ。メイドを数名連れていきなり来た。
「ごめんなさいね。急だけどハリーがわたくしの方が今回は適任ではないかと言ったので力にならせてもらうわ。わたくし主催の夜会に出て人脈作りをするといいわ」
「え!?そんな……甘えてばかりいられません。こうして滞在させてもらうだけでもありがたいです」
「良いのよ。どうせほぼ毎日なにかしらの集まりをしているのよ。逆に話題を提供してくれてこちらの方が嬉しいのよ。明日の夜会に出席しなさいな。たくさんの貴族が来るわよ。ご紹介するわ」
「ありがとうございます!あの、それでデザートなのですが……」
こうして明日の夜会にはアイスクリームをお披露目できることになったのだった。
支店のアイスクリーム屋『サニーサンデー』は王都の新聞にも取材された。サニーちゃんの着ぐるみをリヴィオが着て、すごく不機嫌なかわいいライオンが私の背後にいる写真が載った。
適役がいなかったので、頼んでみたら意外としてくれたリヴィオだが、残念なことに演技力はなかった。
威圧感たっぷりで子どもたちが逃げる雰囲気じゃないの。人選ミス。ニホンの某ディ○ニーランドとやらの遊園地のスタッフを見習ってほしいものだわ。
「もっと愛想よくしなさいよねっ」
「できるか!!」
「着ぐるみから殺意感じるのよ!」
「子供らが殴ってくるからだ!」
確かに一部の子供らは「えーい!へんなやつ!」とふざけてサニーちゃんに攻撃を仕掛けていた。やり返さなかっただけ……えらいのかな?脳裏にめちゃくちゃ戦闘に強い着ぐるみが浮かび、私の頬に一筋の汗が伝う。
サニーちゃん、今度はスタッフに頼もうと決心したのだった。
夕方になり、お互い夜会の準備に取りかかる。私は黒髪に合う青いドレスを選ぶ。髪を編み込み、纏め上げる器用なメイドさん。
「お嬢様はスラッとしておいでですから、このドレスのラインがきれいにみえますね!すっごくお似合いです!クールな感じです」
上手に褒めてくれるメイドさんのおかげで私、いつもの2割増しくらいに女らしくなれたかも。普段は男物に近い服を着て、馬を乗り回し、走り回っているから比較できるかどうかは謎だけど……。
「おい!もう良いか!?始まるぞ」
「はーい!」
ドアを開けると、そこには金糸の入った黒と紫を基調とした服を着ている、喋らなければ王子様のような彼がいた。
「おー………馬を乗り回しているときとは別人だな」
一瞬でリヴィオの王子タイム終了。悪かったわねっと言い返す。
「エスコートしてくれるの?」
「仕方がない。営業するんだろ」
そのとおり。営業スマイル用の笑顔を作る。扉の向こう側は華やかな音楽と着飾った人々。
まずオリビアに招待の礼を述べに行く。
私とリヴィオの姿を見て、心得たとばかりにお客様たちに語りかけた。
「皆様!今日は都で流行している『アイスクリーム』を特別に用意させてもらいましたの!良かったらご賞味くださいな」
私が営業するまでもなく、アイスクリームは噂になっていたようで、キャアキャア言いながら女性客は手を出し、試してみている。
その様子に私は良かったーと安堵する。オリビアがフフフッと笑いながら近づいてきた。
「なかなか貴方達お似合いよ」
「はあ??」
リヴィオが間の抜けた声をあげる。
「ビジネスパートナーです」
私もきっぱりと言っておく。あらーと残念そうなオリビア。リヴィオは余計なこと言うなよっ!と小声で母に釘をさしている。
クールなリヴィオが家では度々子ども扱いされている。面白いものをみれた。ジーニーが見たら指さして大笑いしてるだろうなぁ。
「あらっ?どこの誰かと思ったら……セイラじゃないの?」
ビクッと私は身震いした。背後から嫌な声。まさか!と振り返ると会いたくない人がいた。
「公爵夫人のパーティに来るなんて、図々しいこと!」
ソフィアである。相変わらず美人で、豊かな金色の髪を少し垂らして流行りの型のピンクのドレスを着ている。人形のように愛らしいが、口から出る言葉は毒を含んでいる。周りには聞こえないように耳許まで来てささやく。
「どうやって取り入ったの?」
私の中のセイラである部分がソフィアを怖がっていて口から言葉を失ってしまっている。無言の私を面白く思わなかったようで、スタスタと近づいてきたと思ったら手に持っていた溶けかけたアイスクリームをパッと私に投げつけた。ベットリとドレスに付く。クスクスと笑うソフィア。声は可愛く申し訳ない雰囲気を漂わせる。女優である。
「大変っ!ごめんなさい。許していただける?」
「あ……」
何するのよ!と怒鳴りたかったが、声が出ず、成り行きを見守っていたリヴィオが動いた。金色の目が燃えるように赤く染まっている。
「無礼だぞっ!オレが連れてきた客人と知っての行為か?」
その鋭い一声にソフィアが顔を強ばらせた。バッと私の腕を掴み、自分の後ろへ隠すように下がらせ、使用人に合図し、拭くものを持ってこさせる。そして耳元で怒りを込めた声で私に言った。
「セイラ!おまえ何しに来たんだ?しっかりしろ!」
ハッと目が覚める。本当にそうだ。私は弾かれたように声を出した。臆してる場合ではない。
「ソフィア嬢、構いませんわ。数あるドレスの一枚ですもの」
そこで騒ぎに集まってきた観衆にニッコリと微笑みかける。扇子を口元に当てて優雅にドレスの裾を持つ。
「このアイスクリームは私の領地で作られたものですの。皆様、如何かしら?お気に召したら、ぜひ夜会やお茶会にも、こうしてお届けいたしますわ。だけど一つ気をつけてくださいね!こうやって時々アイスクリームは空を飛ぶようですわ」
ドッと楽しげな笑い声が起こる。私はフワリと優雅にドレスを翻し、お辞儀して退出する。場の雰囲気を悪くしてしまっては公爵家にも申し訳ない。
「少し着替えの時間をいただきますわ。皆様、お楽しみくださいな。失礼いたします」
リヴィオに視線を送る。営業頼んだわよ!と私は意味を込めて見ると頷くリヴィオ。アイコンタクトで会話した。
部屋から出る前にチラリと見たソフィアは顔を赤くして怒りを隠せずにいた。
オリビアは場を盛り上げるために、音楽を!と楽師たちに声をかけた。会場は賑やかさを増した。
「ひどいです!」
「またソフィア様ですか!!」
怒るメイド達だが、すぐにドレスを用意する。
「失礼するわね」
オリビアの声だ。私は慌てて立ち上がる。
「申し訳ありません!騒ぎを起こしてしまって……」
「何を言うの!謝るのはこちらだわ……わたくしの客がこんなことをするなんて……もう二度と呼ばないことにするわ」
今をときめく公爵家の夜会から弾かれることは社交的にかなり痛い。それをわかっているのかいないのか……ソフィアは軽率すぎる。
「このドレス使ってくれる?」
手渡されたのは薄い生地でブルーグレイのドレス。ところどころに真珠が散りばめられた繊細なものだ。どう見ても……高い。
「わたくしの若い時のものなのよ。差し上げるわ。気に入っていて捨てれずにいたのよ」
「そんな!いけません!大事になさってるものでしょう!?」
オリビアはいいのよ。着てほしいのよと微笑む。逆に申し訳ない気持ちになりながらも受けとる。
「ありがとうございます」
私はオリビアの好意に甘えて、ブルーグレイのドレスを着用して戻った。オリビアが着れば似合うだろうが、私はどうだろうか?色気もない地味な自分の容貌に自信がない。
部屋に入った途端ら見た人々がざわめく。なんだろう?
「そ、それ……」
リヴィオすら動揺している。一瞬、何か考えるような間があったが手を差し出す。なに?それ?私は意味がわからず首を傾げた。
「一曲踊ろう」
えー。めんどくさいんだけどと思いつつ、なにやら注目を浴びているので、言われるままに踊る。
「なんで皆、驚いてるの?」
「それ、オレの父さんが母さんにあげたやつだ。婚約披露のとき、結婚式のパーティのとき、兄さんが生まれたときのお披露目……母さんが気に入っていて大切な時に着ていたものだ。まさかそれをセイラに渡すとか何考えてるんだか」
ボソボソと言う。ええええ!?そんな大事にしてたものを!?なぜ私に!?
「い、いいのかしら!?」
「くれるっていうからいいんだろ。似合うと思ったからおまえにやったんだろうしな」
リヴィオがなぜがそう言うと、長い睫毛の目を伏せる。一曲踊り終えると、周囲から集まってくる人達に囲まれた。
「公爵夫人が今、流行りのアイスクリームを取り入れるとは!美味しく頂きましたよ!」
「なんでも、お嬢様はあのバシュレ家の孫娘だそうですね」
「今度、お茶会にアイスクリームを頼んでもいいかしら?」
次から次へ相手をするのが忙しくて、私はソフィアの存在をすっかり忘れていたのだった。きっと覚えていたならば、恐ろしい形相でこちらを見ていたことに気づいていただろうに…。