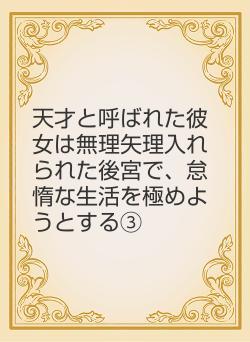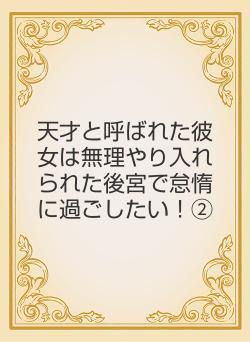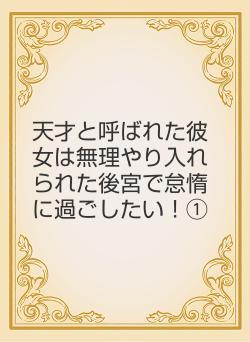執務室でゴソゴソとしていたら、ジーニーが不審な顔をした。
「セイラ、何してるんだ?」
「ちょっと探しものをね……」
本棚の隙間、クローゼットの中、隠し棚、すべて見た。お祖父様が前世の記憶があるものを残していないか、みつけようとしていた。
『コロンブス』の新大陸発見は有名だから、私のいた国じゃなくても知ってるだろうけど、同じ世界の記憶を持っていたのかどうか知りたかった。
日記とか記録と残っていないかと探したが無い。
お手上げだわ。そう思い、嘆息した。
「何を探してるのか言わねーから、手伝いようがない」
リヴィオが暇そうにソファに寝そべって、猫のようにダラーンと伸びている。
「あ、そうだ。探しものと言えば、昨日、学園の方に探し人を尋ねられてさ。……リヴィオ知らないか?」
「は?オレ??」
そうだと頷くジーニー。リヴィオは聞く前から知らねーと言ってめんどくさげに寝そべったままである。
「セイラも覚えてないか?3学年上の先輩でいただろう?『歌姫』を知らないか?」
「あ、ごめん、私は他のクラスの顔と名前覚えてないの」
「おい、アッサリ否定するな。かなりの有名人だと思うんだが?なぁ?リヴィオ?」
リヴィオが寝そべっていたのをやめている。起き上がって、ジーニーを金色の目で見ている。あれ?私以外は知ってるのかしら。
「記憶力良いのに、そういうところに使わないのか?」
「今は使ってるわよ。お客様の好きなもの嫌いなもの、話した内容、出身地とか覚えてるわ。ちゃんとお客様台帳にも書いてあるけど、記憶にも残してるわよ」
学園の時は周囲に興味を持てなかった。かろうじてクラスで関わるメンバーのみ記憶にある。ましてや3学年も上なら覚えてるわけがない。
「通称『歌姫』、学園祭や学園に要人をもてなす時に舞台に立って歌っていただろう?まあ、セイラ……らしいか」
リヴィオは先程から黙ったままである。
「リヴィオの元カノだ」
「へええええ!」
私が驚きの声をあげるとリヴィオが反論する。
「ちーがーう!違うと何回言えばわかるんだ!学園の時から言ってるだろうが!」
リヴィオの必死さに私は応援したくなり、助け舟を出した。
「ジーニー……たぶんリヴィオはあなたにだけには誤解されたくないのよ。ジーニー!リヴィオ!私は応援するわよ」
「いや、待て?セイラは何か誤解してないか?」
ジーニーが私を制止する。
「セイラは何言ってんだ?で、あいつ、どこへ行ったんだ?」
リヴィオが尋ねる。ジーニーがさあ??と首を傾げる。
「学園の方にいないかと聞かれたからいないと言った。それだけだ」
私は話半分になってしまったが、時間に気づいて、本日のお客様を迎えに慌てて旅館へ行ったのだった。
昔は人の顔と名前覚えるのが苦手だったことを思い出す。
周囲に興味を持てなかった。淡々と日々が過ぎていくのを感じていた。好きな本を読み、その世界にだけいる自分。
現実は辛いことの方が多かったから目を向けると傷つくだけだった。関わらないようにし、静かな存在でいるように努め、自分を守っていた。
他の生徒たちは家から送られてくる手紙やプレゼントがあるなか、私はなかった。
家に帰ることを許されない時は一人で寮にいて過ごしたこともあった。シンと静まった廊下、一人で食べる食事は気楽な反面、孤独を余計に意識させた。
時折、祖父が休みを一緒に過ごそうと呼んでくれた時は本当に嬉しかったものだ。だから休暇を過ごしていたナシュレ領は私にとって特別な場所だった。
「おい?セイラ大丈夫か?顔色あんまり良くないぞ」
過去に戻り、ぼんやりと一瞬していた私にリヴィオが声をかける。思わず現実に引き戻されて、ハッとした。
「大丈夫よ。ちょっとぼんやりしただけよ。さ!お客様をお迎えしましょう」
ガラガラと馬車が着いた。中から降り立ったのはまるで妖精さんのように美しい人だった。波打つ金色の長い髪、透き通るような白い肌、青い目をした彼女は優雅に微笑んだ。
「いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました」
私はお辞儀した。
「なんでここに!?エナ!」
「リヴィオ!!」
嬉しい笑顔で駆けてきて、リヴィオに抱きつくエナ。
「待て!やめろ!」
リヴィオが引き剥がそうとしている。私は反応に困りつつ、御者から荷物を受け取る。
愛らしい笑みは見ている誰もが惹きつけられる。スタッフ達もざわめくほどだ。まるで絵本から出てきた妖精さんだ。
「なによ……冷たいわね。久しぶりに会ったのに」
猫なら逆毛をたててるであろうリヴィオの反応。抱きつかれることを警戒している。
「行方不明じゃなかったのかよ!なに呑気に温泉に来てんだ!?」
困ったように頬に手をやる姿もまるで女優のように様になるエナ。
「学園を卒業してから、まともに休みなんてなかったのよ。スケジュール管理をされて、毎日舞台ばかり。楽しかったけど……最近は疲れてきて、楽しく感じられなくて。そんなとき、あなたを新聞で見て、いつか会いに行こうと思ったのよ」
熱烈な愛の告白にも聞こえる!!私とスタッフは興味津々で聞いている。
リヴィオは額に手を当てている。
「わたしのお世話係はリヴィオがいいわ!いいでしょう?」
「えーと……そうですね。じゃあ、リヴィオと客室係と2名でもいいですか?」
リヴィオ一人では無理だろう。リヴィオが私にオレを売るなよ!と言うが……はるばる会いに来てくれたのに邪険にしすぎだろう。
「まあ、いいじゃない。せっかく会いに来てくれたのに」
「おまえ、なんっとも思わないのかよ!?」
「何が??」
私が首を傾げるとリヴィオは拗ねたようにもういいっ!と怒ってエナの荷物を持って歩いて行く。なにを怒っているのだろうか??
その後、チラッと見に行ったが、なかなかリヴィオは様になっていた。大丈夫そうだ。
ただ、時折、エナの無茶ぶりがあるらしいことをペアの客室係から聞いた。
「お茶をお持ちしたら、リヴィオ様もそこへ座って話し相手になりなさいとか、売店にも付き添いなさいとか、お風呂の後には一緒に散歩したいとか言うのですよ!女将、いちスタッフへの接客には度が過ぎてます!」
一緒にいたい、けなげな乙女心なんじゃないかなぁ?
「まぁ、リヴィオのことだし、飽きたら抜けてくるわよ」
私はそう言って、大広間の夕食準備に指示をだす。お客様の中に魚が苦手な人がいると聞いたのでお肉への変更をしてほしいと知らせる。
広間の時計を見る。そろそろ皆が食事に入ってくる。
「お食事の席はこちらでございます」
私は案内しながら、今日の料理やお酒の種類を紹介していく。
「本日のデザートはリンゴシャーベットなんですよ。地元のリンゴなのです。リンゴはちょうど甘みが出てくる季節なんですよ。お嬢様は冷たいデザートは好きですか?」
家族連れの方に話しかける。子供が無邪気にアイスクリーム好きー!と答えてくれる。
「地元のお酒、用意してありますので、どうぞ試してみてくださいね。女性の方でも口当たりがよくて甘みがあり、飲みやすいと評判なんですよー!」
対応していると他のお客さんがざわつきだし、視線が入口付近へ集まる。
リヴィオと腕を組んで入ってくるエナ。お風呂上がりのやや赤みが差した白い頬に金色の髪をまとめて少したらした髪型は女性としてかなり魅力的だ。横に並ぶのは漆黒の髪と金色の目をした黙っていればイケメンのリヴィオ。
まるで姫と王子のようで絵になる。
「おい……」
私に話しかける、黙っていればイケメンのリヴィオさん。私は目だけで頷く。
みんなの目の保養の為に喋るなと合図したつもりだ。
「そろそろ変われ!限界だ。オレは接客無理だっ!」
イケメンタイムは終わった。
私は肩をすくめて、ニッコリと笑顔でエナに向く。
「お食事をどうぞ」
「えーっ。リヴィオも一緒に食べましょうよ!」
猫は束縛を嫌う。まさに『黒猫』リヴィオは逃げるように去っていった。
渋々と座席に座るエナ。フウッとため息をつく。つまらなーいと呟いて、苛立ちながら私に言う。
「お料理さっさと出していって!」
「かしこまりました」
私はスタッフの一人に頼み、調理場に急いでもらえるように耳打ちした。お品書きを見てもらい、説明で時間を稼ぐようにする。
「前菜の……」
「そんな話いいわ!それよりも!あなた、セイラ=バシュレでしょ。久しぶりね。リヴィオの学年の首席だったでしょ?」
「私のこともご存知でしたかー」
私のことはお気になさらずと言いたいが、なんだか、リヴィオがいなくなったら、私に絡んできた。さっきまで知らない顔していたのに……。
「知ってるわよ。おとなしいけど、常にトップに君臨してたでしょ」
そうでしたかねー?と言いつつ、お酒をお酌した。
「リヴィオとわたしの関係、気にならないの?」
「えーと……元カノと聞きましたけど、そうなんですか?」
答えず、ニヤッと笑われた。
前菜のキノコのマリネを置く。お酒を飲みつつ、エナは語りだした。
「学園の時に、付きまとってきた男がいて、そのしつこいやつを蹴散らしてくれて……リヴィオとジーニー!かっこよかったのよー!相手はずっとストーカーまがいのことをしてきてて、怖かったのよ。その後、退学になっていなくなったわ。学園時代が懐かしいわね。あの頃は楽しかったわ」
遠くを見る目をする。『歌姫』という立場、仕事に疲れているのかもしれない。
ウンウンと頷いて私は話を聞くが、一瞬、その男、バシュレ家で会った鞭男じゃないかな?と頭をよぎる。
「『歌姫』として卒業してからも、頑張っていたけど、毎日余裕なくて、だんだん歌も心を込めて歌えなくて薄っぺらくなってきたのを感じてきて、嫌気がさして、つい休暇とったわ」
行方不明と聞いているけど、本人は休暇のつもりらしい。じゃあ、戻るのねと私は思い、微笑む。
「歌が嫌になったわけではないのですね。少しお疲れなのかもしれませんね」
「そうね……」
サクサクとした衣のついた天ぷらをおいしい……と小さく呟いて食べる。
「あなたはこの仕事嫌にならないの?」
「私はこの仕事を始めたばかりなので、エナ様とは比べられないかもしれませんが、皆の喜んでくれる顔をみると、嬉しくて楽しい気持ちになります」
「……ほんとね。わたしもそんなとき、あったわね」
しんみりとしているエナ。
珍しく館内に来たジーニーが現れた。イヤーな顔したリヴィオを引き連れている。戻されたのかな……。
いや!誤解を時にきたのか!?ワクワクと私はしてきた!昼ドラじゃないですか!?いや、深夜の方ですかっ!?
秋野菜と魚の包み焼きを美味しそうに食べていたエナの手が止まる。
「あら!?ジーニーもいたの!?」
「いたの?ではないだろう。学園にも連絡がきていた」
私が想像するような展開は起こらず、会話をする二人。リヴィオは後ろにめんどくそうにいるだけだ。
はぁ…とため息をついて、エナは頰杖をつく。その仕草は絵画のポーズをとったモデルのように美しい。
「学園長らしくなっちゃって!……あら。学園きっての天才の3人が揃ってるのね。卒業したっていうのに、仲良くて羨ましいわ」
さらにトトとテテもいる。同級生が総勢5人も揃うなんて、なかなか無いかも。
「……学園の同級の者たちは絆が強い。幼い頃から一緒にいるからな。エナにもいるだろう?」
幼い頃から全寮制のエスマブル学園で過ごしているからか、確かにそういう面はあるかもしれない。
「わたしにはいないわ。偶像崇拝的な人ばかりよ!ジーニーとリヴィオはわたしに普通に接してくれたわよね」
リヴィオは忘れたとかほざいてるが、ジーニーは頷いている。
「あの……『歌姫』のエナさんですよね?」
家族連れの一組が声をかけてきた。エナはパッと反射的に営業用のキラキラとした笑顔をつくる。思わず皆がその笑顔に見惚れる。
「そうですわ」
「うちの娘がファンなんです!舞台何回も行きました!」
小さい女の子が照れるように母の後ろに隠れている。
「あら……そうなの?ありがとう」
柔らかな表情になるエナ。
「そんなに、エナ様の歌はステキなのですね。私は聴いたことなくて……」
「えっ!?なんですって!?あなた学園にいたわよね!?それなのに聴いたことないですって!?」
私の言葉を遮って驚くエナ。透き通るような青い目が丸くなる。
「信じられないわ!このわたしの歌に興味がなかったと言うの?」
「セイラはそんなやつだ」
リヴィオが腕組をし、なぜか自慢げに私の代わりに答える。
「興味がなかったんだろう」
ジーニーまでもがそういう。フォローなし。
「信じられないわ!わたしの歌を聴いたことが無いとか!許せないわね!」
バッと立ち上がる。ショー用に作った小さい舞台に上がっていく。
「エナはプライド、高いからな」
ボソッとリヴィオがそう言う。他のお客さんの目も舞台に釘付けになる。
「皆様、こんばんは。急ではありますが、わたしの歌を聞いて楽しいひとときを過ごして頂きたいですわ」
すうっと空気を吸い込む。手を前に伸ばす。静まり返る広間。高鳴る期待の眼差しをエナに皆が向けている。
この場の雰囲気を仕草や声……それだけで変えてしまうエナ。
美声が響く。天井に部屋の隅まで……お客さんたちは引き込まれていく。エナの歌の世界へと。
歌は昔から吟遊詩人が歌っている、神と人との恋の歌だった。神が人に恋するが叶わない。寿命がある人とは違う。命を尽きる時、永遠にその子孫を見守り、護り続けると約束する。悲しいけど、ひたむきな恋の歌だ。
涙を流している人もいた。私も胸が熱くなるのを感じる。優しく降り注ぐ声が心に染みていく。
一曲終わったと思ったら、次は子供用の楽しい歌だった。皆が明るい顔になり、自然と体が動き、手拍子が始まった。先程の女の子も喜んで跳ねている。
エナが2曲歌い終えるとニッコリと笑って舞台から降りてくる。拍手が鳴り止まない。
「どう!?どうだったかしら?セイラ=バシュレ!」
「とってもステキでした!今まで聴いたことがなくて損していました」
心からそういう。今まで目を向けていなかったことがたくさんあったのだと最近、感じる。
「エナさん!」
先程の女の子が話しかける。
「なにかしら?」
「あたしも大きくなったら歌う人になりたい!舞台に立ちたい!」
嬉しげにエナは微笑んだ。
「良いわよ。待ってるわ。一緒に歌いましょう」
握手してもらった女の子は幸せな顔をした。エナの表情も晴々としていた。
「セイラ、わがまま言って、リヴィオをひとり占めさせてもらって、ごめんなさいね。何かお詫びしたいわ」
私は良いんですよと笑う。
「いや、迷惑かけられたのオレじゃね?なんでセイラにお詫びなんだ?」
首を傾げるリヴィオにエナは清々しいまでにキッパリと言い放つ。
「『歌姫』に言い寄られて嫌な男はいないでしょう?」
「そうか?ここにいる………っ!」
ジーニーにグイッと首の後ろを引っ張られて後ろへと下げられる。余計なこと言うなと忠告されている。ここで機嫌を損ねられたら困るのはわかる。エナに帰ってもらえなくなる心配をジーニーはしてるのだろう。
「じゃあ、スケジュールが空いていて、ここへ来る時で良いのですが、歌ってください!もう一度、歌を聴きたいです」
「そんなことでいいなら!わたしもまた泊まりに来たいわ。とても気配りしてくれてるのがわかったわ。ありがとう」
来た時とは別人の様にイライラとしたものが消えていた。しかし、ハッとしたような顔をして、つけ加える。
「でもリヴィオは譲らないわよ!負けませんからね!」
「………あ、ハイ?」
わけがわからないが頷いておく。なぜライバル心を燃やされてるんでしょうか?しかしエナは私の返事に満足そうな顔をした。
彼女はまた来るわね!と約束をし、舞台へと戻っていったのだった。
そして小さい事件が起きた。
執務室で私はリヴィオをいつものように、からかうつもりで笑いながら言ったのだ。
「ウフフフ。リヴィオは最近、モテるわねぇ。羨ましいわー!コロンブスにエナの護衛……引く手あまたじゃない!」
リヴィオの表情が一変した。真顔で怒ったような金色の目でこちらを見据えた。褒めたのになんでだろう。
「本気で、言ってるのか?」
「えっ……」
「セイラはオレが必要ないってことか?」
ジリッと間合いを詰めてくる。私は思わず数歩下がった。声が冷たい。
「いや、そういう意味ではなくて……私は『黒猫』が私の護衛するなんてもったいないくらいだと思ってるわ」
リヴィオは答えになっていないなと低い声で呟く。
「オレはジーニーに頼まれたが、誰の護衛でも引き受けるわけじゃねーぞ?」
「わかってるわ」
「絶対わかってねーだろ!」
これは喧嘩ですかね……。
「なんで怒ってるの?」
「別に怒ってねーよ!」
これでは子供の喧嘩である。私はいったいリヴィオが何で怒っているのかわからない。
「ゼキやエナの所へ行っても良いということかよ?」
「それはリヴィオが決めることでしょう。私が決めることはできないわ」
へぇとさらに冷たい声になり、スタスタと私の顔の前まできた。私はさらに下がる。壁に背中がぶつかる。
ちょっと待って!と焦る私。
「えーと、つまり、私はリヴィオが人望あるわねって言いたかったのよ。もちろん私も傍にいてくれて助かってるわ。心強いし、楽しいわよ」
「オレにここに居てほしいってことでいいのか?」
「もちろんよ!居ないとすごく寂しいと思うわ!」
コクコクと頷き、言葉に力を込めて言う。
「寂しいのか……」
私はなぜ怒られたのか?そしてなぜリヴィオを励ましてるような気持ちになるのだろう。なんだ?このシチュエーションは?顔がいつも以上に近くて動けない。
リヴィオは私を壁まで追い詰めて、そのままじっと見つめていたが、しばらくすると口元をニッと笑って緩ませた。
「まあ……今のところはそれでいいってことにするか」
そう呟いて、リヴィオは少し照れたように背中を向けて部屋から出ていったのだった。
なっ!?なんだったのだろう!?取り残された私は壁に寄りかかったまま、動けず固まったままで、しばらく佇んだ。
「セイラ、何してるんだ?」
「ちょっと探しものをね……」
本棚の隙間、クローゼットの中、隠し棚、すべて見た。お祖父様が前世の記憶があるものを残していないか、みつけようとしていた。
『コロンブス』の新大陸発見は有名だから、私のいた国じゃなくても知ってるだろうけど、同じ世界の記憶を持っていたのかどうか知りたかった。
日記とか記録と残っていないかと探したが無い。
お手上げだわ。そう思い、嘆息した。
「何を探してるのか言わねーから、手伝いようがない」
リヴィオが暇そうにソファに寝そべって、猫のようにダラーンと伸びている。
「あ、そうだ。探しものと言えば、昨日、学園の方に探し人を尋ねられてさ。……リヴィオ知らないか?」
「は?オレ??」
そうだと頷くジーニー。リヴィオは聞く前から知らねーと言ってめんどくさげに寝そべったままである。
「セイラも覚えてないか?3学年上の先輩でいただろう?『歌姫』を知らないか?」
「あ、ごめん、私は他のクラスの顔と名前覚えてないの」
「おい、アッサリ否定するな。かなりの有名人だと思うんだが?なぁ?リヴィオ?」
リヴィオが寝そべっていたのをやめている。起き上がって、ジーニーを金色の目で見ている。あれ?私以外は知ってるのかしら。
「記憶力良いのに、そういうところに使わないのか?」
「今は使ってるわよ。お客様の好きなもの嫌いなもの、話した内容、出身地とか覚えてるわ。ちゃんとお客様台帳にも書いてあるけど、記憶にも残してるわよ」
学園の時は周囲に興味を持てなかった。かろうじてクラスで関わるメンバーのみ記憶にある。ましてや3学年も上なら覚えてるわけがない。
「通称『歌姫』、学園祭や学園に要人をもてなす時に舞台に立って歌っていただろう?まあ、セイラ……らしいか」
リヴィオは先程から黙ったままである。
「リヴィオの元カノだ」
「へええええ!」
私が驚きの声をあげるとリヴィオが反論する。
「ちーがーう!違うと何回言えばわかるんだ!学園の時から言ってるだろうが!」
リヴィオの必死さに私は応援したくなり、助け舟を出した。
「ジーニー……たぶんリヴィオはあなたにだけには誤解されたくないのよ。ジーニー!リヴィオ!私は応援するわよ」
「いや、待て?セイラは何か誤解してないか?」
ジーニーが私を制止する。
「セイラは何言ってんだ?で、あいつ、どこへ行ったんだ?」
リヴィオが尋ねる。ジーニーがさあ??と首を傾げる。
「学園の方にいないかと聞かれたからいないと言った。それだけだ」
私は話半分になってしまったが、時間に気づいて、本日のお客様を迎えに慌てて旅館へ行ったのだった。
昔は人の顔と名前覚えるのが苦手だったことを思い出す。
周囲に興味を持てなかった。淡々と日々が過ぎていくのを感じていた。好きな本を読み、その世界にだけいる自分。
現実は辛いことの方が多かったから目を向けると傷つくだけだった。関わらないようにし、静かな存在でいるように努め、自分を守っていた。
他の生徒たちは家から送られてくる手紙やプレゼントがあるなか、私はなかった。
家に帰ることを許されない時は一人で寮にいて過ごしたこともあった。シンと静まった廊下、一人で食べる食事は気楽な反面、孤独を余計に意識させた。
時折、祖父が休みを一緒に過ごそうと呼んでくれた時は本当に嬉しかったものだ。だから休暇を過ごしていたナシュレ領は私にとって特別な場所だった。
「おい?セイラ大丈夫か?顔色あんまり良くないぞ」
過去に戻り、ぼんやりと一瞬していた私にリヴィオが声をかける。思わず現実に引き戻されて、ハッとした。
「大丈夫よ。ちょっとぼんやりしただけよ。さ!お客様をお迎えしましょう」
ガラガラと馬車が着いた。中から降り立ったのはまるで妖精さんのように美しい人だった。波打つ金色の長い髪、透き通るような白い肌、青い目をした彼女は優雅に微笑んだ。
「いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました」
私はお辞儀した。
「なんでここに!?エナ!」
「リヴィオ!!」
嬉しい笑顔で駆けてきて、リヴィオに抱きつくエナ。
「待て!やめろ!」
リヴィオが引き剥がそうとしている。私は反応に困りつつ、御者から荷物を受け取る。
愛らしい笑みは見ている誰もが惹きつけられる。スタッフ達もざわめくほどだ。まるで絵本から出てきた妖精さんだ。
「なによ……冷たいわね。久しぶりに会ったのに」
猫なら逆毛をたててるであろうリヴィオの反応。抱きつかれることを警戒している。
「行方不明じゃなかったのかよ!なに呑気に温泉に来てんだ!?」
困ったように頬に手をやる姿もまるで女優のように様になるエナ。
「学園を卒業してから、まともに休みなんてなかったのよ。スケジュール管理をされて、毎日舞台ばかり。楽しかったけど……最近は疲れてきて、楽しく感じられなくて。そんなとき、あなたを新聞で見て、いつか会いに行こうと思ったのよ」
熱烈な愛の告白にも聞こえる!!私とスタッフは興味津々で聞いている。
リヴィオは額に手を当てている。
「わたしのお世話係はリヴィオがいいわ!いいでしょう?」
「えーと……そうですね。じゃあ、リヴィオと客室係と2名でもいいですか?」
リヴィオ一人では無理だろう。リヴィオが私にオレを売るなよ!と言うが……はるばる会いに来てくれたのに邪険にしすぎだろう。
「まあ、いいじゃない。せっかく会いに来てくれたのに」
「おまえ、なんっとも思わないのかよ!?」
「何が??」
私が首を傾げるとリヴィオは拗ねたようにもういいっ!と怒ってエナの荷物を持って歩いて行く。なにを怒っているのだろうか??
その後、チラッと見に行ったが、なかなかリヴィオは様になっていた。大丈夫そうだ。
ただ、時折、エナの無茶ぶりがあるらしいことをペアの客室係から聞いた。
「お茶をお持ちしたら、リヴィオ様もそこへ座って話し相手になりなさいとか、売店にも付き添いなさいとか、お風呂の後には一緒に散歩したいとか言うのですよ!女将、いちスタッフへの接客には度が過ぎてます!」
一緒にいたい、けなげな乙女心なんじゃないかなぁ?
「まぁ、リヴィオのことだし、飽きたら抜けてくるわよ」
私はそう言って、大広間の夕食準備に指示をだす。お客様の中に魚が苦手な人がいると聞いたのでお肉への変更をしてほしいと知らせる。
広間の時計を見る。そろそろ皆が食事に入ってくる。
「お食事の席はこちらでございます」
私は案内しながら、今日の料理やお酒の種類を紹介していく。
「本日のデザートはリンゴシャーベットなんですよ。地元のリンゴなのです。リンゴはちょうど甘みが出てくる季節なんですよ。お嬢様は冷たいデザートは好きですか?」
家族連れの方に話しかける。子供が無邪気にアイスクリーム好きー!と答えてくれる。
「地元のお酒、用意してありますので、どうぞ試してみてくださいね。女性の方でも口当たりがよくて甘みがあり、飲みやすいと評判なんですよー!」
対応していると他のお客さんがざわつきだし、視線が入口付近へ集まる。
リヴィオと腕を組んで入ってくるエナ。お風呂上がりのやや赤みが差した白い頬に金色の髪をまとめて少したらした髪型は女性としてかなり魅力的だ。横に並ぶのは漆黒の髪と金色の目をした黙っていればイケメンのリヴィオ。
まるで姫と王子のようで絵になる。
「おい……」
私に話しかける、黙っていればイケメンのリヴィオさん。私は目だけで頷く。
みんなの目の保養の為に喋るなと合図したつもりだ。
「そろそろ変われ!限界だ。オレは接客無理だっ!」
イケメンタイムは終わった。
私は肩をすくめて、ニッコリと笑顔でエナに向く。
「お食事をどうぞ」
「えーっ。リヴィオも一緒に食べましょうよ!」
猫は束縛を嫌う。まさに『黒猫』リヴィオは逃げるように去っていった。
渋々と座席に座るエナ。フウッとため息をつく。つまらなーいと呟いて、苛立ちながら私に言う。
「お料理さっさと出していって!」
「かしこまりました」
私はスタッフの一人に頼み、調理場に急いでもらえるように耳打ちした。お品書きを見てもらい、説明で時間を稼ぐようにする。
「前菜の……」
「そんな話いいわ!それよりも!あなた、セイラ=バシュレでしょ。久しぶりね。リヴィオの学年の首席だったでしょ?」
「私のこともご存知でしたかー」
私のことはお気になさらずと言いたいが、なんだか、リヴィオがいなくなったら、私に絡んできた。さっきまで知らない顔していたのに……。
「知ってるわよ。おとなしいけど、常にトップに君臨してたでしょ」
そうでしたかねー?と言いつつ、お酒をお酌した。
「リヴィオとわたしの関係、気にならないの?」
「えーと……元カノと聞きましたけど、そうなんですか?」
答えず、ニヤッと笑われた。
前菜のキノコのマリネを置く。お酒を飲みつつ、エナは語りだした。
「学園の時に、付きまとってきた男がいて、そのしつこいやつを蹴散らしてくれて……リヴィオとジーニー!かっこよかったのよー!相手はずっとストーカーまがいのことをしてきてて、怖かったのよ。その後、退学になっていなくなったわ。学園時代が懐かしいわね。あの頃は楽しかったわ」
遠くを見る目をする。『歌姫』という立場、仕事に疲れているのかもしれない。
ウンウンと頷いて私は話を聞くが、一瞬、その男、バシュレ家で会った鞭男じゃないかな?と頭をよぎる。
「『歌姫』として卒業してからも、頑張っていたけど、毎日余裕なくて、だんだん歌も心を込めて歌えなくて薄っぺらくなってきたのを感じてきて、嫌気がさして、つい休暇とったわ」
行方不明と聞いているけど、本人は休暇のつもりらしい。じゃあ、戻るのねと私は思い、微笑む。
「歌が嫌になったわけではないのですね。少しお疲れなのかもしれませんね」
「そうね……」
サクサクとした衣のついた天ぷらをおいしい……と小さく呟いて食べる。
「あなたはこの仕事嫌にならないの?」
「私はこの仕事を始めたばかりなので、エナ様とは比べられないかもしれませんが、皆の喜んでくれる顔をみると、嬉しくて楽しい気持ちになります」
「……ほんとね。わたしもそんなとき、あったわね」
しんみりとしているエナ。
珍しく館内に来たジーニーが現れた。イヤーな顔したリヴィオを引き連れている。戻されたのかな……。
いや!誤解を時にきたのか!?ワクワクと私はしてきた!昼ドラじゃないですか!?いや、深夜の方ですかっ!?
秋野菜と魚の包み焼きを美味しそうに食べていたエナの手が止まる。
「あら!?ジーニーもいたの!?」
「いたの?ではないだろう。学園にも連絡がきていた」
私が想像するような展開は起こらず、会話をする二人。リヴィオは後ろにめんどくそうにいるだけだ。
はぁ…とため息をついて、エナは頰杖をつく。その仕草は絵画のポーズをとったモデルのように美しい。
「学園長らしくなっちゃって!……あら。学園きっての天才の3人が揃ってるのね。卒業したっていうのに、仲良くて羨ましいわ」
さらにトトとテテもいる。同級生が総勢5人も揃うなんて、なかなか無いかも。
「……学園の同級の者たちは絆が強い。幼い頃から一緒にいるからな。エナにもいるだろう?」
幼い頃から全寮制のエスマブル学園で過ごしているからか、確かにそういう面はあるかもしれない。
「わたしにはいないわ。偶像崇拝的な人ばかりよ!ジーニーとリヴィオはわたしに普通に接してくれたわよね」
リヴィオは忘れたとかほざいてるが、ジーニーは頷いている。
「あの……『歌姫』のエナさんですよね?」
家族連れの一組が声をかけてきた。エナはパッと反射的に営業用のキラキラとした笑顔をつくる。思わず皆がその笑顔に見惚れる。
「そうですわ」
「うちの娘がファンなんです!舞台何回も行きました!」
小さい女の子が照れるように母の後ろに隠れている。
「あら……そうなの?ありがとう」
柔らかな表情になるエナ。
「そんなに、エナ様の歌はステキなのですね。私は聴いたことなくて……」
「えっ!?なんですって!?あなた学園にいたわよね!?それなのに聴いたことないですって!?」
私の言葉を遮って驚くエナ。透き通るような青い目が丸くなる。
「信じられないわ!このわたしの歌に興味がなかったと言うの?」
「セイラはそんなやつだ」
リヴィオが腕組をし、なぜか自慢げに私の代わりに答える。
「興味がなかったんだろう」
ジーニーまでもがそういう。フォローなし。
「信じられないわ!わたしの歌を聴いたことが無いとか!許せないわね!」
バッと立ち上がる。ショー用に作った小さい舞台に上がっていく。
「エナはプライド、高いからな」
ボソッとリヴィオがそう言う。他のお客さんの目も舞台に釘付けになる。
「皆様、こんばんは。急ではありますが、わたしの歌を聞いて楽しいひとときを過ごして頂きたいですわ」
すうっと空気を吸い込む。手を前に伸ばす。静まり返る広間。高鳴る期待の眼差しをエナに皆が向けている。
この場の雰囲気を仕草や声……それだけで変えてしまうエナ。
美声が響く。天井に部屋の隅まで……お客さんたちは引き込まれていく。エナの歌の世界へと。
歌は昔から吟遊詩人が歌っている、神と人との恋の歌だった。神が人に恋するが叶わない。寿命がある人とは違う。命を尽きる時、永遠にその子孫を見守り、護り続けると約束する。悲しいけど、ひたむきな恋の歌だ。
涙を流している人もいた。私も胸が熱くなるのを感じる。優しく降り注ぐ声が心に染みていく。
一曲終わったと思ったら、次は子供用の楽しい歌だった。皆が明るい顔になり、自然と体が動き、手拍子が始まった。先程の女の子も喜んで跳ねている。
エナが2曲歌い終えるとニッコリと笑って舞台から降りてくる。拍手が鳴り止まない。
「どう!?どうだったかしら?セイラ=バシュレ!」
「とってもステキでした!今まで聴いたことがなくて損していました」
心からそういう。今まで目を向けていなかったことがたくさんあったのだと最近、感じる。
「エナさん!」
先程の女の子が話しかける。
「なにかしら?」
「あたしも大きくなったら歌う人になりたい!舞台に立ちたい!」
嬉しげにエナは微笑んだ。
「良いわよ。待ってるわ。一緒に歌いましょう」
握手してもらった女の子は幸せな顔をした。エナの表情も晴々としていた。
「セイラ、わがまま言って、リヴィオをひとり占めさせてもらって、ごめんなさいね。何かお詫びしたいわ」
私は良いんですよと笑う。
「いや、迷惑かけられたのオレじゃね?なんでセイラにお詫びなんだ?」
首を傾げるリヴィオにエナは清々しいまでにキッパリと言い放つ。
「『歌姫』に言い寄られて嫌な男はいないでしょう?」
「そうか?ここにいる………っ!」
ジーニーにグイッと首の後ろを引っ張られて後ろへと下げられる。余計なこと言うなと忠告されている。ここで機嫌を損ねられたら困るのはわかる。エナに帰ってもらえなくなる心配をジーニーはしてるのだろう。
「じゃあ、スケジュールが空いていて、ここへ来る時で良いのですが、歌ってください!もう一度、歌を聴きたいです」
「そんなことでいいなら!わたしもまた泊まりに来たいわ。とても気配りしてくれてるのがわかったわ。ありがとう」
来た時とは別人の様にイライラとしたものが消えていた。しかし、ハッとしたような顔をして、つけ加える。
「でもリヴィオは譲らないわよ!負けませんからね!」
「………あ、ハイ?」
わけがわからないが頷いておく。なぜライバル心を燃やされてるんでしょうか?しかしエナは私の返事に満足そうな顔をした。
彼女はまた来るわね!と約束をし、舞台へと戻っていったのだった。
そして小さい事件が起きた。
執務室で私はリヴィオをいつものように、からかうつもりで笑いながら言ったのだ。
「ウフフフ。リヴィオは最近、モテるわねぇ。羨ましいわー!コロンブスにエナの護衛……引く手あまたじゃない!」
リヴィオの表情が一変した。真顔で怒ったような金色の目でこちらを見据えた。褒めたのになんでだろう。
「本気で、言ってるのか?」
「えっ……」
「セイラはオレが必要ないってことか?」
ジリッと間合いを詰めてくる。私は思わず数歩下がった。声が冷たい。
「いや、そういう意味ではなくて……私は『黒猫』が私の護衛するなんてもったいないくらいだと思ってるわ」
リヴィオは答えになっていないなと低い声で呟く。
「オレはジーニーに頼まれたが、誰の護衛でも引き受けるわけじゃねーぞ?」
「わかってるわ」
「絶対わかってねーだろ!」
これは喧嘩ですかね……。
「なんで怒ってるの?」
「別に怒ってねーよ!」
これでは子供の喧嘩である。私はいったいリヴィオが何で怒っているのかわからない。
「ゼキやエナの所へ行っても良いということかよ?」
「それはリヴィオが決めることでしょう。私が決めることはできないわ」
へぇとさらに冷たい声になり、スタスタと私の顔の前まできた。私はさらに下がる。壁に背中がぶつかる。
ちょっと待って!と焦る私。
「えーと、つまり、私はリヴィオが人望あるわねって言いたかったのよ。もちろん私も傍にいてくれて助かってるわ。心強いし、楽しいわよ」
「オレにここに居てほしいってことでいいのか?」
「もちろんよ!居ないとすごく寂しいと思うわ!」
コクコクと頷き、言葉に力を込めて言う。
「寂しいのか……」
私はなぜ怒られたのか?そしてなぜリヴィオを励ましてるような気持ちになるのだろう。なんだ?このシチュエーションは?顔がいつも以上に近くて動けない。
リヴィオは私を壁まで追い詰めて、そのままじっと見つめていたが、しばらくすると口元をニッと笑って緩ませた。
「まあ……今のところはそれでいいってことにするか」
そう呟いて、リヴィオは少し照れたように背中を向けて部屋から出ていったのだった。
なっ!?なんだったのだろう!?取り残された私は壁に寄りかかったまま、動けず固まったままで、しばらく佇んだ。