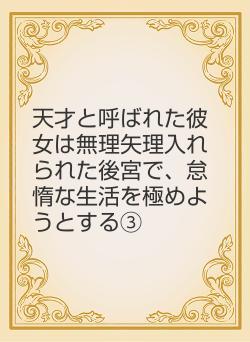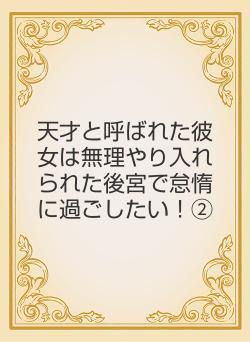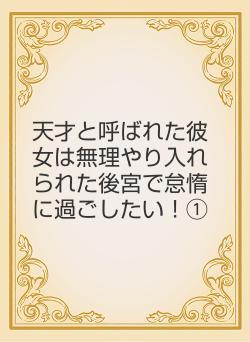ピーヒョロロー、テンテケテン。ピーヒョロロー、テンテケテンと笛の音と太鼓の音楽が流れる。
「何だ?その奇怪な音楽は?」
リヴィオが不気味そうに尋ねてくる。
トトとテテは聞いたことない曲調たけど、けっこうハマるのだーと言ってくれたのに…。
「祭の曲よ!雰囲気良いでしょ?」
庭師のトーマスは気に入ってくれたようで、踊りたくなります!とソレソレッとリズムをとっている。
ワルツの優雅なダンスに馴染みのあるリヴィオはどうもイメージが湧かないらしい。
トトとテテがキャーキャー騒いでいる。射的コーナーで景品を狙い撃ちしているのだ。くまのぬいぐるみにペコンッと当たり、ガッツポーズをする二人。
「これは面白いな」
ジーニーがハマっているのは水ヨーヨーだ。紙こよりの先についた針で釣れたと思ったら水に浸しすぎてプツッと切れた。彼は悔しげに唇を噛んだ。
しかし次は狙いを定め、サッ!と素早く釣った。赤いヨーヨーか釣れ、いつもの真面目な顔が崩れて、子供じみた嬉しそうな顔になる。
「なるほど。そういうことか!もう騙されないぞ!」
そう言いながら2個目の水ヨーヨーに挑戦しだした。
メイドさんたちが列を作っているのはカラフル綿菓子コーナー。ザラメを入れ、木の棒にくるくると巻いていく。
屋敷のコック達までもが綿菓子メーカーに集まり、巻くことに興味津々である。順番だぞ!としてみたい人が続出。
「この丸さを出すのが難しいんだ」
「棒にいかに綺麗に巻けるか!?コツがわかってきたぞ」
綿菓子作るのも面白いよね。わかるよ!と思わず同調する。
子供の頃、ニホンの縁日で見て、玩具の綿菓子メーカーを買って!買ってー!とねだった幼い頃の私を思い出す。
「きゃー!かわいいー!」
「次はわたしも欲しいわ!」
ふわふわのピンクの綿菓子ができると次々と黄色、白、緑など作ってみている。
カラフルな綿菓子を透明容器に入れて「かわいー!」と色を楽しむメイドさん達。
女子の心を掴むのはどちらの世界も共通する部分があるかもしれない。
他にも小さい玩具が景品のくじ引き屋さん、輪投げ、りんご飴など置いた。
旅館の広いホールの一室を夏祭りの縁日イベント一色にした。私にとっては懐かしくもある雰囲気であった。
予想以上に皆が楽しめるようで良かった。
劇団、歌謡ショー、手品など考えたが、これらをするには、まずスカウトからだし、探す時間も必要だし、たとえオッケーが出ても出演のスケジュール調整がいる。
「この夏祭りイベントをお客様に楽しんでもらえるかどうかやってみましょう!」
ハーイ!と夏祭りに夢中な人達は返事を一応返してくれたのだった。
そろそろオープンが近い。アドバイスを受けて売店、夏祭りイベント、メニューの見直しなどを取り入れてみた。
よくここまで来た!と自分を褒めたいところだけど、何よりナシュレの人達の協力、屋敷の面々、学園時代の友人達のおかげだ。もう感謝しかない。
前世では旅館の手伝いすらめんどくさいと思っていたのに本気になっている自分に可笑しくなる。
そして女将の母が背負っていた責任の重さが少しわかった気がした。
感無量で思いにふけっていると、執事のクロウがやや言いにくそうに手紙を持ってきた。
「ん??夜に見るから執務室に置いといて」
いつもなら執務室に置いておくのだが、なぜわざわざ……。
「いえ、お嬢様、これはすぐお渡ししたほうがよろしいかと思い、持って参りました」
嫌な予感がした。私は盆の上に置かれた手紙を受け取り、差出人を見た。
「うっ!!」
思わず呻いてしまった。バシュレ家の紋章で封印してある。差出人は義母でサンドラとサインしてある。
「いやー!見たくないーっ!棄てたいー!!」
「オレが消し炭にしてやろうか?」
いつの間にかリヴィオが居て、手のひらに小さい炎を生み出す。
え!?ちょっと迷わせて!と焦る。
「えーと、大事な用かもしれない。一応、開封してみるわ」
ろくなもんじゃねーだろ!とリヴィオ。そうはいうけど気になるものである。私は読み上げる。
『あなたの父君が病にかかり、寝込んでいます。お見舞いに来たかったらいらっしゃい』
その一言のみ。
……罠?という考えが頭の中をよぎる。
「罠だろう」
いつの間にかジーニーも来て、サラッと私の思考を読んだかのように言う。
「病気ということを、疑ってはいけないかもしれないけど、私もそう思うんだよね」
「じゃ、行かなきゃいいだろ。嫌な予感しかしねー」
答えは一択だろ。とリヴィオは迷いなくそう言うが……。
「でも本当に病気だったら……」
邪険に扱われていた私だが、やはりこの世界で父は血の繋がった唯一の家族なのだ。心配でもある。
「オレがなんかあったらセイラを守ってやるよ。迷ってんなら行こうぜ」
「……!?」
私は手紙からハッと顔をあげてリヴィオを見た。
何!?そのカッコイイ台詞は!?一瞬、誰が言ったのかわからなかったわよ。
「なんだ?驚いた顔して??」
イケメンであることは間違いないし、こんな真顔で守ってやるよとか言われると一瞬ドキッとした。
ハハッとジーニーは私の驚きを察したらしく、時々、リヴィオは天然だよなと可笑しそうに笑う。
なに笑ってるんだよとジーニーを睨むリヴィオ。
「行くのめんどくせーなー。今日か?明日か?」
……心底めんどくさそうだ。
「伺いますって連絡球で知らせておくわ」
おーと気乗りのしない返事を彼はして……タオル片手に旅館の中へ消えて行く。
リヴィオがサウナにハマってるらしいと聞いたけど、事実なのねと背中を見送る。
「あいつに護衛してもらえば間違いないだろう。気をつけて行ってこい」
「ありがとう」
ジーニーはお礼を言う私を見て優しく笑い、学園へ帰っていった。
次の日の朝、馬車に乗り込む。
転移魔法でも良いのだが、なるべく魔力は残しておきたい。罠かもしれない可能性は捨てきれない。
ドレスではなく、黒の制服に近いスタイルの服を選ぶ。男らしいズボン姿を見て、リヴィオは戦いにでも行くのか?と言ったが、あながち間違いではないかもしれない。髪の毛もしっかりと一つに纏めておく。
「連絡球で父の容態を尋ねたけど、義母が詳しくは教えてくれないのよね」
「怪しいな」
めちゃくちゃ怪しいわと私も同意する。嫌な予感が拭いきれない。
「まぁ、父が病気だというのが嘘なら良いのだけど……領地経営をサンドラとソフィアにできるとは思えないのよね」
「そこか……」
苦々しく私は笑う。派手で贅沢が大好きな二人はバシュレ家の財産を食いつぶしている。
父がなぜ注意をしないのかわからないが、父の目が届かなくなれば、さらにお金を湯水の如く使うだろう。
「祖父の財産はそんなにたくさんではないわ。一番大きい利益をあげていた海運業の権利やその会社を国へ渡したのよ」
ウィンディア王国の物となった海運業は王家に莫大な利益をもたらしていると聞く。
「その話はオレも聞いたことあるな」
魔物がある海域まで行くと出現するため、なかなか海路を使っての他国との往来が難しい。
その中で海運を立ち上げた祖父。それこそが伝説と言われる所以である。
しかし父はその海運業を維持できないと判断されたのか、祖父は権利を王家に献上したらしい。
「でもね……海運業がなくとも、この王家から頂いた領地だけで、本来は食べて行けると思うのよね」
王家はバシュレ家へ最大限の感謝を込めて、王都に近い豊かな土地と貴族の称号をくれたのだ。
馬車の外を眺めながら嘆息する。バシュレ家の領地である景色が見える。
「セイラがバシュレ家を継げばじーさんも海運を渡していたんじゃねーの?」
「うーん、どうかしら?私に経営の才能があるかわからないわ」
父と祖父の確執はいつから始まったのだろうか?祖父に似ている私のことを愛せない父に私は気づいていた。幼い頃に抱きしめてもらった記憶一つない。
そんな私が見舞いに来て喜ぶだろうか?しかしサンドラが手紙を書いたということは会いたがっているのかもしれない。
ニホンのドラマというものを見ていた影響で、病床の父がドラマチックに「今まで悪かった」という台詞を言って、手を握る光景が、頭の中に流れる。それは出来すぎかな。
馬車はそんな複雑な思いを乗せつつ、バシュレ家へ運んでくれ、到着したのだった。
「何だ?その奇怪な音楽は?」
リヴィオが不気味そうに尋ねてくる。
トトとテテは聞いたことない曲調たけど、けっこうハマるのだーと言ってくれたのに…。
「祭の曲よ!雰囲気良いでしょ?」
庭師のトーマスは気に入ってくれたようで、踊りたくなります!とソレソレッとリズムをとっている。
ワルツの優雅なダンスに馴染みのあるリヴィオはどうもイメージが湧かないらしい。
トトとテテがキャーキャー騒いでいる。射的コーナーで景品を狙い撃ちしているのだ。くまのぬいぐるみにペコンッと当たり、ガッツポーズをする二人。
「これは面白いな」
ジーニーがハマっているのは水ヨーヨーだ。紙こよりの先についた針で釣れたと思ったら水に浸しすぎてプツッと切れた。彼は悔しげに唇を噛んだ。
しかし次は狙いを定め、サッ!と素早く釣った。赤いヨーヨーか釣れ、いつもの真面目な顔が崩れて、子供じみた嬉しそうな顔になる。
「なるほど。そういうことか!もう騙されないぞ!」
そう言いながら2個目の水ヨーヨーに挑戦しだした。
メイドさんたちが列を作っているのはカラフル綿菓子コーナー。ザラメを入れ、木の棒にくるくると巻いていく。
屋敷のコック達までもが綿菓子メーカーに集まり、巻くことに興味津々である。順番だぞ!としてみたい人が続出。
「この丸さを出すのが難しいんだ」
「棒にいかに綺麗に巻けるか!?コツがわかってきたぞ」
綿菓子作るのも面白いよね。わかるよ!と思わず同調する。
子供の頃、ニホンの縁日で見て、玩具の綿菓子メーカーを買って!買ってー!とねだった幼い頃の私を思い出す。
「きゃー!かわいいー!」
「次はわたしも欲しいわ!」
ふわふわのピンクの綿菓子ができると次々と黄色、白、緑など作ってみている。
カラフルな綿菓子を透明容器に入れて「かわいー!」と色を楽しむメイドさん達。
女子の心を掴むのはどちらの世界も共通する部分があるかもしれない。
他にも小さい玩具が景品のくじ引き屋さん、輪投げ、りんご飴など置いた。
旅館の広いホールの一室を夏祭りの縁日イベント一色にした。私にとっては懐かしくもある雰囲気であった。
予想以上に皆が楽しめるようで良かった。
劇団、歌謡ショー、手品など考えたが、これらをするには、まずスカウトからだし、探す時間も必要だし、たとえオッケーが出ても出演のスケジュール調整がいる。
「この夏祭りイベントをお客様に楽しんでもらえるかどうかやってみましょう!」
ハーイ!と夏祭りに夢中な人達は返事を一応返してくれたのだった。
そろそろオープンが近い。アドバイスを受けて売店、夏祭りイベント、メニューの見直しなどを取り入れてみた。
よくここまで来た!と自分を褒めたいところだけど、何よりナシュレの人達の協力、屋敷の面々、学園時代の友人達のおかげだ。もう感謝しかない。
前世では旅館の手伝いすらめんどくさいと思っていたのに本気になっている自分に可笑しくなる。
そして女将の母が背負っていた責任の重さが少しわかった気がした。
感無量で思いにふけっていると、執事のクロウがやや言いにくそうに手紙を持ってきた。
「ん??夜に見るから執務室に置いといて」
いつもなら執務室に置いておくのだが、なぜわざわざ……。
「いえ、お嬢様、これはすぐお渡ししたほうがよろしいかと思い、持って参りました」
嫌な予感がした。私は盆の上に置かれた手紙を受け取り、差出人を見た。
「うっ!!」
思わず呻いてしまった。バシュレ家の紋章で封印してある。差出人は義母でサンドラとサインしてある。
「いやー!見たくないーっ!棄てたいー!!」
「オレが消し炭にしてやろうか?」
いつの間にかリヴィオが居て、手のひらに小さい炎を生み出す。
え!?ちょっと迷わせて!と焦る。
「えーと、大事な用かもしれない。一応、開封してみるわ」
ろくなもんじゃねーだろ!とリヴィオ。そうはいうけど気になるものである。私は読み上げる。
『あなたの父君が病にかかり、寝込んでいます。お見舞いに来たかったらいらっしゃい』
その一言のみ。
……罠?という考えが頭の中をよぎる。
「罠だろう」
いつの間にかジーニーも来て、サラッと私の思考を読んだかのように言う。
「病気ということを、疑ってはいけないかもしれないけど、私もそう思うんだよね」
「じゃ、行かなきゃいいだろ。嫌な予感しかしねー」
答えは一択だろ。とリヴィオは迷いなくそう言うが……。
「でも本当に病気だったら……」
邪険に扱われていた私だが、やはりこの世界で父は血の繋がった唯一の家族なのだ。心配でもある。
「オレがなんかあったらセイラを守ってやるよ。迷ってんなら行こうぜ」
「……!?」
私は手紙からハッと顔をあげてリヴィオを見た。
何!?そのカッコイイ台詞は!?一瞬、誰が言ったのかわからなかったわよ。
「なんだ?驚いた顔して??」
イケメンであることは間違いないし、こんな真顔で守ってやるよとか言われると一瞬ドキッとした。
ハハッとジーニーは私の驚きを察したらしく、時々、リヴィオは天然だよなと可笑しそうに笑う。
なに笑ってるんだよとジーニーを睨むリヴィオ。
「行くのめんどくせーなー。今日か?明日か?」
……心底めんどくさそうだ。
「伺いますって連絡球で知らせておくわ」
おーと気乗りのしない返事を彼はして……タオル片手に旅館の中へ消えて行く。
リヴィオがサウナにハマってるらしいと聞いたけど、事実なのねと背中を見送る。
「あいつに護衛してもらえば間違いないだろう。気をつけて行ってこい」
「ありがとう」
ジーニーはお礼を言う私を見て優しく笑い、学園へ帰っていった。
次の日の朝、馬車に乗り込む。
転移魔法でも良いのだが、なるべく魔力は残しておきたい。罠かもしれない可能性は捨てきれない。
ドレスではなく、黒の制服に近いスタイルの服を選ぶ。男らしいズボン姿を見て、リヴィオは戦いにでも行くのか?と言ったが、あながち間違いではないかもしれない。髪の毛もしっかりと一つに纏めておく。
「連絡球で父の容態を尋ねたけど、義母が詳しくは教えてくれないのよね」
「怪しいな」
めちゃくちゃ怪しいわと私も同意する。嫌な予感が拭いきれない。
「まぁ、父が病気だというのが嘘なら良いのだけど……領地経営をサンドラとソフィアにできるとは思えないのよね」
「そこか……」
苦々しく私は笑う。派手で贅沢が大好きな二人はバシュレ家の財産を食いつぶしている。
父がなぜ注意をしないのかわからないが、父の目が届かなくなれば、さらにお金を湯水の如く使うだろう。
「祖父の財産はそんなにたくさんではないわ。一番大きい利益をあげていた海運業の権利やその会社を国へ渡したのよ」
ウィンディア王国の物となった海運業は王家に莫大な利益をもたらしていると聞く。
「その話はオレも聞いたことあるな」
魔物がある海域まで行くと出現するため、なかなか海路を使っての他国との往来が難しい。
その中で海運を立ち上げた祖父。それこそが伝説と言われる所以である。
しかし父はその海運業を維持できないと判断されたのか、祖父は権利を王家に献上したらしい。
「でもね……海運業がなくとも、この王家から頂いた領地だけで、本来は食べて行けると思うのよね」
王家はバシュレ家へ最大限の感謝を込めて、王都に近い豊かな土地と貴族の称号をくれたのだ。
馬車の外を眺めながら嘆息する。バシュレ家の領地である景色が見える。
「セイラがバシュレ家を継げばじーさんも海運を渡していたんじゃねーの?」
「うーん、どうかしら?私に経営の才能があるかわからないわ」
父と祖父の確執はいつから始まったのだろうか?祖父に似ている私のことを愛せない父に私は気づいていた。幼い頃に抱きしめてもらった記憶一つない。
そんな私が見舞いに来て喜ぶだろうか?しかしサンドラが手紙を書いたということは会いたがっているのかもしれない。
ニホンのドラマというものを見ていた影響で、病床の父がドラマチックに「今まで悪かった」という台詞を言って、手を握る光景が、頭の中に流れる。それは出来すぎかな。
馬車はそんな複雑な思いを乗せつつ、バシュレ家へ運んでくれ、到着したのだった。