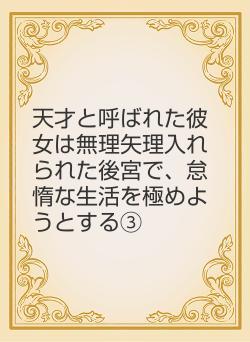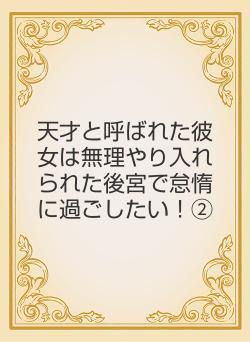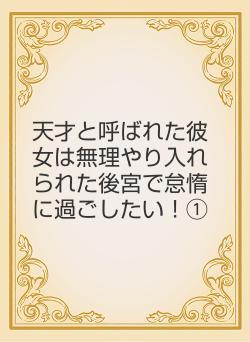私はキッチリとした臙脂色の服を着て、旅館のスタッフは深緑の服を着て、ズラリと並ぶ。晴れたこんな日に相応しくない緊張感はお客様にも伝わってしまうだろう。
そういう私も実はすごくドキドキして、昨日はなかなか寝れなかったのだ。しかしここでは女将!女将として頑張らないと!自分を奮い立たせる。
深呼吸する。そして皆に笑顔を向けた。
「よくここまで頑張り、研修を受け、私についてきてくれたわ。みんななら大丈夫!身分などは関係なく、我が家にお客様が来たと思って接してくれれば絶対うまくいくわ。問題が起きたら一人で解決しないこと。みんなで解決するからね!」
大丈夫!と安心させる。硬かった表情がややほぐれる。
リヴィオが目を細めて言う。
「学園にいた頃とずいぶん変わったよな。いい意味で」
どうだろうか?前世のジョシコーセーの自分は確かに明るい。母と対立することもあったようだが、負けん気があり、根性もあった。今のセイラという自分は学園で物静かに本を読んでいるというイメージなのかもしれないが、ずっと耐えて……我慢強い心の持ち主だと前世の自分なら言うかもしれない。
たぶん互いに補い合っての今の私なのだろう。
フッと可笑しくて笑う。リヴィオは笑わずに金色の目で私の目を見た。そのうち彼なら前世の記憶とやらを話しても良いかもしれない。私に違和感を感じているのだろう。
やがてガラガラと車輪の音がして馬車が2台着いた。カムパネルラ公爵家の家紋が描かれている。ドアが開いた。
一台目からはオリビアと小さい少女が。2台目からはリヴィオにやや似ているがタレ目で黒髪の青年。
いらっしゃいませー!と声をかけるスタッフ達と私。
「末の妹のマリアと2番目の兄のレオンだ」
リヴィオが紹介してくれる。可愛らしいオリビアに似ている金髪碧眼のマリアはドレスの裾を持ち、ちょこんと挨拶した。スタッフからもかーわいーっ!と言う声が思わずヒソヒソと小声で漏れる。
「お招きありがとう。本当はハリーも来たがっていたんだけど、仕事で来れなくて…残念だわ」
「そうなんですね。皆様、忙しいなか、お越しくださって嬉しいですわ。馬車に揺られて、お疲れでしょう?どうぞこちらへ。荷物はお預かりしてお部屋まで届けますわ」
ササッと荷物係が馬車の御者から荷物を受け取る。私は庭園を抜けて玄関へ案内する。
「へぇ!見事なものですね」
レオンと呼ばれたリヴィオの兄が庭園を褒める。興味ゼロで通りすぎてった弟さんとは一味違う予感。
「この庭、四季を楽しめるように植物が植えられているんですね。あの流れる川や石はまるで小さい自然の世界を表しているような庭ですね」
「お気に召して頂いて嬉しいですわ。今の季節は夏を彩る蓮の花が見頃ですわ」
池の方でポンッと咲く、ピンク色の花を示すと綺麗ですねーと微笑む。
褒められて私も嬉しくて笑う。庭師たちのおかげである。風情をよくわかっていてすごい人だ。
「兄さまーっ!はやーく!」
マリアに急かされて、やれやれと肩をすくめるレオン。
「まぁ!この香り、良いわね。ステンドグラスの装飾の模様がきれいだわ」
お香の薫りが微かに室内に薫る。外の光を浴びて花模様のステンドグラスがキラキラとしている。オリビアの横にいるマリアもキョロキョロとしていて、最初の淑女の振る舞いを忘れてしまっている。
「少し異国の雰囲気のするところですね」
レオンはわかってる!私は2度目の頷きを返した。
リヴィオはあいつはインテリアとかにうるさいんだとコソコソ私に言っているが、理解してくれる人がいるのは嬉しいことだ。ましてやこの世界ではなくニホンに寄せた物にしてあるのだから受け入れてもらえるのか不安だったのだ。
「お部屋までご案内いたします」
スタッフの一人がこちらですと案内する。
部屋に入るとスタンバイされていたお菓子どクッション。ほわーんと足を放り出してくつろぐマリアにオリビアがお行儀悪いわよとたしなめる。貴族にはまだ床に机……というのは馴染まないだろうから、ゆったりとしたソファとテーブルにした。
「ふふふ。お家のようにくつろげる宿を目指しておりますから、構いませんよ。くつろげいで頂ける雰囲気を感じられ、嬉しく思います」
そう私は言ってからお茶を注ぎ、お菓子をセットした。窓の障子を開けると庭が見える。遠くには青々とした山。
「まあ!その紙のドア面白いわ!」
「お母様!これ貼ってあるのよ。うすーく」
パタパタと走っていってマリアが触ってみている。
「カーテンがわりです」
後で聞くことになるのだが、別室のレオンは大騒ぎしていたそうだ。これを自分の家にもほしいとか……。
「まぁ、お菓子も変わってて美味しい!」
あんこの入った和菓子をイメージして開発してみたやつだ。
「もう一つ食べたーい!」
マリアがそういうとオリビアが夕飯があるからと止める。
「ユカタのサイズを測らせて頂きます。この着方がわからなかったら、スタッフにお尋ねください」
一応、目の前でこんな感じですと説明する。子供用のユカタをマリアに渡すと目が輝く。
「サニーちゃん!」
「サニーちゃん柄とお花の柄と二種類用意しました。好きな方をお選びください」
選ぶもなにもサニーちゃんに釘づけのマリア。王都ではアイスクリーム屋さんからサニーちゃんが人気が出て、グッズまで売りに出しているのだ。
あらまあ!とオリビアはマリアの喜びようを微笑ましく見ていた。
「それでは、失礼致します」
私は一度下がった。リヴィオが廊下で待っていた。ふーと息をつくところをみられた。
「他の客にもそんな接客するのか?」
「ん??」
「いや、仮にも貴族なのに、他の客にもできるのか?」
「できるわよ??」
リヴィオが私の目を覗き込む。
「平民相手でも?」
「オモテナシするのに身分とかあるの?これ仕事するにも身分とか必要なの?」
「学園でオレたちは過ごしてきているが、そこまで身分を捨てていたわけじゃない。生まれてから貴族として生きてるのに、おまえのその頭を下げる行為が不思議なんだ」
ニホンではあまり身分とか関係なく仕事として捉えていた。頭を下げるのも感謝の気持ちを込めてるし……ああ、でもここではメイドや執事たち、使用人たちのように見えるのか。
「なるほど。リヴィオが言いたいことわかるわ。お辞儀とは来てくれて感謝の気持ちもあるけど…リヴィオならどう?挨拶されたらどうかしら?」
ん??とリヴィオが聞き返す。
「挨拶してくれる人に対して嫌な感情が沸く?」
「いや、そんなこと……」
「ないわよね?むしろ信頼できるような温かい印象を与えるわ。そんな宿にもう一度帰って来たいなと思えるような…温かみのある宿を作りたいの。家に帰ってきたときにおかえりなさいと言ってもらえるような場所を作りたいの。それが挨拶から始まるわ」
「なるほどな」
納得してもらえたようだ。
「メイドのようなことをするから、どうかな?と思ったが、それがセイラの方針ってわけか」
そのとおり!と私はうんうんと頷いた。まぁ……私がニホンにいたら半人前が偉そうに言わない!とニホンの母に怒られていたであろう。女将としてはまだまだ未熟であるし、名乗るのもおこがましい。
「おまえのその方針、オレには無理だな。笑顔を作るのは苦手だ」
本気なのか冗談なのかわからないことを言うリヴィオに思わず吹き出す。
「リヴィオは護衛してくれるだけで助かるわ。正直、ソフィアや……バシュレ家がなにか仕掛けてくる予感がするのよ。このまま事業を広げていけばね……」
「今のところセイラの所で飽きることないな」
それなら良かった……けど、リヴィオは学園で『黒猫』の二つ名を持つほどに才能ある魔法剣士であった。いずれはどこかへ行ってしまうだろうなと思った。
「さて、次は夕食の支度、料理長と話をしてきましょ。リヴィオは事前に好みを伝えてくれたのよね?」
「ああ。言われたとおりに好きなもの嫌いな食べ物は言っておいた。あんまり知らないがな」
いいのよ。本来なら、私が聞き出してみないとダメなのよね……母は何気ない会話の中から聞き出すのがうまかった。未熟者な私は皆の力を借りて頑張ろう。
「よし!厨房へ行くわ」
厨房は忙しそうだった。あらかじめ、メニューは相談して決めてある。
「仕込みは終わりました」
料理長がそう言う。若いがしっかりしている彼は屋敷の料理長の息子である。面談してみると腕前が良いだけでなく、人に対する優しさや自分への厳しさを兼ね備えていた。創意工夫もあり、料理にも真剣……どこか前世の父に似ていた。
「ありがとう。問題はない?」
「ありません。時間通りに順番に出すということも王宮でフルコースを出すという感じと似ているので…」
なるほど。確かに似ている。
「じゃあ、頼むわね!」
はいっ!と白いコックコートを着た彼。ジャンは頷いた。私とメニューを練っていた時も否定せず話を聞いてくれ、考えてくれた。
……思い出す。私は父の作る料理は好きだった。小さい頃、厨房を覗いているとオヤツをサッと魔法のように作ってくれたり、旬の食材を使った料理を見せてくれたり……懐かしいと思うのはおかしいのだろうか?
夕食の時間までに温泉に行っていた三人は目を輝かせて帰ってきた。
「これは疲れがとれますね。水質を調べたくなりました。回復効果のある水ですよね」
レオンは温泉の水に興味津々だった。
「サウナも公爵家の屋敷に欲しくなりましたよ!」
リヴィオがポソッと告げる。
「レオンは新し物好きで、分析もしたがる。だから母が連れてきたんだ」
モニターとしては有り難い。わかってて連れてきてくれたのか…。
「マリア、外のお風呂好きだった〜!」
「わたくしは少し恥ずかしいのでお部屋のお風呂があったことが嬉しかったですわ」
それぞれの感想を頭に入れておく。
「気に入って頂けて良かったです。温泉のお湯はキズ、打ち身、筋肉痛、疲労などに効きます。なにか不都合はなかったですか?」
レオンとマリアはとくになかったようだ。オリビアが部屋に置いてあったアメニティについて聞く。
「このいい香りの化粧水って売ってるのかしら?気に入ったのだけど、わたくし使いたいわ」
「良かったら、帰りにお土産に致しますよ」
そう言ったが……そうだ!売店を作っていなかったことに思い至る。確かに気に入った商品は売店で買えるようにすればいいんだわ。失念していた。
「夕飯はこちらのお部屋です」
広間である。天井に花模様やこの国の象徴である黒竜の絵が描かれている。お祖父様が懇意にしていたという画家に頼んだ。
「天井絵!?」
「でも派手すぎない色合いの絵で、周りの雰囲気と合ってるわ」
二人の感心を無視してマリアはとっくに席について、お腹すいたわと待っている。緑の目をキラキラと宝石のように輝かせて期待を込めている。
「おまたせしました。前菜でございます」
さすがに優雅で綺麗な所作で三人は食べだす。マナーには慣れている。
「これなにかしら?」
小さなグラスに入った物を尋ねる。
「そら豆とコンソメのジュレです」
「キラキラしてて良いわね。今度の夜会に出してみたいわ」
オリビアがそう言いながら採れたて野菜を主体とした前菜を食べていく。スモークサーモンが美味しいとレオンがにっこりする。
「マリアのは!?」
「マリア様のはこちらです」
お子様ランチを運んできた。自分の前に置かれるとなんとも言えない嬉しい顔をした。
ケチャップライス、ミニハンバーグ、エビフライ、くるっと巻いたスパゲッティ、ポテトフライに彩りにプチトマト、ブロッコリー。しぼりたてオレンジジュース。
「うわぁ!美味しそう!それに楽しい!!」
大人用メインはミニ鉄板に香りのある葉っぱをのせ、その上にお肉と野菜を炒めて食べられるようにした。火をおつけしますねーと接客係が言う。
「目の前で、焼かれていくのね!」
「食べごろは火が消えてからです」
ミニ火球を小さいコンロに仕込み、時間になったら消えるシステムだ。レオンがまた狙った目をしている。
「これもオシャレですね!新しい食べ方だ!」
チロチロと燃える炎とジュージュー焼かれていく様子は食欲をそそる。
「川でとれる魚のソテーです。付け合せは山菜の和え物です。とろみがあって美味しいですよ」
一つ一つ料理を運ぶごとに説明をする。
興奮気味に食べ終わり最後のデザートを持ってくる。
季節のフルーツシャーベットにふわふわのピンクの綿菓子を添えて出す。小さい金平糖も散らす。
「かっ!かわいすぎるーーっ!!」
マリアが両手を思わず組む。オリビアもまぁ!と言い、レオンは綿菓子をつついてみている。
「この星型のは飴!?ふわふわの雲も飴!?」
「これは王都でも流行る!」
夕食会は大成功だったのかな??オリビアは口を拭いて、にっこりと言う。
「素晴らしかったわ……でも一つだけいいかしら?」
ハイと私は緊張しつつ返事をした。
「どれも驚きばかりで文句はないわ。ただ、宿でくつろぐならば何かホッとするような故郷の味のようなメニューもいれると落ち着くわ」
たしかに……私は目新しさばかりを狙ってしまった。納得し、頷く。
「貴重な意見です。ありがとうございます」
さすが夜会の主催を何度もしてる公爵夫人である。
「それから、貴族はもてなされることに慣れてます。なにかイベント的な楽しみもあってもいいかもしれませんね」
レオンがそう言う。そういえば……そうかもしれない。温泉宿でワイワイ楽しく盛り上がれる何かがあればいい。
「なるほど……それもわかります。オープンまでに考えてみます」
二人はニッコリ笑い合って最後に言う。
「素晴らしい宿でしたわ。わたくし、今まで、経験したことのない楽しさでしたわ。なにより、お肌がスベスベなことに驚きを隠せませんわ」
「王都で売り出したい物もあった。契約させてほしいな」
概ね。うまくいったようだった。私はホッとしてありがとうございますと二人に感謝した。
そういう私も実はすごくドキドキして、昨日はなかなか寝れなかったのだ。しかしここでは女将!女将として頑張らないと!自分を奮い立たせる。
深呼吸する。そして皆に笑顔を向けた。
「よくここまで頑張り、研修を受け、私についてきてくれたわ。みんななら大丈夫!身分などは関係なく、我が家にお客様が来たと思って接してくれれば絶対うまくいくわ。問題が起きたら一人で解決しないこと。みんなで解決するからね!」
大丈夫!と安心させる。硬かった表情がややほぐれる。
リヴィオが目を細めて言う。
「学園にいた頃とずいぶん変わったよな。いい意味で」
どうだろうか?前世のジョシコーセーの自分は確かに明るい。母と対立することもあったようだが、負けん気があり、根性もあった。今のセイラという自分は学園で物静かに本を読んでいるというイメージなのかもしれないが、ずっと耐えて……我慢強い心の持ち主だと前世の自分なら言うかもしれない。
たぶん互いに補い合っての今の私なのだろう。
フッと可笑しくて笑う。リヴィオは笑わずに金色の目で私の目を見た。そのうち彼なら前世の記憶とやらを話しても良いかもしれない。私に違和感を感じているのだろう。
やがてガラガラと車輪の音がして馬車が2台着いた。カムパネルラ公爵家の家紋が描かれている。ドアが開いた。
一台目からはオリビアと小さい少女が。2台目からはリヴィオにやや似ているがタレ目で黒髪の青年。
いらっしゃいませー!と声をかけるスタッフ達と私。
「末の妹のマリアと2番目の兄のレオンだ」
リヴィオが紹介してくれる。可愛らしいオリビアに似ている金髪碧眼のマリアはドレスの裾を持ち、ちょこんと挨拶した。スタッフからもかーわいーっ!と言う声が思わずヒソヒソと小声で漏れる。
「お招きありがとう。本当はハリーも来たがっていたんだけど、仕事で来れなくて…残念だわ」
「そうなんですね。皆様、忙しいなか、お越しくださって嬉しいですわ。馬車に揺られて、お疲れでしょう?どうぞこちらへ。荷物はお預かりしてお部屋まで届けますわ」
ササッと荷物係が馬車の御者から荷物を受け取る。私は庭園を抜けて玄関へ案内する。
「へぇ!見事なものですね」
レオンと呼ばれたリヴィオの兄が庭園を褒める。興味ゼロで通りすぎてった弟さんとは一味違う予感。
「この庭、四季を楽しめるように植物が植えられているんですね。あの流れる川や石はまるで小さい自然の世界を表しているような庭ですね」
「お気に召して頂いて嬉しいですわ。今の季節は夏を彩る蓮の花が見頃ですわ」
池の方でポンッと咲く、ピンク色の花を示すと綺麗ですねーと微笑む。
褒められて私も嬉しくて笑う。庭師たちのおかげである。風情をよくわかっていてすごい人だ。
「兄さまーっ!はやーく!」
マリアに急かされて、やれやれと肩をすくめるレオン。
「まぁ!この香り、良いわね。ステンドグラスの装飾の模様がきれいだわ」
お香の薫りが微かに室内に薫る。外の光を浴びて花模様のステンドグラスがキラキラとしている。オリビアの横にいるマリアもキョロキョロとしていて、最初の淑女の振る舞いを忘れてしまっている。
「少し異国の雰囲気のするところですね」
レオンはわかってる!私は2度目の頷きを返した。
リヴィオはあいつはインテリアとかにうるさいんだとコソコソ私に言っているが、理解してくれる人がいるのは嬉しいことだ。ましてやこの世界ではなくニホンに寄せた物にしてあるのだから受け入れてもらえるのか不安だったのだ。
「お部屋までご案内いたします」
スタッフの一人がこちらですと案内する。
部屋に入るとスタンバイされていたお菓子どクッション。ほわーんと足を放り出してくつろぐマリアにオリビアがお行儀悪いわよとたしなめる。貴族にはまだ床に机……というのは馴染まないだろうから、ゆったりとしたソファとテーブルにした。
「ふふふ。お家のようにくつろげる宿を目指しておりますから、構いませんよ。くつろげいで頂ける雰囲気を感じられ、嬉しく思います」
そう私は言ってからお茶を注ぎ、お菓子をセットした。窓の障子を開けると庭が見える。遠くには青々とした山。
「まあ!その紙のドア面白いわ!」
「お母様!これ貼ってあるのよ。うすーく」
パタパタと走っていってマリアが触ってみている。
「カーテンがわりです」
後で聞くことになるのだが、別室のレオンは大騒ぎしていたそうだ。これを自分の家にもほしいとか……。
「まぁ、お菓子も変わってて美味しい!」
あんこの入った和菓子をイメージして開発してみたやつだ。
「もう一つ食べたーい!」
マリアがそういうとオリビアが夕飯があるからと止める。
「ユカタのサイズを測らせて頂きます。この着方がわからなかったら、スタッフにお尋ねください」
一応、目の前でこんな感じですと説明する。子供用のユカタをマリアに渡すと目が輝く。
「サニーちゃん!」
「サニーちゃん柄とお花の柄と二種類用意しました。好きな方をお選びください」
選ぶもなにもサニーちゃんに釘づけのマリア。王都ではアイスクリーム屋さんからサニーちゃんが人気が出て、グッズまで売りに出しているのだ。
あらまあ!とオリビアはマリアの喜びようを微笑ましく見ていた。
「それでは、失礼致します」
私は一度下がった。リヴィオが廊下で待っていた。ふーと息をつくところをみられた。
「他の客にもそんな接客するのか?」
「ん??」
「いや、仮にも貴族なのに、他の客にもできるのか?」
「できるわよ??」
リヴィオが私の目を覗き込む。
「平民相手でも?」
「オモテナシするのに身分とかあるの?これ仕事するにも身分とか必要なの?」
「学園でオレたちは過ごしてきているが、そこまで身分を捨てていたわけじゃない。生まれてから貴族として生きてるのに、おまえのその頭を下げる行為が不思議なんだ」
ニホンではあまり身分とか関係なく仕事として捉えていた。頭を下げるのも感謝の気持ちを込めてるし……ああ、でもここではメイドや執事たち、使用人たちのように見えるのか。
「なるほど。リヴィオが言いたいことわかるわ。お辞儀とは来てくれて感謝の気持ちもあるけど…リヴィオならどう?挨拶されたらどうかしら?」
ん??とリヴィオが聞き返す。
「挨拶してくれる人に対して嫌な感情が沸く?」
「いや、そんなこと……」
「ないわよね?むしろ信頼できるような温かい印象を与えるわ。そんな宿にもう一度帰って来たいなと思えるような…温かみのある宿を作りたいの。家に帰ってきたときにおかえりなさいと言ってもらえるような場所を作りたいの。それが挨拶から始まるわ」
「なるほどな」
納得してもらえたようだ。
「メイドのようなことをするから、どうかな?と思ったが、それがセイラの方針ってわけか」
そのとおり!と私はうんうんと頷いた。まぁ……私がニホンにいたら半人前が偉そうに言わない!とニホンの母に怒られていたであろう。女将としてはまだまだ未熟であるし、名乗るのもおこがましい。
「おまえのその方針、オレには無理だな。笑顔を作るのは苦手だ」
本気なのか冗談なのかわからないことを言うリヴィオに思わず吹き出す。
「リヴィオは護衛してくれるだけで助かるわ。正直、ソフィアや……バシュレ家がなにか仕掛けてくる予感がするのよ。このまま事業を広げていけばね……」
「今のところセイラの所で飽きることないな」
それなら良かった……けど、リヴィオは学園で『黒猫』の二つ名を持つほどに才能ある魔法剣士であった。いずれはどこかへ行ってしまうだろうなと思った。
「さて、次は夕食の支度、料理長と話をしてきましょ。リヴィオは事前に好みを伝えてくれたのよね?」
「ああ。言われたとおりに好きなもの嫌いな食べ物は言っておいた。あんまり知らないがな」
いいのよ。本来なら、私が聞き出してみないとダメなのよね……母は何気ない会話の中から聞き出すのがうまかった。未熟者な私は皆の力を借りて頑張ろう。
「よし!厨房へ行くわ」
厨房は忙しそうだった。あらかじめ、メニューは相談して決めてある。
「仕込みは終わりました」
料理長がそう言う。若いがしっかりしている彼は屋敷の料理長の息子である。面談してみると腕前が良いだけでなく、人に対する優しさや自分への厳しさを兼ね備えていた。創意工夫もあり、料理にも真剣……どこか前世の父に似ていた。
「ありがとう。問題はない?」
「ありません。時間通りに順番に出すということも王宮でフルコースを出すという感じと似ているので…」
なるほど。確かに似ている。
「じゃあ、頼むわね!」
はいっ!と白いコックコートを着た彼。ジャンは頷いた。私とメニューを練っていた時も否定せず話を聞いてくれ、考えてくれた。
……思い出す。私は父の作る料理は好きだった。小さい頃、厨房を覗いているとオヤツをサッと魔法のように作ってくれたり、旬の食材を使った料理を見せてくれたり……懐かしいと思うのはおかしいのだろうか?
夕食の時間までに温泉に行っていた三人は目を輝かせて帰ってきた。
「これは疲れがとれますね。水質を調べたくなりました。回復効果のある水ですよね」
レオンは温泉の水に興味津々だった。
「サウナも公爵家の屋敷に欲しくなりましたよ!」
リヴィオがポソッと告げる。
「レオンは新し物好きで、分析もしたがる。だから母が連れてきたんだ」
モニターとしては有り難い。わかってて連れてきてくれたのか…。
「マリア、外のお風呂好きだった〜!」
「わたくしは少し恥ずかしいのでお部屋のお風呂があったことが嬉しかったですわ」
それぞれの感想を頭に入れておく。
「気に入って頂けて良かったです。温泉のお湯はキズ、打ち身、筋肉痛、疲労などに効きます。なにか不都合はなかったですか?」
レオンとマリアはとくになかったようだ。オリビアが部屋に置いてあったアメニティについて聞く。
「このいい香りの化粧水って売ってるのかしら?気に入ったのだけど、わたくし使いたいわ」
「良かったら、帰りにお土産に致しますよ」
そう言ったが……そうだ!売店を作っていなかったことに思い至る。確かに気に入った商品は売店で買えるようにすればいいんだわ。失念していた。
「夕飯はこちらのお部屋です」
広間である。天井に花模様やこの国の象徴である黒竜の絵が描かれている。お祖父様が懇意にしていたという画家に頼んだ。
「天井絵!?」
「でも派手すぎない色合いの絵で、周りの雰囲気と合ってるわ」
二人の感心を無視してマリアはとっくに席について、お腹すいたわと待っている。緑の目をキラキラと宝石のように輝かせて期待を込めている。
「おまたせしました。前菜でございます」
さすがに優雅で綺麗な所作で三人は食べだす。マナーには慣れている。
「これなにかしら?」
小さなグラスに入った物を尋ねる。
「そら豆とコンソメのジュレです」
「キラキラしてて良いわね。今度の夜会に出してみたいわ」
オリビアがそう言いながら採れたて野菜を主体とした前菜を食べていく。スモークサーモンが美味しいとレオンがにっこりする。
「マリアのは!?」
「マリア様のはこちらです」
お子様ランチを運んできた。自分の前に置かれるとなんとも言えない嬉しい顔をした。
ケチャップライス、ミニハンバーグ、エビフライ、くるっと巻いたスパゲッティ、ポテトフライに彩りにプチトマト、ブロッコリー。しぼりたてオレンジジュース。
「うわぁ!美味しそう!それに楽しい!!」
大人用メインはミニ鉄板に香りのある葉っぱをのせ、その上にお肉と野菜を炒めて食べられるようにした。火をおつけしますねーと接客係が言う。
「目の前で、焼かれていくのね!」
「食べごろは火が消えてからです」
ミニ火球を小さいコンロに仕込み、時間になったら消えるシステムだ。レオンがまた狙った目をしている。
「これもオシャレですね!新しい食べ方だ!」
チロチロと燃える炎とジュージュー焼かれていく様子は食欲をそそる。
「川でとれる魚のソテーです。付け合せは山菜の和え物です。とろみがあって美味しいですよ」
一つ一つ料理を運ぶごとに説明をする。
興奮気味に食べ終わり最後のデザートを持ってくる。
季節のフルーツシャーベットにふわふわのピンクの綿菓子を添えて出す。小さい金平糖も散らす。
「かっ!かわいすぎるーーっ!!」
マリアが両手を思わず組む。オリビアもまぁ!と言い、レオンは綿菓子をつついてみている。
「この星型のは飴!?ふわふわの雲も飴!?」
「これは王都でも流行る!」
夕食会は大成功だったのかな??オリビアは口を拭いて、にっこりと言う。
「素晴らしかったわ……でも一つだけいいかしら?」
ハイと私は緊張しつつ返事をした。
「どれも驚きばかりで文句はないわ。ただ、宿でくつろぐならば何かホッとするような故郷の味のようなメニューもいれると落ち着くわ」
たしかに……私は目新しさばかりを狙ってしまった。納得し、頷く。
「貴重な意見です。ありがとうございます」
さすが夜会の主催を何度もしてる公爵夫人である。
「それから、貴族はもてなされることに慣れてます。なにかイベント的な楽しみもあってもいいかもしれませんね」
レオンがそう言う。そういえば……そうかもしれない。温泉宿でワイワイ楽しく盛り上がれる何かがあればいい。
「なるほど……それもわかります。オープンまでに考えてみます」
二人はニッコリ笑い合って最後に言う。
「素晴らしい宿でしたわ。わたくし、今まで、経験したことのない楽しさでしたわ。なにより、お肌がスベスベなことに驚きを隠せませんわ」
「王都で売り出したい物もあった。契約させてほしいな」
概ね。うまくいったようだった。私はホッとしてありがとうございますと二人に感謝した。