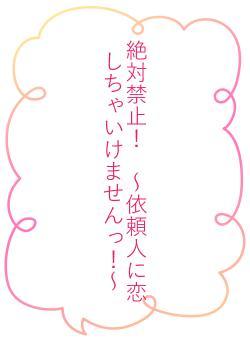「そっか」
市川くん、わたしのこと、友だちだってちゃんと認めてくれてたんだ。
それだけじゃなくて、まさかこんなふうに言ってもらえるなんて、思ってもみなかったから。
うれしすぎて、顔のにやけが収まらないよ。
「なんだよ、その顔。相当ヘンだぞ、おまえ」
市川くんが、ふっと鼻で笑う。
「だって、うれしいんだもん」
「あっそ」
——友だちでそこまで喜ばれると、逆にヘコむわ。
なんてよくわからないつぶやきが聞こえたような気もするんだけど。
そんな細かいことが気にならないくらい、ぶわっと体中から喜びが溢れてくる。
「あのね。さっきの答えだけど、わたしは、少女マンガ好きに悪い人はいないって信じてるからだよ」
「は? そんなもんで簡単に他人信じんの? おまえ、簡単にサギに引っかかるタイプだろ」
市川くんが、声を出して笑いはじめた。
「ヒドイ。そんなに笑わなくてもいいのに。だったら、そのときは市川くんがちゃんと止めてよ」
「は? なんでオレがそんなめんどーなこと、しなくちゃなんねえんだよ」
「じゃあさ。……ねえ、これって、やっぱりサギだと思う?」
わたしはスマホを取り出すと、市川くんに向かって差し出した。
「は? なにが……って、ちょっと待て」
わたしからスマホを取り上げると、まじまじと画面を見つめる市川くん。
数日前に、コンテストに応募していた出版社から、一通のメールが来たんだ。
わたしだって、さすがにサギを疑って一生懸命調べたよ。
だけど、差出人のメアドは、ちゃんとその出版社の編集部のものだった。
そこまでしても、まだ現実のこととは到底思えなくて。
不安でドキドキしながら、メールを確認する市川くんをじっと見つめていたら、市川くんが目を輝かせてわたしの方を見た。
市川くん、わたしのこと、友だちだってちゃんと認めてくれてたんだ。
それだけじゃなくて、まさかこんなふうに言ってもらえるなんて、思ってもみなかったから。
うれしすぎて、顔のにやけが収まらないよ。
「なんだよ、その顔。相当ヘンだぞ、おまえ」
市川くんが、ふっと鼻で笑う。
「だって、うれしいんだもん」
「あっそ」
——友だちでそこまで喜ばれると、逆にヘコむわ。
なんてよくわからないつぶやきが聞こえたような気もするんだけど。
そんな細かいことが気にならないくらい、ぶわっと体中から喜びが溢れてくる。
「あのね。さっきの答えだけど、わたしは、少女マンガ好きに悪い人はいないって信じてるからだよ」
「は? そんなもんで簡単に他人信じんの? おまえ、簡単にサギに引っかかるタイプだろ」
市川くんが、声を出して笑いはじめた。
「ヒドイ。そんなに笑わなくてもいいのに。だったら、そのときは市川くんがちゃんと止めてよ」
「は? なんでオレがそんなめんどーなこと、しなくちゃなんねえんだよ」
「じゃあさ。……ねえ、これって、やっぱりサギだと思う?」
わたしはスマホを取り出すと、市川くんに向かって差し出した。
「は? なにが……って、ちょっと待て」
わたしからスマホを取り上げると、まじまじと画面を見つめる市川くん。
数日前に、コンテストに応募していた出版社から、一通のメールが来たんだ。
わたしだって、さすがにサギを疑って一生懸命調べたよ。
だけど、差出人のメアドは、ちゃんとその出版社の編集部のものだった。
そこまでしても、まだ現実のこととは到底思えなくて。
不安でドキドキしながら、メールを確認する市川くんをじっと見つめていたら、市川くんが目を輝かせてわたしの方を見た。