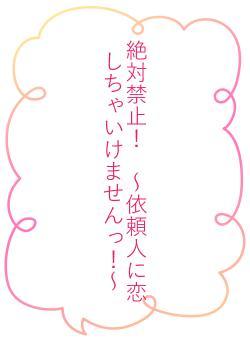あれ以来、一度も市川くんと話せないまま数か月が経ち、いつの間にか季節は春から秋へと移り変わっていた。
街のショーウインドウには、早くも冬物のコートをまとったマネキンが立ち、美しい緑色だった街路樹は黄色く染まっている。
結局、あのとき『友だちになる』って言ってくれた森下さんたちとも長くは続かず、気付いたら元のぼっちに逆戻りしていた。
どちらかというと、いつもクラスの中心にいる森下さんたちのノリにうまく合わせられなくて、『ぼっちの方が気楽なのに』って心の奥底で思っていたのが、バレてしまったんだと思う。
つくづく友だち付き合いっていうのに向いてないんだな、わたし。
顔をうつむかせて、はぁ、と小さくため息を吐いたとき、目の前に壁のように大きな男の人が立っているのに気付いて、わたしは慌てて足を止めた。
「ご、ごめんなさい……」
「あんた、市川クンのお友だちだよね♪ あー、それともカノジョ?」
そーっと顔を上げると、大男がぐいっと顔を近づけてくる。
顔は笑っているのに、目の奥が氷のように冷たく光っていて、背筋がぞわりとする。
バイト先の本屋は目の前にあるのに、怖そうなお兄さんたちにぐるりと取り囲まれて、果てしなく遠く感じる。
ひょっとして、市川くんの、お友だち……?
「アイツ、最近全然姿見せなくなっちまってさあ。ずっとアイツのこと探ってたら、あんたと仲がいいってウワサ耳にしたんだよね。ねえ、ホントのとこ、どーなの?」
「違います。だって、うぜえって言われて……友だちなんかじゃないって……だから、あれから一度も話せてなくて……」
「ふぅん。そんな大事にされてんだ、あんた」
……え?
友だちなんかじゃないって言われたのに?
「でもさ、正直アイツのどこがいいわけ? あんなやつ、いない方がみんなのためになると思わねえ? 今時『一匹狼』気取ってるやつなんか見たことねーし。あ、そっか。バカだからダチもできねーのか」
「それな!」
そう言って、男たちがゲラゲラ笑う。