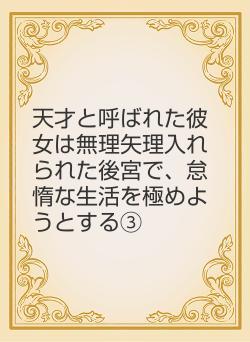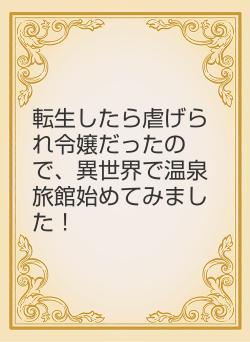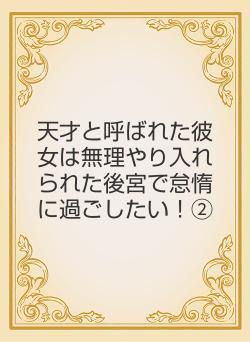「お嬢様、どうなされるんてす?」
「もう答えは出てるのよ」
私が窓辺でのんびり本を片手にお茶を飲んでいる。アナベルの淹れるお茶はやっぱり美味しい。
「えええっ!?いつもと変わらない姿ですけど……」
そう?と私はあくびを一つして、心地よい日差しにウトウトしかける。怠惰な時間、最高潮だわー。
「お嬢様は時々、単純なのか複雑なのか分からなくなります」
アナベルはそう言って首を傾げるのだった。私は本を借りに行ったり庭を散歩したりし、まったりと怠惰な生活を楽しんでいた。
夜になり、山にかかっていた丸い月が空へ登ってゆく。月のおかげで明るい夜だった。
読書をしつつ、お茶を飲むためにカップを傾げる。その瞬間、窓がガタッと鳴る。
「なんで窓から入ってくるのよ!?ウィル?」
「……後宮の鍵が開いてるかどうか確認する勇気がなかったんだ」
以前と同じように潜んできたウィルは困った顔をしている。王様なら堂々とドアから来なさいよと呆れて半眼になる私。
「もう!なんなのよ?自分で、選択肢をあげるよとかカッコいいこと言っておいて……」
「リアンの前だと臆病になるんだ」
私はその言葉が真実であることを疑わない。フッと頬が緩み、笑ってしまう。私は自分からウィルに歩み寄り近づく。そしてギュッと顔をウィルの胸に埋めて、抱きしめた。
顔は恥ずかしくてまともに見れない。でも大事なことだから、目を見て話さなければならない。ドキドキしながら顔をあげて、視線を合わせる。
後は思っていることを口に出すだけだ。勇気を出せ!と自分を奮い立たせる。ウィルはきっと私の何倍も何十倍も王になるために勇気を出して生きてきたのだと思う。
「リ、リアン!?」
「私は暗闇にいた時に、ウィルを信じていた。絶対助けに来てくれるって思っていたわ。その思いで乗り越えられたわ。ウィルとウィルバート、二つの顔を持つあなただけど、大切なのはあなたらしさなのよ」
ウィルがうんと短く小さな声で答える。知っている。小さい頃から一緒にいるんだもの。どの姿が本当の彼なのかわかってる。
私は考えたのだ。全能力をかき集めて、どれがウィルの本当の姿をなのかを。
答えは意外と簡単に見つかった。ウィルバートになっても彼は私のことを大切に考えてた。それが答えだ。
「でも王である以上は見せれない顔があるんだ。どれだけ……もがいて苦しくても、オレは王でいなければならないんだ」
かすかに声が震えている。
「そうね。……《《ウィルバート》》。私はあなたに怠惰な生活をあげるわ」
ウィルの目は潤んでいた。時々年上のくせに涙もろくて、弟のようなるウィルバート。
「《《ウィルバート》》って呼んでくれるんだね。でもどういうことだい?リアンの怠惰な生活は?夢は?もういいのか?」
「王妃になって、傍にいて、愛して、私の全能力を使って助けてあげる。それがこの国のためにもなるから、私の夢だって叶うようなものよ!私はあなたが安心できる場所を作るわ。そうすれば、少しはウィルバートにホッとできる怠惰な時間があげられる。これから一緒に過ごす穏やかな時間が持てるようにするわ」
彼の夏空のような青い色の目が、驚いたように見開く。そして、そっとウィルバートは私の頬に触れて撫でる。優しく、こわごわとした指先で。
「じゃあ、僕はリアンが怠惰な生活がてきるように、この国を平和な国に導いていくことを約束するよ。リアンとなら、できる。頑張れる気がする」
……後宮はいつもどおり、扉に鍵はかけてなかった。
私の言葉に嘘偽りがなかったことをウィルバートはこの後、知ることになる。この国の王妃は聡明で、王を助け、民と共に歩む方だと人々は口にするようになる。
もちろん約束どおり、王と王妃になり、互いに忙しい日々の中でも、二人で過ごす、のんびりとした怠惰な時間を大切にしている。その時間のウィルバートはとても幸せそうで、私もそんな彼を見るのが大好きなのだった。
そう!最後に、大事なことを忘れていた。
「天才リアンは街だけではなくて、王国でも有名になったでしょ?」
両親に得意げに言うことができたのだった。それを付け加えておく。
☆天才と呼ばれた彼女は無理やり入れられた後宮で怠惰に過ごしたい!②に続きます。よろしければ続きもよろしくお願いします。
「もう答えは出てるのよ」
私が窓辺でのんびり本を片手にお茶を飲んでいる。アナベルの淹れるお茶はやっぱり美味しい。
「えええっ!?いつもと変わらない姿ですけど……」
そう?と私はあくびを一つして、心地よい日差しにウトウトしかける。怠惰な時間、最高潮だわー。
「お嬢様は時々、単純なのか複雑なのか分からなくなります」
アナベルはそう言って首を傾げるのだった。私は本を借りに行ったり庭を散歩したりし、まったりと怠惰な生活を楽しんでいた。
夜になり、山にかかっていた丸い月が空へ登ってゆく。月のおかげで明るい夜だった。
読書をしつつ、お茶を飲むためにカップを傾げる。その瞬間、窓がガタッと鳴る。
「なんで窓から入ってくるのよ!?ウィル?」
「……後宮の鍵が開いてるかどうか確認する勇気がなかったんだ」
以前と同じように潜んできたウィルは困った顔をしている。王様なら堂々とドアから来なさいよと呆れて半眼になる私。
「もう!なんなのよ?自分で、選択肢をあげるよとかカッコいいこと言っておいて……」
「リアンの前だと臆病になるんだ」
私はその言葉が真実であることを疑わない。フッと頬が緩み、笑ってしまう。私は自分からウィルに歩み寄り近づく。そしてギュッと顔をウィルの胸に埋めて、抱きしめた。
顔は恥ずかしくてまともに見れない。でも大事なことだから、目を見て話さなければならない。ドキドキしながら顔をあげて、視線を合わせる。
後は思っていることを口に出すだけだ。勇気を出せ!と自分を奮い立たせる。ウィルはきっと私の何倍も何十倍も王になるために勇気を出して生きてきたのだと思う。
「リ、リアン!?」
「私は暗闇にいた時に、ウィルを信じていた。絶対助けに来てくれるって思っていたわ。その思いで乗り越えられたわ。ウィルとウィルバート、二つの顔を持つあなただけど、大切なのはあなたらしさなのよ」
ウィルがうんと短く小さな声で答える。知っている。小さい頃から一緒にいるんだもの。どの姿が本当の彼なのかわかってる。
私は考えたのだ。全能力をかき集めて、どれがウィルの本当の姿をなのかを。
答えは意外と簡単に見つかった。ウィルバートになっても彼は私のことを大切に考えてた。それが答えだ。
「でも王である以上は見せれない顔があるんだ。どれだけ……もがいて苦しくても、オレは王でいなければならないんだ」
かすかに声が震えている。
「そうね。……《《ウィルバート》》。私はあなたに怠惰な生活をあげるわ」
ウィルの目は潤んでいた。時々年上のくせに涙もろくて、弟のようなるウィルバート。
「《《ウィルバート》》って呼んでくれるんだね。でもどういうことだい?リアンの怠惰な生活は?夢は?もういいのか?」
「王妃になって、傍にいて、愛して、私の全能力を使って助けてあげる。それがこの国のためにもなるから、私の夢だって叶うようなものよ!私はあなたが安心できる場所を作るわ。そうすれば、少しはウィルバートにホッとできる怠惰な時間があげられる。これから一緒に過ごす穏やかな時間が持てるようにするわ」
彼の夏空のような青い色の目が、驚いたように見開く。そして、そっとウィルバートは私の頬に触れて撫でる。優しく、こわごわとした指先で。
「じゃあ、僕はリアンが怠惰な生活がてきるように、この国を平和な国に導いていくことを約束するよ。リアンとなら、できる。頑張れる気がする」
……後宮はいつもどおり、扉に鍵はかけてなかった。
私の言葉に嘘偽りがなかったことをウィルバートはこの後、知ることになる。この国の王妃は聡明で、王を助け、民と共に歩む方だと人々は口にするようになる。
もちろん約束どおり、王と王妃になり、互いに忙しい日々の中でも、二人で過ごす、のんびりとした怠惰な時間を大切にしている。その時間のウィルバートはとても幸せそうで、私もそんな彼を見るのが大好きなのだった。
そう!最後に、大事なことを忘れていた。
「天才リアンは街だけではなくて、王国でも有名になったでしょ?」
両親に得意げに言うことができたのだった。それを付け加えておく。
☆天才と呼ばれた彼女は無理やり入れられた後宮で怠惰に過ごしたい!②に続きます。よろしければ続きもよろしくお願いします。