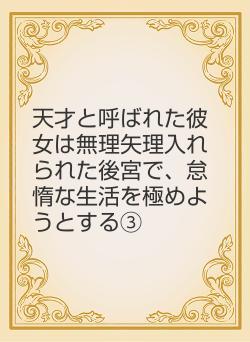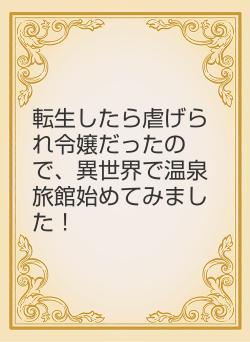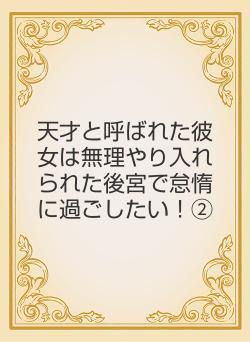「まさか訓練所に来るなんてね。僕に興味を持ってくれてるんだよね!?嬉しいよ」
ウィルは上機嫌で昼食をとっている。リアンが来てくれると言うから……と、なんとわざわざ庭園に食事の場を設定してくれてあった。
ホワホワ〜としたウィルの姿に今はなっている。先程の訓練中の彼とはまったく違う。私の顔を見た途端にスイッチか切り替わり、変化していた気がする。
「偶然なのよ!たまたま見に行ったのよ!」
私が違うの!と否定しているのに、煽ったセオドアは知らん顔している。ウィルは信じず、そうなんだー、偶然ってすごいねーとフフフッと笑っている。
「さてと……リアン、僕は王で君もわかってると思うけど、王の命令は絶対であると思う。だけど一度だけチャンスをあげたい。僕のことが、本当に嫌なら、後宮に鍵をかけておいてほしい。もう行かないし、君を家に帰してあげる。自分の望む道を生きて、夢を叶えるといいよ」
「選択肢をくれるの?欲しい物は手に入れるんじゃなかったの?」
ウィルは、まぁね……と、私の顔を見ず、目を伏せて、どこか寂しい顔をして言う。そんな顔は反則じゃない?しょんぼりとした捨てられた犬みたいな表情をしないでほしい。
「陛下、よろしいのですか?前から言っていますが、買いかぶりすぎでは?」
後ろに控えていたセオドアがボソッとウィルにささやくように言った。
「セオドアはリアンのことを知らないからな。リアン、この川の東側と西側の水の管理についてどう思う?」
私に一枚の紙と地図を見せた。つい、反射的に口から言葉が出る。私塾ではよく、こんな問答を生徒同士がしていたからだ。
「春の間は水田地帯の多い東へ水を流す。夏場は西側に流さないと、あまり雨の振らない地域ゆえ困ります」
セオドアは目をパチパチさせた。ウィルはだよねと書類をサラサラと書き直して印を押す。
「こういうことだ」
セオドアは納得して頭をスッと下げた。
「よけいなことを申しました」
「僕としてはリアンが欲しい。傍にいてほしい。だけどリアンが夢を持ち、努力してきたことも知っているから、選ばせてあげるよ」
ウィルバートという名の王様。これは彼が努力して作り上げた姿なのだろうと思う。昔から何度も傷を作り、私が治癒魔法をかけていたのは木から落ちたせいでも釣りに行って岩場で切ったせいでもなく、こういうことだったのだと今、知った。
『リアンと居るときが一番、僕らしくいれるよ。君の治癒魔法の淡い光は温かで優しい』
傷を治してあげると、そうほんわかとした笑顔で言っていたウィルは普通の人だった。彼はどんな思いで、その言葉を口にしていたのだろう?
今、目の前にいるのは、以前と同じ、優しい雰囲気のウィルなのに、ウィルバートになると、王らしく強く輝くオーラと人を油断させない雰囲気を持つ。
私はフォークとナイフを置いた。
「わかったわ。ウィルが本気で言ってるのがわかるから、私も本気で考えるわ」
「ありがとう」
そうお礼を言って微笑むウィルだったが、その笑顔は作り笑いだと私は気づいていた。
ウィルは上機嫌で昼食をとっている。リアンが来てくれると言うから……と、なんとわざわざ庭園に食事の場を設定してくれてあった。
ホワホワ〜としたウィルの姿に今はなっている。先程の訓練中の彼とはまったく違う。私の顔を見た途端にスイッチか切り替わり、変化していた気がする。
「偶然なのよ!たまたま見に行ったのよ!」
私が違うの!と否定しているのに、煽ったセオドアは知らん顔している。ウィルは信じず、そうなんだー、偶然ってすごいねーとフフフッと笑っている。
「さてと……リアン、僕は王で君もわかってると思うけど、王の命令は絶対であると思う。だけど一度だけチャンスをあげたい。僕のことが、本当に嫌なら、後宮に鍵をかけておいてほしい。もう行かないし、君を家に帰してあげる。自分の望む道を生きて、夢を叶えるといいよ」
「選択肢をくれるの?欲しい物は手に入れるんじゃなかったの?」
ウィルは、まぁね……と、私の顔を見ず、目を伏せて、どこか寂しい顔をして言う。そんな顔は反則じゃない?しょんぼりとした捨てられた犬みたいな表情をしないでほしい。
「陛下、よろしいのですか?前から言っていますが、買いかぶりすぎでは?」
後ろに控えていたセオドアがボソッとウィルにささやくように言った。
「セオドアはリアンのことを知らないからな。リアン、この川の東側と西側の水の管理についてどう思う?」
私に一枚の紙と地図を見せた。つい、反射的に口から言葉が出る。私塾ではよく、こんな問答を生徒同士がしていたからだ。
「春の間は水田地帯の多い東へ水を流す。夏場は西側に流さないと、あまり雨の振らない地域ゆえ困ります」
セオドアは目をパチパチさせた。ウィルはだよねと書類をサラサラと書き直して印を押す。
「こういうことだ」
セオドアは納得して頭をスッと下げた。
「よけいなことを申しました」
「僕としてはリアンが欲しい。傍にいてほしい。だけどリアンが夢を持ち、努力してきたことも知っているから、選ばせてあげるよ」
ウィルバートという名の王様。これは彼が努力して作り上げた姿なのだろうと思う。昔から何度も傷を作り、私が治癒魔法をかけていたのは木から落ちたせいでも釣りに行って岩場で切ったせいでもなく、こういうことだったのだと今、知った。
『リアンと居るときが一番、僕らしくいれるよ。君の治癒魔法の淡い光は温かで優しい』
傷を治してあげると、そうほんわかとした笑顔で言っていたウィルは普通の人だった。彼はどんな思いで、その言葉を口にしていたのだろう?
今、目の前にいるのは、以前と同じ、優しい雰囲気のウィルなのに、ウィルバートになると、王らしく強く輝くオーラと人を油断させない雰囲気を持つ。
私はフォークとナイフを置いた。
「わかったわ。ウィルが本気で言ってるのがわかるから、私も本気で考えるわ」
「ありがとう」
そうお礼を言って微笑むウィルだったが、その笑顔は作り笑いだと私は気づいていた。