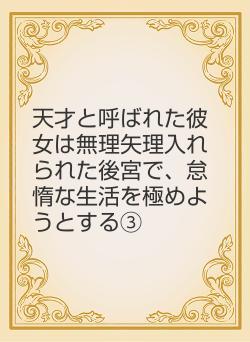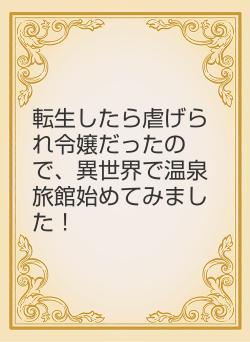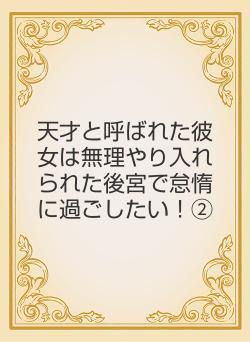「陛下がいきなり図書室に現れたんで、びっくりしましたよ」
そうクロードが愉快そうにメガネの奥の目を細めて笑う。
動けるようになった私はとりあえず図書室へ行った。ウィルは特に私の行動は制限していないが、その変わりに護衛騎士をつけた。静かな人で、影のように私についてくる。
私が図書室へ行った理由は、クロードが一番客観的に私とウィルを見守っていたはずだからだ。
「あー、だめだ。また思い出してきて、笑いが出る!アッハハハハ!いつもキリッとカッコつけてる陛下が、あなたの前だけ、頼りない男だし、本の片付けをしてるし、可笑しくて!」
クロードは眼鏡を外し涙を拭く。私とウィルのやりとりを思い出して涙が出るほど、笑っている。
「不敬だぞ」
ボソっと呟いて嗜める護衛騎士にもクロードは悪びれない。
「あの姿の陛下見たら、みんな同じように思うさ!ずーーっと笑いたいのも言いたいのも我慢してきたんだよ!?褒めてほしいな?でも本当に君のことを陛下は好きなんだなぁと思ったよ。王妃様になってあげなよ。君からの手紙を読んで、青ざめて駆けていく陛下を見せてあげたかったよ」
「簡単に言うわねぇ。怠惰に過ごしたいのに、王妃になったらできないじゃないの」
クロードがおやおや?と首を傾げる。
「本当は君は退屈が嫌いなタイプだと思うけどね?陛下よりも野心家で立ち向かって行く強さのある女性ではないかと見ている」
「人のことを冷静に分析するわね。でも陛下であるウィルは、私の知っていた彼とはだいぶ違うから、戸惑ってしまうのよ。怖かったわ……あの剣を振り上げたときのウィルは……」
首をはねる寸前だった。殺気も本物だった。
「獅子王と呼ばれるだけあって、陛下はやるときはやるよ。だけど王にはそんな決断も必要な時があるってことだ。君がそれを認めて味方でいてあげなきゃ、ちょっとかわいそうじゃないかい?王の地位はただでも孤独を感じやすいのにさ」
「クロードさんは陛下の味方なのね」
「王宮にいるものはみんなそうだと思うよ。陛下に忠誠を誓い、仕える者であるからね」
それはそうねと私は言う。ウィルとは同じ私塾で仲は良かったが、結婚相手や恋愛相手として改めて考えると……ウィルから好きと言われたことを思い出す。顔が赤くなる。
なに、思い出して赤面してるのよ!私、しっかりしなさいよ!と、自分の動揺を隠すため、本を手にとって選ぶフリをし、誤魔化す。顔が熱い。
「あなたは陛下が他の方と結婚されても平気なのですか?」
無愛想な護衛騎士がボソッと言った。
「うっ………何もかもが唐突すぎてわからないのよ」
私は言葉に詰まり、持っていた本で顔を隠す。この天才リアンが答えの出ない問題を抱えるなんてね。
「待つよ」
『ウィルバート陛下!』
クロードと護衛騎士が同時に名を呼ぶ。
ええええ!?いつからウィルはいたのだろう?私は振り返る。真顔で立っていた。
「もうっ!いつから聞いてたの?」
「秘密だよ」
「秘密が多すぎよっ!」
カツカツと足音をさせて、私に近づき、顔を隠していた本をヒョイッと避けて、顎を遠慮なく掴み、自分の方へ向かせるウィル。目をまっすぐ見ることになり、慌ててしまう。
「ちょっ、ちょっと??」
「知られたからには戻れない、時は戻せない。だからオレは前へ進むしかない。リアン、ずっと好きだった。どうか共に王妃として一緒に歩んでくれ」
私の怠惰生活は元に戻れないのでしょうか?と聞きたい言葉を飲みこんだ。あまりにもウィルが真剣だったからだ。また顔が赤くなってきたのを感じる。
「私、王妃は無理よっ!」
そう私が言うと、パッと顔から手が離された。そしてウィルはニッコリと笑う。
「答えはもう少し待つ。とりあえず他の令嬢の方々は後宮から出して、帰ってもらうことにした」
「ちょ、ちょっとウィル!?」
「王様のウィルバートとウィルは少し違うんだ。ごめんね。欲しいものは全力で奪いに行く。それがウィルバートだ」
優しい表情はなく、そこには王として君臨する凛とした彼の姿があった。
私は反論しようと口を開きかけたが、止めた。今、私は自問自答している。ウィルのことを私は好きなの?どうなの?
そしてウィルバートである目の前の彼もまたウィルなのだ。
そうクロードが愉快そうにメガネの奥の目を細めて笑う。
動けるようになった私はとりあえず図書室へ行った。ウィルは特に私の行動は制限していないが、その変わりに護衛騎士をつけた。静かな人で、影のように私についてくる。
私が図書室へ行った理由は、クロードが一番客観的に私とウィルを見守っていたはずだからだ。
「あー、だめだ。また思い出してきて、笑いが出る!アッハハハハ!いつもキリッとカッコつけてる陛下が、あなたの前だけ、頼りない男だし、本の片付けをしてるし、可笑しくて!」
クロードは眼鏡を外し涙を拭く。私とウィルのやりとりを思い出して涙が出るほど、笑っている。
「不敬だぞ」
ボソっと呟いて嗜める護衛騎士にもクロードは悪びれない。
「あの姿の陛下見たら、みんな同じように思うさ!ずーーっと笑いたいのも言いたいのも我慢してきたんだよ!?褒めてほしいな?でも本当に君のことを陛下は好きなんだなぁと思ったよ。王妃様になってあげなよ。君からの手紙を読んで、青ざめて駆けていく陛下を見せてあげたかったよ」
「簡単に言うわねぇ。怠惰に過ごしたいのに、王妃になったらできないじゃないの」
クロードがおやおや?と首を傾げる。
「本当は君は退屈が嫌いなタイプだと思うけどね?陛下よりも野心家で立ち向かって行く強さのある女性ではないかと見ている」
「人のことを冷静に分析するわね。でも陛下であるウィルは、私の知っていた彼とはだいぶ違うから、戸惑ってしまうのよ。怖かったわ……あの剣を振り上げたときのウィルは……」
首をはねる寸前だった。殺気も本物だった。
「獅子王と呼ばれるだけあって、陛下はやるときはやるよ。だけど王にはそんな決断も必要な時があるってことだ。君がそれを認めて味方でいてあげなきゃ、ちょっとかわいそうじゃないかい?王の地位はただでも孤独を感じやすいのにさ」
「クロードさんは陛下の味方なのね」
「王宮にいるものはみんなそうだと思うよ。陛下に忠誠を誓い、仕える者であるからね」
それはそうねと私は言う。ウィルとは同じ私塾で仲は良かったが、結婚相手や恋愛相手として改めて考えると……ウィルから好きと言われたことを思い出す。顔が赤くなる。
なに、思い出して赤面してるのよ!私、しっかりしなさいよ!と、自分の動揺を隠すため、本を手にとって選ぶフリをし、誤魔化す。顔が熱い。
「あなたは陛下が他の方と結婚されても平気なのですか?」
無愛想な護衛騎士がボソッと言った。
「うっ………何もかもが唐突すぎてわからないのよ」
私は言葉に詰まり、持っていた本で顔を隠す。この天才リアンが答えの出ない問題を抱えるなんてね。
「待つよ」
『ウィルバート陛下!』
クロードと護衛騎士が同時に名を呼ぶ。
ええええ!?いつからウィルはいたのだろう?私は振り返る。真顔で立っていた。
「もうっ!いつから聞いてたの?」
「秘密だよ」
「秘密が多すぎよっ!」
カツカツと足音をさせて、私に近づき、顔を隠していた本をヒョイッと避けて、顎を遠慮なく掴み、自分の方へ向かせるウィル。目をまっすぐ見ることになり、慌ててしまう。
「ちょっ、ちょっと??」
「知られたからには戻れない、時は戻せない。だからオレは前へ進むしかない。リアン、ずっと好きだった。どうか共に王妃として一緒に歩んでくれ」
私の怠惰生活は元に戻れないのでしょうか?と聞きたい言葉を飲みこんだ。あまりにもウィルが真剣だったからだ。また顔が赤くなってきたのを感じる。
「私、王妃は無理よっ!」
そう私が言うと、パッと顔から手が離された。そしてウィルはニッコリと笑う。
「答えはもう少し待つ。とりあえず他の令嬢の方々は後宮から出して、帰ってもらうことにした」
「ちょ、ちょっとウィル!?」
「王様のウィルバートとウィルは少し違うんだ。ごめんね。欲しいものは全力で奪いに行く。それがウィルバートだ」
優しい表情はなく、そこには王として君臨する凛とした彼の姿があった。
私は反論しようと口を開きかけたが、止めた。今、私は自問自答している。ウィルのことを私は好きなの?どうなの?
そしてウィルバートである目の前の彼もまたウィルなのだ。