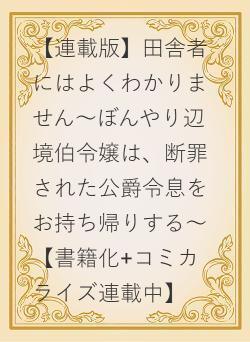キリアのすすめでお茶の席についた公爵様の元に、すぐに淹(い)れたてのお茶が運ばれてくる。
「もしかして、公爵様も休憩時間ですか?」
「俺のことはアレクと呼んでくれと……。いや、まぁそんな感じだ」
そう答えた公爵様の顔に浮かび上がっていた黒文様はきれいに消えていた。浄化を続けることによって、体中にあった黒文様もどんどん薄れてきている。
今思えば、元婚約者のオグマート殿下が公爵様のことを『醜い男』と言っていたのは、私と同じ黒文様があったからなのね。
公爵様は黒文様があっても整った顔をしていたのに、黒文様がなくなった今は、だれが見ても美しい青年だった。日々鍛えているせいか、体つきもたくましい。
ああ、美青年を眺めながら過ごせるって幸せ~。
私は、おいしいお茶を飲みながら、サクサクのクッキーを食べた。フリーベイン公爵領の食事はどれもおいしい。公爵様もカップを口元に運んでいる。
「そういえば、私たち、最近よく会いますね」
お茶を飲んでいた公爵様がゴフッと小さくむせた。なんだか急に顔色が悪くなったような気がする。
「……迷惑だったか?」
「いえ、そういうわけではなく! ご一緒できて楽しいです!」
「……なら、よかった」
どこかホッとした様子の公爵様。王都では公爵様は残虐非道(ざんぎゃくひどう)なんてウワサがあったけど、そんな事実は少しもなかった。
私が公爵様を見つめると、「な、なんだ?」となぜかあせっている。
「私の聖女の力、少しはお役にたっていますか?」
フリーベイン領は王都より邪気が少ないのよね。だから、聖女の仕事も多くない。そのおかげか私の体にも再び黒文様は現れていない。でも、今でも左肩にだけは黒文様が残っている。
公爵様が少しだけ口元をゆるめた。
「ああ、もちろん役にたっている。あなたが来てからは、魔物がめったに現れなくなったからな」
「それは良かったです」
公爵様からは、私が聖女の仕事をするかわりにたくさんの報酬をいただいていた。そのおかげで実家に仕送りができている。
この前家族から届いた手紙には、弟が無事にアカデミーに入学できたと書かれていた。
ふと公爵様の視線を感じて、私は公爵様を見つめた。こころなしか公爵様の顔が赤いような気がする。
「公爵様、どうかしましたか?」
「いや、ベールはもうつけないのだなと思い……」
「あ、つけたほうが良いですか?」
顔の黒文様が消えたので、もう顔は隠していない。
「いや、つけていないほうがいい。その、あなたはとても綺麗だから」
「……きれい? だれが?」
「あなたが」
「あなたって?」
「エステル、あなただ」
公爵様の言葉を理解するのにたっぷり五秒かかってから、私は叫んだ。
「え、えー!? そんなこと初めて言ってもらいました! 嬉しいです! ありがとうございます」
お世辞でもなんでも嬉しくて仕方ない。
「あなたの元婚約者……オグマートは褒めてくれなかったのか?」
「はい、醜い姿だって言われていました」
パキンッと公爵様が持っていたカップの取っ手が割れた。
「公爵様!? 大丈夫ですか!?」
「……大丈夫だ。あなたに仕える神殿の者たちは?」
私は神官たちの冷たい視線を思い出して、うつむいてしまう。
「私は汚らわしい邪気食いなので、なんというかその……遠巻きにされていました、ね」
えへへと私が笑うと、公爵様の顔が急にこわくなった。
「あ、すみません! このような情けないお話をしてしまい」
「いや、聞いて良かった」
公爵様は、控えていたキリアに「今後は、オグマートと神殿から来た手紙は、私にまわさず全て燃やせ」と指示している。
「はい!」
フゥとため息をついた公爵様は、私に向き直った。透き通るような紫色の瞳が私を見つめている。
「俺は、あなたがいつか王都に帰りたいのではないかと思っていた」
「そんな!? ありえません! お願いですからここに置いてください!」
王都に戻っても私の居場所なんてどこにもない。ここでは公爵様もキリアも、みんな優しくしてくれる。
公爵様の手が私の指にそっとふれた。
「あなたが王都に戻る気がないのなら……あなたさえよければ、その……俺と婚約を……。そして今度、隣国の舞踏会にあなたと一緒に参加したい」
語尾がだんだんと小さくなっていく公爵様の横で、キリアが『頑張れ』と言いたそうに両手をにぎりしめている。
私が公爵様と……婚約?
ふいにオグマート殿下の声が聞こえた。
――あいかわらず、醜い姿だな。
胸がチクッと痛む。
公爵様の言葉で混乱してしまっていたけど、おかげで冷静になれたわ。
たしか隣国の舞踏会は、パートナーなしでは参加できなかったはず。ということは、つまり……。
「わかりました! 舞踏会で私が婚約者のふりをすればいいのですね?」
「!? いや、その、ちが……」
「お役にたてて、とても嬉しいです!」
「うっ……」
長い沈黙のあとに公爵様は「……ああ、そういうことだ」と硬い表情で告げる。
「任せてください! 私、立派に婚約者のふりをしてみせます!」
「うむ、頼んだぞ」
そういった公爵様は、どこか遠い目をしていた。もしかしたら、私が婚約者役をうまくできるのか不安なのかもしれない。だったら、ちゃんとできることを証明しないと!
「これからは、アレク様と呼ばせていただきますね!」
「あ、ああ!」
パァと表情を輝かせるアレク様。
なぜか、キリアや周りにいるメイドたちから、何か言いたそうな視線を感じた。
やっぱりみんな、私がうまくできるか不安よね。
よく考えたら、私は社交界デビューをしていない。実家にそんな余裕がなかったからこそ、聖女になるために神殿の門をくぐった。
聖女の私とオグマート殿下の婚約が正式に結ばれたとき、婚約発表をかねて、一度だけ殿下と一緒に舞踏会に参加したことがある。
あのときは、黒文様がまだ私の顔にまで出ていなかった。だから手足をすべて隠すようなドレスを着て参加した。
覚えているのは私をエスコートするオグマート殿下の嫌そうな顔。
小声で何度も「必要以上に俺に近づくな!」と、きつく注意を受けた。ダンスは踊らなかった。
あれ以来、舞踏会には一度も参加していない。
ダンスは聖女になる前は大好きだったけど、今はもう自信がない。
「あの、アレク様。ダンスはお好きですか?」
「いや」
私はホッと胸をなでおろした。
「私、ダンスに自信がなかったので良かったです。もしアレク様がダンスがお好きなら、一緒に練習させていただこうかと思っていました」
「……」
しばらく何かを考えこんでいたアレク様は咳ばらいをした。
「いや、だが一曲くらいは踊らないといけない……はず」
なぜか視線が合わない。
「そうなんですか!? では、ダンスの練習に付き合っていただけませんか?」
「ああ、喜んで!」
ようやく視線があった。
アレク様はいつもとても優しい目をしている。そんなアレク様と一緒なら舞踏会も楽しいかもしれない。
「もしかして、公爵様も休憩時間ですか?」
「俺のことはアレクと呼んでくれと……。いや、まぁそんな感じだ」
そう答えた公爵様の顔に浮かび上がっていた黒文様はきれいに消えていた。浄化を続けることによって、体中にあった黒文様もどんどん薄れてきている。
今思えば、元婚約者のオグマート殿下が公爵様のことを『醜い男』と言っていたのは、私と同じ黒文様があったからなのね。
公爵様は黒文様があっても整った顔をしていたのに、黒文様がなくなった今は、だれが見ても美しい青年だった。日々鍛えているせいか、体つきもたくましい。
ああ、美青年を眺めながら過ごせるって幸せ~。
私は、おいしいお茶を飲みながら、サクサクのクッキーを食べた。フリーベイン公爵領の食事はどれもおいしい。公爵様もカップを口元に運んでいる。
「そういえば、私たち、最近よく会いますね」
お茶を飲んでいた公爵様がゴフッと小さくむせた。なんだか急に顔色が悪くなったような気がする。
「……迷惑だったか?」
「いえ、そういうわけではなく! ご一緒できて楽しいです!」
「……なら、よかった」
どこかホッとした様子の公爵様。王都では公爵様は残虐非道(ざんぎゃくひどう)なんてウワサがあったけど、そんな事実は少しもなかった。
私が公爵様を見つめると、「な、なんだ?」となぜかあせっている。
「私の聖女の力、少しはお役にたっていますか?」
フリーベイン領は王都より邪気が少ないのよね。だから、聖女の仕事も多くない。そのおかげか私の体にも再び黒文様は現れていない。でも、今でも左肩にだけは黒文様が残っている。
公爵様が少しだけ口元をゆるめた。
「ああ、もちろん役にたっている。あなたが来てからは、魔物がめったに現れなくなったからな」
「それは良かったです」
公爵様からは、私が聖女の仕事をするかわりにたくさんの報酬をいただいていた。そのおかげで実家に仕送りができている。
この前家族から届いた手紙には、弟が無事にアカデミーに入学できたと書かれていた。
ふと公爵様の視線を感じて、私は公爵様を見つめた。こころなしか公爵様の顔が赤いような気がする。
「公爵様、どうかしましたか?」
「いや、ベールはもうつけないのだなと思い……」
「あ、つけたほうが良いですか?」
顔の黒文様が消えたので、もう顔は隠していない。
「いや、つけていないほうがいい。その、あなたはとても綺麗だから」
「……きれい? だれが?」
「あなたが」
「あなたって?」
「エステル、あなただ」
公爵様の言葉を理解するのにたっぷり五秒かかってから、私は叫んだ。
「え、えー!? そんなこと初めて言ってもらいました! 嬉しいです! ありがとうございます」
お世辞でもなんでも嬉しくて仕方ない。
「あなたの元婚約者……オグマートは褒めてくれなかったのか?」
「はい、醜い姿だって言われていました」
パキンッと公爵様が持っていたカップの取っ手が割れた。
「公爵様!? 大丈夫ですか!?」
「……大丈夫だ。あなたに仕える神殿の者たちは?」
私は神官たちの冷たい視線を思い出して、うつむいてしまう。
「私は汚らわしい邪気食いなので、なんというかその……遠巻きにされていました、ね」
えへへと私が笑うと、公爵様の顔が急にこわくなった。
「あ、すみません! このような情けないお話をしてしまい」
「いや、聞いて良かった」
公爵様は、控えていたキリアに「今後は、オグマートと神殿から来た手紙は、私にまわさず全て燃やせ」と指示している。
「はい!」
フゥとため息をついた公爵様は、私に向き直った。透き通るような紫色の瞳が私を見つめている。
「俺は、あなたがいつか王都に帰りたいのではないかと思っていた」
「そんな!? ありえません! お願いですからここに置いてください!」
王都に戻っても私の居場所なんてどこにもない。ここでは公爵様もキリアも、みんな優しくしてくれる。
公爵様の手が私の指にそっとふれた。
「あなたが王都に戻る気がないのなら……あなたさえよければ、その……俺と婚約を……。そして今度、隣国の舞踏会にあなたと一緒に参加したい」
語尾がだんだんと小さくなっていく公爵様の横で、キリアが『頑張れ』と言いたそうに両手をにぎりしめている。
私が公爵様と……婚約?
ふいにオグマート殿下の声が聞こえた。
――あいかわらず、醜い姿だな。
胸がチクッと痛む。
公爵様の言葉で混乱してしまっていたけど、おかげで冷静になれたわ。
たしか隣国の舞踏会は、パートナーなしでは参加できなかったはず。ということは、つまり……。
「わかりました! 舞踏会で私が婚約者のふりをすればいいのですね?」
「!? いや、その、ちが……」
「お役にたてて、とても嬉しいです!」
「うっ……」
長い沈黙のあとに公爵様は「……ああ、そういうことだ」と硬い表情で告げる。
「任せてください! 私、立派に婚約者のふりをしてみせます!」
「うむ、頼んだぞ」
そういった公爵様は、どこか遠い目をしていた。もしかしたら、私が婚約者役をうまくできるのか不安なのかもしれない。だったら、ちゃんとできることを証明しないと!
「これからは、アレク様と呼ばせていただきますね!」
「あ、ああ!」
パァと表情を輝かせるアレク様。
なぜか、キリアや周りにいるメイドたちから、何か言いたそうな視線を感じた。
やっぱりみんな、私がうまくできるか不安よね。
よく考えたら、私は社交界デビューをしていない。実家にそんな余裕がなかったからこそ、聖女になるために神殿の門をくぐった。
聖女の私とオグマート殿下の婚約が正式に結ばれたとき、婚約発表をかねて、一度だけ殿下と一緒に舞踏会に参加したことがある。
あのときは、黒文様がまだ私の顔にまで出ていなかった。だから手足をすべて隠すようなドレスを着て参加した。
覚えているのは私をエスコートするオグマート殿下の嫌そうな顔。
小声で何度も「必要以上に俺に近づくな!」と、きつく注意を受けた。ダンスは踊らなかった。
あれ以来、舞踏会には一度も参加していない。
ダンスは聖女になる前は大好きだったけど、今はもう自信がない。
「あの、アレク様。ダンスはお好きですか?」
「いや」
私はホッと胸をなでおろした。
「私、ダンスに自信がなかったので良かったです。もしアレク様がダンスがお好きなら、一緒に練習させていただこうかと思っていました」
「……」
しばらく何かを考えこんでいたアレク様は咳ばらいをした。
「いや、だが一曲くらいは踊らないといけない……はず」
なぜか視線が合わない。
「そうなんですか!? では、ダンスの練習に付き合っていただけませんか?」
「ああ、喜んで!」
ようやく視線があった。
アレク様はいつもとても優しい目をしている。そんなアレク様と一緒なら舞踏会も楽しいかもしれない。