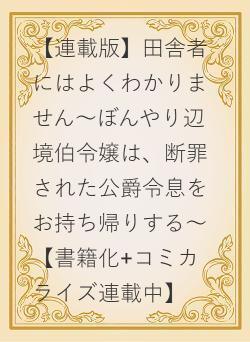いろんなことがありすぎたせいか、そのあとの私は高熱を出してしまった。
朦朧(もうろう)とする意識の中で、アレク様がかいがいしくお世話してくれる様子を見ていた。
おでこを冷やしてくれたり、スープをあーんで食べさせてくれたり。寝るときは私が眠りにつくまでずっと手を握ってくれていた。
私の父も母のことを大切にしているけど、さすがにここまではしていなかったわ。アレク様には迷惑をかけて申し訳ないと思いつつ、その想いがくすぐったくて嬉しい。
もし、アレク様が体調を崩したときは、私も同じようにお世話しようと心に決めた。
アレク様のお世話のかいもあり、二日ほどベッドの上ですごしたら元気になった。
ホッと胸をなでおろしているアレク様に、私はどうしても伝えなければいけないことがある。
「アレク様、大聖女様のことでお話があります。実は……」
優しい表情を浮かべていたアレク様の顔が深刻なものに変わる。
私は大聖女様に選ばれた三人は、いなくなってしまう大聖女様の代わりをできること、そして、大聖女様はフリーベイン領ではなく、ゼルセラ神聖国の地下深くにある神殿にいることを告げる。
「フリーベイン領に魔物が頻繁に出るのは、英雄の剣を奪いたい存在がいるせいだそうです」
それまで黙って私の話を聞いていたアレク様は、両手で私の手を包み込んだ。
「エステル。お願いだから、自分が犠牲になるなんて言わないでくれ」
怖いくらい真剣なアレク様に、私はうなずく。
「はい、もちろんです」
本当は『アレク様が苦しむくらいなら私が』と思ってしまったこともあった。でも、私がアレク様のそばにいられて幸せを感じているように、アレク様が幸せになるには私が必要だと言ってくれた。
だからもう、私は大切な人を守るために、自分だけが犠牲になればいいなんて思わない。
大切な人たちは、私のことも大切に思ってくれているのだから。
安堵のため息をつくアレク様に「アレク様こそ、絶対に自分を犠牲にしないでくださいね?」と釘をさしておく。
「ああ、もちろんだ。だが、だとしたらどうする?」
アレク様の問いに私はきっぱりと答えた。
「だれかを犠牲にしない方法を考えましょう。大聖女様は私達三人で決めてくださいと言っていましたけど、他の人に相談してはいけませんとは言っていませんでしたから」
*
手始めに私は聖女の研究をしているフィン様に相談することにした。
訪ねて来たフィン様は、私とアレク様を見るなりボロボロと涙を流す。
「エステルが無事で良かったです……。すみません、王宮の警備が甘かったせいで……」
「フィン様のせいではありませんよ」
「でも……」
肩をおとすフィン様に、私は微笑みかけた。
「フィン様。でしたら、私に力を貸していただけませんか?」
顔をあげたフィン様は「もちろんです! なんでも言ってください!」と頼もしい返事をくれる。
「実は……」
私は大聖女様から聞いた話をもう一度話した。
大聖女様はもうすぐいなくなってしまうこと。
私、アレク様、オグマートの三人は大聖女様の後を継げる者たちだということ。
大聖女様はフリーベイン領ではなく、ゼルセラ神聖国の地下深くにある神殿にいること。
話を聞いているうちに、フィン様の顔から血の気が引いていった。
「そ、そんな……それって絶対にだれかが大聖女様の後を継がないといけないんですか? そんなことをしたら、その人は……」
私はゆっくりとうなずいた。
「これから何十年、何百年とたった一人で邪気を浄化し続けることになってしまいます」
自分で口にしながら、あまりの恐ろしさにゾクッと寒気がする。
うつむいたフィン様は、両手をぎゅっと握りしめた。
「だったら……だったら、オグマートが犠牲になるべきでは? 幸い我が国の騎士達に死者はでませんでしたが、聖女様を攫(さら)った彼はゼルセラ神聖国でも我が国でも罪人です」
「それは賛成できません」
「どうしてですか?」
今までオグマートにされたことを思うと、私が彼をかばうのはおかしいのかもしれない。でも……。
「私、大聖女様と約束したんです。『皆が幸せになれる方法を必ず見つけてみせます。そして、大聖女様に会いに行きますね!』って。だから、だれかを犠牲にしなくて良い方法を探したいんです」
フィン様は困ったように微笑んだ。
「エステル。やはりあなたは聖女様なのですね」
「え? はい。いちおう……」
クスッと笑ったフィン様の涙はもう乾いていた。
「わかりました、探しましょう。そして、だれも犠牲にならなくて良い方法を必ず見つけましょう」
「はい!」
それからの私たちはアレク様を含めた三人でいろいろ話し合った。話し合いでは解決できず、次の日の朝、図書館に向かいたくさんの本や資料を漁った。
それでも結論はでない。
疲れた顔で滞在先の邸宅に戻って来た私たちは、人払いをしてまた話し合いを始めた。
アレク様に「大聖女様がいなくなった世界には魔物があふれるのだな?」と尋ねられたので、私は「はい」と答える。
「それを阻止するには、だれかが大聖女様の代わりをしないといけない。それはできない……だとしたら、もう魔物のあふれている世界を受け入れるしかないのでは?」
「で、でも、アレク様。そうなったら、人々はどうなるんですか?」
「エステルが来てくれるまでフリーベイン領には頻繁に魔物が出ていた。しかし、魔物を退治することで領民の安全は守られていたんだ」
フリーベイン領の人たちは、決して不幸ではない。むしろ、皆フリーベイン領を誇りに思って暮らしている。
アレク様の言葉を受けて、フィン様は「たしかに」とつぶやいた。
「大聖女様がもたらしてくださった長き平和の間、人は数を増やして繁栄し続けてきました。大聖女様の時代より、国も文化も戦力も比べ物にならないほど発展しています。もし、今、魔物があふれだしても、大きな被害を出さずフリーベイン領のようにうまく対処できるかも」
フィン殿下は「でも……」とうなだれた。
「それは、公爵のように強い戦力を持っている者に限ります。我が国は頻繁に魔物退治ができるほどの戦力は持っていません。他国もそうでしょう。騎士たちの中にも、喜んで危ない魔物退治をする人たちなんかいませんよ」
フィン様の言葉に私は何かが引っかかった。
私も本当は聖女なんかしたくなかったけど、私は聖女になることを選んだ。
それはなぜか?
「……あっ、お金」
私のつぶやきを聞いたアレク様が、すぐに察して「なるほど」と同意する。
「どういうことですか?」と不思議そうなフィン様。
「お金ですよ。お金! 魔物を退治した者たちに国から報酬を与えればいいんですよ! それだけじゃなくて、名誉もあれば最高です!」
フィン様は理解できないようで首をかしげている。
お金がなければ生きていけない。お金を稼ぐためなら、なんだってする人たちがいることを、王族として生まれたフィン様はわからないんだわ。
私だって、本当は家族と離れて聖女になんかなりたくなかった。でも、貧乏貴族の私が家族を養えるくらい多額のお金を稼ぐ方法は、身売りをするくらいしか思いつかない。それなら、聖女になるほうがはるかにましだったから、私は迷わず聖女になった。
聖女ならお金と共に名誉もついてくる。
「ゼルセラ神聖国の聖女と同じですよ! 聖女になればお金ももらえて名誉も与えられる。それなら、大変な仕事でもやりたい人が必ずいるはず!」
フィン様がポンッと手を打った。
「それって大昔にあったけど、平和な今はなくなってしまった職業。えっと……たしか、冒険者?」
私とアレク様は初めて聞く言葉に顔を見合わせる。
フィン様がいうには、冒険者とは、大聖女様が現れる前の時代に、魔物があふれている土地を勇敢に旅していた者たちのことをいうらしい。彼らは村と村を渡り歩き物資を運搬したり、雇われて魔物退治をしたりすることもあったとのこと。
「魔物退治をする者たちのことを冒険者と呼び、そういう職業を作ってしまえばいいのでは?」
フィン様の言葉にアレク様もうなずく。
「なるほど。殿下、それならば、国をまたいで冒険者たちを支援するのはどうでしょうか?」
「いいですね! 各国が支援する職業ならば、自然と名誉も付いてくる」
フィン様は「とまぁ、そんなことを言ったとしても、しょせんは机上の空論。そう上手くはいかないと思いますが、魔物があふれだしたら各国も真剣に対策を考えるしかなくなりますものね。そのときにこの案はとても役立ちそうです」とため息をついた。
「ひとまず、私はこの件を内密に父様……国王陛下に進言します。その際に、大聖女様の代わりができる者がいることは隠します。このことは決して他の者たちに知られてはいけません」
「わかりました。俺たちもゼルセラ神聖国に帰り、国王陛下に進言します」
「公爵、エステル。くれぐれも気をつけてくださいね。僕はあなたたちの味方ですが……。だれか一人が犠牲になって今の平和が保たれるとわかったら、多くの人は一人の犠牲者を出すことを選ぶはずですから」
フィン様の言葉に、私たちは静かにうなずいた。
朦朧(もうろう)とする意識の中で、アレク様がかいがいしくお世話してくれる様子を見ていた。
おでこを冷やしてくれたり、スープをあーんで食べさせてくれたり。寝るときは私が眠りにつくまでずっと手を握ってくれていた。
私の父も母のことを大切にしているけど、さすがにここまではしていなかったわ。アレク様には迷惑をかけて申し訳ないと思いつつ、その想いがくすぐったくて嬉しい。
もし、アレク様が体調を崩したときは、私も同じようにお世話しようと心に決めた。
アレク様のお世話のかいもあり、二日ほどベッドの上ですごしたら元気になった。
ホッと胸をなでおろしているアレク様に、私はどうしても伝えなければいけないことがある。
「アレク様、大聖女様のことでお話があります。実は……」
優しい表情を浮かべていたアレク様の顔が深刻なものに変わる。
私は大聖女様に選ばれた三人は、いなくなってしまう大聖女様の代わりをできること、そして、大聖女様はフリーベイン領ではなく、ゼルセラ神聖国の地下深くにある神殿にいることを告げる。
「フリーベイン領に魔物が頻繁に出るのは、英雄の剣を奪いたい存在がいるせいだそうです」
それまで黙って私の話を聞いていたアレク様は、両手で私の手を包み込んだ。
「エステル。お願いだから、自分が犠牲になるなんて言わないでくれ」
怖いくらい真剣なアレク様に、私はうなずく。
「はい、もちろんです」
本当は『アレク様が苦しむくらいなら私が』と思ってしまったこともあった。でも、私がアレク様のそばにいられて幸せを感じているように、アレク様が幸せになるには私が必要だと言ってくれた。
だからもう、私は大切な人を守るために、自分だけが犠牲になればいいなんて思わない。
大切な人たちは、私のことも大切に思ってくれているのだから。
安堵のため息をつくアレク様に「アレク様こそ、絶対に自分を犠牲にしないでくださいね?」と釘をさしておく。
「ああ、もちろんだ。だが、だとしたらどうする?」
アレク様の問いに私はきっぱりと答えた。
「だれかを犠牲にしない方法を考えましょう。大聖女様は私達三人で決めてくださいと言っていましたけど、他の人に相談してはいけませんとは言っていませんでしたから」
*
手始めに私は聖女の研究をしているフィン様に相談することにした。
訪ねて来たフィン様は、私とアレク様を見るなりボロボロと涙を流す。
「エステルが無事で良かったです……。すみません、王宮の警備が甘かったせいで……」
「フィン様のせいではありませんよ」
「でも……」
肩をおとすフィン様に、私は微笑みかけた。
「フィン様。でしたら、私に力を貸していただけませんか?」
顔をあげたフィン様は「もちろんです! なんでも言ってください!」と頼もしい返事をくれる。
「実は……」
私は大聖女様から聞いた話をもう一度話した。
大聖女様はもうすぐいなくなってしまうこと。
私、アレク様、オグマートの三人は大聖女様の後を継げる者たちだということ。
大聖女様はフリーベイン領ではなく、ゼルセラ神聖国の地下深くにある神殿にいること。
話を聞いているうちに、フィン様の顔から血の気が引いていった。
「そ、そんな……それって絶対にだれかが大聖女様の後を継がないといけないんですか? そんなことをしたら、その人は……」
私はゆっくりとうなずいた。
「これから何十年、何百年とたった一人で邪気を浄化し続けることになってしまいます」
自分で口にしながら、あまりの恐ろしさにゾクッと寒気がする。
うつむいたフィン様は、両手をぎゅっと握りしめた。
「だったら……だったら、オグマートが犠牲になるべきでは? 幸い我が国の騎士達に死者はでませんでしたが、聖女様を攫(さら)った彼はゼルセラ神聖国でも我が国でも罪人です」
「それは賛成できません」
「どうしてですか?」
今までオグマートにされたことを思うと、私が彼をかばうのはおかしいのかもしれない。でも……。
「私、大聖女様と約束したんです。『皆が幸せになれる方法を必ず見つけてみせます。そして、大聖女様に会いに行きますね!』って。だから、だれかを犠牲にしなくて良い方法を探したいんです」
フィン様は困ったように微笑んだ。
「エステル。やはりあなたは聖女様なのですね」
「え? はい。いちおう……」
クスッと笑ったフィン様の涙はもう乾いていた。
「わかりました、探しましょう。そして、だれも犠牲にならなくて良い方法を必ず見つけましょう」
「はい!」
それからの私たちはアレク様を含めた三人でいろいろ話し合った。話し合いでは解決できず、次の日の朝、図書館に向かいたくさんの本や資料を漁った。
それでも結論はでない。
疲れた顔で滞在先の邸宅に戻って来た私たちは、人払いをしてまた話し合いを始めた。
アレク様に「大聖女様がいなくなった世界には魔物があふれるのだな?」と尋ねられたので、私は「はい」と答える。
「それを阻止するには、だれかが大聖女様の代わりをしないといけない。それはできない……だとしたら、もう魔物のあふれている世界を受け入れるしかないのでは?」
「で、でも、アレク様。そうなったら、人々はどうなるんですか?」
「エステルが来てくれるまでフリーベイン領には頻繁に魔物が出ていた。しかし、魔物を退治することで領民の安全は守られていたんだ」
フリーベイン領の人たちは、決して不幸ではない。むしろ、皆フリーベイン領を誇りに思って暮らしている。
アレク様の言葉を受けて、フィン様は「たしかに」とつぶやいた。
「大聖女様がもたらしてくださった長き平和の間、人は数を増やして繁栄し続けてきました。大聖女様の時代より、国も文化も戦力も比べ物にならないほど発展しています。もし、今、魔物があふれだしても、大きな被害を出さずフリーベイン領のようにうまく対処できるかも」
フィン殿下は「でも……」とうなだれた。
「それは、公爵のように強い戦力を持っている者に限ります。我が国は頻繁に魔物退治ができるほどの戦力は持っていません。他国もそうでしょう。騎士たちの中にも、喜んで危ない魔物退治をする人たちなんかいませんよ」
フィン様の言葉に私は何かが引っかかった。
私も本当は聖女なんかしたくなかったけど、私は聖女になることを選んだ。
それはなぜか?
「……あっ、お金」
私のつぶやきを聞いたアレク様が、すぐに察して「なるほど」と同意する。
「どういうことですか?」と不思議そうなフィン様。
「お金ですよ。お金! 魔物を退治した者たちに国から報酬を与えればいいんですよ! それだけじゃなくて、名誉もあれば最高です!」
フィン様は理解できないようで首をかしげている。
お金がなければ生きていけない。お金を稼ぐためなら、なんだってする人たちがいることを、王族として生まれたフィン様はわからないんだわ。
私だって、本当は家族と離れて聖女になんかなりたくなかった。でも、貧乏貴族の私が家族を養えるくらい多額のお金を稼ぐ方法は、身売りをするくらいしか思いつかない。それなら、聖女になるほうがはるかにましだったから、私は迷わず聖女になった。
聖女ならお金と共に名誉もついてくる。
「ゼルセラ神聖国の聖女と同じですよ! 聖女になればお金ももらえて名誉も与えられる。それなら、大変な仕事でもやりたい人が必ずいるはず!」
フィン様がポンッと手を打った。
「それって大昔にあったけど、平和な今はなくなってしまった職業。えっと……たしか、冒険者?」
私とアレク様は初めて聞く言葉に顔を見合わせる。
フィン様がいうには、冒険者とは、大聖女様が現れる前の時代に、魔物があふれている土地を勇敢に旅していた者たちのことをいうらしい。彼らは村と村を渡り歩き物資を運搬したり、雇われて魔物退治をしたりすることもあったとのこと。
「魔物退治をする者たちのことを冒険者と呼び、そういう職業を作ってしまえばいいのでは?」
フィン様の言葉にアレク様もうなずく。
「なるほど。殿下、それならば、国をまたいで冒険者たちを支援するのはどうでしょうか?」
「いいですね! 各国が支援する職業ならば、自然と名誉も付いてくる」
フィン様は「とまぁ、そんなことを言ったとしても、しょせんは机上の空論。そう上手くはいかないと思いますが、魔物があふれだしたら各国も真剣に対策を考えるしかなくなりますものね。そのときにこの案はとても役立ちそうです」とため息をついた。
「ひとまず、私はこの件を内密に父様……国王陛下に進言します。その際に、大聖女様の代わりができる者がいることは隠します。このことは決して他の者たちに知られてはいけません」
「わかりました。俺たちもゼルセラ神聖国に帰り、国王陛下に進言します」
「公爵、エステル。くれぐれも気をつけてくださいね。僕はあなたたちの味方ですが……。だれか一人が犠牲になって今の平和が保たれるとわかったら、多くの人は一人の犠牲者を出すことを選ぶはずですから」
フィン様の言葉に、私たちは静かにうなずいた。