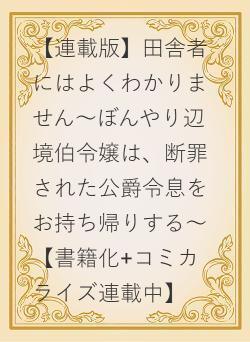馬車にゆられてたどり着いたカーニャ国の王宮はとても広く、その豪華さに目を奪われる。月明かりに照らされた王宮は、まるで夜空に浮かんでいるように見えてとても幻想的だった。
アレク様にエスコートされて会場入りすると、入口に立っていた係の者が声を張り上げる。
「フリーベイン公爵様、その婚約者エステル様のご入場です」
会場にいた貴族たちの視線が一斉に集まった。
その場から逃げ出したい気持ちをグッとこらえて、私は必死に微笑みを顔に貼り付ける。
一度だけ自国で参加した舞踏会会場より、さらに華やかですべてが輝いているわ。
チラリとアレク様を見ると、堂々としていて少しも気後れしていない。
さすがアレク様。頼もしいわ。私も堂々としておかないと。
背筋を伸ばしていると、会場にファンファーレが鳴り響いた。
先ほど私たちを紹介してくれた係の者が、「国王陛下、王妃殿下のご入場です」と声を張り上げた。
その場にいた貴族たちは、一斉にうやうやしく首(こうべ)を垂れる。
「つづきまして、王太子殿下と王太子妃殿下、並びに第二王子殿下とその婚約者様。さらに――」
恐ろしいことに係の者の読み上げは、第六王子殿下のフィン様まで続いた。
その間、ずっと同じ姿勢で頭を下げているので、私は全身がプルプルしてしまった。王族が多いとこういう苦労もあるのね。
カーニャ国では側室制度があるから王家の血を引く方が多いんだわ。
その点、自国のゼルセラ神聖国には側室制度はない。国王陛下と王妃殿下の間に三人の王子がいるのみ。
カーニャ国の国王陛下のありがたい挨拶が終わると、楽団が演奏を始めて会場内は和やかな空気になった。
それぞれがパートナーと手を取り合って、会場の中心へと向かう。
あっダンスをするのね。
私がアレク様を見るとアレク様はニコリと微笑み、私に右手を差し出した。
「俺と踊っていただけますか?」
「はい!」
手を取り合いダンスの輪の中に入っていく。
何度も何度もくり返し練習したおかげで、身体がステップを覚えている。アレク様のリードはとてもうまく、私たちの呼吸はぴったりと合っていた。
紫色の優しい瞳が私だけを見つめてくれている。
「楽しいな」
「はい、とっても楽しいです」
煌びやかな王宮で、王子様のように素敵な男性とダンスを踊る。それは乙女ならだれもが夢見る出来事。
でも、アレク様とならどこでダンスをしたって楽しい。もし、二人とも泥だらけだったとしても、アレク様とだったらきっと楽しく微笑み合える。
ダンスを踊り終えた私たちは、ウェイターからグラスを受け取りのどを潤した。果実の甘みが口に広がっていく。
「なんだかよくわからないけど、おいしいですね」
「ああ、よくわからないがおいしいな。……少し甘すぎるが」
小声でヒソヒソとそんな会話をする。
私もそうだけど、アレク様も同じくらい貴族らしいことに興味がないみたい。だから、舞踏会で出される飲み物の名前なんて二人ともさっぱりわからない。
無事にダンスが終わってホッとしたのもつかの間、ワッと人が寄ってきて私とアレク様は取り囲まれてしまった。集まってきた人たちから私を庇うように、アレク様が一歩前に出た。
その結果。
「フリーベイン公爵様、お初にお目にかかります! 私は――」
「婚約者様は、ゼルセラ神聖国の聖女様だとか!? ぜひご挨拶を――」
「私はこの国で絹織物の生産をしておりまして、ぜひフリーベイン領と取引を――」
次々に話しかけてこようとする人たちに向かってアレク様は片手をあげる。すると、シンッと辺りが静まり返った。
「光栄だが、その話はまたの機会に」
アレク様は私の肩を抱き寄せると、サッサとその場をあとにした。
「いいんですか?」
「いいんだ。エステルも、私が血まみれ公爵と呼ばれていることを知っているだろう?」
「はい……」
事実無根のウワサだけど、たしかに王都でもそう言われていた。
「そのウワサを信じずに、私の元にやって来た者とはすでに取引している。だから、今さら取引先を増やそうとは思わない」
「なるほど……」
アレク様に黒文様が浮かんでいても、それを恐れずに訪ねていった人たちがいたのね。その人たちとの交流を大切にしているアレク様の気持ちはよくわかる。
人々の視線から逃げるように、私たちはバルコニーへと出た。
ダンスで火照った身体に、ひんやりとした夜風が心地いい。
「あっ」と声が聞こえたかと思うと、アレク様の手が私の肩から離れていった。
アレク様の頬は赤く染まっている。
もしかして、さっき飲んだのお酒だったのかしら?
「大丈夫ですか? 顔が赤くなっていますよ」
私はそっとアレク様の頬に手をのばした。
「もしかしてアレク様、お酒に弱い……とか?」
もしそうだったら意外だわ。お酒に弱いアレク様を想像すると、ちょっと可愛いかもしれない。
アレク様から返事はない。ただ、ぼぅと私を見つめている。
「えっと、アレク様?」
「あ、ああ。いや、酔っていない」
「でもお顔が」
「それは……あなたに見惚れていたから」
赤い顔のアレク様の隣で、今度は私が顔を赤くした。
アレク様にエスコートされて会場入りすると、入口に立っていた係の者が声を張り上げる。
「フリーベイン公爵様、その婚約者エステル様のご入場です」
会場にいた貴族たちの視線が一斉に集まった。
その場から逃げ出したい気持ちをグッとこらえて、私は必死に微笑みを顔に貼り付ける。
一度だけ自国で参加した舞踏会会場より、さらに華やかですべてが輝いているわ。
チラリとアレク様を見ると、堂々としていて少しも気後れしていない。
さすがアレク様。頼もしいわ。私も堂々としておかないと。
背筋を伸ばしていると、会場にファンファーレが鳴り響いた。
先ほど私たちを紹介してくれた係の者が、「国王陛下、王妃殿下のご入場です」と声を張り上げた。
その場にいた貴族たちは、一斉にうやうやしく首(こうべ)を垂れる。
「つづきまして、王太子殿下と王太子妃殿下、並びに第二王子殿下とその婚約者様。さらに――」
恐ろしいことに係の者の読み上げは、第六王子殿下のフィン様まで続いた。
その間、ずっと同じ姿勢で頭を下げているので、私は全身がプルプルしてしまった。王族が多いとこういう苦労もあるのね。
カーニャ国では側室制度があるから王家の血を引く方が多いんだわ。
その点、自国のゼルセラ神聖国には側室制度はない。国王陛下と王妃殿下の間に三人の王子がいるのみ。
カーニャ国の国王陛下のありがたい挨拶が終わると、楽団が演奏を始めて会場内は和やかな空気になった。
それぞれがパートナーと手を取り合って、会場の中心へと向かう。
あっダンスをするのね。
私がアレク様を見るとアレク様はニコリと微笑み、私に右手を差し出した。
「俺と踊っていただけますか?」
「はい!」
手を取り合いダンスの輪の中に入っていく。
何度も何度もくり返し練習したおかげで、身体がステップを覚えている。アレク様のリードはとてもうまく、私たちの呼吸はぴったりと合っていた。
紫色の優しい瞳が私だけを見つめてくれている。
「楽しいな」
「はい、とっても楽しいです」
煌びやかな王宮で、王子様のように素敵な男性とダンスを踊る。それは乙女ならだれもが夢見る出来事。
でも、アレク様とならどこでダンスをしたって楽しい。もし、二人とも泥だらけだったとしても、アレク様とだったらきっと楽しく微笑み合える。
ダンスを踊り終えた私たちは、ウェイターからグラスを受け取りのどを潤した。果実の甘みが口に広がっていく。
「なんだかよくわからないけど、おいしいですね」
「ああ、よくわからないがおいしいな。……少し甘すぎるが」
小声でヒソヒソとそんな会話をする。
私もそうだけど、アレク様も同じくらい貴族らしいことに興味がないみたい。だから、舞踏会で出される飲み物の名前なんて二人ともさっぱりわからない。
無事にダンスが終わってホッとしたのもつかの間、ワッと人が寄ってきて私とアレク様は取り囲まれてしまった。集まってきた人たちから私を庇うように、アレク様が一歩前に出た。
その結果。
「フリーベイン公爵様、お初にお目にかかります! 私は――」
「婚約者様は、ゼルセラ神聖国の聖女様だとか!? ぜひご挨拶を――」
「私はこの国で絹織物の生産をしておりまして、ぜひフリーベイン領と取引を――」
次々に話しかけてこようとする人たちに向かってアレク様は片手をあげる。すると、シンッと辺りが静まり返った。
「光栄だが、その話はまたの機会に」
アレク様は私の肩を抱き寄せると、サッサとその場をあとにした。
「いいんですか?」
「いいんだ。エステルも、私が血まみれ公爵と呼ばれていることを知っているだろう?」
「はい……」
事実無根のウワサだけど、たしかに王都でもそう言われていた。
「そのウワサを信じずに、私の元にやって来た者とはすでに取引している。だから、今さら取引先を増やそうとは思わない」
「なるほど……」
アレク様に黒文様が浮かんでいても、それを恐れずに訪ねていった人たちがいたのね。その人たちとの交流を大切にしているアレク様の気持ちはよくわかる。
人々の視線から逃げるように、私たちはバルコニーへと出た。
ダンスで火照った身体に、ひんやりとした夜風が心地いい。
「あっ」と声が聞こえたかと思うと、アレク様の手が私の肩から離れていった。
アレク様の頬は赤く染まっている。
もしかして、さっき飲んだのお酒だったのかしら?
「大丈夫ですか? 顔が赤くなっていますよ」
私はそっとアレク様の頬に手をのばした。
「もしかしてアレク様、お酒に弱い……とか?」
もしそうだったら意外だわ。お酒に弱いアレク様を想像すると、ちょっと可愛いかもしれない。
アレク様から返事はない。ただ、ぼぅと私を見つめている。
「えっと、アレク様?」
「あ、ああ。いや、酔っていない」
「でもお顔が」
「それは……あなたに見惚れていたから」
赤い顔のアレク様の隣で、今度は私が顔を赤くした。