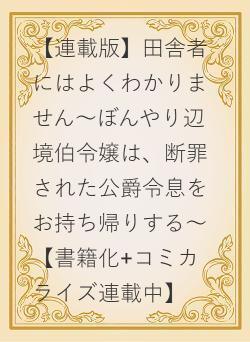それから数日後。
途中で馬車から荷馬車に乗り換えて、私の旅は続いていた。
のどかな風景に思わずあくびが出てしまう。ポカポカ陽気が心地いい。
神殿から追い出されてしまった私は、王都を包み込むように存在していた邪気を浄化するというお役目がなくなった。
こんなにのんびり過ごすのは久しぶりだわ。なんだか身体の調子がいつもより良い気がする。
それでも顔を隠すための黒ベールは手放せない。邪気の象徴であるこの黒い文様は、見る人を怖がらせてしまうから。
オグマート殿下には嫌われてしまったけど、フリーベイン公爵領では、上手くやっていかないと……。
私は馬車に揺られながら、毎日の日課である祈りを始めた。
聖女の祈りを受け取ってくださるのは、大昔にこの国を救ってくださった大聖女様だ。初代聖女様でもある彼女は、その偉業からこの国の守り神として崇められていた。
祈りを捧げたあとに、邪気を浄化できるようになる人のことをこの国では聖女と呼ぶ。邪気を浄化できる力は不思議と女性にしか現れない。
お役目のなくなった私は、祈りのあとに離れて暮らす家族や領民達の無事を願った。
「どうか、皆が笑顔で暮らせますように」
私がそうつぶやいたとたんに、ドドドッという地鳴りが聞こえてきた。
荷馬車の御者が「な、なんだ、ありゃ!?」と声を上げている。御者が指さすほうを見ると、遠くで土煙が上がっていた。それがすごい勢いでこちらに近づいてくる。
土煙を上げていたのは立派な騎馬隊で、あっという間に荷馬車は騎馬隊に取り囲まれてしまった。
「ひ、ひぇえ」と悲鳴をあげる御者を守るために、私は荷馬車から降りた。
「これは何事ですか?」
そう尋ねると、騎士たちは一斉に馬から降りて地面に片膝をつく。
「聖女エステル様ですね? 我らはフリーベイン公爵家の騎士です。エステル様をお迎えに上がりました」
「わ、私を?」
驚く私を騎士達は「どうぞ、こちらへ」と豪華な馬車に案内した。一人の凛々しい女性騎士が私のカバンを運んでくれる。
「聖女様の荷物はこれだけですか?」
「あ、はい」
私の荷物を運んでくれている女性騎士は、馬車に一緒に乗りこむと礼儀正しく頭を下げた。
「キリアと申します。これから聖女様の護衛にあたらせていただきます」
「ご、護衛ですか?」
「王都では護衛はつきませんでしたか?」
「はい、私は神殿内にずっといたので……」
キリアは「では、慣れないかもしれませんが、ここは王都と違い危ないので、どうか私を護衛としてお側に置いてください」と再び頭を下げる。
「ええ!? そんなっ、私のほうこそよろしくお願いします」
私もあわてて頭を下げると顔を隠していたベールがずれてしまった。視線が合ったキリアはポカンと口を開ける。
「み、見えましたか?」
「……あ、はい」
ベールで隠していた禍々しい黒文様を見られてしまった。
「すみません……」
「いえ、こちらこそ」
ふぅとため息をつくキリア。
「公爵閣下は、エステル様のような方を婚約者にできて幸せですね」
「……え? 今、なんて?」
「はい、公爵閣下は幸せ者だと」
「いえ、その少し前です」
「あ、エステル様のような方を婚約者(・・・)にできて……ですか?」
「んん?」
聞き間違いでなければ、私が公爵様の婚約者になったと言われている。
「私が、公爵様の婚約者、ですか?」
「はい、そうです」
「あの、私はフリーベイン公爵領の下働きとしてここに来ました」
「下働き……ええっ!? しかし、オグマート殿下から閣下にたしかに連絡が!」
キリアがいうには、オグマート殿下から公爵様宛に手紙が届いたそうだ。
その内容は『いらなくなった婚約者をおまえにくれてやる』だった。
「だからエステル様は、閣下の婚約者になられたのですよね?」
「あ、あー……」
私は頭を抱えた。オグマート殿下がいい加減な手紙を送ったせいで、だいぶ誤解をさせてしまっている。
オグマート殿下は『エステルはいらないから、おまえにやる。好きにしろ』という意味で手紙を送ったのに、受け取った公爵様は『いらなくなったエステルをおまえの婚約者として与える』という意味で受け取ってしまっている。
これは、なんというか、大変な誤解が……。
公爵様も聖女と呼ばれている女性は、きっと美人だと思っているはず。
ど、どうしましょう。こんな私が婚約者だなんて、公爵様も嫌がるわ。悩んでも仕方がないので、公爵様に会って直接誤解を解くしかない。
謝っても許してもらえず、追い出されるかも?
はぁ、再就職は前途多難だわ。
*
それからさらに数日後。
私とキリアを乗せた馬車は、ようやくフリーベイン公爵領にたどり着いた。
馬車の中から見える景色は牧歌的だった。たくさんの羊がのんびりと草をはみ、その横で羊飼いの少年が歌っている。
フリーベイン公爵領は、危ないところだと聞いていたけどそうは見えない。
興味津々の私に、護衛騎士のキリアは「何もないところでしょう?」と微笑んだ。
「いいえ、とても住みやすそうですね。魔物が出ると聞いていたのですが、ただのウワサだったようです」
平和なことは良いことだけど、平和な場所には聖女の仕事はないかもしれない。私が不安に思っていると、キリアは深刻な顔をした。
「いいえ、魔物は出ます」
「出るんですか!?」
喜ぶことではないけど、仕事があるかもしれないとつい喜んでしまう。
「ご心配なさらず。公爵閣下が魔物をすべて討伐してくださっています。我ら騎士団も討伐に参加しております」
「そうなのですね!」
魔物は邪気を吸うと強くなるといわれているので、邪気を浄化できる聖女なら討伐の役にたてるかもしれない。
「では、私も聖女として、その討伐に参加させていただいて……」
キリアは「未来の公爵夫人に、そのようなことはさせられません!」と顔を青くする。
「いや、ですから、それは誤解で……」
そんなやりとりをしているうちに公爵邸についてしまった。公爵邸は、王都の華やかなお城とは違い要塞のような作りになっていた。
私が馬車から降りると、馬車から公爵邸の入り口まで、ずらりと使用人が並んでいる。
「ようこそお越しくださいました! 聖女エステル様!」
「ひぇっ」
勘違いから大歓迎されてしまっているわ。
は、早く公爵様にお会いして謝罪しないと……。
ベールが脱げてしまわないように押さえながら私は「よろしくお願いいたします」と頭を下げた。
そのとたんに、使用人たちがザワッとざわめき「聖女様が私たちに頭を下げた?」やら「なんてお優しいのかしら」というささやきが聞こえてくる。
ここの人たちは、みんな良い人ばかりみたい。
好意的に受け入れてもらえて嬉しいけど、問題は公爵様の婚約者と誤解されていることだわ。
困ったことに公爵邸には、婚約者専用の豪華な自室まで準備されていた。
「わぁ、お姫様が住むところみたい」
私のつぶやきを聞いたキリアが、「神殿とは違いますか?」と話しかけてくれる。
神殿内では、私は聖女と呼ばれながら影で邪気食いと嫌悪されていた。
ずっと腫れ物にさわるように遠巻きにされていたので、キリアの距離感が嬉しくて仕方ない。
「はい、ぜんぜん違います」
神殿から与えられた私の自室は、簡素な作りで家具も必要最低限のものしか置かれていなかった。
あ、でも、ここは公爵様の婚約者用のお部屋なのよね? 私が住んで良いところではないわ。
「あの、公爵様は?」
「今は外出されていますが、夜にはお戻りになられます」
「夜……そうですか。では、明日にでもお時間をつくってほしいとお伝え願えますか?」
「はい、もちろんです!」
申し訳ないけど、一晩だけこの素敵な部屋に泊まらせてもらおう。
そのあと私は、お風呂に入るように勧められて身ぎれいになった。その際に手伝うといってくれたメイドの申し出は丁重にお断りした。
こんな黒文様まみれの身体は見せられないものね。
「あれ?」
身体を洗おうとしたとき、黒文様がとても薄くなっていることに気がついた。
「前は、もっとたくさんあったような……?」
鏡で確認したかったけど、ここには置かれていない。あとから確認しようと思いながら私はお風呂から上がった。身体を拭いて、自分で持ってきていた神殿服に着替える。顔を黒ベールで隠すことも忘れない。
私がお風呂から上がるのを部屋で待ち構えていたメイドは、綺麗なワンピースを手に持っていた。
「わぁ、素敵。これはどなたのですか?」
部屋に控えていたメイドに尋ねると「もちろん、エステル様のものです」と言われてしまう。
こ、こんなに綺麗なワンピースが私のもの!? あ、そういえば、公爵様の婚約者と勘違いされているんだった。
「お気に召しませんか? でしたら、すぐに別のものをお持ちします!」
青い顔で部屋から飛び出していこうとするメイドを、私は必死にとめる。
「いえいえ、これが良いです! これを着ます!」
今、話をややこしくするわけにはいかないので、メイドに部屋の外に出てもらい、私はワンピースに着替えた。とても着心地が良くてうっとりしてしまう。綺麗なワンピースに着替えたあとも、顔を隠す黒ベールは外すわけにはいかない。
急いでメイドに「着替えました!」と報告すると、彼女は「お似合いです!」と満面の笑みで褒めてくれた。
おかしな格好をしているのに、公爵家の使用人たちは、誰もとがめたり、嫌な顔をしたりしない。
それどころか、おいしいごちそうをたくさん食べさせてくれた。
ああ、誤解だけど、誤解だけど幸せ!
私が涙を浮かべながら「おいしいです! こんなにおいしい食事は初めてです!」と繰り返していると、使用人たちは、みんな温かい笑みを浮かべる。
明日からは、私も同じ使用人ですけど、どうか嫌わず仲間に入れてくださいね!
そんなことを思いながら、私はふかふかなベッドで眠った。
途中で馬車から荷馬車に乗り換えて、私の旅は続いていた。
のどかな風景に思わずあくびが出てしまう。ポカポカ陽気が心地いい。
神殿から追い出されてしまった私は、王都を包み込むように存在していた邪気を浄化するというお役目がなくなった。
こんなにのんびり過ごすのは久しぶりだわ。なんだか身体の調子がいつもより良い気がする。
それでも顔を隠すための黒ベールは手放せない。邪気の象徴であるこの黒い文様は、見る人を怖がらせてしまうから。
オグマート殿下には嫌われてしまったけど、フリーベイン公爵領では、上手くやっていかないと……。
私は馬車に揺られながら、毎日の日課である祈りを始めた。
聖女の祈りを受け取ってくださるのは、大昔にこの国を救ってくださった大聖女様だ。初代聖女様でもある彼女は、その偉業からこの国の守り神として崇められていた。
祈りを捧げたあとに、邪気を浄化できるようになる人のことをこの国では聖女と呼ぶ。邪気を浄化できる力は不思議と女性にしか現れない。
お役目のなくなった私は、祈りのあとに離れて暮らす家族や領民達の無事を願った。
「どうか、皆が笑顔で暮らせますように」
私がそうつぶやいたとたんに、ドドドッという地鳴りが聞こえてきた。
荷馬車の御者が「な、なんだ、ありゃ!?」と声を上げている。御者が指さすほうを見ると、遠くで土煙が上がっていた。それがすごい勢いでこちらに近づいてくる。
土煙を上げていたのは立派な騎馬隊で、あっという間に荷馬車は騎馬隊に取り囲まれてしまった。
「ひ、ひぇえ」と悲鳴をあげる御者を守るために、私は荷馬車から降りた。
「これは何事ですか?」
そう尋ねると、騎士たちは一斉に馬から降りて地面に片膝をつく。
「聖女エステル様ですね? 我らはフリーベイン公爵家の騎士です。エステル様をお迎えに上がりました」
「わ、私を?」
驚く私を騎士達は「どうぞ、こちらへ」と豪華な馬車に案内した。一人の凛々しい女性騎士が私のカバンを運んでくれる。
「聖女様の荷物はこれだけですか?」
「あ、はい」
私の荷物を運んでくれている女性騎士は、馬車に一緒に乗りこむと礼儀正しく頭を下げた。
「キリアと申します。これから聖女様の護衛にあたらせていただきます」
「ご、護衛ですか?」
「王都では護衛はつきませんでしたか?」
「はい、私は神殿内にずっといたので……」
キリアは「では、慣れないかもしれませんが、ここは王都と違い危ないので、どうか私を護衛としてお側に置いてください」と再び頭を下げる。
「ええ!? そんなっ、私のほうこそよろしくお願いします」
私もあわてて頭を下げると顔を隠していたベールがずれてしまった。視線が合ったキリアはポカンと口を開ける。
「み、見えましたか?」
「……あ、はい」
ベールで隠していた禍々しい黒文様を見られてしまった。
「すみません……」
「いえ、こちらこそ」
ふぅとため息をつくキリア。
「公爵閣下は、エステル様のような方を婚約者にできて幸せですね」
「……え? 今、なんて?」
「はい、公爵閣下は幸せ者だと」
「いえ、その少し前です」
「あ、エステル様のような方を婚約者(・・・)にできて……ですか?」
「んん?」
聞き間違いでなければ、私が公爵様の婚約者になったと言われている。
「私が、公爵様の婚約者、ですか?」
「はい、そうです」
「あの、私はフリーベイン公爵領の下働きとしてここに来ました」
「下働き……ええっ!? しかし、オグマート殿下から閣下にたしかに連絡が!」
キリアがいうには、オグマート殿下から公爵様宛に手紙が届いたそうだ。
その内容は『いらなくなった婚約者をおまえにくれてやる』だった。
「だからエステル様は、閣下の婚約者になられたのですよね?」
「あ、あー……」
私は頭を抱えた。オグマート殿下がいい加減な手紙を送ったせいで、だいぶ誤解をさせてしまっている。
オグマート殿下は『エステルはいらないから、おまえにやる。好きにしろ』という意味で手紙を送ったのに、受け取った公爵様は『いらなくなったエステルをおまえの婚約者として与える』という意味で受け取ってしまっている。
これは、なんというか、大変な誤解が……。
公爵様も聖女と呼ばれている女性は、きっと美人だと思っているはず。
ど、どうしましょう。こんな私が婚約者だなんて、公爵様も嫌がるわ。悩んでも仕方がないので、公爵様に会って直接誤解を解くしかない。
謝っても許してもらえず、追い出されるかも?
はぁ、再就職は前途多難だわ。
*
それからさらに数日後。
私とキリアを乗せた馬車は、ようやくフリーベイン公爵領にたどり着いた。
馬車の中から見える景色は牧歌的だった。たくさんの羊がのんびりと草をはみ、その横で羊飼いの少年が歌っている。
フリーベイン公爵領は、危ないところだと聞いていたけどそうは見えない。
興味津々の私に、護衛騎士のキリアは「何もないところでしょう?」と微笑んだ。
「いいえ、とても住みやすそうですね。魔物が出ると聞いていたのですが、ただのウワサだったようです」
平和なことは良いことだけど、平和な場所には聖女の仕事はないかもしれない。私が不安に思っていると、キリアは深刻な顔をした。
「いいえ、魔物は出ます」
「出るんですか!?」
喜ぶことではないけど、仕事があるかもしれないとつい喜んでしまう。
「ご心配なさらず。公爵閣下が魔物をすべて討伐してくださっています。我ら騎士団も討伐に参加しております」
「そうなのですね!」
魔物は邪気を吸うと強くなるといわれているので、邪気を浄化できる聖女なら討伐の役にたてるかもしれない。
「では、私も聖女として、その討伐に参加させていただいて……」
キリアは「未来の公爵夫人に、そのようなことはさせられません!」と顔を青くする。
「いや、ですから、それは誤解で……」
そんなやりとりをしているうちに公爵邸についてしまった。公爵邸は、王都の華やかなお城とは違い要塞のような作りになっていた。
私が馬車から降りると、馬車から公爵邸の入り口まで、ずらりと使用人が並んでいる。
「ようこそお越しくださいました! 聖女エステル様!」
「ひぇっ」
勘違いから大歓迎されてしまっているわ。
は、早く公爵様にお会いして謝罪しないと……。
ベールが脱げてしまわないように押さえながら私は「よろしくお願いいたします」と頭を下げた。
そのとたんに、使用人たちがザワッとざわめき「聖女様が私たちに頭を下げた?」やら「なんてお優しいのかしら」というささやきが聞こえてくる。
ここの人たちは、みんな良い人ばかりみたい。
好意的に受け入れてもらえて嬉しいけど、問題は公爵様の婚約者と誤解されていることだわ。
困ったことに公爵邸には、婚約者専用の豪華な自室まで準備されていた。
「わぁ、お姫様が住むところみたい」
私のつぶやきを聞いたキリアが、「神殿とは違いますか?」と話しかけてくれる。
神殿内では、私は聖女と呼ばれながら影で邪気食いと嫌悪されていた。
ずっと腫れ物にさわるように遠巻きにされていたので、キリアの距離感が嬉しくて仕方ない。
「はい、ぜんぜん違います」
神殿から与えられた私の自室は、簡素な作りで家具も必要最低限のものしか置かれていなかった。
あ、でも、ここは公爵様の婚約者用のお部屋なのよね? 私が住んで良いところではないわ。
「あの、公爵様は?」
「今は外出されていますが、夜にはお戻りになられます」
「夜……そうですか。では、明日にでもお時間をつくってほしいとお伝え願えますか?」
「はい、もちろんです!」
申し訳ないけど、一晩だけこの素敵な部屋に泊まらせてもらおう。
そのあと私は、お風呂に入るように勧められて身ぎれいになった。その際に手伝うといってくれたメイドの申し出は丁重にお断りした。
こんな黒文様まみれの身体は見せられないものね。
「あれ?」
身体を洗おうとしたとき、黒文様がとても薄くなっていることに気がついた。
「前は、もっとたくさんあったような……?」
鏡で確認したかったけど、ここには置かれていない。あとから確認しようと思いながら私はお風呂から上がった。身体を拭いて、自分で持ってきていた神殿服に着替える。顔を黒ベールで隠すことも忘れない。
私がお風呂から上がるのを部屋で待ち構えていたメイドは、綺麗なワンピースを手に持っていた。
「わぁ、素敵。これはどなたのですか?」
部屋に控えていたメイドに尋ねると「もちろん、エステル様のものです」と言われてしまう。
こ、こんなに綺麗なワンピースが私のもの!? あ、そういえば、公爵様の婚約者と勘違いされているんだった。
「お気に召しませんか? でしたら、すぐに別のものをお持ちします!」
青い顔で部屋から飛び出していこうとするメイドを、私は必死にとめる。
「いえいえ、これが良いです! これを着ます!」
今、話をややこしくするわけにはいかないので、メイドに部屋の外に出てもらい、私はワンピースに着替えた。とても着心地が良くてうっとりしてしまう。綺麗なワンピースに着替えたあとも、顔を隠す黒ベールは外すわけにはいかない。
急いでメイドに「着替えました!」と報告すると、彼女は「お似合いです!」と満面の笑みで褒めてくれた。
おかしな格好をしているのに、公爵家の使用人たちは、誰もとがめたり、嫌な顔をしたりしない。
それどころか、おいしいごちそうをたくさん食べさせてくれた。
ああ、誤解だけど、誤解だけど幸せ!
私が涙を浮かべながら「おいしいです! こんなにおいしい食事は初めてです!」と繰り返していると、使用人たちは、みんな温かい笑みを浮かべる。
明日からは、私も同じ使用人ですけど、どうか嫌わず仲間に入れてくださいね!
そんなことを思いながら、私はふかふかなベッドで眠った。