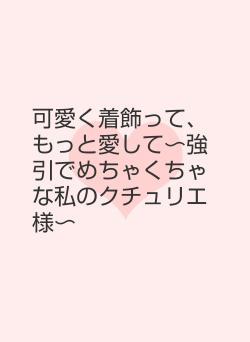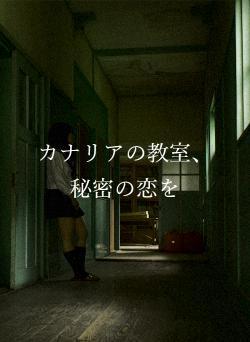「ねぇ、お父さん…最期はどんなふうだった?」
「…眠るみたいだった」
真白の手が一瞬止まる、でもすぐにスプーンでカレーをすくった。
「静かに眠って逝ったよ、全然苦しそうじゃなくてそれだけはよかったかな」
お父さんは最期何を思ってたかな、やっぱり心配だったよね真白のこと。
「そっか」
「うん」
今もきっと、思ってるよね。
「心細かったよね、真白1人で」
「うーん、まぁそれは…それなりに」
コップのお茶をゴクッと飲んで、私の方を見た。
「でもまた瑠璃ねーちゃんと会えたしね」
ゆっくりコップを置いて真っ直ぐ私を見る。
「覚えてる?父さんと俺が出て行った日」
「覚えてるよ、日曜日の朝だったよね」
「うん…、急に離婚することになったからって言われて訳もわからず父さんに手を引かれて…」
お父さんの仕事の転勤のタイミングだったらしい、そんなこと言われても子供の私たちにはわからなかったけどもう夫婦生活の終わっていたお母さんはついて行けなくて。
「俺はそれが行きたくなくてさ、父さんに繋がれてない方の手を必死に伸ばしてたんだ」
泣いていた、行きたくないのもわかってた。助けを求めるように手を伸ばしていた真白のこと、今でも鮮明に残ってる。
「瑠璃ねーちゃんに掴んでほしくて」
口角を上げる、少しだけ笑うようにして。
「離れるの嫌だったからなぁ、瑠璃ねーちゃんと」
「…眠るみたいだった」
真白の手が一瞬止まる、でもすぐにスプーンでカレーをすくった。
「静かに眠って逝ったよ、全然苦しそうじゃなくてそれだけはよかったかな」
お父さんは最期何を思ってたかな、やっぱり心配だったよね真白のこと。
「そっか」
「うん」
今もきっと、思ってるよね。
「心細かったよね、真白1人で」
「うーん、まぁそれは…それなりに」
コップのお茶をゴクッと飲んで、私の方を見た。
「でもまた瑠璃ねーちゃんと会えたしね」
ゆっくりコップを置いて真っ直ぐ私を見る。
「覚えてる?父さんと俺が出て行った日」
「覚えてるよ、日曜日の朝だったよね」
「うん…、急に離婚することになったからって言われて訳もわからず父さんに手を引かれて…」
お父さんの仕事の転勤のタイミングだったらしい、そんなこと言われても子供の私たちにはわからなかったけどもう夫婦生活の終わっていたお母さんはついて行けなくて。
「俺はそれが行きたくなくてさ、父さんに繋がれてない方の手を必死に伸ばしてたんだ」
泣いていた、行きたくないのもわかってた。助けを求めるように手を伸ばしていた真白のこと、今でも鮮明に残ってる。
「瑠璃ねーちゃんに掴んでほしくて」
口角を上げる、少しだけ笑うようにして。
「離れるの嫌だったからなぁ、瑠璃ねーちゃんと」