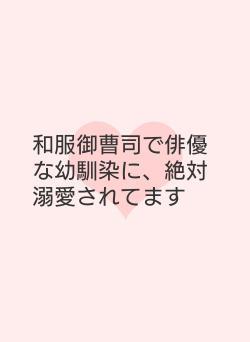夜、桃花は会社近くの高級ホテルに備え付けのバーで、慣れない酒を飲んでいた。
薄暗い店内ではジャズが流れており、サックス演者が客の前で演奏を披露している。
二階堂副社長のことを忘れたかったのだが、ヤケ酒以外の方法が思いつかなかったのだ。
(二階堂社長が持っていた写真の女性が誰か気になって仕方がない……)
カウンターの向こうから、マスターがグラスを差し出してきた。
桃花はそれを受け取ると、グラスの中の綺麗な色の碧い液体に視線を注ぐ。
その色は、二階堂副社長の瞳の色を想起させてくる。
(やっぱり、最近本当に変だわ……私、本当にどうしてしまったの……?)
自分が自分ではなくなってしまったかのようで、なんだか胸がざわついた。
どうにか気持ちを落ちつけたくて、お酒の入ったグラスを一気に煽る。
「お酒、おいしい……」
青リンゴの甘酸っぱさが口の中に広がると同時に、炭酸が舌先を刺激してくる。
普段はほとんど飲まないのに、甘くて色んな味がして楽しくなってきて、どんどん注文してグラスを空にした。
そうして、透明だけど小さなショットグラスの入ったお酒をぐいっと一息に飲み干す。
「大人の味……ちょっと苦い……」
美味しいけれども苦みがある。しかも、なんだか喉が熱くて、クラクラしてくる。
(もしかして強いの飲んじゃった……?)
頭の芯がボウッとしてきた。
そうして、カウンターに突っ伏して、頭をコツンと机の上にぶつけかけた時、肘をぐいっと引っ張られる。
「ねえねえ」
軽い調子で声を掛けられると、またしても、とある人物の姿が頭の中に浮かんできた。
(まさか、二階堂副社長……?)
桃花はのろのろと背後を振り返った。ちょっと頭を動かすだけで、頭のクラクラがすごい。
だが、そこにいたのは、色素が薄い髪色に浅黒い肌をした、軽薄そうな男性だった。
Tシャツに英語表記で卑猥なスラングが描かれている。意味が分からずに着用しているのか、それとも分かった上で着用しているのかは定かではない。
「ねえ、君、せっかくだから、オレと一緒に行こうよ、酔っちゃってるし、ちょうど良いでしょう?」
「ごめんなさい……結構です」
酔っているとはいえ、さすがに相手の男が怪しいことには気づいた。
(ちょうど良いの定義もよく分からないし……)
「ねえねえ、そんなこと言わずに、ほら、こっちに来てよ……」
しかしながら、きっぱりと断ったにも関わらず、わりと強引に肘を引っ張ってくるではないか。
大声を出して人を呼ぶか、手を振り払って反抗しようかと悩んでいた、その時。