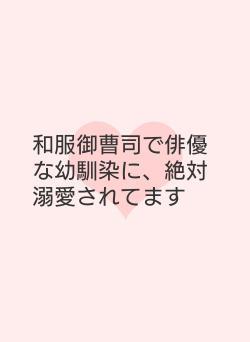結局仕事に集中できないまま過ごしてしまった。
終業時刻はとっくに終わっていたが、会議が夕方遅くまで白熱したことと、その議事録を作成していたため、普段の倍以上の時間がかかってしまったのだ。
二階堂副社長はもう終業して良かったはずなのに、桃花の手伝いをしながら待ってくれていた。
(上司を補佐する立場の専属秘書なのに、上司に手伝ってもらうなんて本末転倒すぎる)
桃花は心の中で自分自身を呪いながら、なんとか仕事をやり終えた。
「桃花ちゃん、お疲れ様」
「ひゃあっ!」
二階堂副社長がひんやり冷たい缶コーヒーを桃花の頬に押し当ててくる。
「びっくりさせないでください!」
「桃花ちゃんの反応がいちいち可愛くてね」
「……っ……」
桃花の頬が勝手に赤らんでいく。
ふいっと顔を逸らしつつ、缶コーヒーの蓋を開けて縁に口をつける。
(ちゃんとミルクが入ってる)
クールな女性社員を装って頑張っていた桃花だったが、正直ブラックコーヒーは苦手だ。
毎朝、二階堂副社長にコーヒーを作って手渡しているのだが、その時に彼女も一緒に一服している。その際に、ミルクとシュガースティックを注ぎがちなのだが、もしかしなくても、彼には見られてしまっていたのかもしれない。
桃花がコーヒーを全て飲み干した後、二階堂副社長が声をかけてきた。
「ああ、今日も車で送るよ、さあ、行こうか?」
「はい、ありがとうございます」
そうして、副社長室を出ると、ビルの地下駐車場へと向かい、二階堂副社長の白い愛車に二人して乗り込んだ。
車内では彼は好きなクラシックの音楽が流れており、爽やかな海を連想させるフレグランスが香っていた。
彼は軽妙な語り口調で、最近の竹芝部長の面白い出来事などを喋っていたけれど、桃花の気持ちは晴れなかった。
「桃花ちゃん、どうしたの?」
「え?」
「なんだか今日は半日調子が悪そうだったね?」
二階堂副社長に今日の桃花の仕事ぶりを指摘されてしまい、なんとなく恥ずかしくなってしまう。
「ごめんなさい、ご迷惑をおかけしてしまって」
「俺は別に君に謝ってもらいたいわけじゃないよ」
「ええっと、副社長が気になさるようなことは何もなくて……」
けれども、どうしてもうまく覇気が出なかった。
ちょうど桃花の自宅マンション前に停車する。
「ありがとうございました、それでは」
そうして、退席しようとした桃花の手首を、二階堂副社長の手が掴んだ。