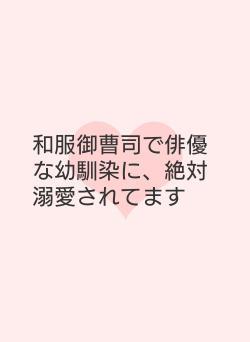再び結ばれ合った二人はそっと口づけを交わし合った。
「総悟さん」
「桃花ちゃん」
総悟が少しだけ泣きそうな笑顔を浮かべると、そっと桃花の頬に片手を添えた。
「こんなにも幸せだなんて――俺の夢じゃないよね?」
「もちろん」
総悟の声が震えた。指先も少しだけ震えている。
「ずっとまた君とこんな風に繋がり会える日を夢見てた。君との誓いを守っていたけど……もう二度と君にこんな風に触れられないって、半分は諦めてしまっていたから」
「私も、もう一生こんな風に貴方と抱きしめ合えるとは思っていませんでした」
少しだけ泣きそうな彼の様子を見ていると、彼女も少しだけ目頭が熱くなってくる。
二人はまたどちらからともなく口づけ合った後、視線を交し合う。
「そうだ、桃花ちゃん、実はね」
彼はまた枕元に手を伸ばした。
先ほどと同じような黒い箱だが、先ほどのものとは別のようだ。
そうして彼が中身を取り出すと、彼女の薬指にそっと別の何かを通した。
「総悟さん、これは……」
「さっき渡したのは二年前の俺から――今渡したのは、今の俺からだよ」
桃花の薬指には、ダイヤの指輪だけでなく――彼の瞳と同じ翡翠色の指輪が輝いていたのだ。
「こんな二つも……!」
彼女は驚きの声を上げてしまう。
「桃花ちゃん、改めて、俺の奥さんになってもらいたい」
ドクンドクンドクン。
桃花の心臓の音が心地よいリズムを刻む。
そうして、泣きそうになりながら微笑んだ。
「はい、もちろんです」
「やった! ありがとう、桃花ちゃん!」
総悟が歓喜の声を上げた後、蕩けるような笑みを浮かべた。
「また俺のところに帰ってきてくれてありがとう。俺にたくさんの幸せをプレゼントしてくれてありがとう――もう絶対に君を離さない、ずっと俺のそばにいてほしい……俺には君だけだ、桃花」
「はい、私もです、総悟さん」
桃花もこれまでで一番の微笑みを返す。
すると、総悟のもう片方の手が桃花の頬に添えられた。
「ねえ、本当に夢じゃないよね?」
「もちろん」
喜んでいたはずの総悟だったが、少しだけ泣きそうだった。
「繋がってるだけじゃ足りないんだ」
そうして、彼が切望するかのように告げてくる。
「本当に君が俺のそばに帰ってきたんだって分かるように、もっと俺にちゃんと顔を見せてほしい」
「はい」
彼の望む通り、彼女はしっかりと視線を合わせた。
「君がちゃんとここにいるんだって、もっと俺に確かめさせてほしい」
「はい」
桃花は総悟のことを安心させるために、彼の身体を慈しむように抱きしめる。
「もう君が俺から離れないって教えてほしい」
そうして――二人は口づけ合うと、再び身体を絡め合う。
互いがそこに存在することを確かめ合うように――その夜は一晩中、二人は愛し合い続けたのだった。