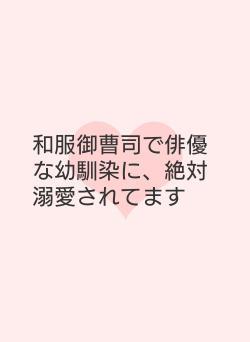すると、彼の親指がそっと彼女の眼下に宛がわれた。
「目の下にクマがある」
「え?」
「桃花ちゃん、俺のサポートのためにって、家でまで仕事やってるんでしょう?」
二階堂副社長が子どもを叱る親のような口調で桃花のことを諭しはじめた。
「あ……」
桃花には心当たりがあった。
実は、副社長である総悟の専属秘書に選ばれたため、彼の仕事内容をしっかり把握しないといけないと思って、連日調べ物をしていたら寝不足が続いていたのだ。
「さっきの社長の件もそうだけど、一人で難しそうな時は誰かを呼んで良いんだ。下手したら、二人共倒れになってたよ。人間なんだから、できることとできないことがある。何でも自分一人でやろうとしなくて良いんだ」
「……それは……」
叱られた気持ちになって、桃花はシュンと落ち込んでしまった。
その時。
彼が彼女の頭を慈しむように撫ではじめる。
(……あ……)
そうして、二階堂副社長が穏やかな口調で語りかけてきた。
「この数日の君を見てたらさ、両親を亡くして以来、一人で一生懸命やってきたんだろうなって思う。それは君のすごい美徳だ。だけど、君にできないところがあったとしても、俺はそれで君の評価を落とすなんてことはないんだからさ」
ドクン。
ドクンドクン。
自分がずっと抱えてきた心の問題に触れられた気がした。
桃花は自身の重ね合わせた両手をぎゅっと掴む。
「ですが……誰かに頼るだなんて、そんなことは……」
その時、彼の指が彼女の顎を掴んできた。
二人の視線が交じり合う。
二階堂副社長が真摯な声音で告げてきた。
「誰かに頼ることで、その人が君を迷惑だって思ったり、嫌いになるなんてことは絶対にない。むしろ、頼ってこられたら嬉しいぐらいだよ。それどころか、俺は君にもっと頼られたいって、ずっと前から思ってる」
……ずっと前から。
(いったいいつから……?)
桃花の心が揺れ動く。
「ねえ、君も僕の専属秘書だけど、僕も君の専属上司なんだしさ。ちゃんと俺のことを信じて、俺のことを頼ってほしい」
一人で何でもやるのが当たり前になってしまって、誰かに頼れば迷惑をかけてしまうのではないか?
ずっとそんな思いを抱えてこれまで生きてきた。
だけど、そんな自分の氷のように固まった心をホロホロと溶かしてくるような優しさが、二階堂副社長の声音には滲んでいた。
「私は……副社長に頼っても良いのですか……?」
「もちろん」
彼から蕩けるような笑みを向けられ、彼女の心臓は少女の頃のように高鳴ってくる。
(二階堂副社長に頼る……頼っても良い……)
自分に言い聞かせていると、なんだか胸がポカポカ熱くなってきた。
「さて……」
ギシリ。
彼の手が離れると同時にベッドのスプリングが鳴った。
二階堂副社長が桃花のそばから離れる……!
「副社長、行かないでください、私は……」
なぜだか妙に彼が離れるのが寂しく感じてしまった。
思わず彼女が彼に手を伸ばそうとした瞬間、どうしてだか彼女の視界が反転して、背中がベッドにぺたんとついた。
身体の上に柔らかな重みがかかる。
(あれ……?)
気づけば、桃花は二階堂副社長に押し倒されてしまっているではないか。
「まさか、桃花ちゃんから俺に行かないでって言ってくれるなんて……」
先ほどまでとは違って、彼は悪戯を思いついた少年のような表情を浮かべていた。
舌なめずりをしながら、長い指でネクタイを緩めると、彼の鎖骨が露わになる。
「さて、せっかく君に求められたんだから、ひと肌脱ごうかな……」
彼の手が彼女の太腿をストッキング越しにそっと撫でようとしてくる。
「ひゃっ……!」
「大丈夫、君にちゃんと応えてあげるから」
目まぐるしい状況変化についていけないでいたが……
ちらっと彼のジャケットのポケットから写真が覗いているのに気づいて頭がクリアになる。
(この人……大事な女性がいるはずなのに……それ以外に気になる女性もいるとかいう話で……)
二階堂副社長の手がスカートの裾にかかった頃には、桃花の身体がわなわなと震えはじめた。
「見直した私が馬鹿でした!!!! 大事な女性を大事にしてください!!!!」
医務室に桃花の怒声が響く。
「ええっ、桃花ちゃんのことじゃなくて……!?」
二階堂副社長の戸惑いの声も室内に響いた。
なんだかんだでせっかくの良いところが帳消しになりかけたけれども……
この日の出来事以来、桃花は少しだけ二階堂副社長に心を開くようになる。
彼もちゃんと仕事をするようになっていって……
そうして、これから数日後、二人の恋が急展開を迎えるなんて……
この時は思ってもみなかったのだった。