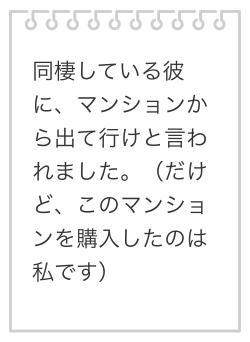伯爵令嬢のフィーナ=セネットには、当時仲良くしていた幼馴染みが2人いた。
どちらも同じ伯爵家の男の子で、身分も年齢も一緒のせいか親同士も仲が良かった。10歳になった時、その内の1人と婚約する事になった。
両親からそう言われたフィーナは、仲が良かったのですんなり受け入れた。愛や恋など分からないが、頑張って彼を支えて行こうと思っていた。
だけど、それはフィーナだけだった様だった。
「フィーナ。悪いけど、好きな人が出来た。婚約を破棄しよう」
婚約者だったマックにそう言われたのは、フィーナ12歳の誕生日の楽しい日だった。
朝から仲の良い両家と、もう1人の幼馴染みの一家が集まり、誕生日パーティーを開いて祝われた後、マックと庭を散策していた時にシレッと悪びれた様子もなく言われた。
「……いいけど。破棄じゃなくて解消でしょ?」
「え?」
「私が何かした訳ではないのだから、解消でしょ? 破棄じゃまるで私に非があるみたいじゃない」
「はぁぁっ? 俺には非なんかないだろ! 逆にブタと婚約してやっていた俺に感謝して欲しいぐらいだし!?」
一瞬フィーナは破棄と言われたのに、なんで冷静なんだとマックは思ったが、非がないと言われ頭にきてしまった。
だが、改めてマックはフィーナを指差して怒った様子で言い放った。
そうフィーナは少しだけ、他家の令嬢よりふくよかだった。
元々幼馴染みだっただけで、婚約する事になった事に憤りを感じていたのに、マックはフィーナの体型が気に入らなかった。
パーティーにフィーナを連れて行けば、クスクスと笑われている様に感じて凄く恥ずかしい。周りの女性とフィーナを見比べ、自分にはもっと綺麗な女性が似合うと、常々思っていたのである。
「あっ、そう? そういう事。性格だったら仕方ないと思ってたけど。それもどうでもイイや。私は好かれてもいない男性と結婚する気はないから」
仲の良い両家の親が勝手に決めた婚約だし、正直言ってフィーナはどうでも良かった。
色恋なんてまだよく分からないし、それより食欲が勝るお年頃だったから余計だ。
「ふん? 強がりなんて言いやがって。俺に破棄されたらお前みたいなブタ、貰い手なんか無いだろうよ」
フィーナが余りにも冷静だったために、マックは嫌味の1つでも言ってやりたくなっていた。
泣きつけとまで言わないが、ここまで無関心に言われると腹が立つのだ。
「もう婚約者ではないのだから、そんな心配は必要ないんじゃない? あぁ、まだハーネット家のご両親もいるから私から言っておくわ」
大体、言うにしても誕生日に言うとか、人としてどうなのよ。
そうフィーナは捨て台詞を吐いて、マックの元を去ったのだった。
屋敷にいた両家の両親は事情を知り、マックの暴言には憤慨していたけれど、言われたフィーナがなんとも思っていないのが分かり婚約は解消となった。
フィーナはマックに振られた時、それ程ショックではなかった。
だけど、部屋に戻り1人になると知らない内に涙が頬を伝っていた。自分でも気付かないくらい、彼の事を好きだったらしい。
「マックの事は忘れなよ」
そう言って励ましてくれたのは、もう1人の幼馴染みのクリスだった。
気にかけてくれるクリスのお陰もあり、次第に元気を取り戻していったフィーナ。
その後、マックの両親から改めて、フィーナ宛てに謝罪文と贈り物があり、正式に婚約は白紙になったのだった。
心配するマックの両親には気にしなくてイイと、フィーナからも手紙と贈り物をし、彼の両親とは今も仲の良い関係にある。
マックとは疎遠になってはいたけれど、もう1人の幼馴染み、クリスとはまだ交流を続けていた。
気にかけてくれているのか一緒にいる事も多く、フィーナは自然とクリスを好きになっていた。
そんなある日、フィーナは少しずつ痩せて綺麗になり始めていた。
マックの事も過去の事と割り切った頃、珍しく着飾ってクリスに好きだと告白をした。
「ゴメン。そんなつもりで仲良くしてた訳じゃなかったんだ」
──見事に玉砕した。
幼馴染みとして励ましていたのを、フィーナが勘違いしたと言う事らしかった。
フィーナは「そっか」と笑って返したが、家に帰って号泣した。2人の幼馴染みに振られたのである。
それが、無性に悲しくて寂しかった。
* * *
ーーそれから、3年の月日が流れた。
仲がよかった2人の幼馴染みとは、会う回数も次第に少なくなり疎遠になった。学園でスレ違う事もあったけど、フィーナはどちらかがいると、自然と避けていた。
気にしない様にはしていたが、フィーナは2人の幼馴染みに振られ、男性に対して軽いトラウマになっていたのだ。
同じ身分で同じ領地のため、夜会では2人の幼馴染みに会わない時はない。エスコートは婚約してた頃はマックが、解消した後はクリスがしてくれていた。
しかし今は、父か伯父がしてくれていた。
自分がまだ心にケリをつけられずにいる中、彼等が色んな女性とダンスを踊る。
胸を痛める事はないけど、なんだか寂しく虚しい気持ちだった。お陰ですっかり大人しくなってしまったフィーナは、壁の花と化す事も多かった。
そして、次第に夜会は欠席する様になっていくのであった。
それを見兼ねた両親には、男は幼馴染み2人だけではないのだからと、他の婚約者を勧められてはいるが、乗る気にはなれなかった。
だが、いつかは誰かと結婚しなければならないだろう。
そんな時、出会ったのがルーフィス=ハウルサイドである。
侯爵家の長子で妻を病気で亡くした人だった。
普段夜会に参加しないフィーナが、両親を安心させるために久々に出た夜会だ。なるべく幼馴染みの2人が参加しなさそうな場を選んで、ビクビクしながら出席した夜会だった。
そこで、従姪をエスコートする役目として、たまたま来ていたのが、ルーフィスとの初めての出会いであった。
その頃、すっかり痩せて綺麗になったフィーナが、ベロベロに酔った子爵の男に絡まれ、それを助けてくれたのがルーフィスだった。
その後、夜会で会うと気にかけてくれ、自然と親しくなっていた。
金髪碧眼で美丈夫。10歳以上歳上で、物腰が柔らかいルーフィスにフィーナは少なからず惹かれている。
そんな彼が、数年前に妻を亡くしたのだと知ったのは、それから暫くしてからだった。
特定の相手を持ちたくないルーフィス。
暫くは、1人でいたいフィーナの意見が合致し、夜会で会えば何となく一緒に過ごす様になっていた。
「フィー、お兄様を宜しくね?」
その夜会のとある日、ルーフィスと一緒にいるフィーナに、彼の再従姉妹はとこサリーがニコッと笑って言った。
血縁的にはルーフィスの父方の再従姉妹。優しく美丈夫の彼を兄の様に慕っているため、兄と呼んでいるとか。
「え?」
「フィーと一緒にいると、お兄様スゴく穏やかな表情をするの。あんなお兄様初めて見たわ」
亡くした妻といた時でさえ、そんな表情はしていなかったらしい。それだけ心を許しているのだと、サリーは言っていた。
「結婚しろ、なんて言わないわよ。ただ、友人として支えてくれたらなって……私のワガママ」
サリーはそう言って笑った。
フィーナに押しつけている訳ではない。ただ、妻が亡くなり沈んでいたルーフィスが、フィーナのお陰で元気になったから、暫く傍にいてくれたら嬉しいとの話だった。
実際は突然消えたので、探〈調査〉したり後処理などで、忙しく疲労していただけだと、後から知った。
「私も、ルーフィス様が傍にいると安心するから、あの方に相手が出来るまでは程良い距離でいたいと思うわ」
侯爵家の長子が、いつまで経っても後妻を迎えない訳にはいかないし、自分もいつまでも独身とはいかない。
ならば、どちらかに相手が決まるまでは、良い関係でいたいと願う。
「うん、ありがとう」
フィーナの返答が正解だったかは分からないが、サリーは嬉しそうに笑ったのだった。
* * *
「今更ながらだが、私といると……キミに男が寄らなくなるのではないかな?」
とある夜会でいつも通り、中庭で時間を潰していると、一緒にいたルーフィスが顎を撫でながら呟いた。
本当に今更である。
痩せて綺麗になったフィーナには、結婚の打診がかなりあった。だが、身分が高いルーフィスといる事ですぐに諦め身を引いている。
ちなみにフィーナの両親も、その勘違いの中に入っている。
夜会で噂されれば自然と両親の耳に入り、ルーフィスと上手くいっていると、盛大に喜んでいた。
相手の身分が侯爵と高いため、少しばかり恐縮してはいたが、やっと結婚する気になってくれたかと、ホッとしている様ではあった。
ルーフィスの両親も、ようやく息子が身を固める気になってくれたかと、胸を撫で下ろしていると聞いたのは後の話だ。
「虫除けになって頂き、大変感謝すれども迷惑とは思っておりません」
「しかし、男の私とは違って、キミはそろそろ相手を見つけないと困る事になる立場だろう」
フィーナが気にした様子もなく言ったので、ルーフィスは溜め息を吐き肩を落とした。
男なら晩婚でも大して言われないが、女は別だ。
子が産めなくなると疎遠にされるし、歳を食えば女と言うだけで難ありとされる。嫌な世の中である。
「最終的には、修道院でも良いかなと」
愛を期待していた訳ではないが、あんなにハッキリ拒絶されると、新しい人と結婚生活が上手くいける自信がない。
なら、ひっそりと暮らしたいのが本音だ。
「若いのに枯れ過ぎだよ」
苦笑いしたルーフィスが、コツンとフィーナの頭を叩いた。
「そう言うルーフィス様はどうなんですか? 長子なのでしょ?」
叩かれた頭が、なんだか温かい気がしてプイッとそっぽを向いた。
人の心配より自分では? とフィーナは返した。
「弟に子供がいるから問題はないさ」
「弟に丸投げですか。それ程までに……」
元妻が忘れられない? との言葉は飲み込み俯いた。
そこは、踏み入ってはならない気がした。
「愛してはないよ」
フィーナの飲み込んだ言葉に返事が返ってきた。
「え?」
「そこに愛などなかった」
「…………」
初めて聞いた話だった。
ルーフィスは彼女が好きで忘れられないから、もう誰とも結婚しないのだと思っていたし、そう周りから聞いていた。
だがそれは、勝手な想像であり事実ではなかった。
「政略から始まった結婚とはいえ、私なりに彼女を幸せにはするつもりだったんだけど……彼女には伝わらなかったみたいだ」
「奥様は?」
ルーフィス様を好きだったのかと、フィーナが言葉を紡げば、ルーフィスは苦々しく笑った。
「彼女は本気だった」
「…………」
「だけど彼女の本気に、私は返せなかった」
「…………」
「私はこの通り表情が乏しいからね。彼女の理想とする生活にはならなかったのだろう。だから、彼女は表情豊かな男を余所に作り出て行ったんだよ」
「え? 亡くなったのでは?」
それが社交界では有名な話だ。だからこそ、ルーフィスは後妻を迎えないのだと。
「体ていが悪いだろう?」
だから、死んだ事にした……と体裁を "テイ" と揶揄する様にして、ルーフィスは小さく笑っていた。
侯爵家の奥方が、男を作り屋敷から出て行ったともなれば、皆が歓喜する醜聞である。彼女の家もタダでは済まないだろう。
すべてを懸念したルーフィスが、揉み消したのだと言っていた。
「ルーフィス様はそれで良いのですか?」
それでは、歩み寄ろうとしていたルーフィスが可哀想な気がした。勝手に出て行った彼女のために、家族のためにそこまでしてあげたのだ。
「キミは彼女がいなくなって、ホッとした私を……軽蔑するかい?」
妻の愛はルーフィスにとって、重荷でしかなかった。だから、男を作っていなくなったと知った時、解放された気持ちだった。
打てば響く様な夫なら、良かったのかもしれないなと、疲れた様子で呟いていた。
「奥様を全く愛していなかったと聞いて、少し喜ぶ私を軽蔑しますか?」
愛していたのなら、絶対に勝てないと感じていたからだ。彼の心を持ったまま亡くなってしまったのなら、一生彼の心は彼女のものだ。
そう考えてしまうくらいに、フィーナはルーフィスを愛しているのだと、今口にしながら初めて気付いて驚いていた。
「少しと聞いた私が、大変残念がっているのをキミは信じてくれるかい?」
ルーフィスは困った様子で微笑んだ。
「その言葉を聞いて喜ぶくらいには、私はルーフィス様を気になっているのかもしれません」
フィーナはルーフィスの目を見て、玉砕覚悟で人生最後の告白をした。
「私もフィーナ、キミを気になっているのかもしれない」
不器用なルーフィスが、優しく微笑んでそれに応えた。
「疑問が確信に変わるか、私と試してみてくれないか?」
ルーフィスはそう言って、フィーナを引き寄せると額にキスを落とした。
「疑問のまま終わるかもしれませんよ?」
フィーナも背伸びをして、ルーフィスの頬にキスを返した。
「それもまた一興だと思うのは、大概だと思うかな?」
ルーフィスは仕返しとばかりに、頬にキスを返す。
「そこまで愛してはないので大丈夫ですよ?」
フィーナはチラッと見てから、小さく小さく笑ってルーフィスの顎にキスをした。
「愛してないよ。私のフィーナ」
「私も愛してません。ルーフィス様」
そう言って笑った2人の影は、自然と1つになったのだった。