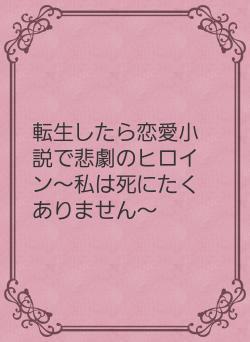すると、お祖母様に向かって静かに手を上げる男性がいた。
父の弟である隆司さんだ。
先程、話しかけて来た沙織さんの父親だ。
「お祖母様、皆さま、少しよろしいでしょうか。私は恵美さんを神宮寺家の後継者として認めることはできません。彼女はつい最近まで一般の家庭で育てられました。そのため、神宮寺家の教育やしきたりなど、全く分かっていないと思われます。僭越ながら、後継者に相応しいのは、我が娘である沙織ではないかと思います。皆さんいかがでしょうか?」
隆司さんの話を聞き、会場が一斉にどよめいた。
確かに私はつい最近まで神宮寺家の事など、何も知らなかった。
隆司叔父様が言っていることは当然なのかも知れない。
私は自分の手をグッと握り、拳に力を入れた。
私は何のためにここに戻って来たのだろうか。
複雑な気持ちで、なぜかフルフルと震えてしまうのだった。
少しの間、なにも言わずに目を閉じて皆の話を聞いていたお祖母様は、ゆっくりと目を開けたのだ。
「分かりました。隆司さん、それでは神宮寺家の後継者は私達ではなく、龍崎と早乙女に決めてもらいましょうか?」
私の心臓がドクドクと激しく鳴り出した。
龍崎と早乙女は沙織さんを選んでしまうのかも知れない。
とても悲しいけれど、それは受け入れるしかない。
名前を呼ばれた龍崎と早乙女は皆の前に立った。
早乙女は沙織さんに手を差し伸べている。
(…やはり私は選んでもらえなかった…)
沙織さんは顔を赤くして、早乙女に手を伸ばす。
すると、早乙女は皆に向って話し始めた。
「沙織様はこんなに美しく素敵な女性です。」
沙織は頬を赤くして、喜んでいるようだ。
さらに早乙女は話し続けた。
「しかし、誰が私達に相応しいかは、この後すぐに分かるでしょう。」
突然、何を言っているのか分からない。
すると、次の瞬間、いきなりガシャーンと硝子が割れるような大きな音がしたのだ。
その音の方へ振り返ると、すでにそこには大きな炎がゴオゴオと音をたてて迫ってくるではないか。
皆はパニックになりドアから逃げようと走り始めた。
しかし、ドアには鍵がかかっているようで誰も出ることは出来ない。
皆が炎を避けるように出口へ走るが、お祖母様は走ることが出来ない。
お母さんは腰が抜けてしまったようで蹲っている。
お父さん一人では、二人を助けられない。
パニックになっているからなのか、誰もお祖母様達を助けようとしていないのだ。
私は急いでお祖母様に駆け寄った。
「お祖母様、私の背中に乗ってください!!」
私は自分の着ていた帯を急いで解いて、帯紐でおばあ様を背負い自分に縛り付けた。
私がおばあ様を背負い逃げるには、こうするしかないと思ったのだ。
夢中でおばあ様を背負い立ち上がった。
そしてドアに向かって走り出そうとした時、嘘のように炎はスッと消えてしまったのだ。
割れた硝子も元の通りだ。
皆が驚き振り返ると、早乙女が微笑を浮べて話し始めた。
「驚かせて申し訳ございません。その割れた硝子や炎はすべて幻です。」
さらに龍崎が話し始めた。
「皆さん、少し落ち着いて周りを見てもらえますか?」
皆、ドアに殺到し、我さきに逃げようとしていた。
私は部屋の真ん中でおばあ様を背負って逃げるところだったのだ。
すると、龍崎が私に近づいて来た。
そしてドアの近くで、逃げようとしていた沙織さんに向って話し始めた。
「沙織さん、貴女は自分が助かるために周りも見ないで逃げ出しましたね。それを責めることはできません。でも、そうしなかった女性が一人いることに気づいてください。」
皆が私を見ている気がする。
私は帯を解いておばあ様を背負っているので、とても酷い姿だ。
恥ずかしすぎる姿を皆に見られてしまった。
そして龍崎はさらに私に近づいて言葉を続けた。
「恵美様、貴女は自分だけが助かろうとせずに、お祖母様を助けようと背負ったのですよね?」
「…は…はい。」
早乙女と龍崎は私の両側に立って、私の手を取り、手の甲に口づけたのだ。
「私達は見た目の美しさに心は奪われません。しかし、自分の危険をかえりみず、周りを気遣う優しい心はとても美しく、心を奪われました。私達は恵美様を後継者と決めたいと思います。」
何が起こったのだろうか?
お父さんとお母さんは手を叩いて涙ぐんでいる。
おばあ様は背中から降りて、私に抱き着いた。
「私の目に狂いは無かったわね。恵美、貴女は立派な後継者ですよ。」
会場中から拍手が起こった。
しかしその時だった、何かを床に叩きつけるような音がしたのだ。
“ガシャン!”
どうやら隆司叔父様がグラスを床に叩きつけた音だった。
沙織さんは少し悔しそうな顔をこちらに向けたが、二人は逃げるようにドアから出て行ってしまったのだ。
私が選ばれたことに腹を立てたのだろう。
なぜか少し申し訳なく思ってしまう自分もいた。